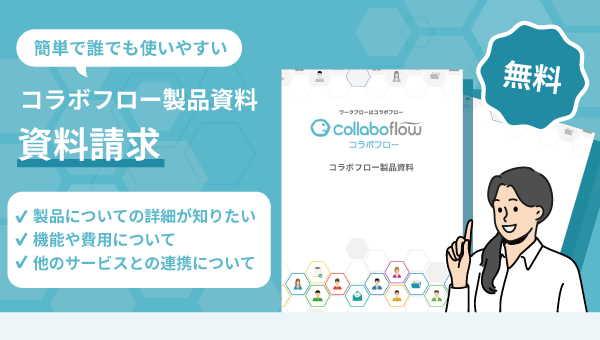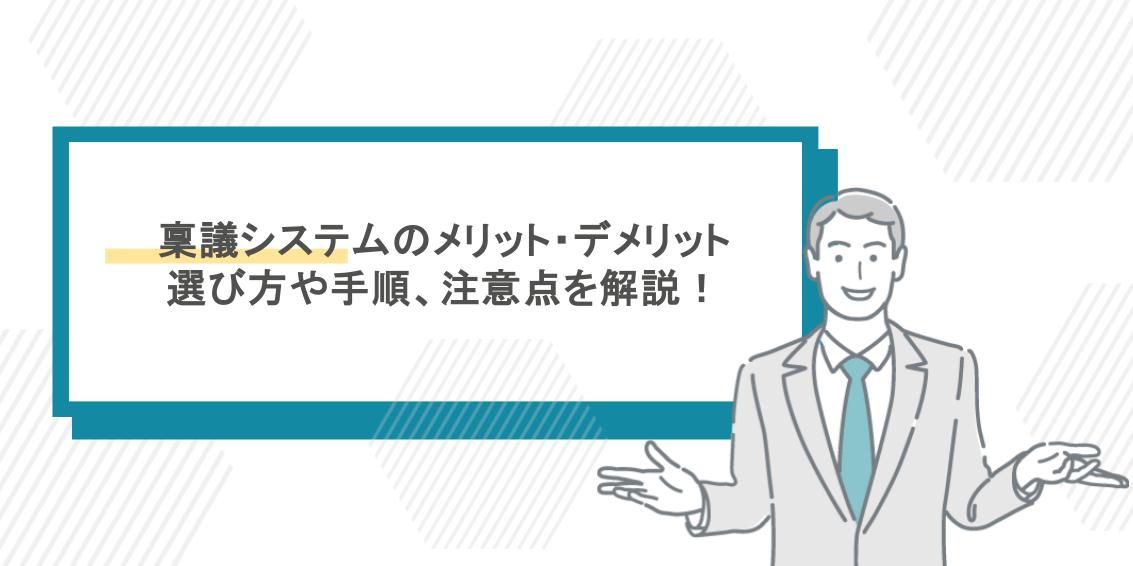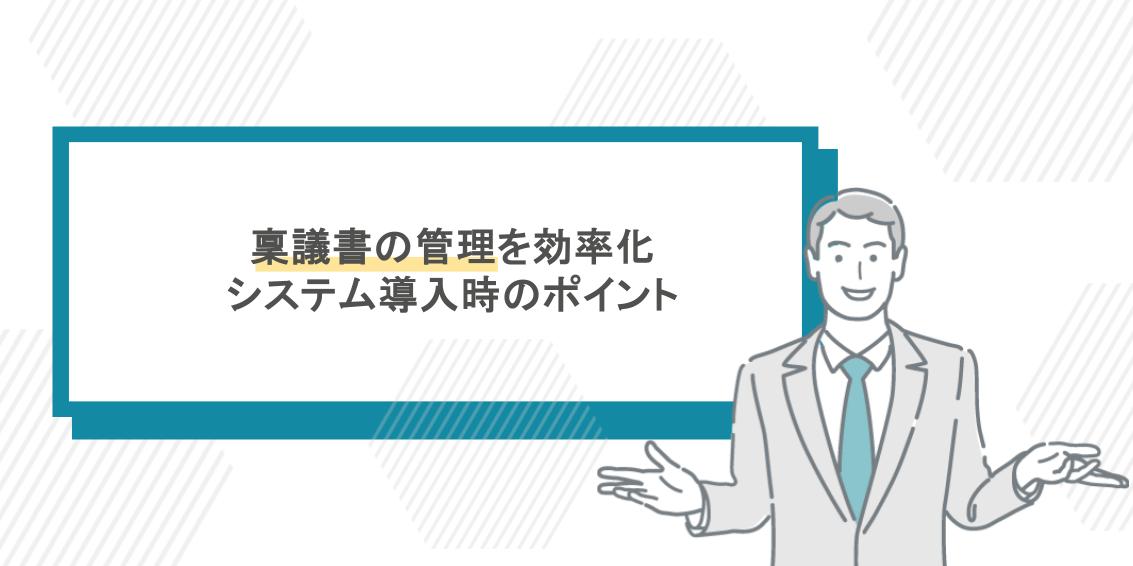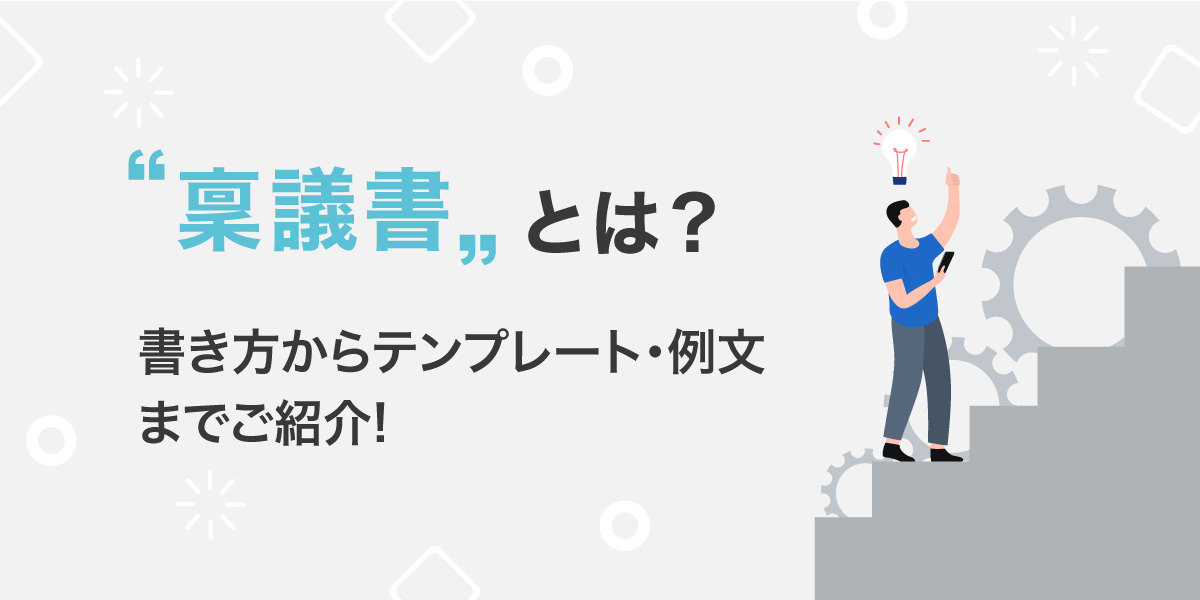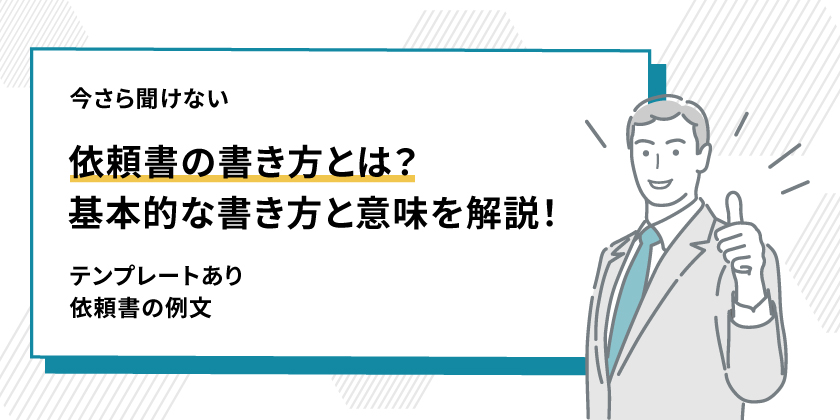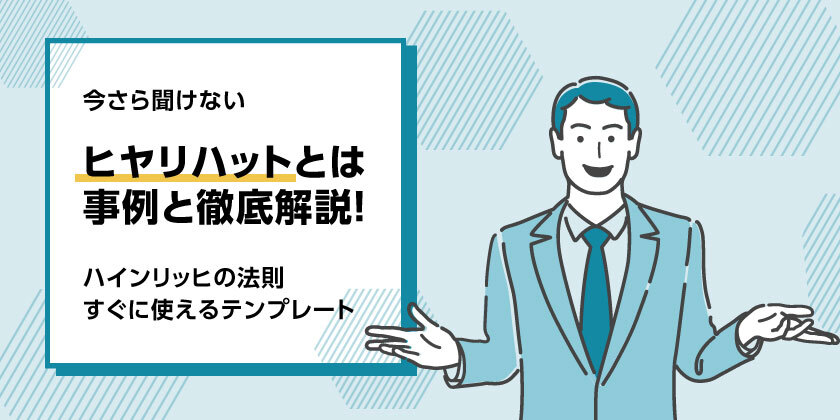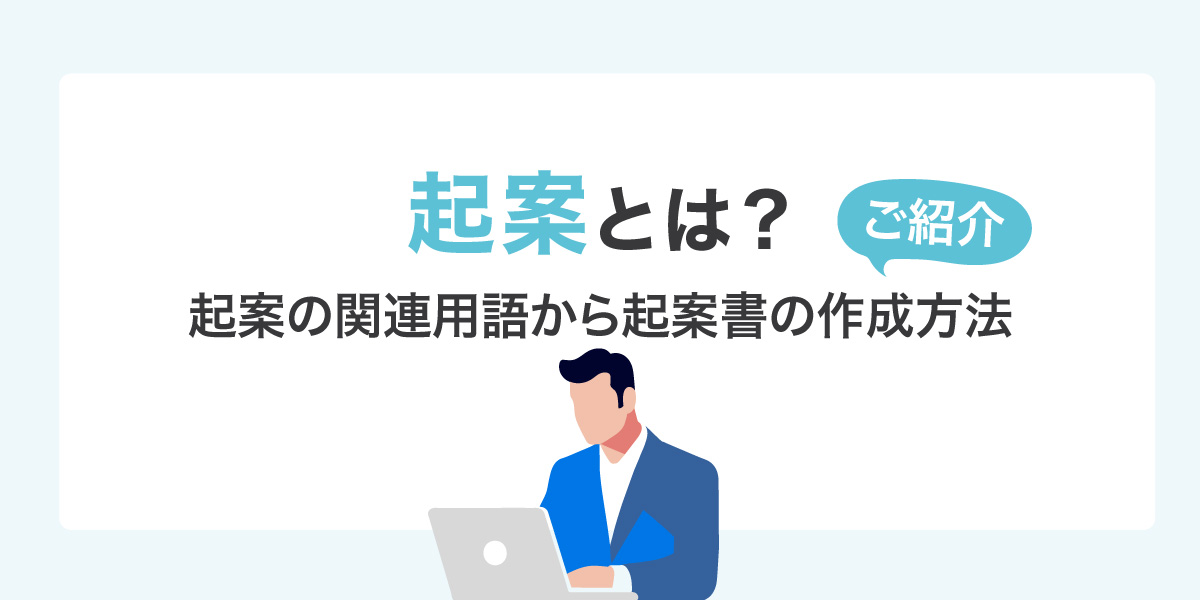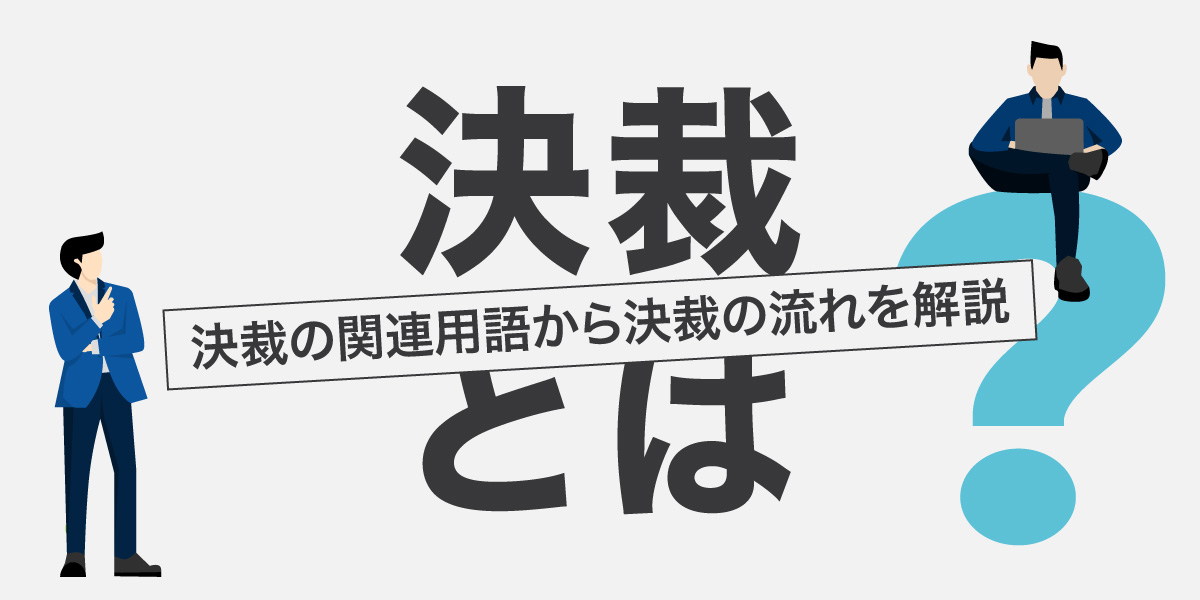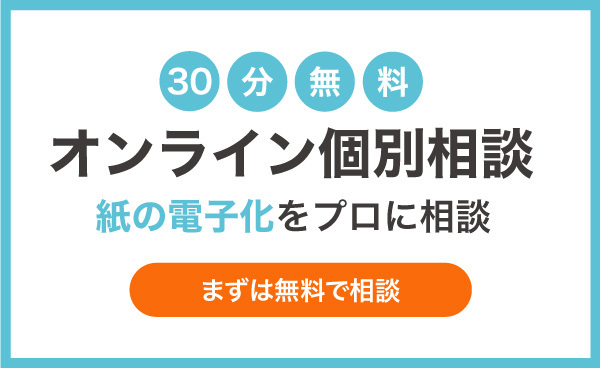この記事の目次
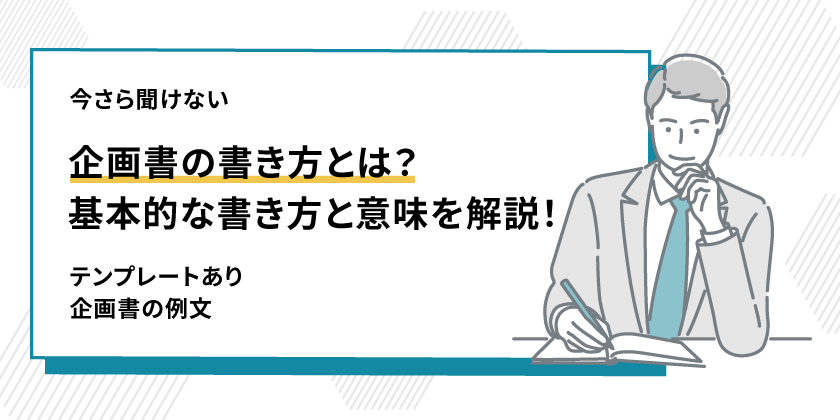
企画書は、企業内において新しいプロジェクトを始める、既存の業務を改善するなど、今までと違う業務に取り組むために必要です。社内稟議を通過させるには、説得力のある内容や充実した構成が求められます。今回の記事は、企画書の書き方を解説します。
企画書とは
ビジネスにおいて、新規事業は企画書から始まります。アイデアを思いついたときに上司に伝えると「企画書を書いて」と言われた経験をもつ方もいるでしょう。
記事の最初に、企画書の目的を紹介します。
企画書を作成する目的
企画書は、社内に限らず新しいプロジェクトをスタートさせるにあたり、ステークフォルダーとの合意形成する最初の手段です。
企画書の役割はアイデア、事業の将来性、収益や予算、スケジュールなどを関係者に伝えることにあります。言い換えれば、ビジネスのアイデアや施策を実現するための「手順」や「手法」を記述した書類です。
企画書にはプロジェクトの目的、リソースも含めた必要となる予算、達成する目標、ゴール時の業績貢献度などを記載します。その上で関係者の理解を得て、決裁者から承認されることが企画書の目的です。
企画書と似ている用語とその違い
企画書と似ている用語として「提案書」「稟議書」「起案書」「申請書」があります。新規プロジェクトを始めるにあたって、これらの書類は連動して使用されるケースが多いといえます。違いについて確認しましょう。
提案書
提案書と企画書は同じ書類を指すケースが多く見られます。
違いとして、提案書はプロジェクトのさっくりとした方向性を示すもの、企画書は具体的なプランを盛り込んだものです。提案書をベースに顧客や社内で協議を行い、具体性を持たせてきっちりと書面化したものが企画書といえます。提案書はアイデアで、企画書は実行に向けた賛同を得るための書類とも表現できます。
書き方自体に大きな違いがあるわけではないため、提案書をベースにブラッシュアップして企画書に展開するとよいでしょう。
関連記事はこちら
⇒提案書のテンプレートや構成例を紹介!相手に伝わる書き方のポイントを解説
稟議書
稟議書は、予算が必要なケース、新規取引先と契約を取り交わす必要があるケースなどで、決済を下してもらうための承認書類です。
企業によって決裁金額や会社に及ぼす影響度に応じて稟議書を回す範囲が変わります。管掌役員承認までで済む場合や、社長決済まで必要となる場合まで、社内で細かな条件規定があります。
稟議書の目的としては案件の他部署との連携や情報共有を行うことです。取締役会で検討を要する案件は、社内各部署のあらゆる観点から投資の必要性や金額の妥当性を判断する材料となります。
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
起案書
起案書は事業上の必要な決裁を得るために必要となる書類です。起案文書と表現される場合もあります。
企画書を作成して企画が承認され、事業として正式に稟議にかけるための議案を会議に諮る際に使用される書類です。企業によっては議案書と呼んでいます。自治体などの公共団体では、起案書が住民への説明責任を果たす根拠となります。
関連記事はこちら
⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介
申請書
申請書は社内向けの申請や、公的な制度利用を行いたいときに使用します。身近な例としては、経費精算や有給休暇申請などがあげられます。公的制度としては医療費控除や青色申告などが代表的な例です。
申請書は企業内で定められたルールやシステムに従って、必要情報を記入の上で申請します。承認ルートに従って書類が回り、最終承認を経て経費が支払われたり有給休暇を取得できたりします。
企画書の書き方【事前準備】
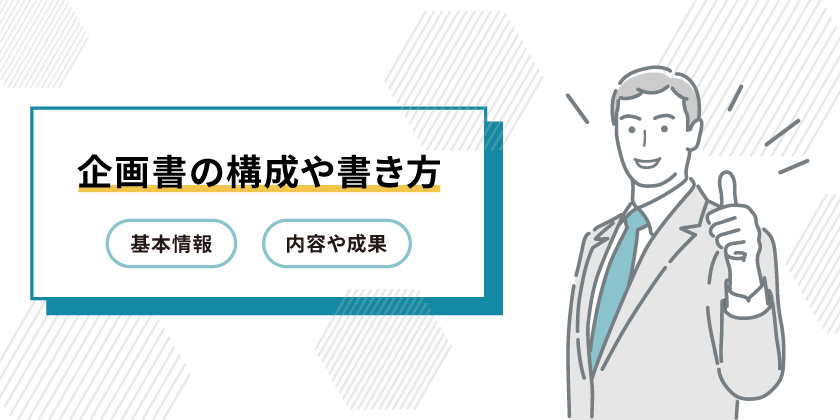
やみくもに企画書を作成しても、説得力のある内容にはなりません。「なぜこの企画が必要なのか?」を明確に示すことが大切です。ここでは、企画書に説得力を持たせるために、事前に準備しておくポイントを解説します。
企画目標・ゴールを明確にする
最初に行うことは、現状分析です。
課題や具体的な方策を検討します。同時にその方策を実行するにあたり、どのような効果が期待できるか、金額的な目安とスケジュールはどの程度なのかといった概要もまとめましょう。
情報の収集、分析
プロジェクトの成功の鍵を握るポイントは、リサーチを含めた徹底的な情報収集です。関係者、特にステークホルダーが疑問を抱かないように、信頼性の高い情報を集めましょう。
収集した情報をしっかりと分析し、立案したプロジェクトを数字的に裏付けていきます。リサーチして情報を集めて分析をし、疑問点があればその答えが得られる情報を探して分析します。このようなサイクルを回すことで、プロジェクトの方向性や目標の妥当性が定まります。
ターゲットを明確にする
目標が定まったら、ターゲットを選定します。
ターゲットは社内の役員や社外の顧客など企画によってさまざまです。ターゲットが明確でないと、企画案自体がぼんやりしたものになって説得力を失います。
ターゲットと同時に、企画運営の主体もはっきりさせます。プロジェクトを進める主体をターゲットに向けて明示することも大切です。
企画書の書き方【主な構成】
企画書には書き方のテクニック、つまり構成に関するポイントがあります。必要となる要素と順番をしっかりと頭に入れて構成しましょう。ここからは、企画書の構成作成のポイントを紹介します。
サマリーと基本情報
タイトルの次ページには、サマリー、つまり要約を書きます。エグゼクティブサマリーとも呼ばれ、企画書の導入部にあたります。
サマリーはとても重要です。いきなりディテールを書いても、なかなか興味を持って読んでもらえません。ひと目で関心を引くような、関係者に読み進めてもらえるよう説得力のある文章を心がけましょう。サマリーに企画によって得られる結果を書いておくと、より関心を持ってもらえます。
また、サマリーのあとは、目標や予算、スケジュールなどの基本情報を記載しましょう。
企画の背景と現状分析
企画の冒頭で、企画の背景を説明しましょう。「なぜこの企画を提案するか」を現状分析とともに示します。企画背景にストーリー性があると、理解しやすく納得感が高まるでしょう。
現状分析にはSWATや3C4Cなどのフレームワークの使用をおすすめします。客観的な視点が加わり説得力が増すでしょう。
また、数値で表せるものは数値化し、図やグラフも使用すると資料としての価値が高まります。
企画の具体的な内容
プロジェクトの目的に合わせて、企画の具体的な内容を記述します。
コンセプト、ターゲット、プロセス、ツールを明確にすることが重要です。頭文字をとってCTPTとも呼ばれ、この4項目に沿って現状分析や課題認識をすると、解決策を明示しやすくなります。
訴求する相手や製品、サービスを決めて、CTPTを通じて抽出された課題に対する具体的な施策を記述すると、提示する企画に対する理解度が深まるでしょう。
企画で得られる成果
企画書は、提案者目線だけで書かないことが大前提です。提案される側にとっての企画の存在理由を意識しましょう。
メリットだけでなくデメリットの明記も大切です。その上で、デメリットを上回るメリットがあることを提示します。
スケジュールや収支
企画書の内容に賛同してもらえても、スケジュールとお金が曖昧だと実効性がないと判断されます。
特に、スケジュールの妥当性は企画をスタートさせるときの重要なコンセプトです。スケジュールが短いと「対応できない」と感じられてしまうでしょう。スケジュールが長いと企画の魅力が減少します。実施スケジュールは現実的かつ明確にしておきましょう。
最終的には、お金が企画の成否を分けます。営業からは「いくら売上が上がるのか?」管理からは「どれだけ費用削減につながるのか?」を問われます。費用対効果、いわゆるROIを算出し、収支を分かりやすく記載しましょう。
「ヒト・モノ・カネ」に代表されるリソース分配も、合わせて示しておきます。
企画書に説得力を与えるポイント
企画書の説得力を高めるための、テクニカルなポイントを確認しましょう。文章のわかりやすさや文字の大きさも大切ですが、数値やグラフなどのビジュアルも大切です。読んで分かるだけではなく、見て分かる企画書づくりを目指しましょう。
フレームワークの活用
フレームワークの活用は企画書の説得力を上げます。フレームワークはビジネスや業務の分析を行い、課題解決に結びつける方策です。
主なフレームワークとしては「6W2H」「3C分析」「SWOT分析」があります。3CとSWOTで課題の分析、解決を行い、6W2Hで企画書の抜け漏れをチェックするとよいでしょう。
数値データを活用して説得力を持たせる
「見るだけで分かる」ような企画書を作りたいときは、数値データの活用が効果的です。
企画実行で見込まれるインパクトや目標のほか、現状分析から課題解決後の状態まで、数値化できるものは全て数値化しましょう。プロジェクトの完成により発生する、副次的な効果(ブランディングや販売チャネル拡大など)も提示できると、企画書の説得力が増します。
ただし、業界動向や最新トレンドなど、外部データを活用するときは、データの信頼性に注意してください。自分にだけ都合のよいデータにならないよう気をつけましょう。
シンプルな内容にする
企画書は「シンプル・イズ・ベスト」です。フレームワークに従って簡潔にかつ分かりやすい構成を心がけましょう。
企画書の情報量を多くするために、あまり必要のない内容を盛り込むことは逆効果です。ページ数が多い企画書は飛ばし読みされやすく、複雑な内容は読むモチベーションを下げるでしょう。
また、専門職にしかわからない用語での記載は避けましょう。誰にでも伝わるように、噛み砕いた表現を心がけます。
デザインや文字・行間を整える
読みやすさや見やすさにも心がけてください。文字が小さ過ぎないか、読む必要あるポイントはどこなのかなど、ページ全体のデザインに配慮しましょう。
ワークフローは図で、数値はグラフで表示すると、読みやすくなります。数値データは、流れの中でポイントとなる値だけを記載します。
テンプレートを活用する
企画書の一からの作成は大変な作業です。企画書に慣れるまでは、テンプレートを活用するとよいでしょう。
インターネット上ではさまざまなテンプレートが配布されているため、作成したい企画に向いたものを選んで活用します。社内でこれまでに作られた企画書のデータがあれば、そのフォーマットの利用もおすすめです。
企画書のためのテンプレート
企画書のテンプレートを用意しているサイトは複数あります。ここでは代表的なテンプレートサイトを紹介します。
Microsoft
Microsoftは正式テンプレートを自社サイトで公開しています。
さまざまなシチュエーションのテンプレートが配布されているので、検索して自分の目的に合ったテンプレートを探してみましょう。この正式テンプレート集には2つのソフトウェのほかに、「Excel」や「Forms」など同社製品向けのテンプレートも数多くアップされています。
参考
⇒Excelの無料テンプレート
Word
企画書作成でよく使用されるMicrosoftのWordです。Wordで企画書を作成するメリットは、簡潔で分かりやすい点にあります。特にシンプルな企画書を作成するのに向いています。
企画書にWordを使用する場合、A4用紙1枚で完結させるというケースが多い印象です。シート1枚なので、画面上でも印刷しても見やすくなります。出先での営業提案などの企画提案に重宝するでしょう。ペラ1枚なので、どれだけ重要ポイントに絞って表現できるかが腕の見せ所です。
PowerPoint
おそらく、日本でもっとも一般的に企画書作成に使用されているソフトウェアがMicrosoftのPowerPointでしょう。グラフや写真、図解など自由にビジュアル要素を組み入れ、動画を挿入することも可能です。見栄えのする企画書を作るにはうってつけだといえます。
Wordとは対照的に複数枚で構成され、提出先の理解を深めたり、じっくり議論する資料として向いています。各種要素を入れるのが容易なので、煩雑な資料にならないよう気をつけましょう。
ワークフローを導入して企画書をフォーマット化しよう
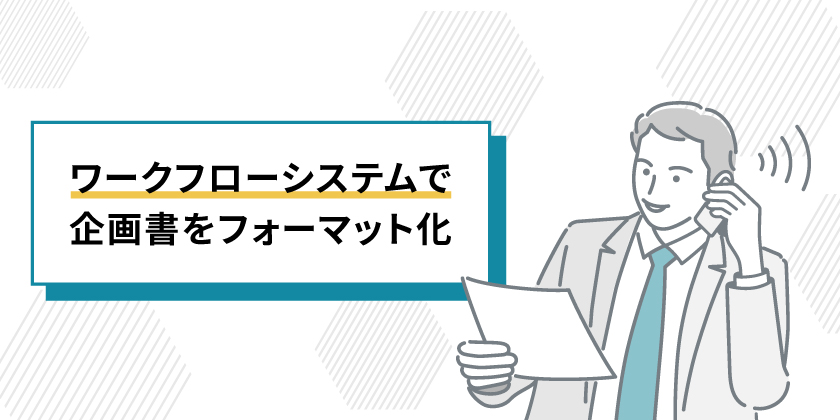
企画書は企画する人の想いが反映され、それゆえに、自分のスタイルで作る傾向があります。しかし、仕様にばらつきが生じると、多くの社員から企画提案を受ける経営陣にとっては、要点が理解しにくくなります。
そこでお勧めしたいものがワークフローの導入です。ワークフローを使って企画書をフォーマット化すれば、提案を受ける側がどこを見ればよいのかを直感的に理解できます。作成側も一から書類を作成する手間を省けます。
企画書以外の書類もフォーマット化でき、業務全体の効率アップにもつながるでしょう。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
まとめ
説得力のある企画書を作成するには、数字面での根拠とゴールの明確化が重要です。企画者が企画書の内容に集中して取り組むためには、ワークフローシステムのようなツールも検討しましょう。
株式会社コラボスタイルから、「コラボフロー」というワークフローが提供されています。サイトには書類作成ノウハウを盛り込んだコラムを多く発信しているので、企画書作成時にお役立てください。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
⇒書類の電子化とは?導入前後で知りたいポイントや導入ステップを解説
⇒帳票とは?帳票の種類から作成手順、効率化まで解説