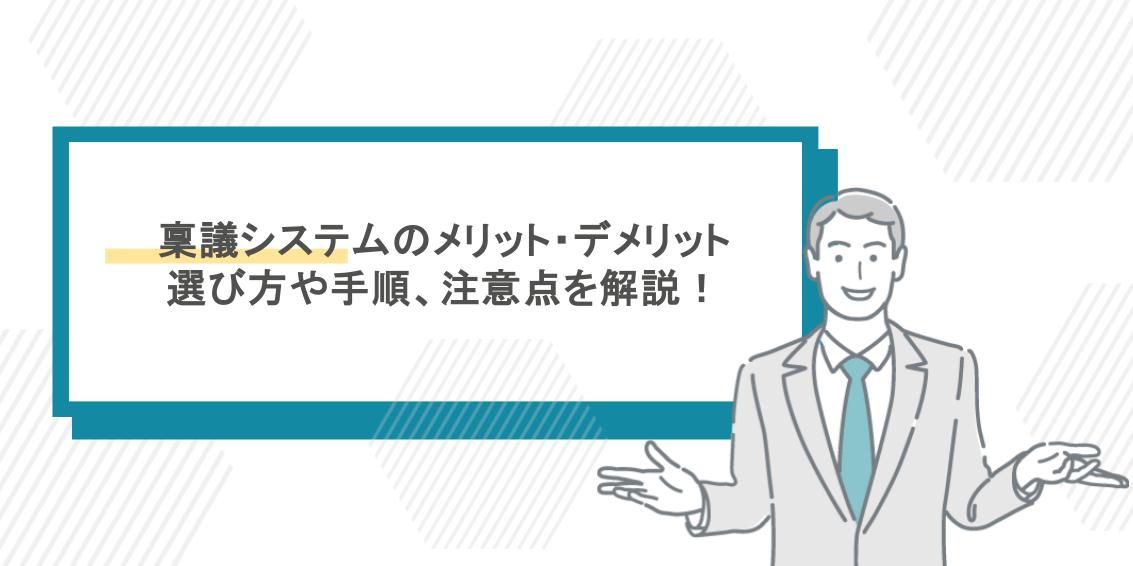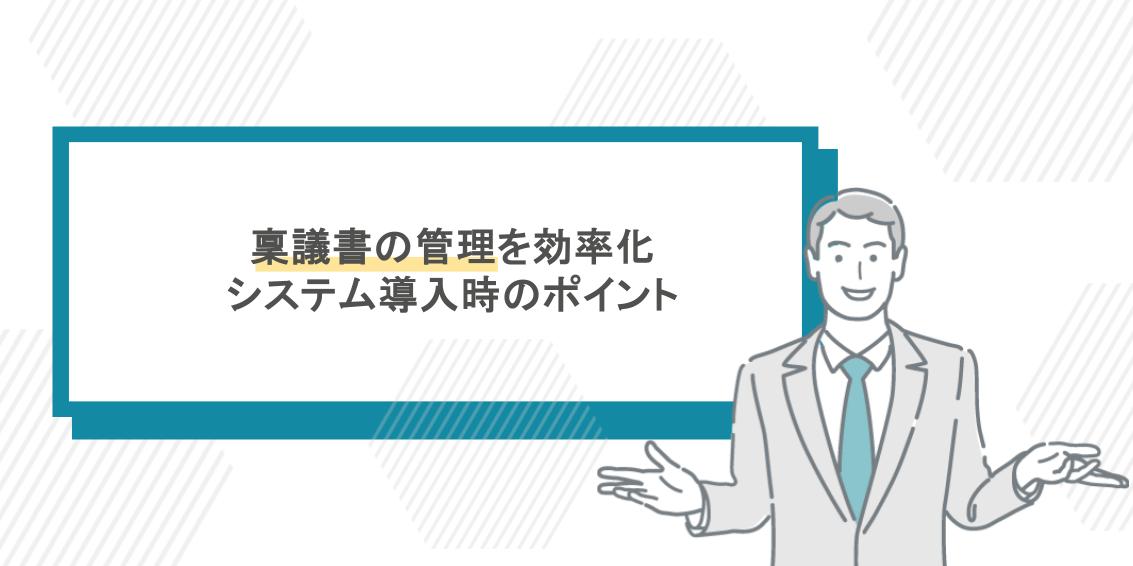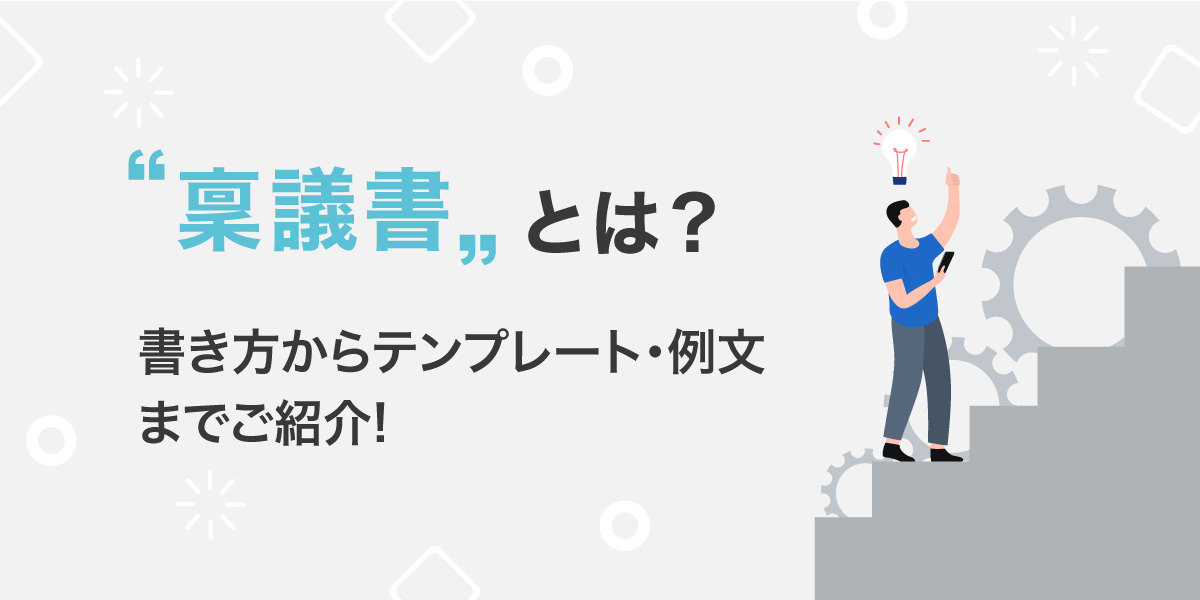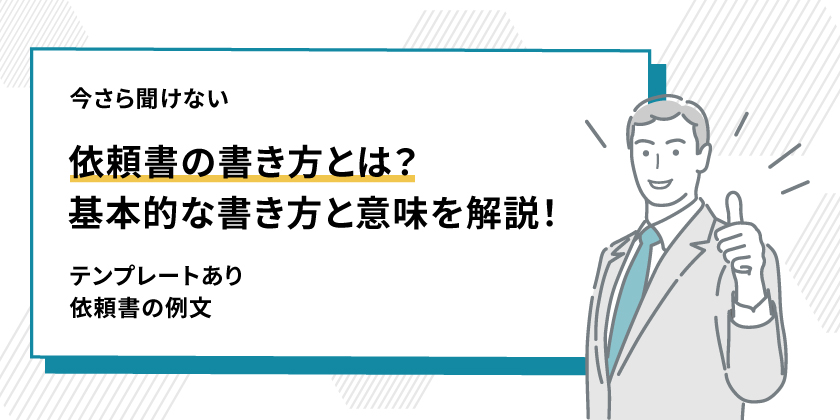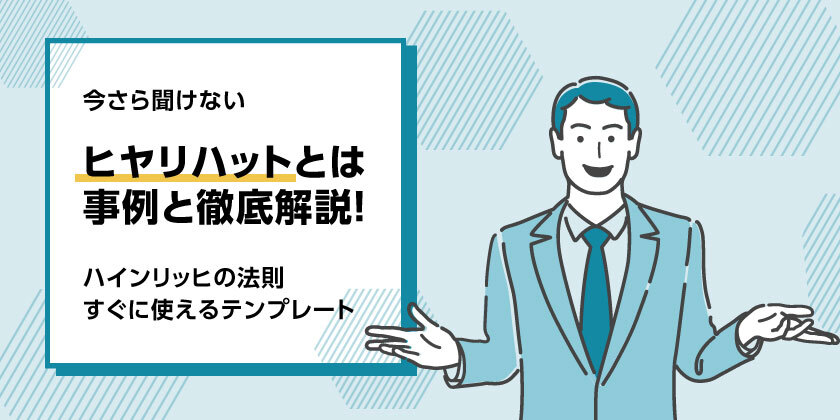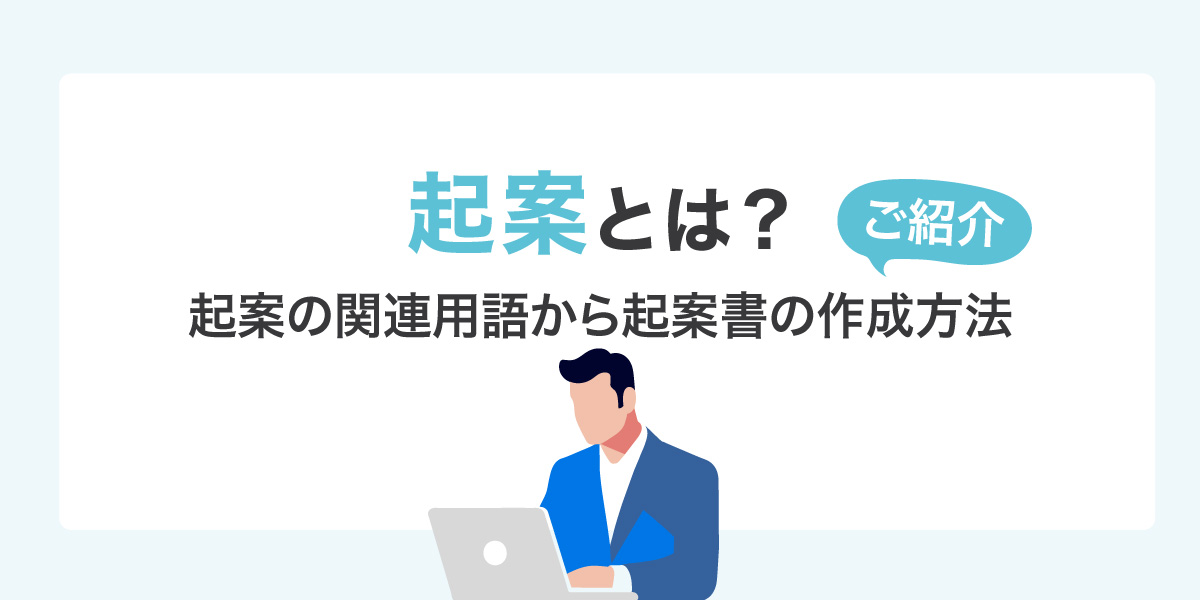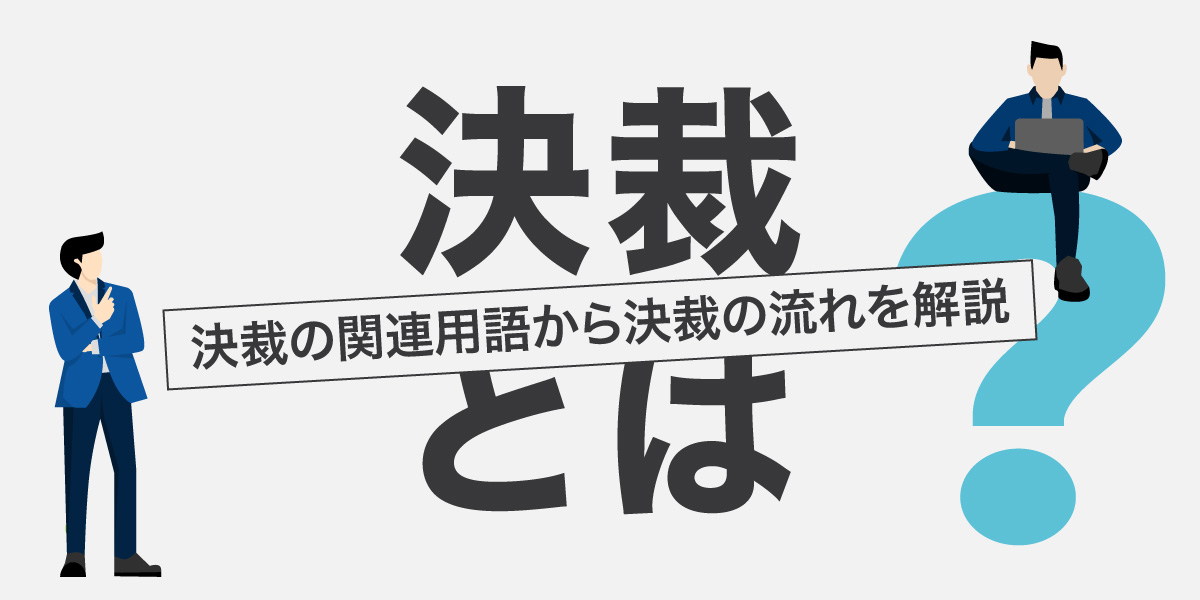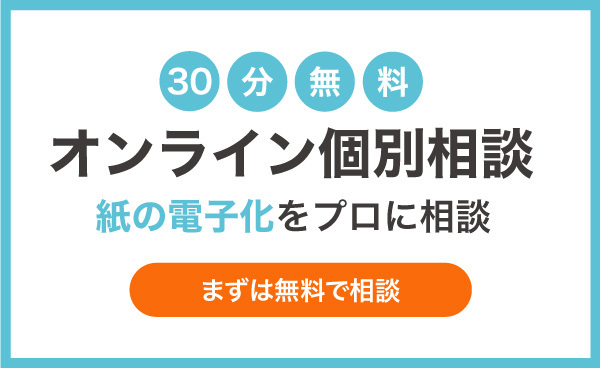この記事の目次
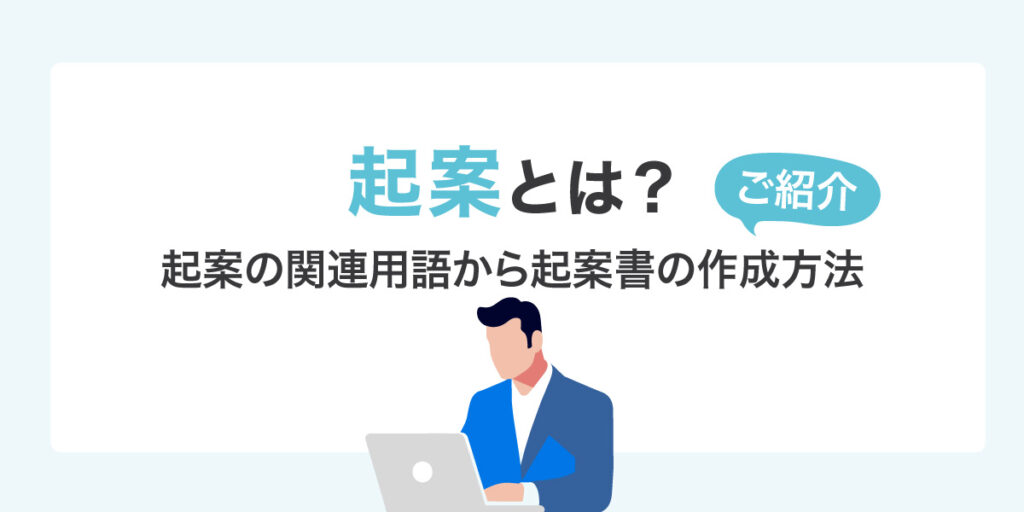
会社や組織の中で、「起案」という言葉を耳にすることがあります。
起案とは、ビジネスにおいて成功を収めるための重要なプロセスです。
起案は、問題の発見や新たなアイデアの提案など、具体的な行動に繋がる重要なプロセスです。この記事では、起案の重要性や効果的な手法について解説します。
起案は、さまざまな状況や目的で活用されます。新しい製品やサービスの開発、市場展開の戦略策定、業務プロセスの改善など、ビジネスにおけるあらゆる領域で起案が求められます。
起案とは
起案とは、特定の課題や目標に対して解決策や計画を提案し、実行に移すための一連の手続きを指します。企業や組織が成長していくために、効果的な起案が不可欠です。
起案書などを作成し、回覧させることでプロジェクトを円滑に進めることもできます。
起案は、さまざまな状況や目的で活用されます。新しい製品やサービスの開発、市場展開の戦略策定、業務プロセスの改善など、ビジネスにおけるあらゆる領域で起案が求められます。
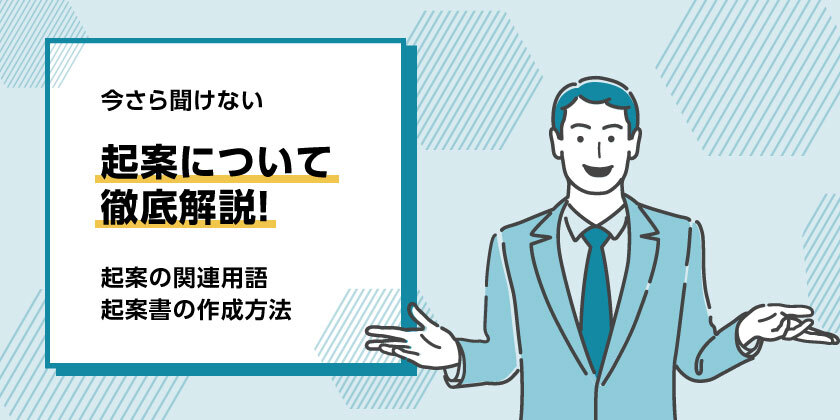
起案と似た意味の言葉や関連用語
・提案
特定の課題に対して解決策やアイデアを提示することです。相手を説得し合意を得ることを目指します。
・企画
目標達成のための計画やアイデアを立てることです。事業やプロジェクトの基盤となり、成功への道筋を示します。
・計画
目標達成のための手段やスケジュールを策定することです。具体的な目標やタスク、役割を明確にし、実行に向けた戦略を立てます。
・案出し
問題解決やアイデア発掘のためにアイデアを出すことです。自由な発想とグループディスカッションが重要です。
・発案
新たなアイデアやコンセプトを思いつくことです。創造力と洞察力によって問題解決や価値創造につながります。
・立案
計画や戦略を立てることです。具体的な手順や責任を示し、実現可能なビジョンを描きます。
起案書とは
起案書とは、起案者が考えたアイデアや解決策、プロジェクトの詳細な説明や実施計画、費用対効果の分析などをまとめた文書です。
起案書は、起案者自身がアイデアを整理し、他の関係者に対してプレゼンテーションするための資料として利用されます。また、起案書は実行のためのロードマップとして機能し、プロジェクトの進行管理や成果の評価にも活用されます。
起案書に記載する内容
起案書に記載する内容ついて解説します。
起案書を書く際には以下のような流れが一般的です。
・背景と目的の明確化
起案書の冒頭には、背景と目的を明確に述べることが重要です。目的が定まっていないと、読む人が混乱してしまいます。
起案書の目的は、新しいアイデアやプロジェクトを提案することにあります。そのため、どのような問題点を解決しようとしているのか、どのような効果を期待しているのかを明確にすることが必要です。
・目標とアプローチの設定
起案書では、達成すべき目標とそのためのアプローチを設定します。目標は具体的で計量的な指標として表現し、アプローチは目標達成のための戦略や手法を示します。
・調査と分析の実施
起案書を作成する前に、関連データや情報を収集し、分析を行います。市場調査、競合分析、顧客ニーズの把握など、必要な情報を適切に整理します。この情報は起案の根拠や裏付けとなります。
・行動計画(アクションプラン)の作成
行動計画は、具体的なタスクや実施する内容のリストです。目標を達成するためのステップやスケジュールを明確に示し、責任者や担当者、期限を記載します。
・リスクと課題の評価
起案書では、リスクや課題に対する評価も行います。可能性のあるリスクや課題を洗い出し、それに対する対策やリスクマネジメントの手法まで考慮します。
・予算とリターンの評価
起案書には、必要な予算や予測されるリターンも含めることが重要です。予算の設定やROI(投資利益率)の評価を行い、経済的な面も考慮に入れます。
・結論と推奨事項
最後に、起案書の結論と具体的な推奨事項をまとめます。起案の結果や予測される成果、さらなる調査や検討が必要な場合にはそれを明示します。
以上が一般的な起案書に記載する必要がある内容です。
起案書を書く時のポイント
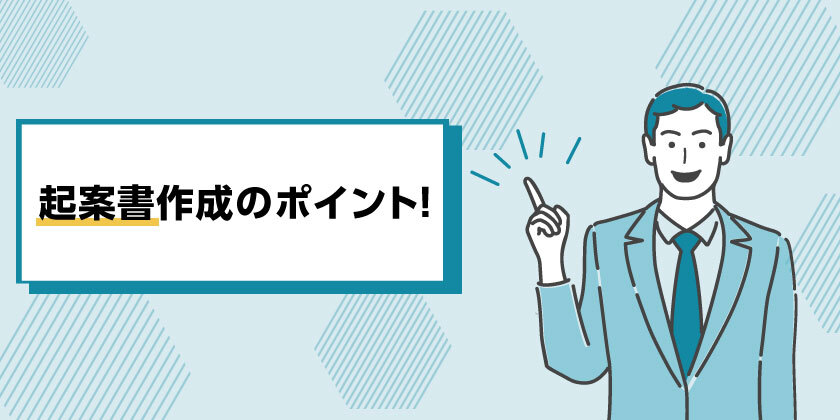
起案書を書く際のポイントは以下の通りです。あらためてポイントをしっかりと抑えておきましょう。
・背景を説明する
起案書は、新しいアイデアやプロジェクトを提案するものであるため、その背景を説明することが必要です。なぜそのアイデアやプロジェクトが必要なのか、どのような問題があるのか、それをどのように解決するのかを具体的に説明する必要があります。
・提案内容を具体的に説明する
起案書には、提案内容を具体的に説明することが必要です。具体的な提案内容を示すことで、読む人にイメージを持ってもらいやすくなります。提案内容には、どのような手順で進めるのか、どのような結果を得ることができるのか、必要な予算や人員は何人必要なのかなど、詳細な情報を盛り込むようにしましょう。
・参考文献やデータを引用する
起案書には、提案内容を裏付けるための参考文献やデータを引用することが必要です。引用する文献やデータは、信頼性の高いものを選ぶようにしましょう。また、引用した文献やデータについては、出典を明確に記載することが大切です。
・わかりやすくまとめる
起案書は、多くの人に読まれることを前提に書かれます。そのため、わかりやすい文章にまとめることが必要です。簡潔かつ明確に書くようにしましょう。また、図表やグラフを活用して、視覚的にわかりやすくすることも重要です。
起案者の意味と役割
起案者とは、起案をこれから行う人、もしくは起案を行った人を指します。起案書を作成する者が起案者です。
起案者の主な役割の一つは、ビジネス上の課題や機会を特定し、それに対する解決策を考えることです。
提案されたアイデアや解決策と評価、実行計画から進行までを担う場合が多くあります。
起案者は、優先順位を考え、プロジェクトの進捗状況を監視し、必要に応じて修正や調整を行いながら、目標の達成に向けて主導的な役割を果たします。
起案者に求められる能力としては、クリエイティビティ、リーダーシップ、問題解決能力、分析力などが挙げられます。
起案者が行う作業
起案者が行うべきこととポイントを簡潔に説明します。
・ニーズの分析
起案者は、ビジネスや組織のニーズを把握するために調査やデータ収集を行います。市場動向や顧客の要望を把握し、改善や新しいアイデアの可能性を見極めることが重要です。
・目標の設定
起案者は、具体的で明確な目標を設定します。目標はSMART原則に基づいて具体的、計測可能、達成可能、リアルな期限を持つように設定することがポイントです。
・アイデアの生成
起案者は、ニーズと目標に基づいてアイデアを生成します。創造的な思考やブレインストーミングを活用し、新しい視点や斬新な解決策を見つけ出す努力が求められます。
・プランの策定
起案者は、アイデアを具体的な計画や戦略に落とし込みます。実現可能な手順やスケジュール、必要なリソースや予算などを考慮し、プランを具体化することが重要です。
・コミュニケーションと協力
起案者は、関係者とのコミュニケーションを図り、協力関係を築きます。プランやアイデアを適切に伝え、他のメンバーや上司との意見交換やフィードバックを受けることで、より良い結果を生み出すことができます。
・評価と改善
起案者は、実施後の成果や効果を評価し、必要に応じて改善策を提案します。フィードバックやデータを活用し、継続的な改善と効率化を図ることが重要です。
起案者は、ビジネスの成果や目標達成に直接的な影響を与える役割を担っています。
ニーズの把握、目標の設定、アイデアの生成、プランの策定、コミュニケーションと協力、評価と改善といったポイントを意識しながら、効果的な起案を行うことが求められます。
稟議における起案とは
起案は、新しいアイデアや提案を考え、実現するための計画や戦略を立てるプロセスです。
起案者は、ビジネスのニーズや課題を分析し、それに対する解決策や改善策を考えます。起案の成果物としては、「起案書」と呼ばれる書類があります。
稟議は、経営判断に関わる重要な業務について、上司や管理者の承認を求める手続きです。
稟議は、予算の決定、人事異動、契約の締結など、重要な意思決定に関わる際に行われます。
稟議の際に作成される書類を稟議書と言います。稟議書は、申請書とも呼ばれ、具体的な内容や理由、影響範囲、必要なものなどが明記されます。
稟議の流れの中における起案とは、稟議の初期段階を指します。
一般的な稟議の流れとして、起案→申請→回議→承認→決裁という流れがあります。稟議を通す際の起案は、特定の課題や目標に対して解決策や計画の発端と言えます。
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
⇒決裁とは?関連用語から決裁の流れまで解説
⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
起案した時の流れ
起案の流れを具体的に解説します。
・起案(提案)の準備
起案者は、起案を適切に伝えるために必要な資料やプレゼンテーションを準備します。起案書や関連するデータや情報を整理し、分かりやすく文書にまとめます。
・起案の発表
起案者は、提案を関係者や上司に対して、内容を提示します。提案前の段階で、事前にコミュニケーションを取り、根回しを行うことも重要です。
起案書やプレゼンテーション資料を回議し承認を得ます。起案した計画を進行するには理解と支持を得ることが必要です。
・起案した計画の実施
起案した提案が承認された場合、起案者は実施の計画を立てます。具体的なタスクやスケジュール、担当者の割り当てなどを明確に定め、実施に向けた準備を進めます。
起案した計画が問題なく進行するか、進捗や成果を確認し、必要に応じて問題に対処する必要があります。
・評価と改善
起案した計画を実施した後には成果の確認、評価を行います。データを残し、次の起案やプランに生かすことも重要です。
起案の電子化
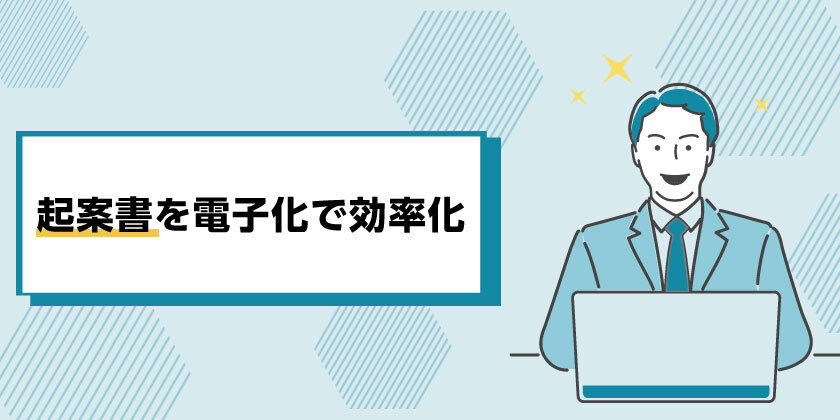
起案の電子化について解説します。
起案の電子化は、従来の紙で運用されていた起案書や文書をPC上やWEB上で、デジタル形式に変換するプロセスです。これにより、効率的な情報管理や共有が可能となります。
電子化には以下のようなメリットがあります。
・データの一元化
電子化により、起案書や関連する情報を一つの場所に集約することができます。フィルタなどのデータ検索やアクセスが容易になり、情報の一元管理が実現します。
・リアルタイムな共有と連携
電子化された起案書はオンライン上で共有できます。関係者はリアルタイムで情報を閲覧し、コメントやフィードバックを追加することができます。また、他のビジネスアプリケーションとの連携も容易になります。
・バージョン管理と履歴追跡
電子化により、起案書のバージョン管理が簡単になります。変更履歴や修正箇所の追跡も自動化され、過去のバージョンに戻ることも可能です。
・ワークフローの効率化
電子化された起案書はワークフローに組み込むことができます。承認プロセスやタスクの割り当てなどが自動化され、効率的な業務進行が実現します。
・データのセキュリティとバックアップ
電子化により、データのセキュリティ管理が強化されます。アクセス制御や権限設定を行い、機密性を確保することができます。また、定期的なバックアップを行うことでデータの保護も行えます。
起案の電子化により、効率的な情報管理や共有、業務プロセスの改善が期待できます。
ワークフローシステムなどを活用して電子化することで、業務効率化を行うことができます。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
ワークフローシステムによる効率化
起案書の効率化には、ワークフローシステムの活用を推奨しています。ワークフローシステムを活用した起案書の効率化方法をご紹介します。
・電子フォームの活用
起案書を電子フォームとして作成し、必要な情報を適切なフィールドに入力することで、手作業による入力やフォーマットの作成作業を省略できます。さらに、自動計算やデータの整合性チェックなどの機能を組み込むことで、記入漏れなどを防ぐことができ、正確性や一貫性を向上させることができます。
・承認プロセスの自動化
ワークフローシステムを活用することで、起案書の承認プロセスを自動化できます。
起案者が作成した起案書が、ワークフローシステム内で指定された承認者に自動的にルーティングされ、承認の進捗状況をリアルタイムで把握できます。これにより、承認プロセスの追跡と遅延の防止が可能となります。
・通知とリマインダー機能の活用
ワークフローシステムは通知とリマインダー機能を備えていることが多く、これを活用することで、起案書作成や承認の状況に関するリアルタイムな情報を受け取ることができます。期限の迫った起案書や承認待ちの書類について自動的に通知が送られるため、作業の効率性が向上します。
・データの集計と分析
ワークフローシステムを活用することで、起案書のデータを集計し分析することが容易になります。例えば、承認までの所要時間や担当者ごとの作業量などのデータを抽出し、プロセスの改善や効率化に役立てることができます。
まとめ:起案するときに注意すべき点
起案は組織やプロジェクトの成功に欠かせない重要な業務プロセスです。
新たなアイデアや戦略を生み出し、問題解決や成果を達成するための基盤となります。起案書のポイントを抑えて、作成に取り組みましょう。
しかし、起案だけでは十分ではありません。その後、稟議や決裁といったプロセスが続きます。
稟議は、上位の管理層や関係者に対して起案内容を説明し、承認を得る手続きです。重要な意思決定をするためには、関係者の合意と支持を確保する必要があります。
決裁は、稟議を経た上で最終的な承認を得ることです。決裁を受けることで、起案が正式に承認され、実行に移ることが可能になります。
起案、稟議、決裁を電子化して業務効率をアップすることもできます。ワークフローシステムを活用して、スムーズに業務を進めていきましょう。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。
Excelで使用している帳票や申請書を、見た目そのままWEB申請フォームを作成でき、紙からの移行も簡単に行えます。
コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。