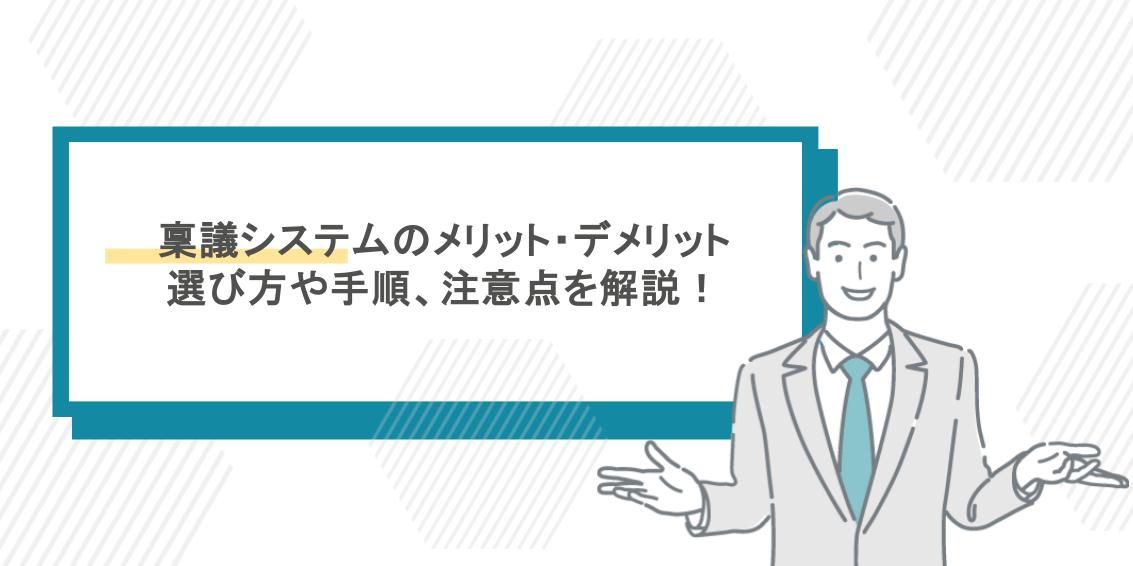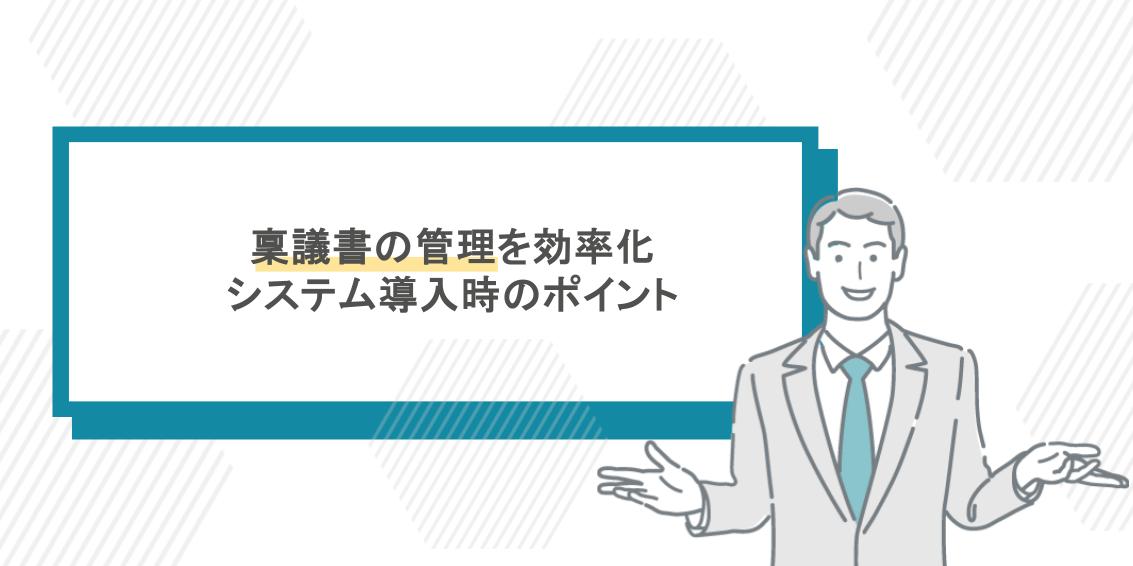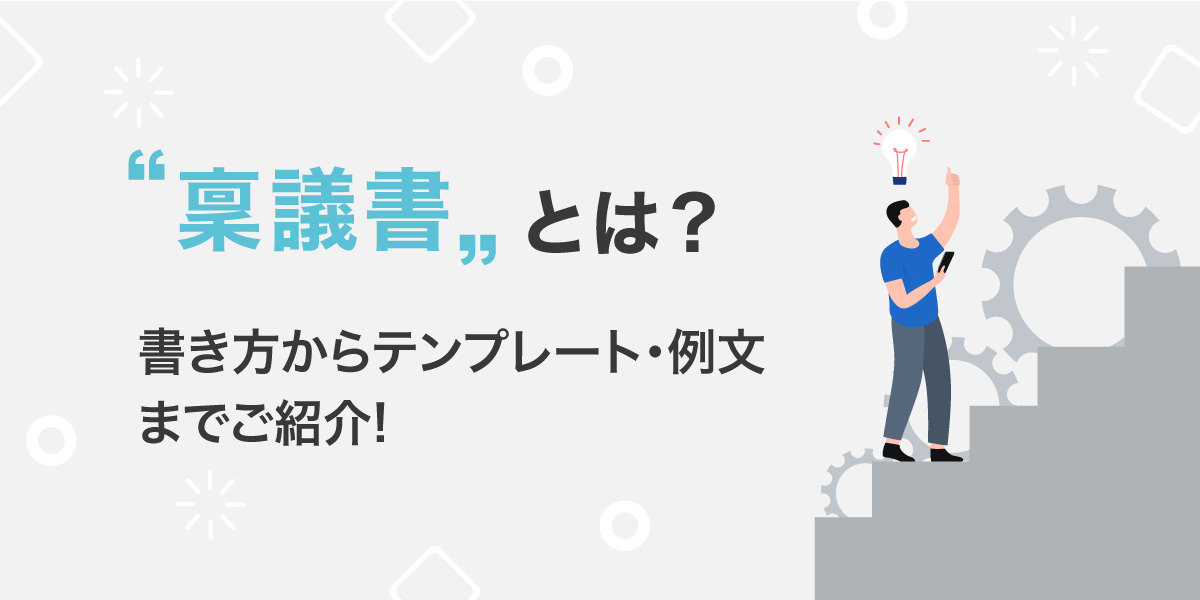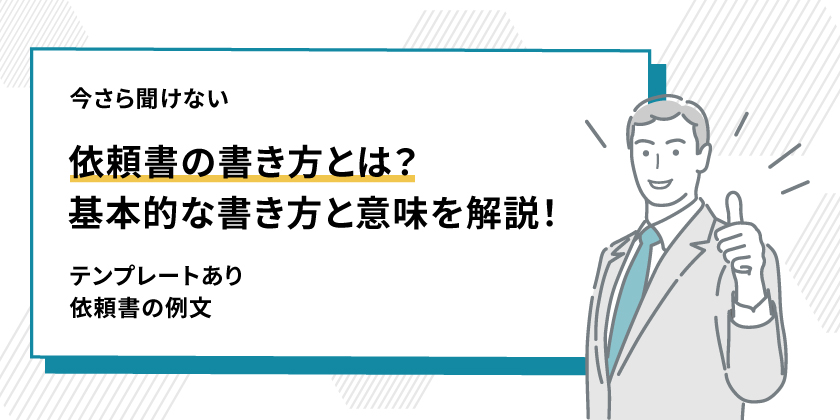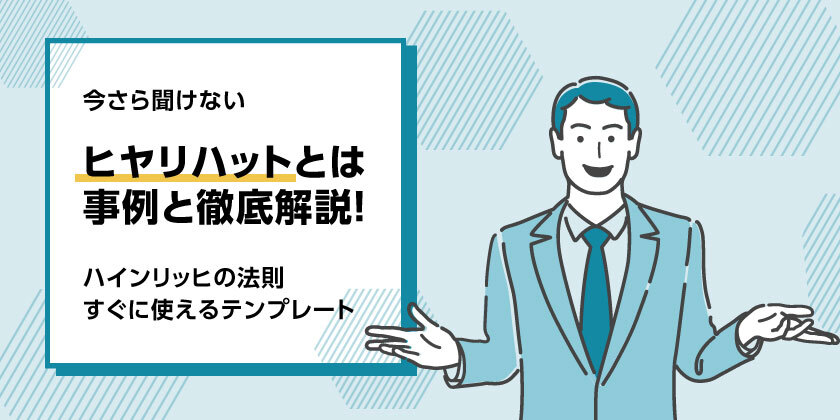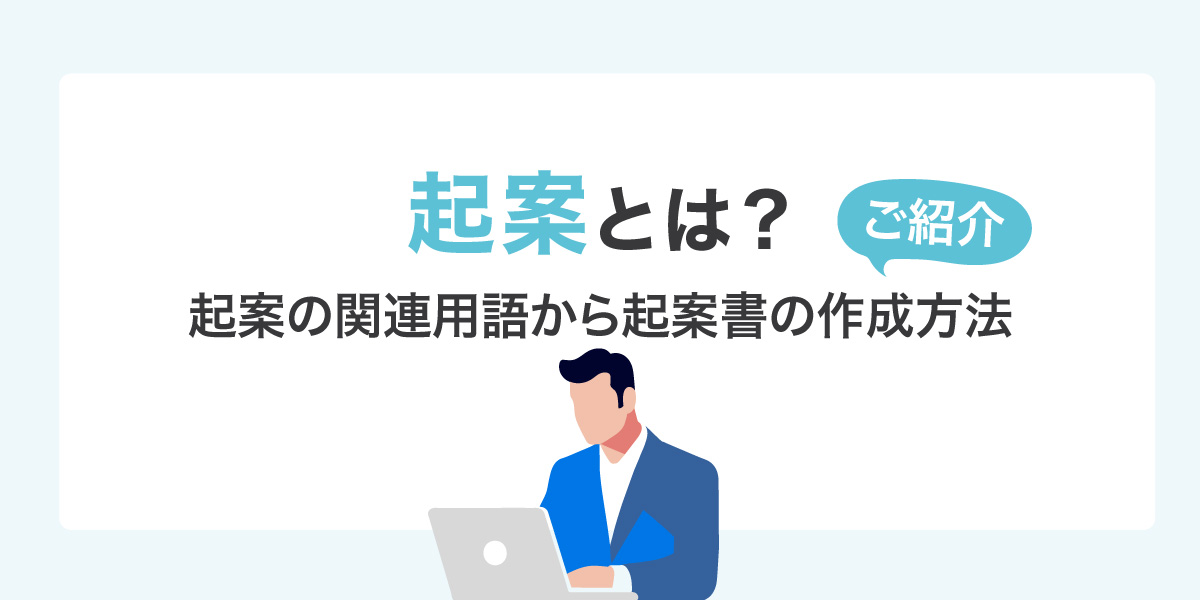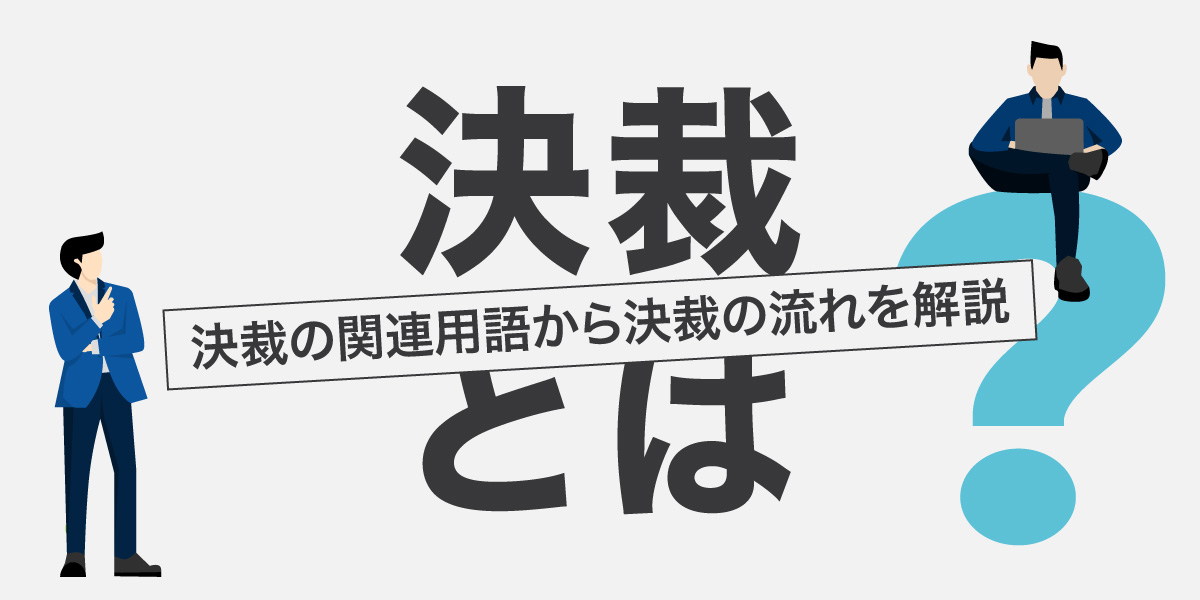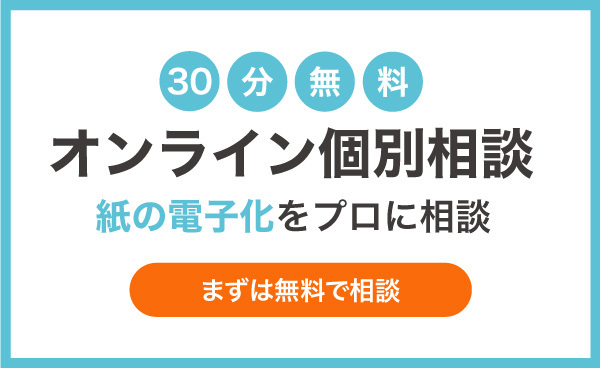この記事の目次
ペーパーレス化とは
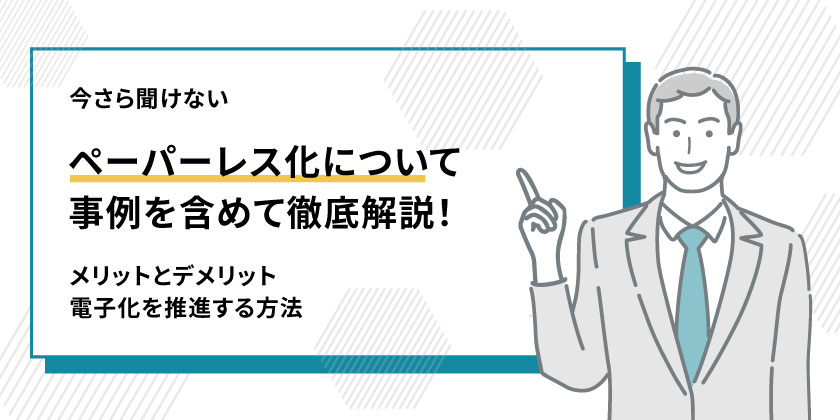
ペーパーレス化とは、紙の資料や文書を電子化して保存・活用することです。現在、働き方改革や環境保全などの背景から、国がペーパーレス化を促進しており、企業でも推進するケースが増えています。
しかし、ペーパーレス化について「どんなメリットがあるの?」「どうやって推進すればいいの?」などの疑問を抱く方も多いでしょう。
そこで、本記事では、ペーパーレス化が必要とされる理由を説明した上で、メリットや推進方法などについて、わかりやすく解説します。
ペーパーレス化とは
「ペーパーレス化」とは、紙の利用を減らし、デジタル化された資料・文書を活用することを指します。
IT技術の進歩や国による促進、法整備の進展が、ペーパーレス化推進の背景として考えられます。
ペーパーレスを推進する対象として下記が挙げられます。
- 稟議書、申請書
- 報告書や届け出
- 伝票や契約書
- 会議資料や保管書類
- 給与明細
- 販促物
なお、ペーパーレス化を実現させるには、従来のワークフローを作り直す必要があるため、社内での浸透に苦労するケースもあります。
しかし、業務効率の向上やコスト削減、環境保全などのメリットが大きいため、多くの企業がペーパーレス化に向けて積極的に取り組んでいます。
関連記事はこちら
⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
ペーパーレス化が重要視される理由
ペーパーレス化が重要視される主な理由は、下記の通りです。
- 業務効率の向上
- 環境保全
- データの安全性向上
ペーパーレス化を推進する5つのメリット
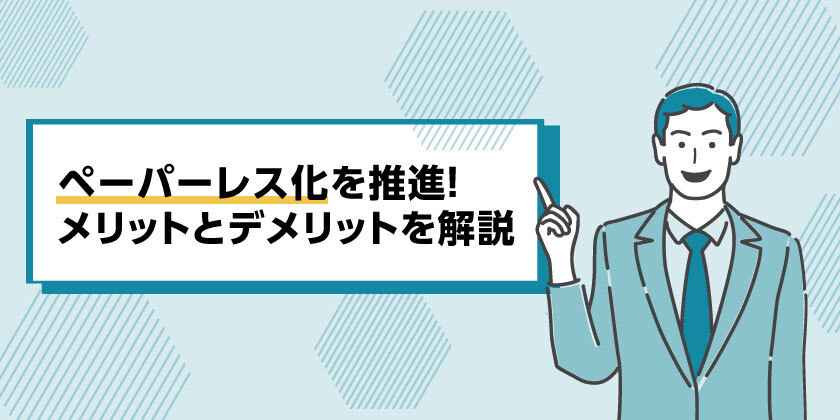
【メリット1】業務効率化により生産性の向上が見込める
紙の文書や書類をデータ化することで、情報の共有や検索が簡単になり、業務効率が向上するメリットがあります。
例えば、ペーパーレス化を推進することで、紙の書類を探す手間がなくなり、スマートフォンやパソコンから、デジタル化された書類をすぐ確認することが可能です。
これによって、従業員の工数を削減でき、業務効率化による生産性向上が見込めます。
【メリット2】紙によるセキュリティリスクを低減できる
ペーパーレス化の推進により、紙の文書の紛失や盗難リスクが減少し、セキュリティ対策が強化されるメリットがあります。
紙の資料を取り扱う場合、置き忘れや紛失などが発生する可能性があります。一方で、ペーパーレス化の場合は、資料がデータで保存されるため、物理的な紛失リスクを減らすことが可能です。
また、基本的にペーパーレス化では、セキュリティが強化されたツールやシステムを使用できます。例えば、データ暗号化やアクセス制限、定期的なセキュリティ更新など、複数の対策を行うことが可能です。
もちろん、セキュリティが強化されたツールやシステムを利用しても、サイバー攻撃のリスクはゼロではありません。しかし、クラウドストレージや専用のファイル共有システムを使うことで、不正アクセスやデータの改ざん、流出のリスクを抑えられます。
【メリット3】コスト削減により利益の向上につながる
コストの削減の実現によって利益の向上につながることも、ペーパーレス化を推進するメリットの一つです。
紙の資料を使う場合、用紙や印刷の費用がかかります。さらに、書類の保管や管理にもコストが必要です。
しかし、ペーパーレス化を推進すると、スマートフォンやパソコンだけで資料の閲覧や共有ができるため、管理コストが不要になります。その結果、企業の利益の向上にもつなげることが可能です。
【メリット4】働き方の多様化で従業員満足度の向上を図れる
ペーパーレス化を推進することで、柔軟な働き方や快適な職場環境を実現できます。その結果、従業員満足度の向上にもつながるメリットがあります。
紙を使用した業務がなくなることで、オフィス以外でも仕事ができるようになり、リモートワークを簡単に推進することが可能です。
これにより、従業員は仕事とプライベートのバランスを保ちやすくなり、ストレスを軽減できます。
また、クラウドストレージや共有のツールを使えば、リモートワークでも従業員同士で情報を簡単に共有でき、部門間の連携もスムーズになります。
【メリット5】環境保全(SDGs)で企業イメージの向上が期待できる
ペーパーレス化を推進することで環境保全(SDGs)につながり、企業イメージの向上が期待できます。
紙はもともと木材からできているため、大量に使用することは森林破壊につながる恐れがあります。しかし、データ化された資料を活用すれば、紙の資源を浪費せず、環境保全に貢献することが可能です。
その結果、環境に貢献している企業としてイメージが向上し、求職者の応募が増加したり、ESG投資(環境・社会・ガバナンスの要素を考慮した投資)を受けられたりする可能性があります。
昨今話題のSDGsでもペーパーレス化が推奨されています。環境に配慮しているイメージを定着させ、企業としてのイメージ価値を向上させることができます。イメージの向上は、企業のブランド力や持続可能な成長にも期待できるメリットがあります。
SDGsとは持続可能な開発目標と言い2001年に策定されたミレニアム開発目標の後継です。SDGsの中には17のゴールと169のターゲットがあり、ペーパーレスは(8番働きがいも経済成長も)と12番(つくる責任つかう責任)にあたります。
ペーパーレス化を推進する4つのデメリットと解決策
ペーパーレス化を推進するデメリットは、下記の通りです。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
- 初期コストやランニングコストがかかる
- 従業員への社内教育が必要になる
- 取引先や顧客への認識のすり合わせが必要になる
- 電子データのセキュリティ対策の準備が必要になる
【デメリット1】初期コストやランニングコストがかかる
ペーパーレス化を推進すると、長期的にはコスト削減が期待できますが、初期投資が大きくなることもあります。
紙を使わなくなる代わりに、パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスを支給する必要があり、一時的にコストが増えることがあるでしょう。
例えば、製造現場で紙の作業指示書やマニュアルを利用している場合、新たにタブレットやパソコンなどの端末を設置する必要があります。
また、ペーパーレス化のシステムやサービスを利用する際には一定の料金が発生するため、場合によっては、紙を使うよりもランニングコストが高くなることがあります。
そのため、ペーパーレス化を推進するときは、効果とコストのバランスを検討することが大切です。また、一度にすべての部署で推進するのではなく、小さな範囲から少しずつ進めることをおすすめします。
【デメリット2】従業員への社内教育が必要になる
ペーパーレス化を推進する場合、従業員は新しいシステムやサービスを使うことになります。これにより、従来のワークフローが大幅に変更されるため、社内教育が必要となる点に注意が必要です。
特に、電子データに不慣れな従業員が多い場合、継続的な教育が必要な場合もあります。
社内教育が不十分なまま、ペーパーレス化の推進が進行してしまうと、従業員が戸惑ってペーパーレス化に適応できず、結果的に手間がかかることがあるため注意しましょう。
また、従業員がペーパーレス化にスムーズに適応できるよう、わかりやすいマニュアルを作成したり、疑問点があれば気軽に質問できる仕組みを整備したりすることが大切です。
【デメリット3】取引先や顧客と認識のすり合わせが必要になる
取引先や顧客との打ち合わせなどで、紙の資料を使用していた場合は、ペーパーレス化することで相手側のワークフローにも影響を与える可能性があります。
そのため、ペーパーレス化を推進する際は、取引先や顧客と認識のすり合わせが必要です。
例えば、受発注方法を郵送からWebシステムに置き換える際は、同じシステムを推進してもらう必要があります。
そのため、取引先に対しても、ペーパーレス化のメリットをわかりやすく説明し、マニュアルを提供するなど、お互いにすり合わせの手間が発生することには注意が必要です。
【デメリット4】電子データのセキュリティ対策の準備が必要になる
ペーパーレス化によって電子データを取り扱う場合、情報漏えいや不正アクセスのリスクが生じる可能性があるため、セキュリティ対策が必要になります。
電子データはコピーが容易な上に劣化しないため、改ざんや削除が簡単にできる可能性があります。
そのため、情報の暗号化やアクセス権限の設定、定期的なアップデートなど、さまざまなセキュリティ対策が必要です。
また、ペーパーレス化をすることで、外部から不正アクセスされるリスクがあります。場合によっては、情報流出の発見が遅れ、取引先や顧客に迷惑がかかる可能性もあります。具体的な対策方法として、以下の実施を視野に入れましょう。
下記に加えて、従業員のセキュリティ意識を高めるためには、定期的な社内教育も大切です。
- セキュリティポリシーの策定
- 管理体制の整備
- アクセス制限の設定
- 最新セキュリティソフトの推進
ペーパーレス化を推進するためのポイント3つ
ペーパーレス化を推進するためのポイントは、下記の通りです。
- ペーパーレス化の必要性を社内周知する
- 部署・業務ごとにペーパーレス化を始める
- 適切なアクセス権限を設定する
【ポイント1】ペーパーレス化の必要性を社内周知する
ペーパーレス化を推進するためには、全従業員にペーパーレス化の必要性を周知することが大切です。
経営者や管理職だけがペーパーレス化に積極的でも、現場のスタッフに伝わらなければ社内に浸透させることはできません。
なかには、ワークフローの変更に抵抗する従業員がいる場合もあります。ペーパーレス化の必要性を理解できていなければ、推進したシステムが効果的に利用されないこともあります。
また、システムの利用に対して消極的になった場合、紙よりも生産性が低下する可能性もあります。
そのため、経営陣や管理職は従業員に対して、ペーパーレス化の必要性やメリットを明確にすることが重要です。
【ポイント2】部署・業務ごとにペーパーレス化を始める
ペーパーレス化を推進する際は、一度にすべての業務に適用するのではなく、部署や業務ごとに小さく始めるのがおすすめです。
すべての業務に一気に適用すると、修正が必要になったり、うまくいかずに取りやめになったりすることがあり、損失が大きくなる可能性があります。
例えば、オフィス業務の場合であれば、すべての部署ではなく「一つの部署」「一つの課」などから小さく始めることがおすすめです。また、製造現場であれば、始めは一つの生産ラインのみに適用しましょう。
小規模から始めて、成功した手法や改良した手法を徐々に展開することで、効率よく社内に浸透させることができます。
【ポイント3】適切なアクセス権限を設定する
ペーパーレス化を推進するには、各データに適切なアクセス権限を設定する必要があります。
アクセス権限を設定しなければ、企業の重要な情報を誰もが閲覧可能になり、情報漏えいのリスクが高まるからです。
そのため、役職や部門ごとにアクセス権限を設定し、権限によって「閲覧」や「書き込み」などの制限を付与するようにしましょう。
アクセス権限を適切に設定すれば、必要な情報を必要な人だけと共有できるので、セキュリティ対策はもちろん、業務効率化にもつながります。
ペーパーレス化を推進する方法
ペーパーレス化を推進するためのポイントは、下記の通りです。
| 方法 | 目的 |
| デジタルシステム | ・社内申請の手続きをシステム化し、印刷や決裁にかかる時間を削減したい・データの保存や共有、バックアップをしたい |
| 電子署名 | ・契約書や承認書類の署名手続きを簡素化したい・郵送や手渡しでの書類のやり取りを減らしたい |
| OCR技術 | ・紙の書類や画像からデジタルテキストに変換したい・データの検索や編集を簡単に行いたい |
| 電子化代行サービス | ・大量の紙の書類をデジタル化したいが、自社での作業が難しい・専門的な知識が必要なデータ変換がある |
前提として、ペーパーレス化は、目的ではなく手段です。そのため、ペーパーレス化を推進する際は、最初に方法を選ぶのではなく、「何を実現したいのか」という目的を明確化しましょう。
例えば、FAXを廃止して電子取引に移行したい場合は、受注システムのようにFAXに変わる仕組みやツールの推進が必要です。
一方、FAXで受信する伝票をデジタル化してペーパーレスで管理したい場合は、伝票を文字認識してデータ化できるOCR技術が適しています。
このように、目的によって適切な方法が異なるため、実現したいことを最初に明確化しましょう。
ペーパーレス化の推進にはワークフローシステムがおすすめ
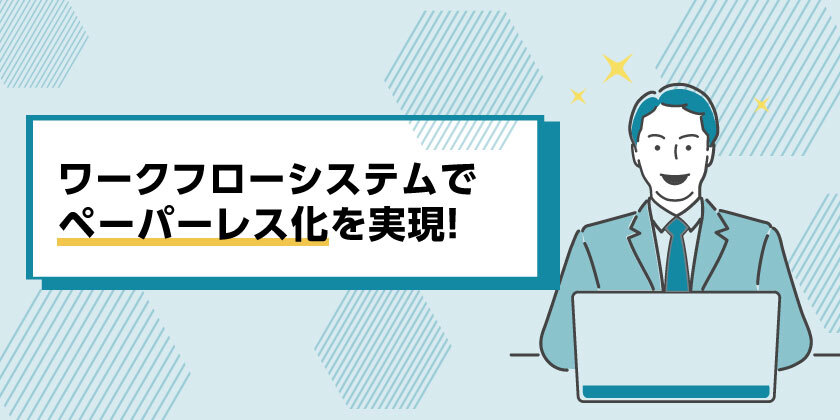
ペーパーレス化を実現するためには、ワークフローシステムの導入がおすすめです。
ワークフローシステムとは、業務の流れや手順を自動化してくれるシステムのことを指します。導入することにより、下記の効果が得られます。
- 業務効率化
- 決済時間の短縮
- 多彩なワークスタイルへの対応
- 内部統制の強化
なかでも、株式会社コラボスタイルのワークフローシステム「コラボフロー」は、直感的な操作で簡単に運用できるため、初めてペーパーレス化のシステムを導入する場合にもおすすめです。
専門的なプログラミング知識やソフトウェアは一切不要で、Excelで作成した帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換できます。
関連記事はこちら
⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
ワークフローシステムによるペーパーレス化の成功事例
今回は、ワークフローシステム「コラボフロー」導入によって、ペーパーレス化を成功させた2社の事例を紹介します。それぞれで紹介しているポイントは、以下の3点です。
- 導入までに抱えていた課題
- 削減できた紙の量
- 実現できた業務効率化の内容
株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズ様の事例
1.導入までに抱えていた課題
各担当者がローカルルールを持ち、業務が属人化していた・紙ベースの書類管理が大変で、目当ての書類を探すのに時間がかかった・業務フローが滞り、全体の業務に支障をきたしていた
2.削減できた紙の量:全体の約85%
3.実現できた業務効率化の内容
管理業務の負担が減り、目当ての書類を簡単に検索できるようになった・担当者や承認者を可視化でき、承認フローのチェックも簡単になった
人・モノ・情報の3つの面での課題
株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズ様では、紙を約85%削減し、業務効率化を実現しました。
以前は、紙とExcelを使用していたため、人・モノ・情報の3つの面で課題がありました。
- 人:各担当者がローカルルールを持ち、業務が属人化してい
- モノ:紙ベースの書類管理が困難で、必要な書類を探すのに時間がかかった
- 情報:業務フローが滞り、全体の業務に支障をきたしていた
しかし、ワークフローシステムを導入することで、紙の使用量を大幅に削減できました。それにより、管理業務の負担が軽減され、必要な書類を簡単に検索できるようになったそうです。
さらに、担当者や承認者を可視化することで、承認フローのチェックも簡単になりました。
株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズ様の成功事例については、下記の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
⇒紙ベースの運用やローカルルールの横行が問題に。コラボフロー導入で85%の紙削減と業務フローの円滑化を実現
アコム株式会社様の事例
1.導入までに抱えていた課題
社内の申請や承認手続きに関わる紙の種類が300種類ほどあった・紙を回覧すると承認を得るまでに時間がかかり、保管するにも手間がかかっていた
2.削減できた紙の量:1,000枚以上
3.実現できた業務効率化の内容
紙の書類を回覧・保管・廃棄する工数が減り、約300時間の作業時間削減に成功
帳票の電子化で業務時間を削減
アコム株式会社様では、紙の帳票を減らし、約300時間の業務時間削減に成功しました。
以前は、社内の申請や承認手続きに関する紙の種類が300種類ほどあり、非効率的でした。紙を回覧すると承認を得るまでに時間がかかり、保管にも手間がかかっていたそうです。
しかし、ワークフローシステムを導入することで、6種類の書類だけで約300時間の作業時間を削減し、年間1,000枚以上の紙を削減することができました。
さらに、紙の書類を回覧・保管・廃棄する作業も、ワークフローシステムによって簡略化できました。
なお、アコム株式会社様の成功事例については、下記の記事で詳しく紹介しているのであわせてご覧ください。
⇒紙の帳票を減らし約300時間の業務時間を削減! コラボフローの導入で業務効率化を実現
ペーパーレス化を推進する際の注意点
ペーパーレス化を推進する際の注意点は、下記の通りです。
- データのセキュリティ対策を徹底する
- 定期的にバックアップを実施する
- 法規制とコンプライアンスを遵守する
【注意点1】データのセキュリティ対策を徹底する
ペーパーレス化に伴う電子データの利用・保管には、徹底したセキュリティ対策が必要です。
電子データの利用は便利な反面、不正アクセスや情報漏洩のリスクを抱えており、下記のような手口があります。
- ブルートフォースアタック:すべての文字列を組み合わせてログインを試みる
- 辞書攻撃:パスワードに使用されやすい単語を組み合わせてログインを試みる
機密情報の保護と情報流出を防ぐためには、適切なセキュリティ対策を行うことが大切です。
なお、基本的にベンダー企業が提供するツールやシステムでは、セキュリティ対策が徹底されています。不正アクセスや情報漏えいのリスクが少なく、運用・保守コストもかからないため、おすすめです。
【注意点2】定期的にバックアップを実施する
セキュリティ対策を万全にしていても、データの紛失や破損リスクを完全に防ぐことはできません。そのため、定期的なバックアップが非常に重要です。
例えば、自然災害が発生し、データを保管していたサーバーが物理的に破損したり、従業員の誤操作によって重要なデータが削除されたりすることもあります。
このような事態に備えて、クラウドストレージや外部デバイスを利用して、データを複数の場所にバックアップすることがおすすめです。これにより、データの復元が可能になります。
【注意点3】法規制とコンプライアンスを遵守する
ペーパーレス化によって電子化された書類は、法規制や業界のコンプライアンス基準に従って、保管・運用する必要があります。
特に、個人情報を含む機密情報には厳しいルールが適用される場合も多いため、取り扱いには注意が必要です。
例えば、ペーパーレス化に関する法律として、下記内容があります。
- 改正電子帳簿保存法
- e-文書法について
改正電子帳簿保存法
改正電子帳簿保存法は、2022年1月1日から施行された法律です。従来の電子帳簿保存法と比べると、要件が緩和されました。改正に関する重要なポイントは下記の通りです。
- 電子保存・スキャナ保存で必要だった事前承認が不要になった
- スキャナ保存におけるタイムスタンプ要件が緩和され、適正事務処理要件が廃止された
- 検索要件が緩和された ・電子取引の書面保存が認められなくなり、電子保存が義務化された
これらの改正ポイントに対応する方法として、下記の内容が挙げられます。
- 検索要件に対応したシステムを利用する
- ダウンロード可能な状態にしてファイル名で運用する
- 検索しやすい索引を作成する
(※)令和5年(2023年)12月31日までの期間で行われる電子取引は、やむを得ない事情があると認められた場合に限り、電子データの出力書面を保存することができる緩和措置が設けられています。
e-文書法について
e-文書法(※)は、紙ではなく電磁的記録による文書の保存を認める法律です。電子保存をするにあたって、以下の対応が求められています。
- 見読性:パソコンのディスプレイに表示するなど、求めに応じてすぐに表示できる状態にする
- 安全性:アクセスや修正などのログを残したりタイムスタンプを付与したりする
- 機密性:アクセス権限を設定して、パスワード管理を徹底する
- 検索性:保存された情報を検索できるように体系化する
また、電子帳簿保存法との違いは下記の通りです。
| 違い | e-文書法 | 電子帳簿保存法 |
| 対象となる文書 | 会社法や商法などに基づき、民間企業において保存義務のある法定文書 | 財務省と国税庁が管轄する法律に関する文書 |
| 対象となる文書の例 | ・各種帳簿類・議事録・注文書・見積書 など | ・総勘定元帳・賃借対照表・損益計算書・納品書 など |
| 文書保存のための要件 | ・見読性・安全性・機密性・検索性対象文書によって保存要件が定められている | ・真実性の確保・関係書類の備付け・見読可能性の確保・検索機能の 確保 |
どちらもペーパーレス化の推進にあたって重要な法律であるため、しっかりと確認しておきましょう。
(※)正式名称は「民間事業者などが行う書面の保存などにおける情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者などが行う書面の保存などにおける情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律」
まとめ:ペーパーレス化を実現して業務効率化を実現
ペーパーレス化を効率よく推進するためには、目的を明確にしてからツールやシステムを導入し、企業が一丸となって取り組むことが大切です。まずは小さい範囲から推進を始め、段階的に社内全体へ浸透させることにより、業務効率化の実現を図りましょう。
また、ペーパーレス化を推進する際は「ワークフローシステム」の導入をおすすめします。業務の流れや手順を自動化してくれ、業務効率化や決裁時間の短縮などの効果を得ることが可能です。
ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。