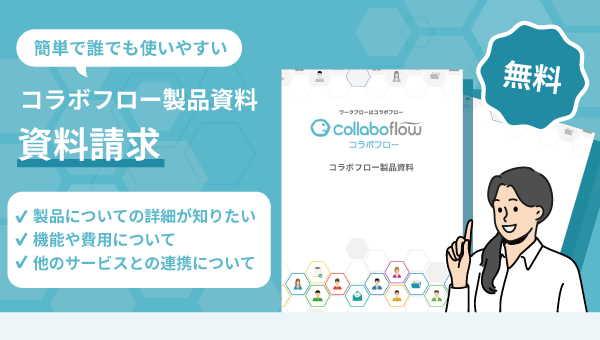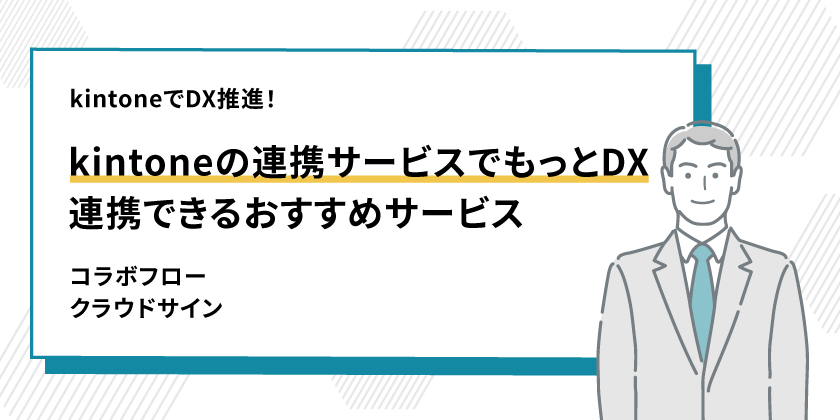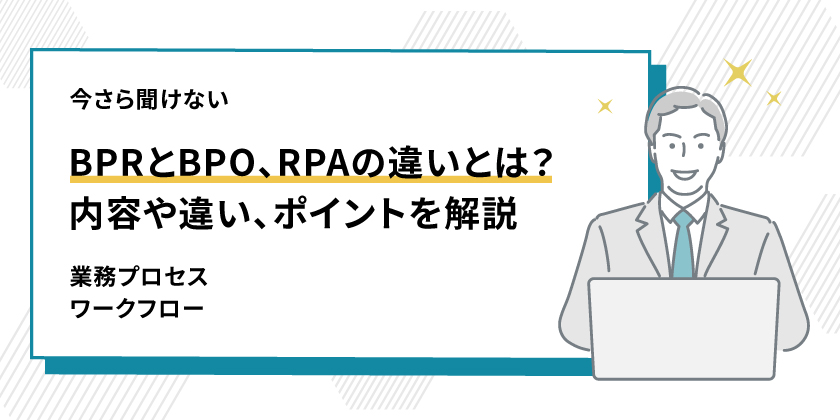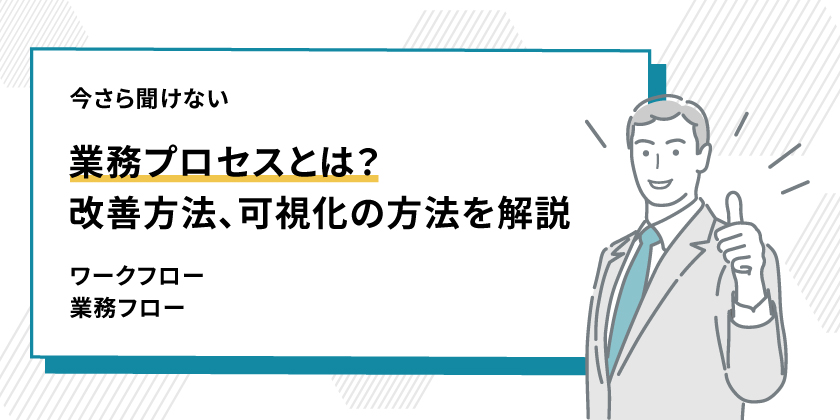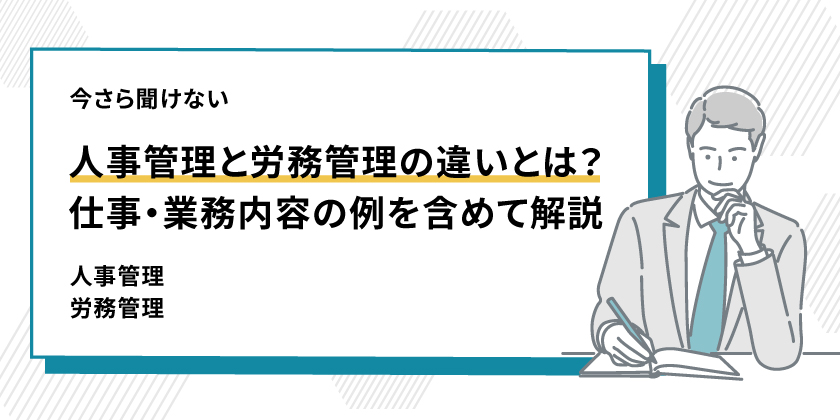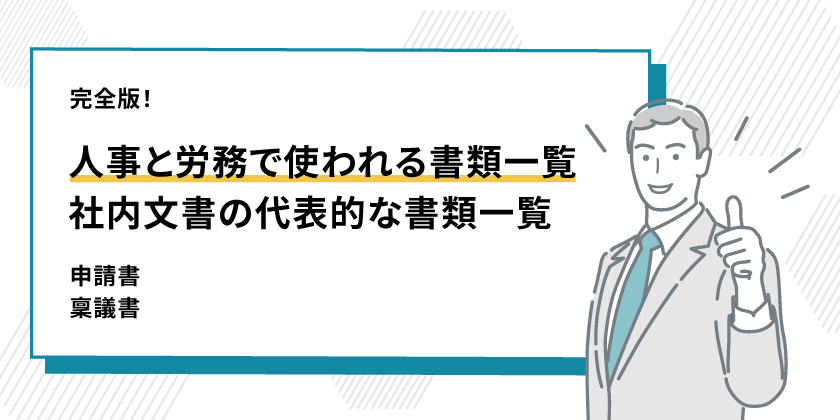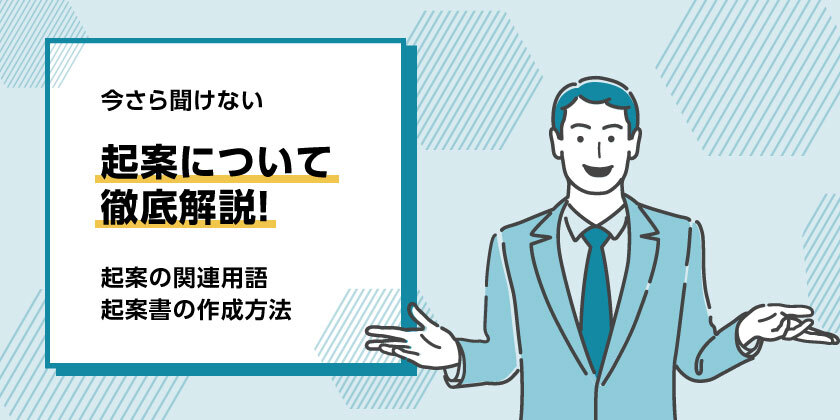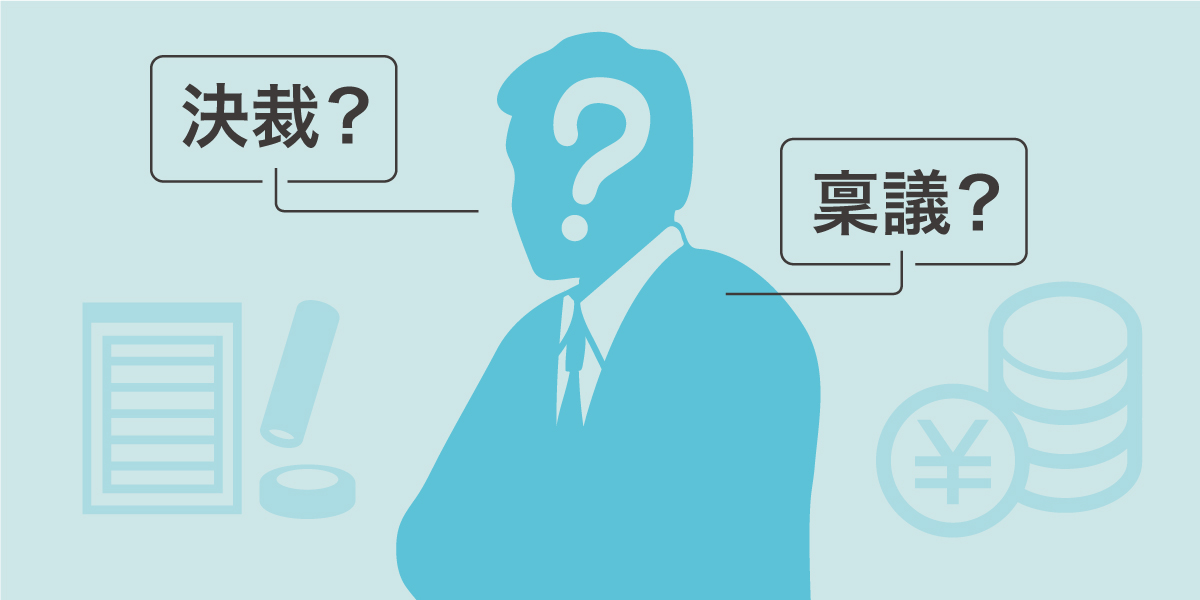この記事の目次
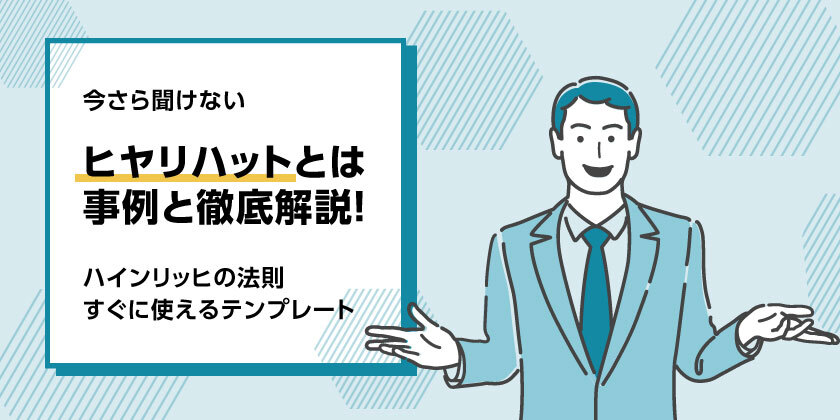
ヒヤリハットとは、危険なことが起こったものの、幸い事故や災害には至らなかった事象のことを指します。
事故の予兆とも言える事象であるため、対策が遅れると重大な事故や災害につながる恐れがあります。
「ヒヤリハット対策の方法を知りたい」「ヒヤリハットの報告を社内に定着させるためにはどうすればいい?」とお考えの方に向けて、本記事では、ヒヤリハットが起きる原因や報告書を作成するときのポイント、ヒヤリハットの報告を社内に定着させるコツについて解説していきます。
従業員が積極的にヒヤリハット報告をするための方法を知り、社内で事故の発生を未然に防止できるようにしましょう。
ヒヤリハットとは
ヒヤリハットとは、業務中に「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりするような危険なことが起こったものの、幸い事故や災害には至らなかった事象のことを指します。
「一歩間違えれば重大な事故だった…」というケースも多いため、日々の業務においてヒヤリハットを撲滅することが、重大な災害の未然防止につながります。
ヒヤリハットは小さなものも多いため軽視する従業員もいますが、対策してこそ重大な事故を防止できます。
ここからは、ヒヤリハットの理解をさらに深めるため、以下の内容について見ていきましょう。
・ヒヤリハット対策の重要性と「ハインリッヒの法則」
・インシデントやアクシデントとの違い
ヒヤリハット対策の重要性と「ハインリッヒの法則」
ヒヤリハットと同時に、よく扱われるのがハインリッヒの法則です。
ハインリッヒの法則は「1:29:300の法則」とも呼ばれ、事故の程度を比率化したものです。1件の重大事故の裏には、29件の軽傷事故と300件の無傷事故があると言われています。
この300件の無傷事故がヒヤリハットで、1件の重大事故を防ぐためには300件のヒヤリハットを対策するのが重要です。
重大な事故が発生した際の事後対策だけではなく、普段からヒヤリハットが発生する度に対策を打つことで、重大な事故を未然防止できます。
関連記事はこちら
⇒ハインリッヒの法則とはどのような考え方?活用する場面も紹介
インシデントやアクシデントとの違い
ヒヤリハットと同様に、重大な事故や危険な行動に関連する言葉で「インシデント」や「アクシデント」があります。それぞれの意味は、以下の通りです。
・ヒヤリハット:危険な状況が起こったが、幸い事故や災害には至らなかった場合に用いられる用語
・インシデント:何らかの問題が生じたときに用いられる用語
・アクシデント:「事故」や「災害」などを指す一般的な用語
この3つは、おもに事故発生の時間軸や体験の有無が異なります。
| 項目 | 時間軸 | 体験の有無 |
| ヒヤリハット | 発生前 | 体験している |
| インシデント | 発生前 | 体験していない場合もある |
| アクシデント | 発生後 | 体験している |
インシデントとヒヤリハットは似ていますが、ヒヤリハットは体験・発見しているのに対し、インシデントは体験・発見していない場合も含みます。そのため、誰も発生に気づいていないインシデントもあります。
また、アクシデントは、すでに発生している事故のことです。つまり、ヒヤリハットはアクシデントにつながる手前の状態であり、ヒヤリハットを対策することでアクシデントの未然防止につながります。
たとえば、ある会社で「棚の上にあるものを取るときには脚立を使う」というルールがあった場合に、新入社員がルールを知らずに椅子を使っている状態がインシデントです。
新入社員が椅子から落ちそうになったけど、事なきを得た状態がヒヤリハット、実際に落ちてケガをしてしまった状態がアクシデントになります。
ヒヤリハットが起きる原因
ヒヤリハットは、大きく下記が原因で発生します。
・ヒューマンエラー:ストレスや疲れ、焦り、慣れによる油断など
・労働環境:5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)が徹底されていない
・運用体制・制度:情報共有の徹底、ヒヤリハットの報告体制がない、安全意識の欠如
なかでも、特に運用体制・制度はとても重要です。なぜなら、しっかりした体制・制度がないとミスにつながりやすく、ヒヤリハットを招く原因となってしまうからです。
たとえば、情報共有や安全意識が欠如していると、ヒューマンエラーが起こりやすくなってしまいます。この点運用体制・制度をしっかり決めていれば、防げることも多いのではないでしょうか。
運用体制・制度をしっかりと整えるうえで重要なのが、ワークフローシステムの導入です。
ワークフローシステムとは、社内申請や承認・確認などのワークフローを効率化するシステムです。
ワークフローシステムの導入により、ヒヤリハットが発生した場合の報告・共有・対応の一連のフローが効率化され、迅速かつ正確な対応が可能になります。
なお、以下の記事でも「ワークフローシステム」に関する詳細を解説しています。気になった方は、ぜひご確認ください。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
ヒヤリハットが起きたときの基本的な対策の流れ
ヒヤリハットが発生したときの基本的な流れは、下記のとおりです。
・報告書の作成
・事案・原因の検討
・事故防止策・対策方法の策定
従業員からヒヤリハットの報告書が提出された際、安全管理の担当者は必ず事案を分析し、原因究明と対策を実施しましょう。なぜかというと、事象発生の共有と注意喚起のみでは従業員の意識に頼ることとなり、根本的な原因対策にならないからです。
注意された当初は意識していても、時間が経てば風化するため、再発する可能性があります。手間はかかりますが、意識の有無に関わらず「発生しない状況」を作り出すことが重要です。
対策としては、ワークフローシステムを活用した報告書を運用することがおすすめです。
【業界別】ヒヤリハットのよくある事例と対策
いくつかの業界におけるヒヤリハットの事例と対策を紹介します。
・製造業
・建設業
・小売業
・医療・介護業界
製造業では「装置が停止している=安全」という考えが、無意識に働きます。装置に巻き込まれると人命に関わる場合もあるため、ヒヤリハットの対策が欠かせません。順番に見ていきましょう。
【製造業】よくある事例と対策
製造業におけるヒヤリハットの事例と、対策を紹介します。
ある製造工場でのことです。
製造装置で製品が詰まり、機械が停止しました。
Aさんは「運転が完了し、機械が自動停止した」と思い込み、詰まりを除去すべくカバーを外して手を入れました。
すると、機械が突然動き出し、手が挟まれそうになったそうです。
ヒヤリハットの原因は、完全な停止を確認しなかったこととカバーを外した際に自動停止する安全装置が備わっていなかったこととされています。
上記の例では、対策としてカバーを外すと機械が停止する安全装置を取り付け、除去作業の際に停止ボタンを押すことを義務づけました。
【建設業】よくある事例と対策
建設業におけるヒヤリハットの事例と、対策を紹介します。
ある工事現場でのことです。
作業員のBさんは、高さ5mの足場を歩行中、足場板のツメがちぎれて足場が傾き、バランスを崩して転落しそうになりました。
原因は作業前の点検不足で、足場の劣化に気づけなかったことです。
上記の対策として、この現場では作業前に足場の点検をおこなうこととしました。
【小売業】よくある事例と対策
小売業におけるヒヤリハットの事例と、対策を紹介します。
あるスーパーでのことです。
Cさんは店内からバックヤードに移動するため扉を開けました。
そこにはキャスター付きの台車が置かれていたため、左足が乗ってしまい、滑って転倒しそうになりました。
原因は、台車の置く位置を扉を開けてすぐの場所に指定していたことでした。
対策としてドアの死角となる場所に台車を置かないこと、台車の置き場所を決めました。
【医療・介護業界】よくある事例と対策
医療・介護業界におけるヒヤリハットの事例と、対策を紹介します。
老人介護施設でのことです。
Dさんは起床介助の作業を始めました。施設利用者を布団から車いすに移乗するため抱えようとしたところ、無理な体勢から体を痛めそうになったそうです。
原因は、1人で作業していたことや無理な体勢のまま続行したこととされています。
そこで、無理な体勢で作業しないことや複数名で作業することを対策としました。
ヒヤリハット対策には「報告書」の活用がおすすめ
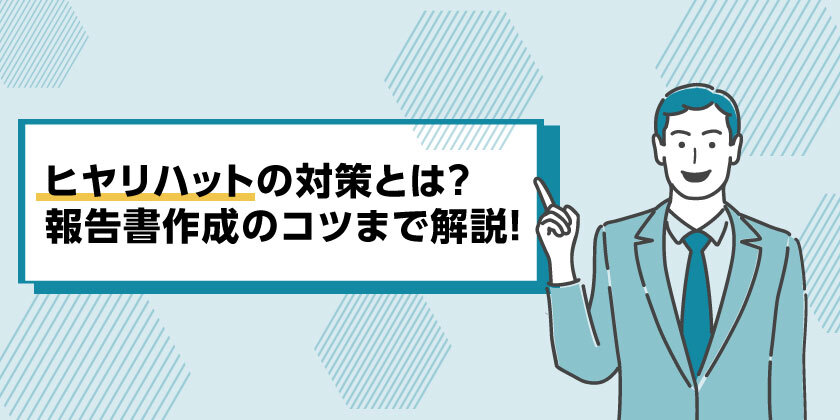
ヒヤリハット対策のためには「報告書」を活用するのがおすすめです。
報告書を活用することで、体系的にヒヤリハットの全貌が把握できる上、当時の情報の蓄積や管理にも役立ちます。
紙の報告書は管理が煩雑化しますが、データ化して取り扱えば管理や改善活動、効率化も可能です。
また、ワークフローシステムなどを活用することで、紙を電子化できます。
ヒヤリハット報告書とは
ヒヤリハット報告書とは、従業員に起きたヒヤリハットを報告するための手段です。一般的には口頭で報告するものではなく、報告書を活用して体系的にまとめます。
また、内容を一覧化したファイルを用意することで、ヒヤリハットの内容や対応の進捗状況を把握できるため、効率的な改善が可能です。
どのようなフォーマットで報告書を作成すればいいのかわからない方に向けて、報告書のテンプレートを配布しています。すぐに報告書を利用したい方は、下記をご確認ください。
書類テンプレートのダウンロードはこちら
リンクをクリックして、使いたい書類を検索してください。
⇒テンプレート一覧ページ
ワークフローシステム「コラボフロー」にアップロードして活用できるExcelテンプレートを無料で配布中
ヒヤリハット報告書を作成するときのポイント5つ
ヒヤリハット報告書を作成するときのポイントは、下記のとおりです。
ヒヤリハットが起きたらすぐに報告する
5W1Hを意識して情報をまとめる
客観的な視点で原因を考える
報告書では専門用語の使用を避ける
最悪のケースを想定し再発防止の意識を高める
報告書を作成する際は、他部署の従業員や新入社員でもわかるようにするため、専門用語の使用を避けるのがおすすめです。順番に見ていきましょう。
【ポイント1】ヒヤリハットが起きたらすぐに報告する
ヒヤリハットが起きたら、できる限りすぐに報告するようにしましょう。時間がないからと後回しにしては、記憶が曖昧になり発生時の状況を具体的に書けなくなってしまいます。
特に、発生した事象そのものは覚えていても、当時の環境や前後の行動は忘れてしまいがちです。そのため、できる限りすぐに報告書を作成することをおすすめします。
報告が遅くなればなるほど、原因を見つけたり対策を考えたりしづらくなるので、迅速に報告することが重要です。
【ポイント2】5W1Hを意識して情報をまとめる
報告書を作成する際は、5W1Hを意識することが重要です。
| いつ(When) | いつ発生したのか |
| どこで(Where) | どこで発生したのか |
| 誰が(Who) | 当事者、関係者は誰か |
| 何を(What) | 何が起こったのか |
| なぜ(Why) | 発生した背景や原因 |
| どのように(How) | どのように対応するのか |
5W1Hを意識することで、抜け漏れを防ぎつつ内容をわかりやすく伝えられます。
たとえば、下記は製造業の例です。
| いつ(When) | 14時頃 |
| どこで(Where) | 生産ラインで |
| 誰が(Who) | 自分が |
| 何を(What) | 装置に腕が挟まりそうになった |
| なぜ(Why) | 装置の完全停止を確認しなかった |
| どのように(How) | 停止ボタンを押してから対応する |
このように5W1Hで具体的に報告すると、同じような事象が発生したときに対応しやすくなります。
【ポイント3】客観的な視点で原因を考える
報告書に原因を記入する際は、主観的な視点ではなく客観的な視点で考えることが重要です。主観的な視点で報告書を書くと、本質的な原因が見えにくくなります。
たとえば「○○の作業手順は担当者が知っていて当たり前」と、担当者が悪いことにしてしまうと、教育や研修の体系見直しなどの本質的な対策にいきつきません。また犯人捜しや責任の所在を見つけることが目的となってしまうこともあります。
そのため、報告書を作成する際は、発生した事象をありのまま書くことが望ましいです。
【ポイント4】報告書では専門用語の使用を避ける
報告書を作成する際は、専門用語の使用をできる限り避けましょう。ヒヤリハットの報告書は部署内の従業員以外にも、他部署や第三者にも見られる機会があるからです。
たとえば、安全管理の担当者はそれぞれの部署の業務を正確に把握しているわけではありません。内容によっては報告書だけでは理解できないため事象を正しく確認するため直接従業員に確認する必要があり、把握に時間がかかってしまいます。
このように、専門用語を使ってしまうと、内容が正しく伝わらない恐れもあるため、できる限り誰でもわかる言葉を使いましょう。
【ポイント5】最悪のケースを想定し再発防止の意識を高める
ヒヤリハット報告書を作成する目的は、重大な事故を未然に防止することです。そのため、ヒヤリハット報告書の作成が目的となってしまっては意味がありません。
従業員には、ただ単に報告書を作成してもらうのではなく、その目的や本質を理解してもらう必要があります。
そこで、ヒヤリハット報告書を社内で回覧させることで、社内意識の向上につなげることができます。
また、ヒヤリハット報告書を社内で活用するときには、ワークフローシステムなどを活用することがおすすめです。
【テンプレート付き】ヒヤリハット報告書の書き方例
テンプレートを用いた、ヒヤリハット報告書の書き方の例を紹介します。
| 項目 | 内容 |
| 報告者 | ・名前、所属部署、報告日を記載する |
| 発生場所 | ・ヒヤリハットが発生した場所、日時、状況を記載する・詳細な現場の状況や関係者の名前、所属部署(連絡先)なども記載する |
| ヒヤリハットの内容・事象 | ・具体的に何が起こったのかを明確に記載する・事象を把握してからどのような対応をとったのかを記載する |
| ヒヤリハットの考えられる原因 | ・誰が関係していたか、何が原因だったのかを記載する |
| 発生を防ぐための対策方法・改善案 | ・どのような問題があったか、どのように改善するかなどの提案を記載する・今後、同様の事象が発生しないための対策を明確に記載する・その他の安全対策や周知徹底、トレーニングなどの提案を記載する |
| 署名と承認 | ・署名と承認の日付を記載する・ヒヤリハット報告書に署名し、承認する人物を記載する |
ここで紹介したヒヤリハット報告書のテンプレートは、下記からダウンロードできます。社内で決まったテンプレートがなかったり、使いやすいテンプレートをお探しの場合はぜひダウンロードの上、ご活用ください!
\登録いらずで無料テンプレート公開中!/
書類テンプレートのダウンロードはこちら
リンクをクリックして、使いたい書類を検索してください。
⇒テンプレート一覧ページ
ワークフローシステム「コラボフロー」にアップロードして活用できるExcelテンプレートを無料で配布中
ヒヤリハットの報告を社内に定着させる4つのコツ
ヒヤリハットの報告を社内に定着させるコツは、下記のとおりです。
従業員のモチベーションにつながる報告制度を設ける
ヒヤリハットを報告する時間を作る
定期的に安全教育をおこなう
報告書のフォーマット・申請フォームを用意する
ヒヤリハットの報告は定常業務ではないため、従業員にとっては優先度の低い業務といえます。そのため、従業員のモチベーションにつなげることが重要です。ひとつずつ見ていきましょう。
【コツ1】従業員のモチベーションにつながる報告制度を設ける
ヒヤリハット報告によって犯人捜しをしてしまうと、萎縮して報告する従業員が減る恐れがあります。
一方で、モチベーションアップにつながる制度を設けられればヒヤリハット報告が定着しやすくなるでしょう。
たとえば、ヒヤリハット報告で人事評価を上げたり奨励金を渡したりすることが挙げられます。ヒヤリハットの報告が評価のプラスになれば、積極的な報告が期待できるため、従業員のための施策を講じましょう。
【コツ2】ヒヤリハットを報告する時間を作る
ヒヤリハットの報告を定着させるために、報告する時間を作りましょう。従業員にとっては通常業務がメインとなるため、ヒヤリハット報告に時間を作ることが難しいからです。
たとえば、朝礼や夕礼、定例会など定期的にヒヤリハット報告のための時間を作ることが挙げられます。このような場で上司が率先して報告することで、従業員全体が報告しやすい社風づくりを心がけましょう。
【コツ3】定期的に安全教育をおこなう
ヒヤリハットを定着させるためには、定期的な安全教育が重要です。定期的に教育をおこなわなければ、徐々に意識が低下する恐れがあります。
安全教育の例として、KYT(危険予知トレーニング)があります。KYTとは、業務にひそむ危険の要因を事前に考える訓練です。
一方的に講義などを聞くだけの安全教育では効果が薄いため、KYTのように、より実践的な内容を定期的におこなうのがおすすめです。
【コツ4】報告書のフォーマット・申請フォームを用意する
報告書のフォーマットや申請フォームを用意して、報告を簡単にすることがおすすめです。毎回一から報告書を作成すると手間がかかるため、従業員が報告を面倒に感じ、避けようとする可能性があります。
フォーマットがあればスムーズに作成できるうえ、管理者側も同一のフォーマットで提出されるため管理が簡単です。
また、報告書のフォーマットを用意するほかにも、申請フォームを作成すると報告のハードルが下がります。
従業員がヒヤリハット報告をする上での負担を軽くするためにも、報告書のフォーマットや申請フォームを用意しましょう。
さらに、ワークフローシステムなどを活用することで、WEB上に簡単に申請フォームを作成することができます。
効率的にヒヤリハット報告するなら「ワークフローシステム」を活用しよう
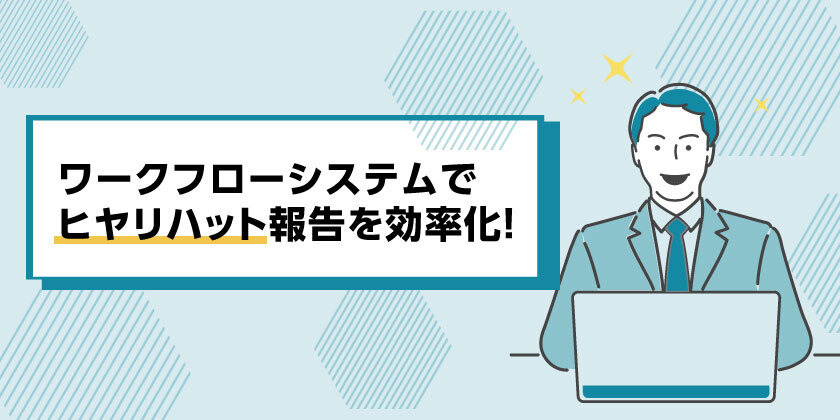
効率的にヒヤリハット報告する場合は、ワークフローシステムの活用がおすすめです。
システム導入に費用がかかるものの、それを上回るメリットを享受できる可能性があります。
そもそもワークフローシステムとは?
ワークフローシステムとは、企業内で発生する申請や承認・確認などのワークフローを効率化するシステムです。ワークフローシステムのおもな機能は、下記のとおりです。
・申請書類のフォーマットを作成
・承認ルートを設定
・進捗状況を可視化
・各書類のアーカイブ・検索
書類を申請・承認する際は「書類が承認者に届いていない」「担当者が書類を見忘れる」などのヒューマンエラーが発生する恐れがあります。進捗状況を可視化することで、書類がフローのどこで止まっているのか簡単に確認可能です。
さらに、クラウドワークフローシステムの「コラボフロー」では、条件に従って自動で申請書の経路を分岐したり相談や確認をしたりできます。
ヒヤリハット報告をワークフローシステムでおこなうメリット
ヒヤリハット報告をワークフローシステムでおこなうメリットは、下記のとおりです。
| メリット | 詳細 |
| 1.報告書のテンプレートを簡単に用意できる | ・フォーマットがあるので、何度でも同じ形式の報告書を簡単に作成できる。・報告書の作成にかかる時間や労力を、大幅に削減できる。 |
| 2.文書の回覧がスムーズにできる | ・データで管理できるので、文書の配布や回覧がスムーズになる。・報告書を一度アップロードすれば、指定した関係者全員が同時にアクセスできる |
| 3.確認漏れ、共有漏れがなくなる | ・進捗状況を可視化できるので、確認漏れや共有漏れが起こる可能性を大幅に削減できる。 |
| 4.内部統制の強化につながる | ・承認ルートや状況を追跡できるので、組織の内部統制が強化される。・内部統制を強化できると、リスク管理やコンプライアンスの確保につながる。 |
| 5.報告書の管理が楽になる | ・各報告書のアーカイブや検索が可能なので、いつでも書類に簡単にアクセスできる。・紙の書類と比較して、紛失するリスクを低減できる。 |
ワークフローシステムを利用することで、内部統制の強化につながります。社内のワークフローが可視化されるため、適切なフローに乗っていない進行を防止可能です。また、承認をスキップしたり事後確認としたりなどの不正なフローも予防できます。
なお、コラボフローは簡単に導入・運用ができるワークフローシステムです。コラボフローの詳細は、下記より無料資料をダウンロードの上、ご確認ください。
まとめ:ヒヤリハット対策には報告書の活用が重要
ヒヤリハットとは、業務中にヒヤリとしたりハッとしたりした危険な現象です。重大な事故には至らなかったものの、一歩間違えれば大きな事故につながります。ハインリッヒの法則では、1件の重大事故の裏に、300件のヒヤリハットがあると言われています。
そのため、報告書を活用して積極的に対策することで、重大な事故の未然防止が可能です。一方で従業員に報告書を提出させるには、それなりの負担がかかってしまいます。その点、コラボフローでは、Excelファイルの既存フォームをそのままの見た目でWebフォームに変更できます。
フォーム入力にすることで従業員の利便性が上がり、積極的なヒヤリハット報告を期待できます。コラボフローの詳細は、下記より無料資料をダウンロードのうえご確認ください。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。