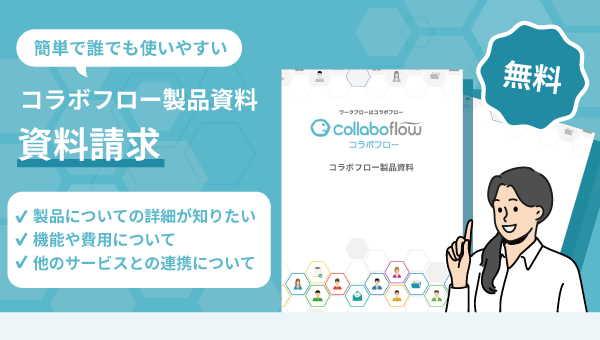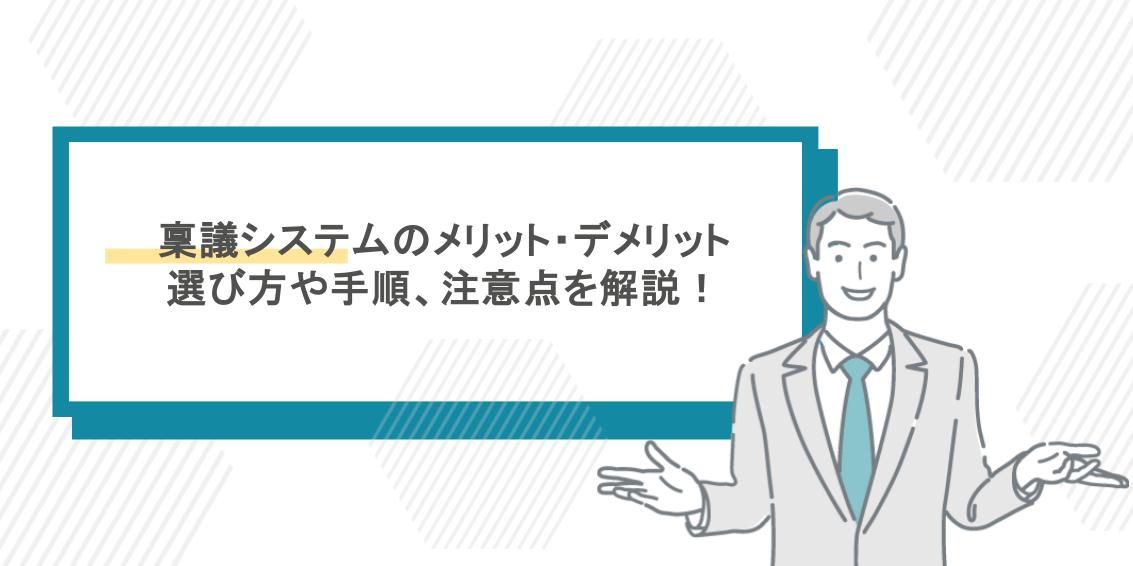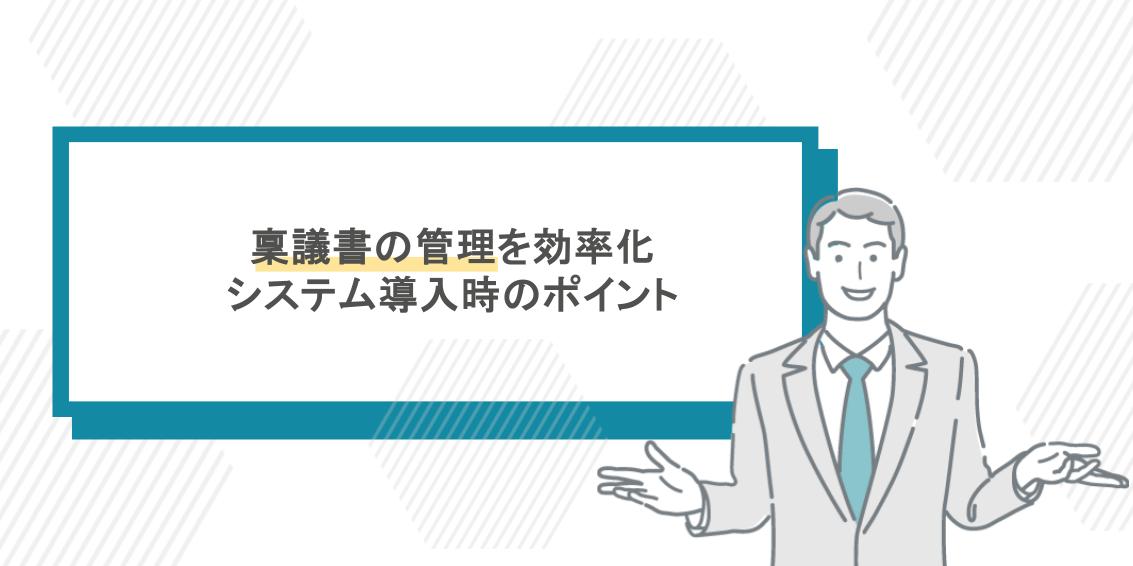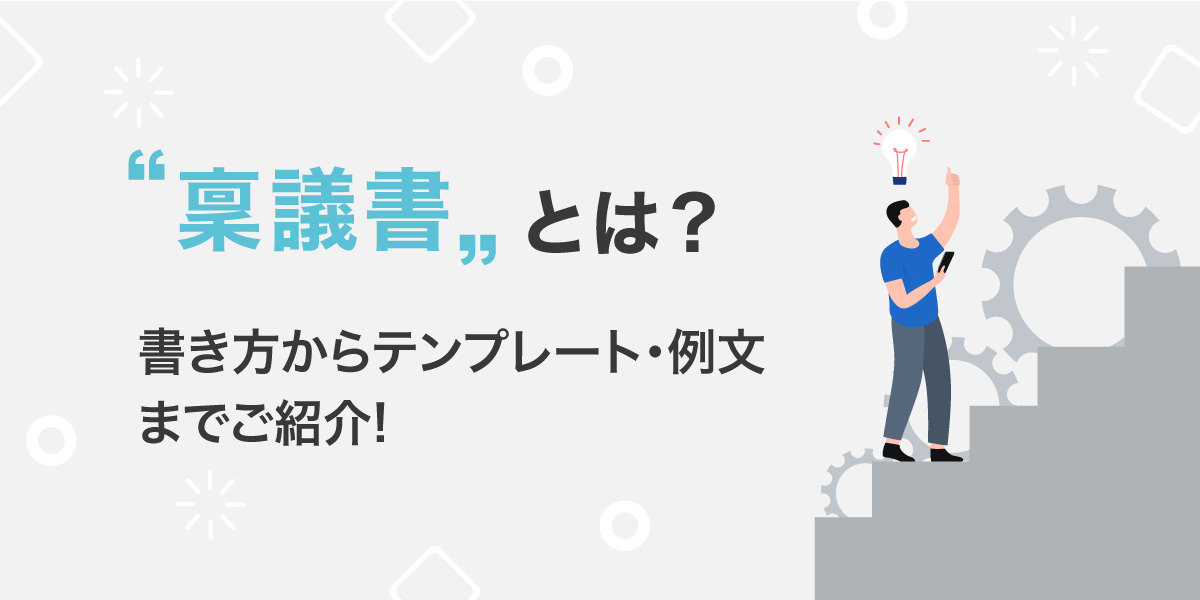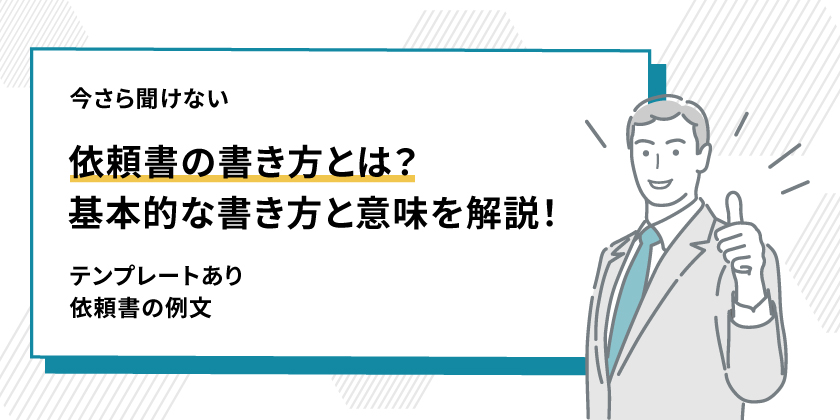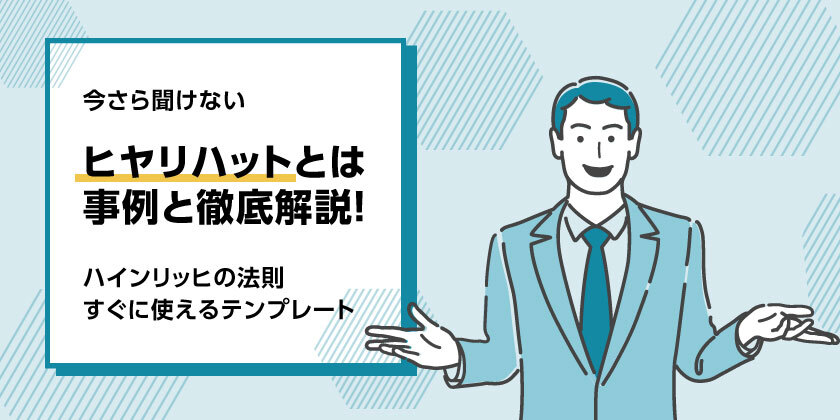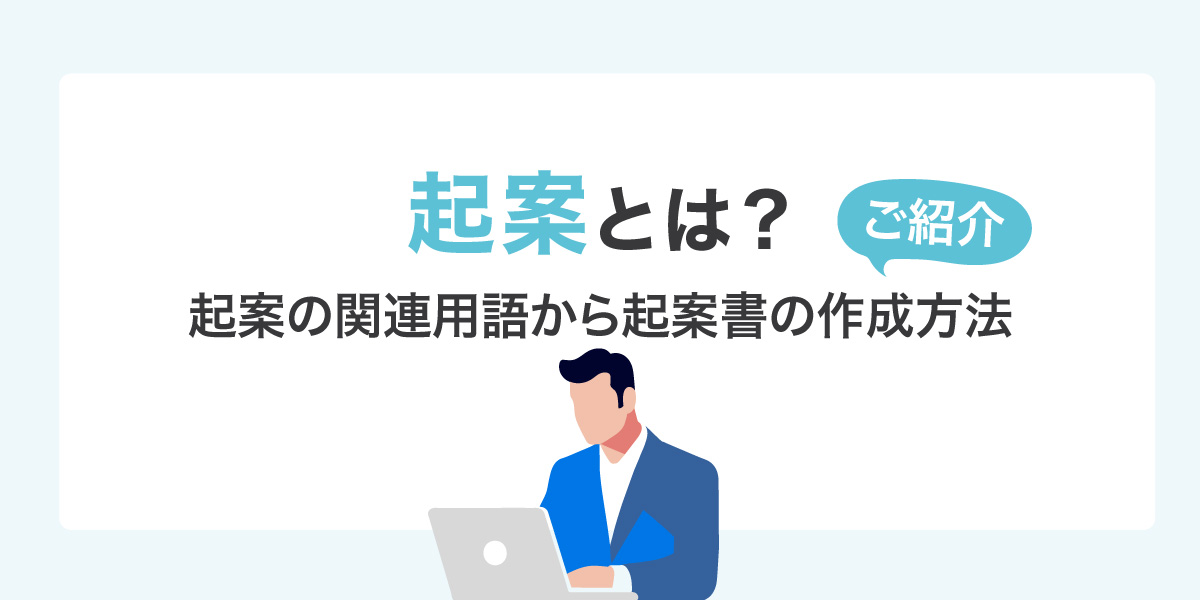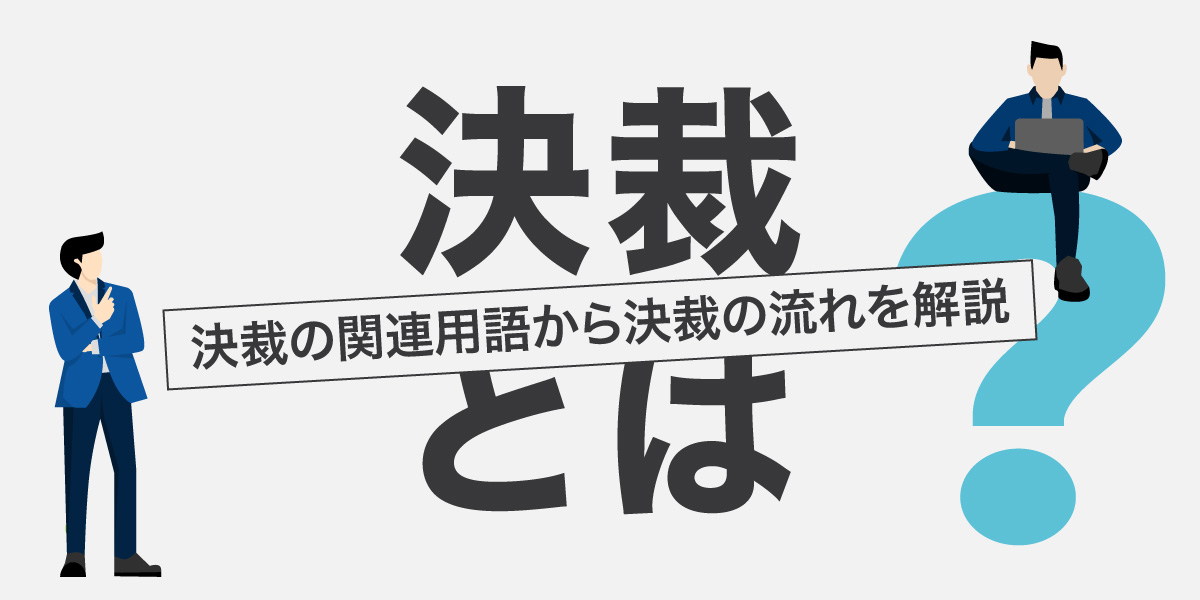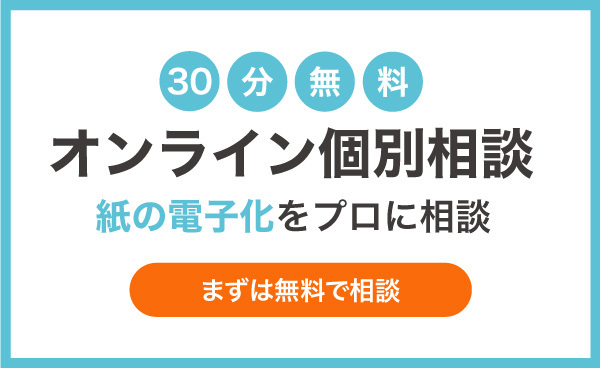この記事の目次
報告書はビジネスシーンにおいては必要です。報告書の種類や書き方、押さえるべきポイントはご存じでしょうか。
今回の記事では、ビジネスを上手く進めるために大切な報告書について解説します。
報告書とは
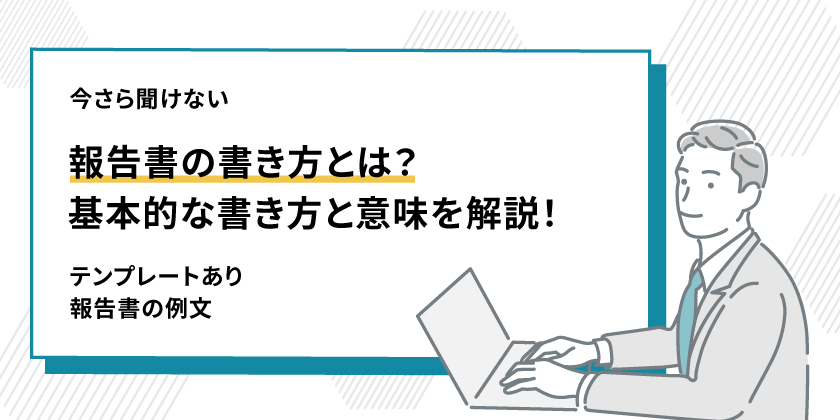
報告書とは、起きた事柄について報告する内容をまとめた書類です。ビジネスシーンにおいては、指示された業務を行った際、上司に結果や経緯を報告するために作成します。
報告書には以下のような種類があります。
●業務や出張の内容を上司へ報告するための「営業報告書」
●調査や研究の結果を報告する「調査報告書」
●クレームやトラブルがあった際経緯を報告する「経緯報告書」
●研修の内容や研修で得た知識をまとめた「研修報告書」
上記のように、報告書はビジネスのさまざまな場面で用いられる重要な書類です。
報告書の目的
報告書を作成する主な目的は「情報の共有」です。
起きた事柄や経緯を共有して、今後の事業等に活用するために報告書を作成します。報告書は社内に提出するために作成するものと社外に提出するために作成するものがあり、それぞれ主な目的は次のとおりです。
●社内に提出する場合:業務の進捗や経験を共有し、次回以降の業務に反映
●社外に提出する場合:取引先との信頼関係構築や回復
報告書の種類
報告書を作成する主な目的は「情報の共有」です。
起きた事柄や経緯を共有して、今後の事業等に活用するために報告書を作成します。報告書は社内に提出するために作成するものと社外に提出するために作成するものがあり、それぞれ主な目的は次のとおりです。
●社内に提出する場合:業務の進捗や経験を共有し、次回以降の業務に反映
●社外に提出する場合:取引先との信頼関係構築や回復
営業の報告書
営業に関する報告書は、日・週・月ごとなど、特定の期間ごとに作成します。報告する内容は、行動内容・業務の進捗状況・業務実績などさまざまです。また、半期・四半期など節目のタイミングで作成するものは、今後の展開や業務計画の見通しなども書きます。
営業に関する業務内容や成約結果、反省点を、上司や同じチームのメンバーに共有するために作成します。
研修の報告書
社内研修や社外でセミナーを受けた際も報告書は欠かせません。
研修やセミナーの内容だけでなく、そこから何を習得したのかを報告します。講師や研修内容など要点を記載して、習得したものや何が業務に活かせるものをまとめます。
出張の報告書
出張報告書は、特に営業部で頻繁に作成されます。
営業の担当者は、エリアや商材・顧客の性質に分けて担当しています。中規模以上の企業では営業ツールを保有して、営業日報でお互いの状況や成果を報告します。
重要顧客や長期出張のときは、多くのケースで別途報告書が必要です。海外出張の場合は、国内よりも費用がかかり、滞在期間が長くなりやすいため報告書が長文になります。要旨を設けて詳細を記載しましょう。
トラブルの報告書
不良品を出荷してしまった、クレームを受けた、機械トラブルが起きた、などトラブルが起きたときも報告書の提出が必要です。
不良品を出荷した場合、スピーディで正確な記載が求められます。不良品を出荷してしまった原因を明らかにし、今後の再発防止策をまとめるために作成します。クレームを受けた際は、内容や改善点、対応を報告書にまとめます。機械トラブルでは、機械の損失具合や復旧予定などの報告が欠かせません。
財務・経理の報告書
財務・経理に関する報告書は、会社の資金を管理するために重要な書類です。
財務や経理の報告書として、一定の期間内の収入や、支出額、支出先を管理する「収支会計報告書」や「支払報告書」があげられます。また、利益がどの程度出たかを明確にするために、当期の損益計算書や貸借対照表・キャッシュフロー計算書などをもとにして会社の資金や収益を報告することもあります。
調査、分析の報告書
戦略事業部や経営企画室などの部署では、経営分析の報告書を作成します。
これらの部署は経営にインパクトを与える事柄について課題提起を行い、評価基準を明確にしたうえで分析を行います。その分析結果の報告にも報告書が用いられます。マーケティング部門や、分析を戦略に活かす事業に役立てられるでしょう。
調査や分析の報告書に書かれる項目は以下の通りです。
●調査目的
●実施した日時
●調査の対象者
●調査方法
●回収状況
●アンケートの集計結果
報告書には、結果の数字だけではなく調査内容の詳細も記載します。
報告書を読みやすくする書き方・ポイント
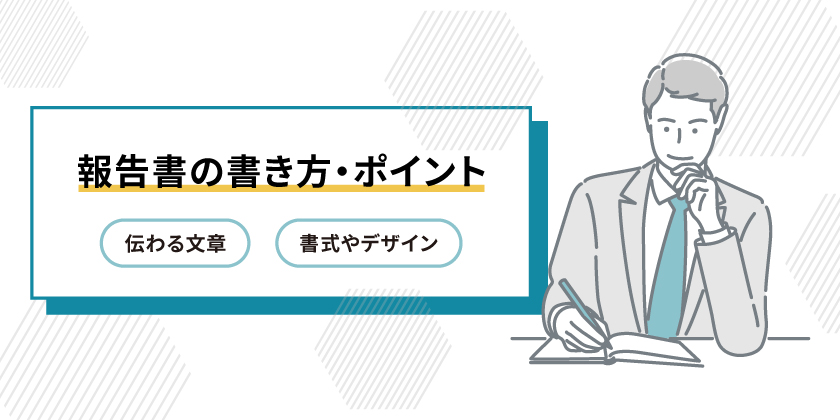
報告書は重要な書類であるため、読む人が分かりやすいように正確で簡潔な内容を心がけなくてはなりません。ここからは、読みやすい報告書の書き方や上手く書くうえでのポイントを紹介します。ぜひ参考にしてください。
事前情報をしっかり集める
報告書を書き始める前に、記載する内容や素材などを収集して情報を整理します。
現場にいない人にも起きた事柄や状況・正確な情報を伝えるために、相手にとって必要な項目を集めましょう。内容に関するメモを作ったり、起きたことを箇条書きにしたりして分かりやすく整理しておくことが大切です。
報告書は事実を正確に伝える目的で作成します。自分の曖昧な記憶やひらめきに頼らず、資料と正確な情報をもとにしましょう。
構成を3段階にする
ビジネス文書は「標題・内容要旨・詳細内容」の3層構造で情報の整理や要約をするとわかりやすくなります。
3層構造はピラミッドのような構造で、下に行くほど詳細な内容になる点が特徴です。標題は報告書の目的を示します。「内容要旨」で内容の要約をして、「詳細内容」で報告書の説明と掘り下げた内容を記載します。
対象と目的を明確にする
報告書を書く対象と目的は明確にしておきましょう。このポイントを押さえておくと、読み手の期待に応える有意義で読みやすい報告書になります。
目的が定まっていないまま書き始めると、本来報告する内容と自分の書いた内容が異なってしまう可能性が生じます。提出する相手が会社のトップや役員など上層部の場合、報告する内容やメリットやデメリットなどを明確にすると、上層部が判断しやすい構成になるでしょう。
客観的に伝わる文章
報告書は客観的に伝わる文章で作成するのが大切です。「5W2H」の要素を意識しましょう。「5W2H」とは、以下の7つの要素で構成されるフレームワークです。
●When(いつ)
●Where(どこで)
●Who(誰が)
●What(何を)
●Why(なぜ)
●How(どのように)
●How much(どのくらい)
PREP法を意識して結論・理由・具体例・結論を組んで、分かりやすく簡潔な報告書を作成します。また、報告書には、具体的な数字やデータ、実際に起きたことなど客観的な事実も正確に記載しましょう。
文字数に留意する
報告書を作成した後は、文字の数を確認します。文字量が多いと読みにくくなりやすいといえます。
一般的な報告書は、要旨でA4用紙1枚程度、詳細内容でA4用紙2〜3枚程度が適当です。上層部に提出するときは、1分程度で読めるよう簡潔に、約200字程度でまとめます。
推敲、チェックを入念に行う
報告書を書き終えたら、声に出して読み、違和感がないかをチェックします。読みにくいと感じる文章は、短くしたり読点を活用したりして読みやすく訂正しましょう。
また、数量・金額などの数字や単位、商品名や施設名などの固有名詞、相手の意思や納期など、情報に関して入念にチェックを行います。報告書は正確な情報を伝える目的であり、間違いや漏れがあるとトラブルに発展してしまう可能性があります。
書式やデザインに気を配る
多くの人の目に触れる報告書は、読みやすいレイアウトも大切です。
文字のサイズやフォントスタイル、改行などのレイアウトが揃っていることを確認します。フォントスタイルは「メイリオ」や「ゴシック体」が判読性に長けていて報告書の使用に向いています。長文の場合はすっきりとしたデザインの「明朝体」がおすすめです。
報告書でよく使えるテンプレート・ツール
報告書を作成・提出する際に、よく使われているテンプレートやツールをご紹介します。作成目的やターゲット、内容によって報告書の形式も変わるため、適したものを選びましょう。
word、Excel
WordやExcelを使用するとスタンダードな形式の報告書が作成できます。WordやExcelは、ビジネスに欠かせないツールであり多くの人が利用しているでしょう。
Word・Excelには業務報告書や出張申請書、会計報告書などのテンプレートが存在します。テンプレート検索から”報告書”を選択することで、各報告書のテンプレートが利用できます。
Adobe Stockでは、本格的な報告書のテンプレートを配布しています。ビギナー向けにチュートリアルも用意されていて、まずは無料で体験版の利用も可能です。
Adobe Stockのテンプレートは正式な報告書であり、社外向けに作成する場合に適しています。
ワークフローシステム【コラボフロー】
コラボフローには、ビジネスで使えるさまざまなテンプレート・フォーマットが数多く用意されています。
通常フォームやExcelフォーム・コラボフォームで、さまざまな報告書や申請書のテンプレート・フォーマットが存在します。種類が豊富で内容によって細かく分かれていて、業種別・業務別、フォーム分類で検索が可能。目的のテンプレートを瞬時に探せるでしょう。
テンプレートダウンロードはこちら
リンクをクリックして、使いたい書類を検索してください。
⇒テンプレート一覧ページ
ワークフローを導入して報告書をフォーマット化しよう
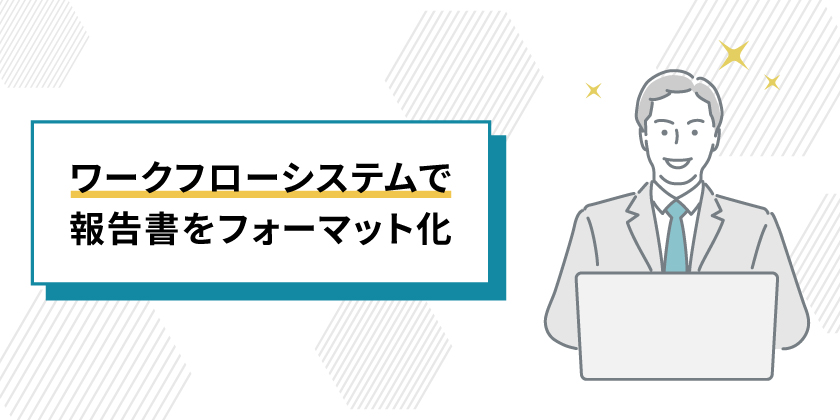
報告書にはさまざまな種類があり、内容や書き方もそれぞれ異なります。紙による業務は担当者の不在で滞る場合もあり、企業の負担になっているケースも多いでしょう。ワークフローを導入すると、さまざまな手間が省けて業務の効率化が可能です。
●報告書を1から作成する手間がかからない
●作成内容にまだらが出ない
●やりとりがスムーズになる
●誰のもとにタスクがあるか明確になる
上記のようなメリットが挙げられます。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
まとめ
今回の記事では、報告書の特徴や種類、作成時のポイントを紹介しました。報告書は業務に必須のため、今回の記事を参考にしてよりよい報告書を作成しましょう。
報告書にはさまざまな種類があり、紙による提出は時間と労力がかかってしまいます。申請業務が多いと書類の管理も大変になるでしょう。そういったときはワークフローシステムの活用がおすすめです。ペーパーレス化で業務効率の改善に取り組みたいときは、ぜひワークフローシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
⇒書類の電子化とは?導入前後で知りたいポイントや導入ステップを解説
⇒帳票とは?帳票の種類から作成手順、効率化まで解説