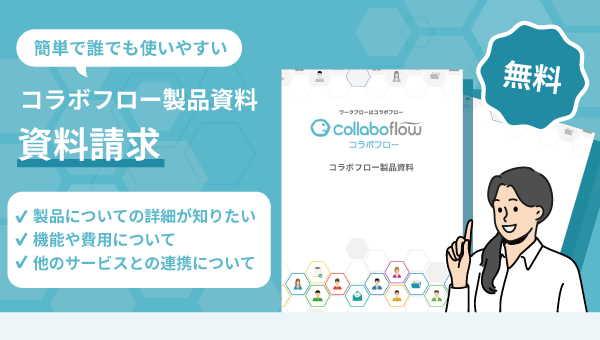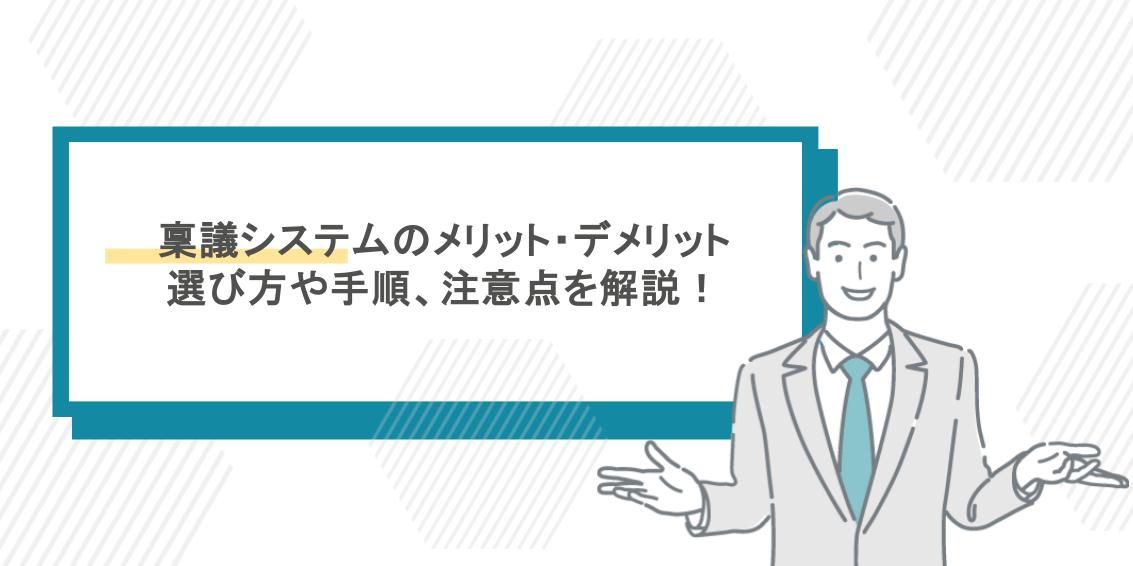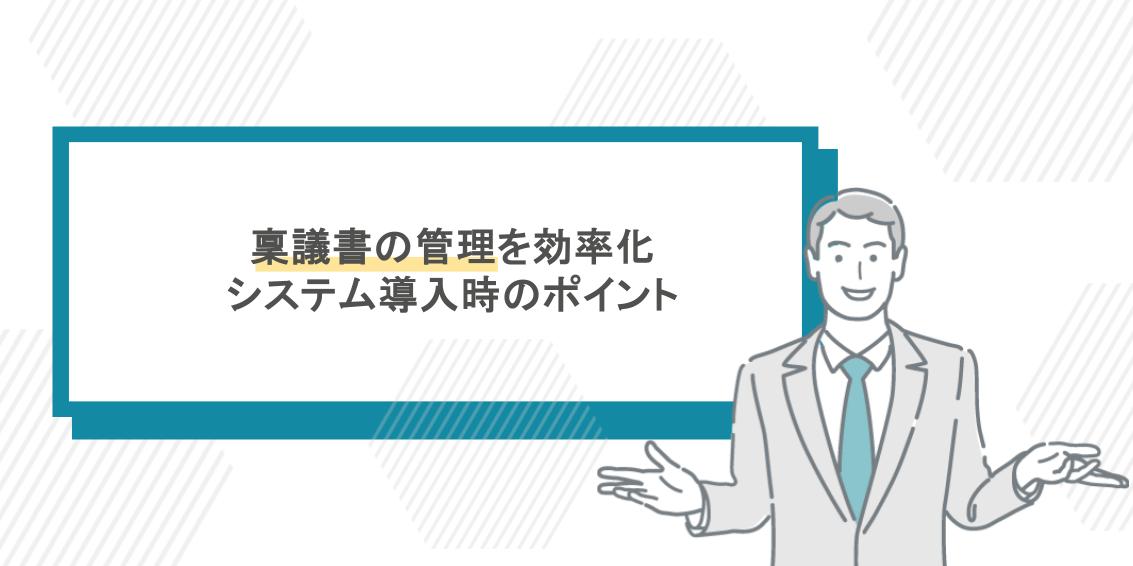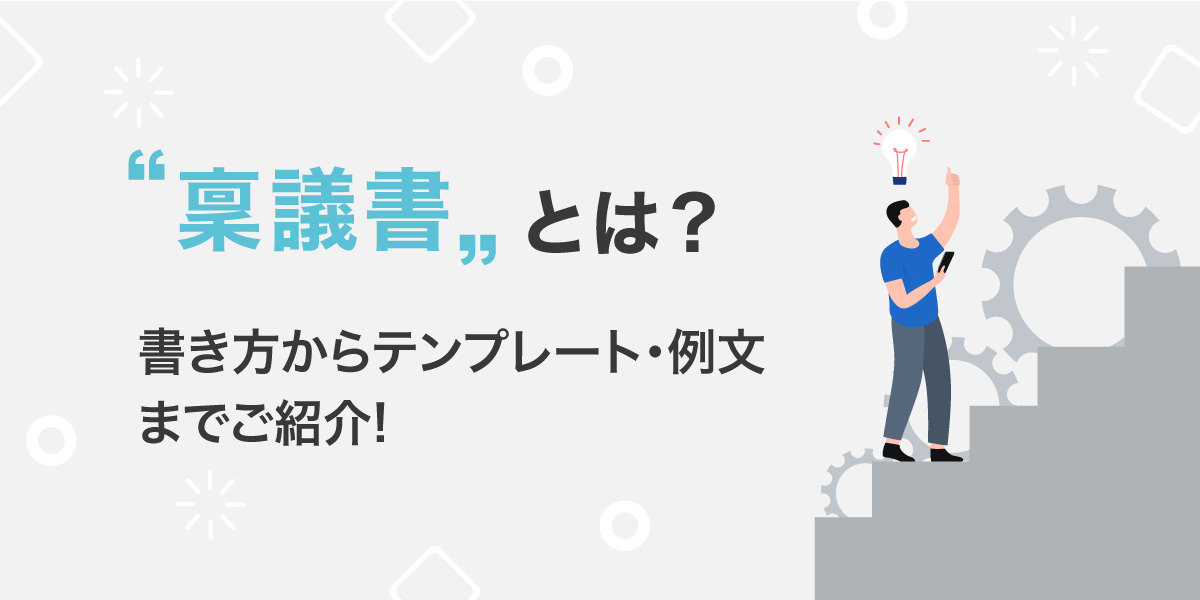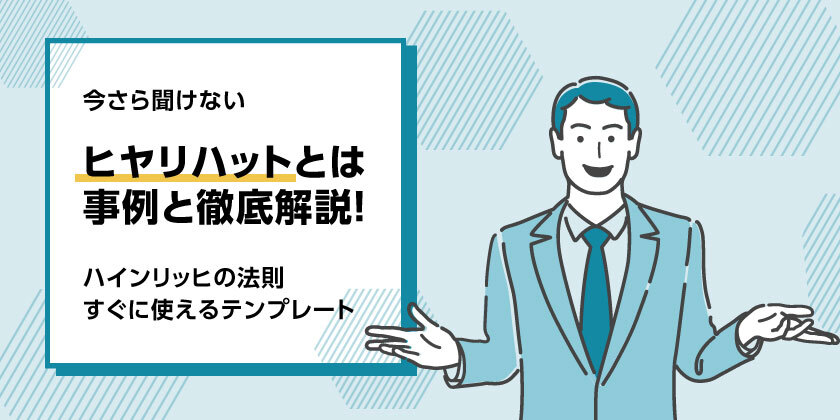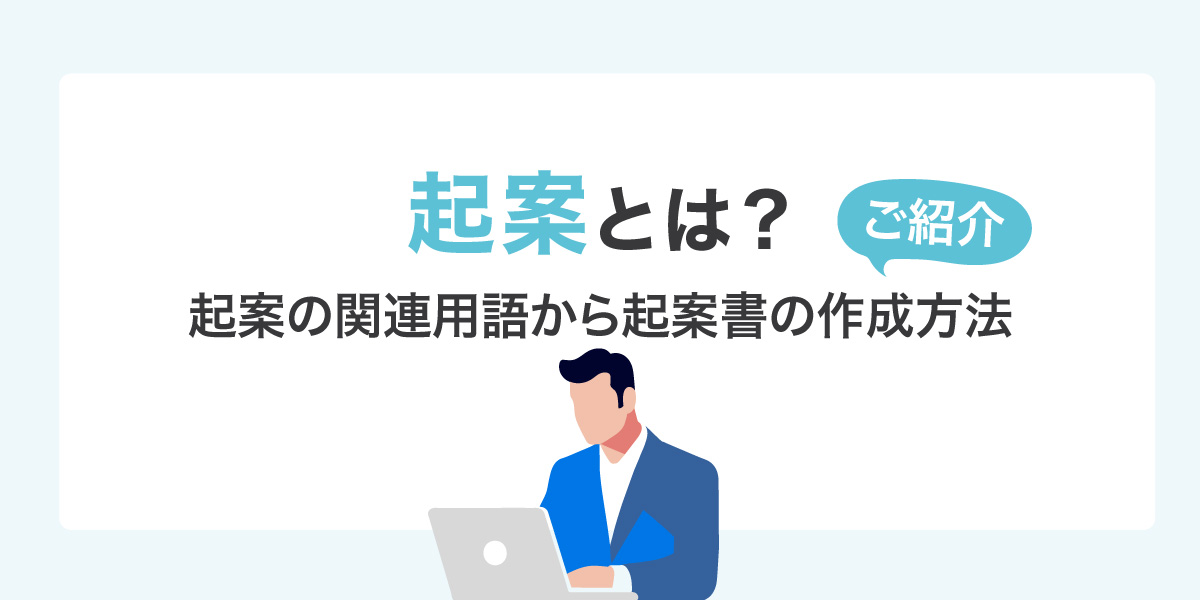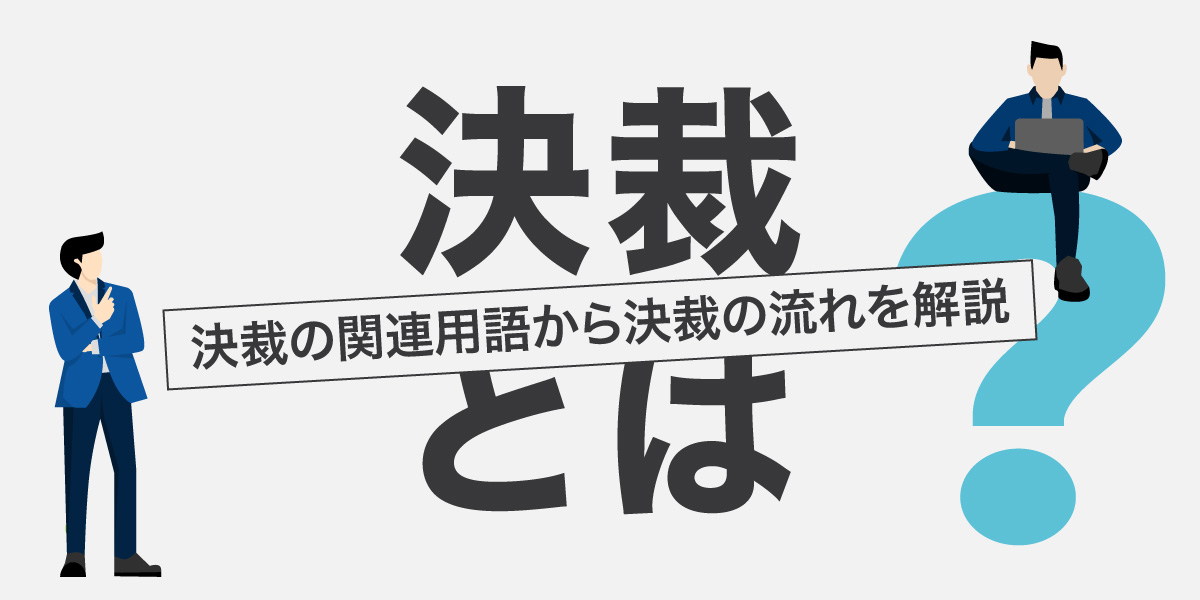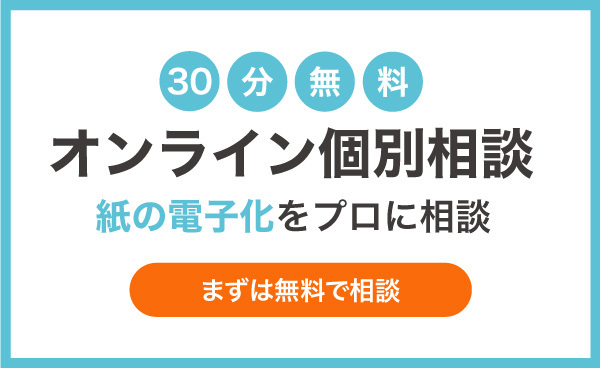この記事の目次
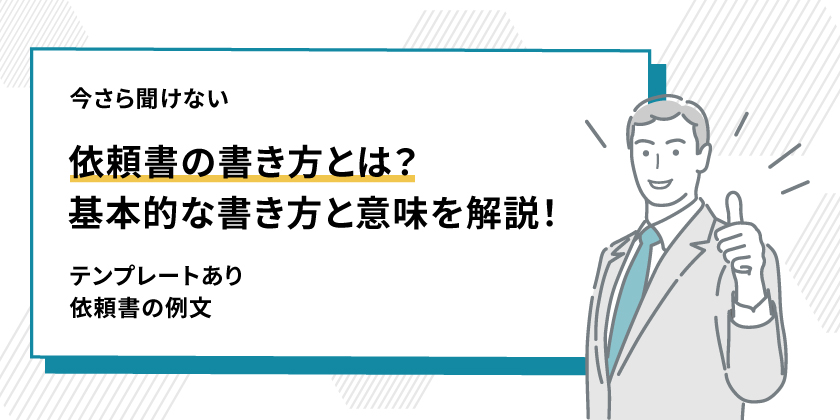
依頼書は、会社の取引先や個人に対してお願いをする際に作成する書類です。ビジネスにおいて頻繁に使用される書類であり、社内関連部署への依頼や社外の個人への依頼などで必要です。
今回は、さまざまな相手に向けて作成する依頼書の書き方をテンプレート付きで紹介します。
依頼書とは
依頼書とは、相手に対して何かを依頼する際に作成する書類です。お願いする相手はさまざまで、社外の取引先や個人をはじめ、社内の関連部署などがあげられます。
口づてではなく、依頼内容を正確に正しく伝えるために、依頼書がよく用いられます。正しく依頼を伝えることと、その以来の履歴を残し、後のトラブル防止にもつながります。
相手に依頼を受けてもらうために、依頼書は丁寧に、情報の過不足なく作成することが重要です。
資料ダウンロードはこちら
⇒ワークフローツールを選定する上で絶対に押さえるべきポイントは?
⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント
依頼書の代表的な種類
社内外の関係者に対して使用する依頼書にはさまざまな種類が存在します。ここでは、代表的な依頼書をピックアップして解説します。
発注依頼書
発注依頼書とは、商品や備品などを購入する際、外部業者へ注文の承認を得る書類です。
関係する取引先と金銭のやり取りを伴うため、事前に申請する依頼書の代表といえます。発注依頼書は、大規模な仕入れや試作品の制作から事務用の文具などに、大企業から零細企業まで幅広く使用されます。
発注依頼書には、「商品名」「数量」「納品先」「決済方法」などの情報を記載します。
支払依頼書
支払依頼書とは、取引先から届いた請求書に対する支払いや処理を、社内の経理部署に依頼する社内文書です。
取引先からの請求書は、発注した部署の担当者へ届きます。担当者は、社内の経理部署に請求書を回して支払処理を依頼しなければなりません。経理部署に対して、請求書だけでなく支払依頼書も渡すことで、間違いやミスを防止できます。
押印依頼書
押印依頼書とは、取引先や社内関連部署の決裁を必要とする書類に、押印を依頼する書類です。取引の信頼性や正確性を確保する役割を担います。
例えば、新たに契約を結ぶ取引先に対して、契約書への押印を依頼する際に使用します。
依頼書の基本的な書き方とテンプレート
依頼書の書き方は定型化されていて、記載する項目はほとんど同じです。ここからは、依頼書の基本的な書き方やテンプレートを紹介します。
相手が読んだときにすぐ理解できるように、簡潔に記載しましょう。依頼を快く承諾してもらうためにも、相手の立場に立ち失礼のない文章を作成するようにしましょう。
依頼書テンプレートダウンロードはこちら
⇒依頼書テンプレート一覧ページ
前文・文末
依頼書の前文には、挨拶や季節の案内を入れます。例えば「拝啓」「謹啓」「時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」などがあげられます。
文末には「敬具」や「謹白」「取り急ぎお願いまで」など、締めの表現を使用しましょう。
表紙やタイトル
タイトルは目立つ大きさにして、依頼内容を一目で分かるようにします。以下、タイトルの例を紹介します。
●弊社雑誌における原稿執筆のお願いにつきまして
●講演の依頼について
●セミナー講師のご依頼
依頼の内容
依頼の内容は、「してほしいこと」をできる限り具体的に記載します。内容が曖昧だと、相手と認識にズレが生じてトラブルに発展する恐れが生じます。
例えば、文章の執筆を依頼するケースでは、原稿のテーマや文字数をはっきり記載しましょう。チラシやポスターなどのデザイン制作は、デザインのイメージを明確に記載します。イメージ画像や過去に使用したチラシやポスターなどを添付すると、認識のずれが生じにくくなるでしょう。
また、「依頼完了までの期限」も忘れずに記載します。
依頼書を書くときの注意点
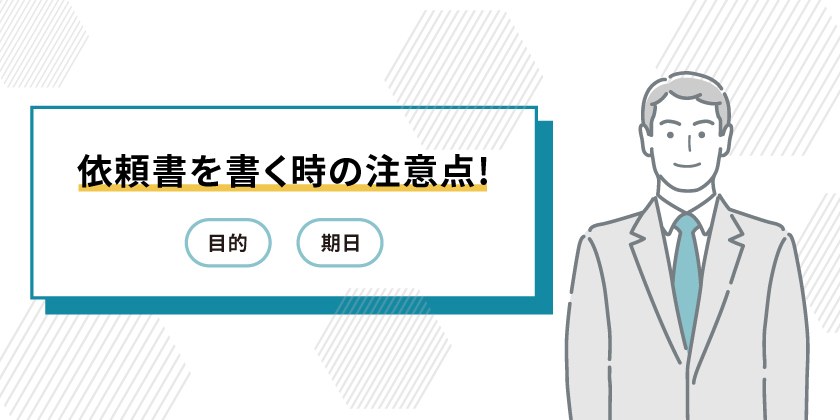
依頼書は、一般的には社外の取引先や個人に対して送付するケースが多いといえます。依頼書の内容に間違いや記載ミスなどがあると、会社の信用問題にもつながるでしょう。
ここからは、依頼書を書くときの注意点を紹介します。
目的を明記する
依頼相手とのミスマッチや認識の齟齬を防ぐために、依頼目的は明確に記載/span>します。「この仕事をお願いする理由」「依頼の目的や背景」を分かりやすく伝えると、依頼相手からの同意が得やすくなります。
例えば上司に押印依頼書を提出する際は、このプロジェクトが重要性をロジカルに伝えます。また、有識者に取材を行うケースでは、取材目的をはっきり提示しましょう。
期日を設定する
相手に何かをお願いするときは、必ず期日を設定します。リミットを決めていないと、相手と認識のズレが生じます。
依頼段階でスケジュールが未定の場合も、大まかな期日を記載するようにしましょう。これだけで、認識のずれにより生じる多くのトラブルを回避できます。
社外向けの依頼書のポイントと例文
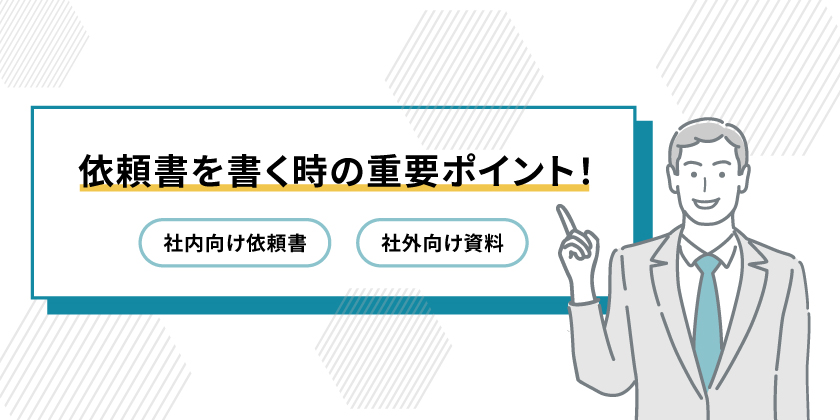
社外向けの依頼書におけるポイントを例文とともに解説します。依頼書を書く際の参考にしてください。
分かりやすく簡潔に
初めて取引を行う相手への依頼書は、丁寧に作成する必要があります。しかし、依頼の内容を長々と記載すると、読みにくく内容がわかりづらいものになるでしょう。依頼書は、わかりやすさと簡潔さを意識して作成します。
例文
以下、法人企業へ製品の発注を依頼する際の例文です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
貴社製品「〇〇」のお見積もりのお願い
拝啓
貴社ますますご清栄のこと、心より喜び申し上げます。平素より格段のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、この度弊社では、貴社製品の「〇〇」の購入を検討しております。つきましては、下記の条件でお見積もりをいただきたく存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、〇月〇日までにご送付くださいますよう、お願い申し上げます。
敬具
記
品名:「〇〇(品番:△△)」
数量:100個
納期期日:〇月〇日
納品場所:〇〇営業所 〇〇支店
支払い方法:納品後〇〇日以内に銀行振込
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社内向けの依頼書のポイントと例文
社内向けの依頼書は、社外向けのものとはポイントが少し異なります。丁寧さよりも要件の伝わりやすさを優先して作成しましょう。
5W3Hを意識する
社内向けでは、体裁よりも内容や目的を分かりやすくすることに重点をおきます。
社内文書には「5W3H」を意識して情報を記載しましょう。「5W3H」とは次のことをいいます。
●When(いつ「時期」)
●Where(どこで「場所」)
●Who(誰が「対象」)
●What(何を「課題」)
●Why(なぜ「動機」)
●How(どのように「手段」)
●How Many(どれくらい「規模」)
●How Much(いくら「価格」)
依頼書の作成をしたことがない人や文章の作成が苦手な人などは、「5W3H」を意識して記述しましょう。情報の抜けや漏れを防げます。
例文
社内へキャッチコピーを募集する際の例文を以下に示します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タイトル「〇〇に関するキャッチコピーを公募します」
拝啓
皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、この度弊社では〇〇プロジェクトを始動する運びとなりました。
そこで、国内外へ大々的にマーケティングを行うにあたり、プロジェクトのキャッチコピーを社内公募いたします。
ご多忙のところ大変恐縮ですが、添付資料Aをご確認の上、◯月◯日までにマーケティング部〇〇課へキャッチコピーを提出いただきますようお願い申し上げます。
敬具
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人に向けた依頼書のポイントと例文
個人に対する依頼書のポイントは、社外向けの依頼書とほとんど同じです。しかし、細かい点では違いもあります。ここからは個人に向けた依頼書のポイントと例文を紹介します。
依頼内容は具体的に
他の依頼書と同様に、後々のトラブルを避けるため、依頼内容は簡潔で分かりやすく具体的にしましょう。
また、社外の方に対して依頼書を作成し送る場合には、その人の所属なども確認しましょう。例えば、個人が会社や大学などの組織に所属していると、個人だけでなく所属先にも許可を取らなければならないかもしれません。
例文
以下、有識者へ講演を依頼する際の例文を記載します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
拝啓
春寒の候、先生におかれましてはいよいよご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、突然のお願いであり甚だ恐縮でございますが、この度弊社製品である『◯◯』の販路拡大のため、〇〇に関してのセミナーを開催いたします。
つきましては、〇〇でご活躍中の先生に、是非ともご講演いただきたくお願い申し上げる次第でございます。
ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。
敬具
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワークフローシステムを導入して効率的に依頼書を作ろう
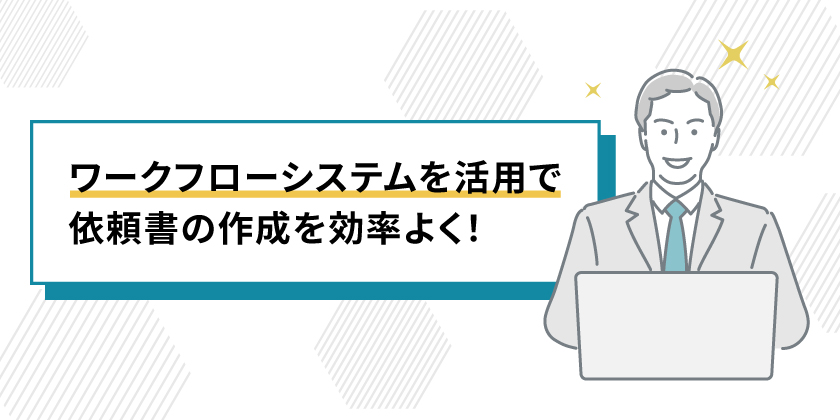
依頼書の作成には、ある程度の経験が必要です。個々の従業員が独自の依頼書を作成すると、依頼相手の混乱を招き、思わぬトラブルにつながる恐れがあります。
トラブル防止や社内業務の効率化を図るために、ワークフローシステムの導入がおすすめです。記事の最後に、ワークフローシステムのメリットを説明します。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
統一された依頼書で業務を最適化できる
従業員が独自のフォーマットで依頼書を作成すると、依頼書の内容や記載事項にばらつきが生じます。これが原因で、余計な手間や仕事が増えるかもしれません。
ワークフローシステムを導入すれば、誰でも統一された依頼書が作成できます。個人に左右されず、業務を最適化できるでしょう。
多様なワークスタイルに対応できる
オンライン上で利用できるワークフローシステムを導入すると、テレワークやフリーランスで仕事をする相手に、仕事を依頼しやすくなります。
依頼書を隙間時間に作成することもできるため、効率よく依頼書作成業務を進められます。依頼元や依頼先のワークスタイルに左右されない依頼書作成が可能です。
まとめ
今回の記事では、依頼書の作成方法や例文を紹介しました。依頼書は、相手に仕事を頼む際に必要な書類です。作成時のコツや注意点を意識して、仕事をスムーズに進めましょう。
また、依頼書作成の効率化を目指すには、ワークフローシステムの導入が欠かせません。株式会社コラボシステムでは、ワークフローシステム『コラボフロー』を提供しています。社内業務の更なる効率化を検討している場合は、お気軽にお問合せください。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
⇒書類の電子化とは?導入前後で知りたいポイントや導入ステップを解説
⇒帳票とは?帳票の種類から作成手順、効率化まで解説