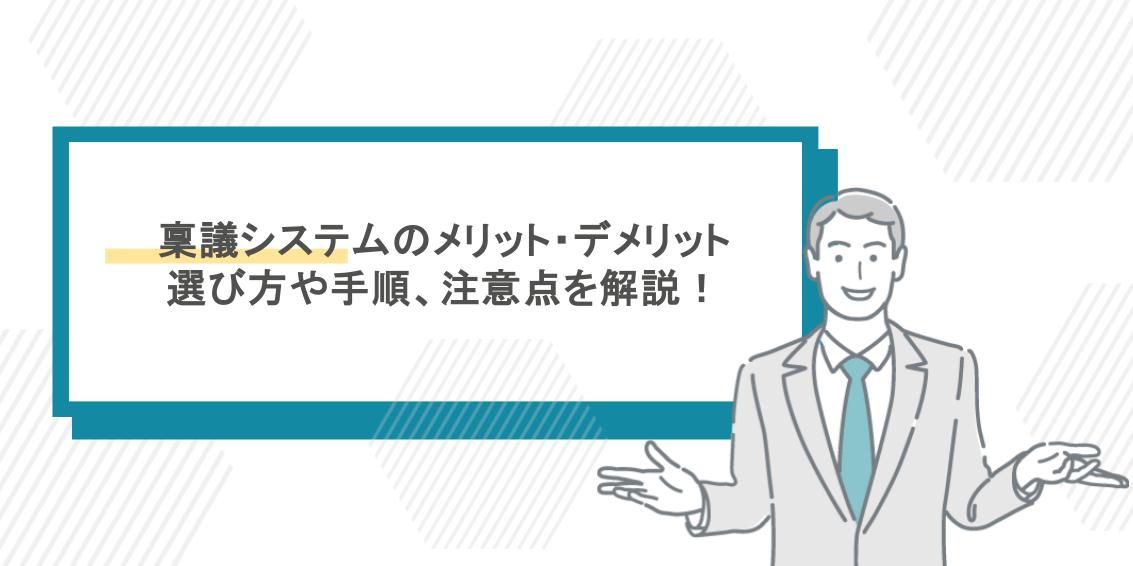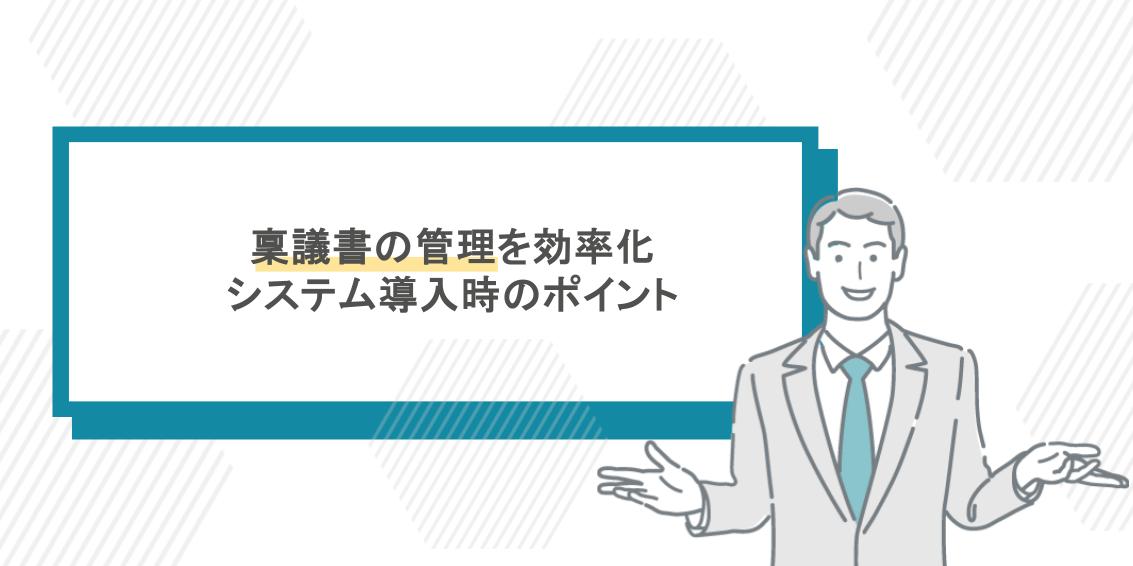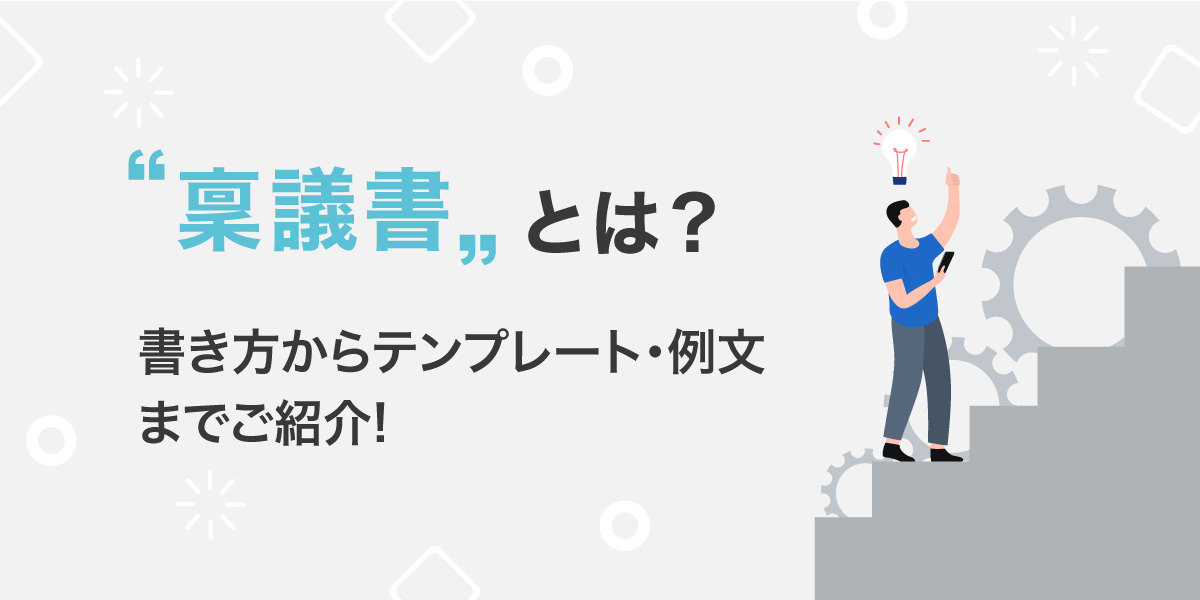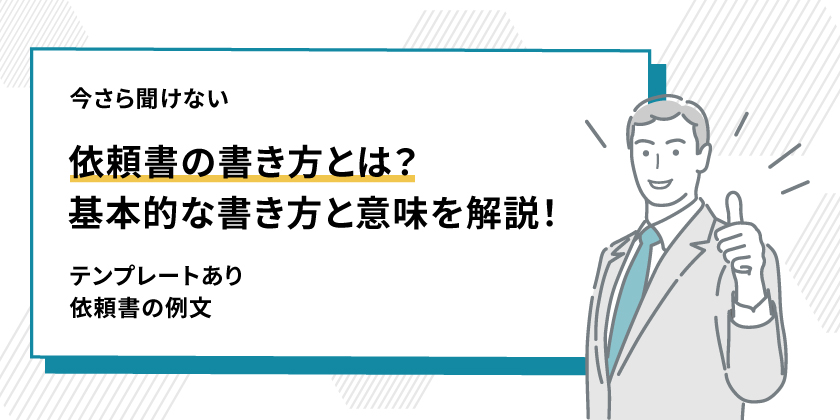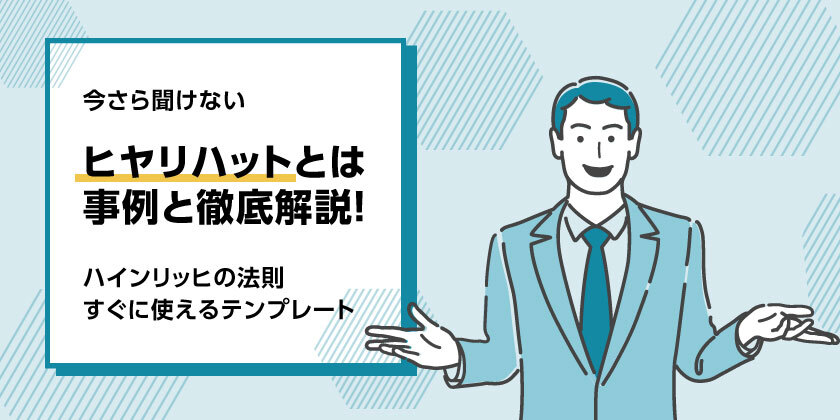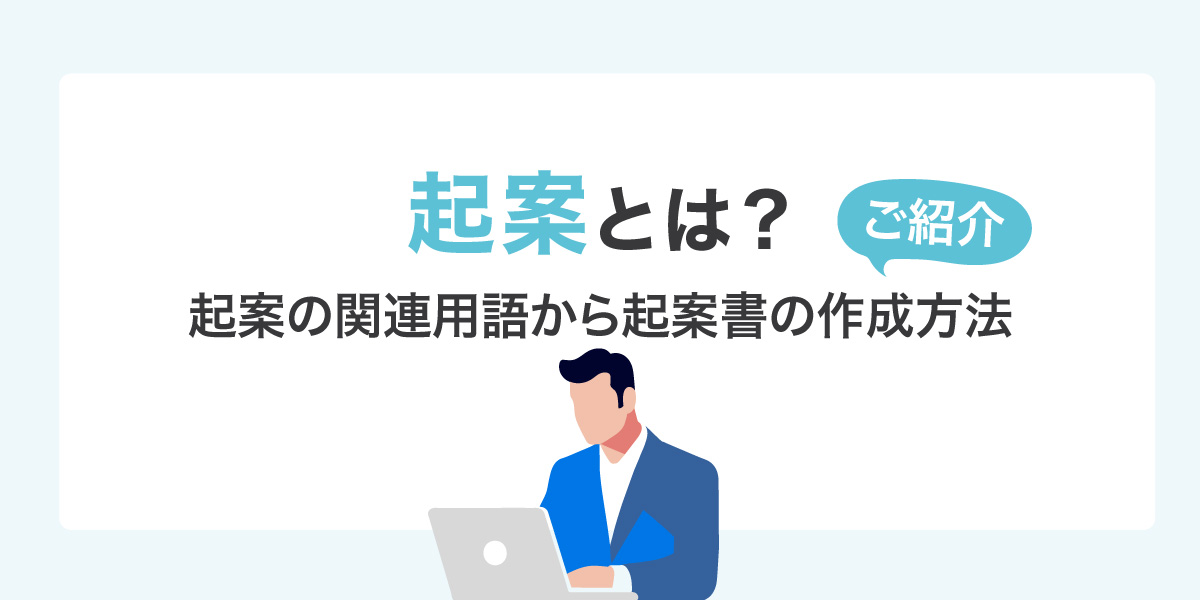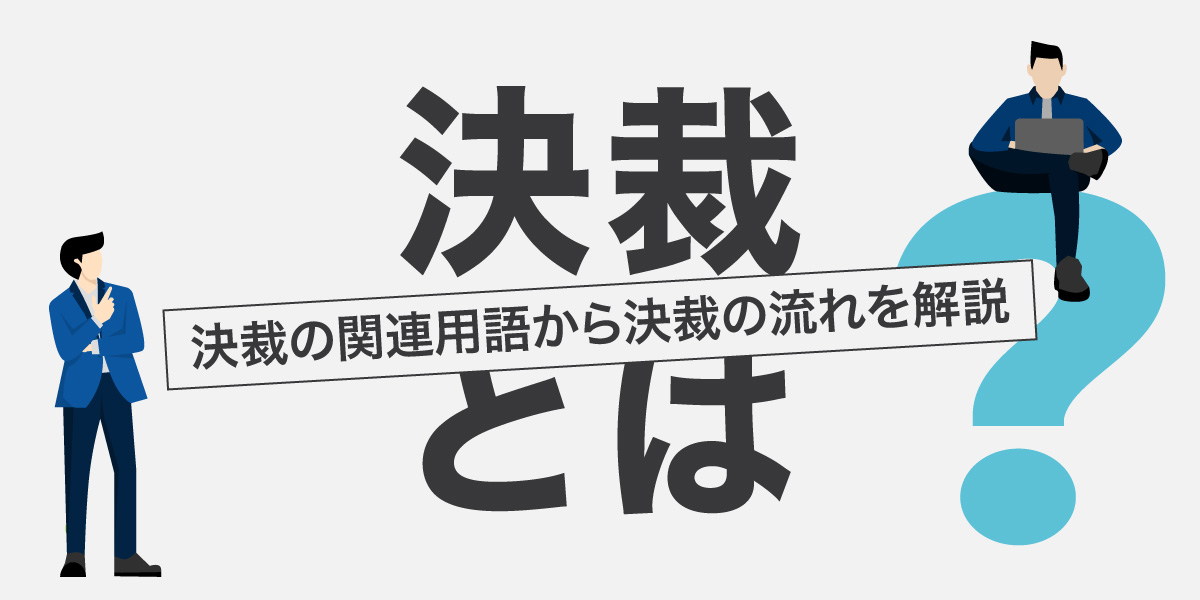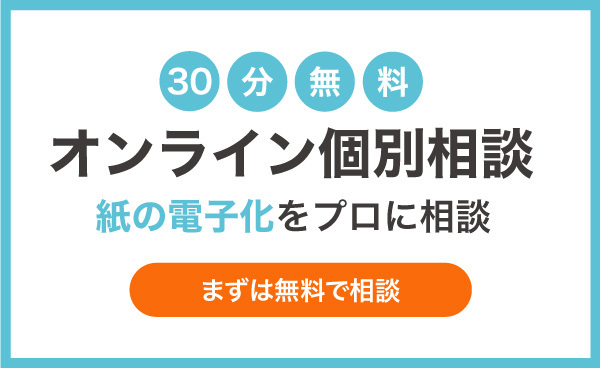この記事の目次
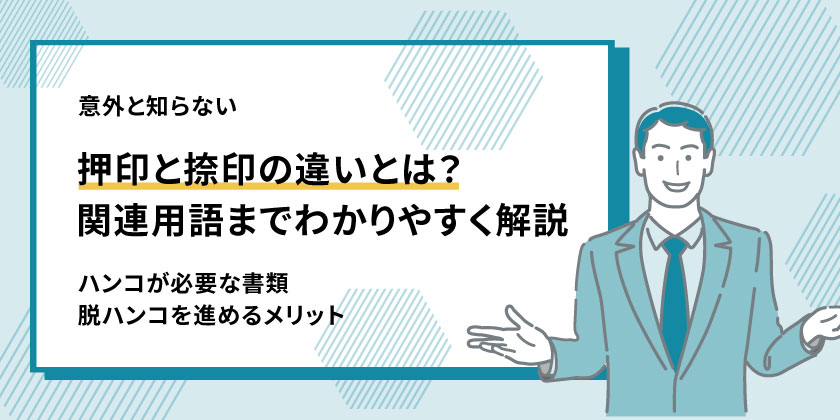
ビジネスにおいて、書類にハンコを押すことを「押印」や「捺印」と呼びます。この2つの呼称について、「何が違うのかよくわからない」と感じる人も多いでしょう。今回の記事では、押印と捺印の違いや、そのほかの混同しやすい言葉を紹介します。
そもそも、押印と捺印の違いとは
押印と捺印は、どちらも書類にハンコを押すことを指す言葉です。それぞれ異なる言葉の略称を語源としていて、厳密には意味が異なります。
ここでは、押印と捺印に加えて、そのほかの混同しやすい言葉の意味をまとめて紹介します。
それぞれの語源と意味
押印は、「記名押印(きめいおういん)」の略称です。名前が記されている書面に印鑑を押すことを指します。
捺印は「署名捺印(しょめいなついん)」の略称です。自筆による署名を添えて印鑑を押すことを指します。
2つの用語の最も大きな違いは、その場で記名するかどうかです。この違いにより、法的拘束力にも差が生じます。正式名称と共に覚えると意味を混同しにくくなります。
そのほかの混同しやすい言葉
押印・捺印と混同しやすい言葉を、以下に示します。いずれの言葉もビジネスシーンでよく使われるため、併せて覚えましょう。
・印章:書類に押すハンコそのもの
・印鑑:所有者が登録されているハンコ
・印影:ハンコを押した後の状態
・割印:両書類にまたがって1つの印章を押すこと
法的効力で見る押印と捺印の違い
押印と捺印は、文書に法的拘束力を持たせます。より効力が強いものは捺印です。
印影だけが施される押印に対して、捺印は自筆による署名も施されるためです。自筆の記名があれば、筆跡鑑定から本人性を担保できるでしょう。
重要な書類には、捺印が一般的です。ただし、近年は捺印・捺印が必要な書類は減少傾向にあります。
文書の真正性については、民事訴訟法第228条4に記載されています。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
参考:民事訴訟法第228条4|e-Gov法令検索
押印、捺印が必要な書類一覧
電子化が進んでいるとはいえ、現在でも紙にハンコを押す機会は多いといえます。押印や捺印が求められる状況はどのようなものでしょうか。
ここからは、押印が必要な書類・捺印が必要な書類を紹介します。
押印が必要な書類
押印が必要な書類の例として、以下一例です。捺印が必要な書類と比べると、証拠能力が求められないものが多いといえます。
・稟議書:承認をもらいたい事案について、上長や関係者など複数人に趣旨の説明・承認を得るための書類です。
・決裁書:稟議書と同様ですが、承認をもらいたい事案について1人の責任者に説明・承認を得るための書類です。
・休暇申請書:休暇を希望する場合に、上長に承認を得るための書類です。
・請求書:取引先へ納品した商品やサービスの料金を請求するときに発行する書類です。
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
⇒決裁とは?関連用語から決裁の流れまで解説
⇒書類の電子化とは?導入前後で知りたいポイントや導入ステップを解説
⇒帳票とは?帳票の種類から作成手順、効率化まで解説
捺印が必要な書類
捺印が必要な書類の例を、以下に示します。
・銀行関係の書類:主に口座開設をする際、本人である証明をするために届出印が必要となる書類です。
・印鑑証明書:会社設立、引越し時の賃貸契約、自動車の購入など重要且つ高額な取引を行う場合に必要な書類です。
一般的に、銀行関係の書類に用いられる印鑑は銀行印。高額な資金が動くときに用いられる印鑑は実印として必要です。
押印・捺印を電子化することは可能?
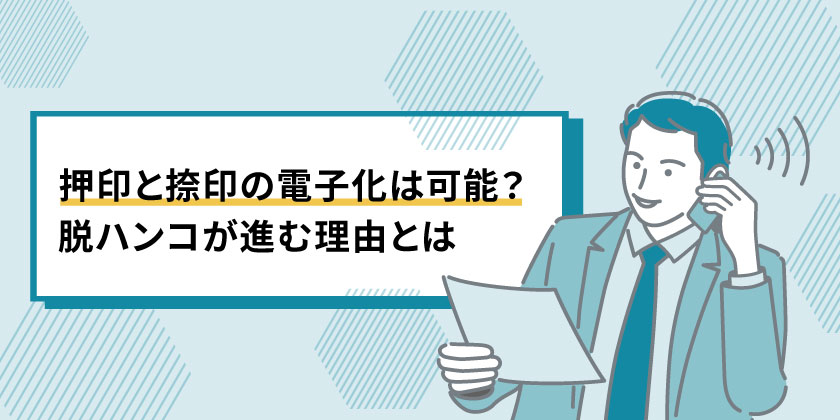
近年は脱ハンコの動きが広まっており、紙でのやり取りが必要な手続きもシステム上で完了できるようになりました。
書類の申請がシステム上で完結すれば、押印と捺印は電子化が可能です。ハンコを押すためだけに出社をやめる目的で、ワークフローシステムを導入する企業が増えています。今後はよりハンコを使う機会は減るでしょう。
脱ハンコが進む理由・背景・現状
近年、紙にハンコを押さずに申請できる「脱ハンコ化」を推進する企業が増えています。ここからは、脱ハンコ化が進められている理由や、脱ハンコ化する企業の割合について説明します。
国が推進を行っているから
脱ハンコ化が急速に進んでいる大きな理由に、国が書類の電子化・脱ハンコ化を推進していることが挙げられます。これは、少子高齢化による労働力不足の改善、解消や、労働生産性の向上が目的です。
日本政府は現在、従来の文書に押印・捺印する作業を基本とした業務の改革を推進しています。2020年9月には、行政内の手続きで発生する押印を99%廃止することを決定しました。この流れに沿う形で、民間企業でも脱ハンコ化が進められています。
内閣府:地方公共団体における押印見直しマニュアルの見直しについて
内閣府:押印についての質問
テレワークが当たり前になったから
新型コロナウイルスを契機に企業がテレワーク導入推進を行った影響もあるでしょう。
実際に、新型コロナウイルス感染症が拡大した2019年12月以降、新しい働き方としてテレワークを導入した企業が、2020年の20.2%から2023年では51.9%と半数以上に増加してます。
最近では新型コロナウイルス感染症が第5類に分類され、外出自粛やマスクの装着義務が緩和されています。
しかし数値としては、既に半数以上の企業がテレワークを導入・順次導入予定の企業も多いことから、今後もテレワークの定着が当たり前になると想定されます。
厚生労働省:テレワークの導入状況
企業の電子契約の利用率
2022年に何らかの形で電子契約を利用している企業の割合は69.7%でした。この数字は、2021年の67.2%から若干増加しています。
細かい利用状況としては「当事者型電子署名」を利用している企業が26%で最も多いという結果でした。
今後電子契約の利用率を高めるために解決すべき課題として、以下が挙げられます。
・導入メリットが分からない
・導入に手間がかかる
・法制度の理解ができていない
・体制の構築が不十分
これらの課題を解決すれば、脱ハンコ化を進められるでしょう。
脱ハンコで企業が得るメリット
脱ハンコ化に取り組むと、さまざまなメリットが得られます。ここからは、脱ハンコ化によって得られるメリットを紹介します。システム導入を検討する時の参考にしましょう。
テレワーク・DXの普及
近年、働き方改革の一環として、出社せずに仕事をする働き方(テレワーク)が普及しています。特に2020年以降、新型コロナウイルス感染症対策が流行し、毎日の様に出社をしない働き方が広まりました。つまり、どこにいても仕事ができる仕組みの導入・体制の構築が求められています。
脱ハンコ化がされていない企業では、書類に判を押すためだけに出社しなくてはなりません。そういった状況を無くす目的でも脱ハンコ化が推進されています。
コスト、リードタイムの削減
業務の電子化・脱ハンコ化を進めると、ペーパーレス化も同時に実現します。紙や印刷代、郵送費などを節約でき、コストカットに有効です。
書類や資料を印刷せずにオンライン上でやり取りができるようになることで、保管スペースや管理する人材の作業コストが不要になります。
手渡しや郵送で発生する、書類のやり取りの時間ロスがなくなり、社内の処理スピードが圧倒的に向上します。電子化と脱ハンコ化は、さまざまな業務の無駄の削減につながるでしょう。
関連記事はこちら
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
コンプライアンス、セキュリティの強化
重要な書類を紙でやり取りすると、管理が煩雑になり紛失や破損のリスクがあります。
書類をデータ化し、社内のシステムでやり取りすることで、書類の受け渡しの間に紛失する可能性が少なくなります。
また、社外に置き忘れたり、盗難されたりすることも防げ、セキュリティ向上にも有効といえるでしょう。
承認や業務完了の際に通知が届くようにすれば、進捗状況を社内で共有しやすくなります。間違いがあった際に警告も発信でき、ヒューマンエラーの減少にも有効です。
脱ハンコを進める上で発生する課題
書類の脱ハンコ化にはさまざまなメリットがありますが、導入には課題がいくつかあります。
例えば、電子契約システムの利用に導入費用がかかるほか、システムの導入によって全体的なフローの見直しが必要になる点も課題です。
また、社内の人々にシステムが必要なことを理解させる時間がかかる場合もあります。
場合によっては、電子化できない書類も存在します。
上記のような課題を事前に把握することで、脱ハンコをスムーズに進めることができるでしょう。
ワークフローシステム導入で脱ハンコの推進
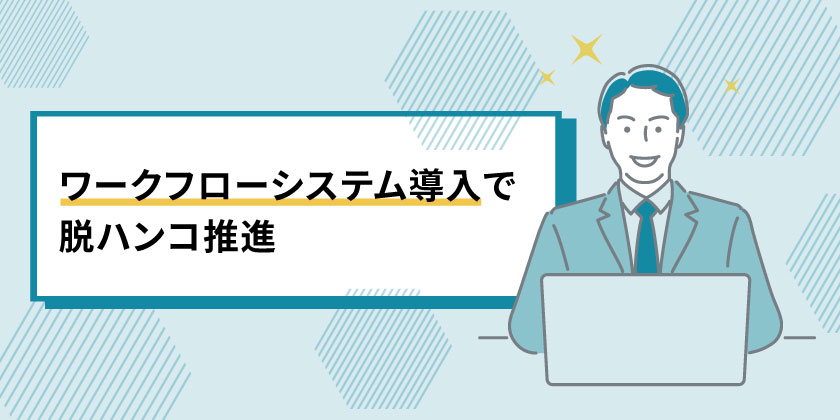
前述した通り、脱ハンコ化の重要性や課題を理解しても、全ての業務を電子化することは難しいものです。一気に全てを変えようとせず、いくつかのステップを踏んで電子化・脱ハンコ化導入を推進しましょう。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
押印が必要な書類の選別を行う
近年の法整備を受け、社内書類や請求書、領収書などへの押印が不要になりつつあります。
まず、脱ハンコ化を進める際は、社内で使用している書類について紙での押印が必要なものか否か判断しましょう。
電子化が必要なものと不必要なものを振り分けることで、取り組むべき書類の優先順位をつけることができます。電子化が容易で扱いやすい書類から脱ハンコを進めるようにしましょう。
ワークフローシステムで脱ハンコ
ワークフローシステムは、申請書や報告書などを処理するシステムです。出社が必要だったり、時間がかかるハンコ作業をワークフローシステムに切り替えることで、大幅に業務の効率化が期待できます。
また、ワークフローシステムを利用すると申請処理をシステム上で行うことができ、紙の書類への押印・捺印作業の削減が可能です。利用するシステムによっては印影の作成なども可能です。
ワークフローシステムを用いて、社内でハンコを使用する申請書、報告書などの自動化を促進しましょう。
まとめ
押印と捺印は書類に法的拘束力を持たせる重要な業務です。脱ハンコ化によって物理的に押印・捺印する機会は減りつつあります。
脱ハンコ化はテレワークの促進・ペーパーレス化・作業の効率化などさまざまな恩恵をもたらします。脱ハンコ化を検討する際は、ワークフローシステムの導入がおすすめです。株式会社コラボスタイルではワークフローシステム「コラボフロー」を提供しています。システム導入検討の際はぜひお問い合わせください。
ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。