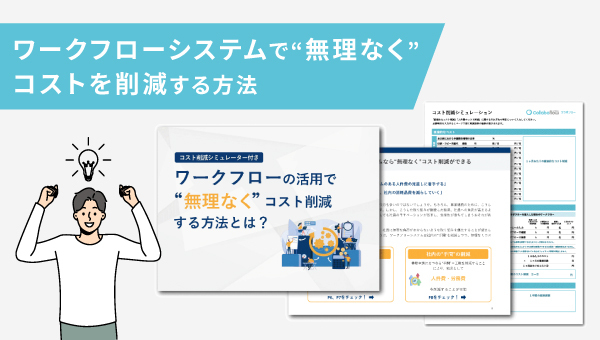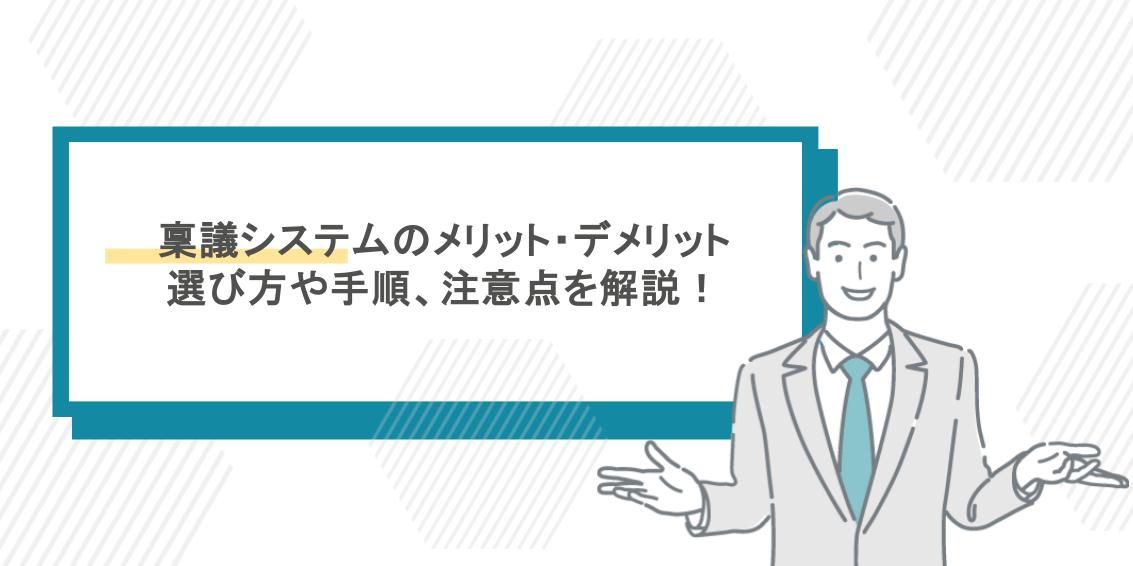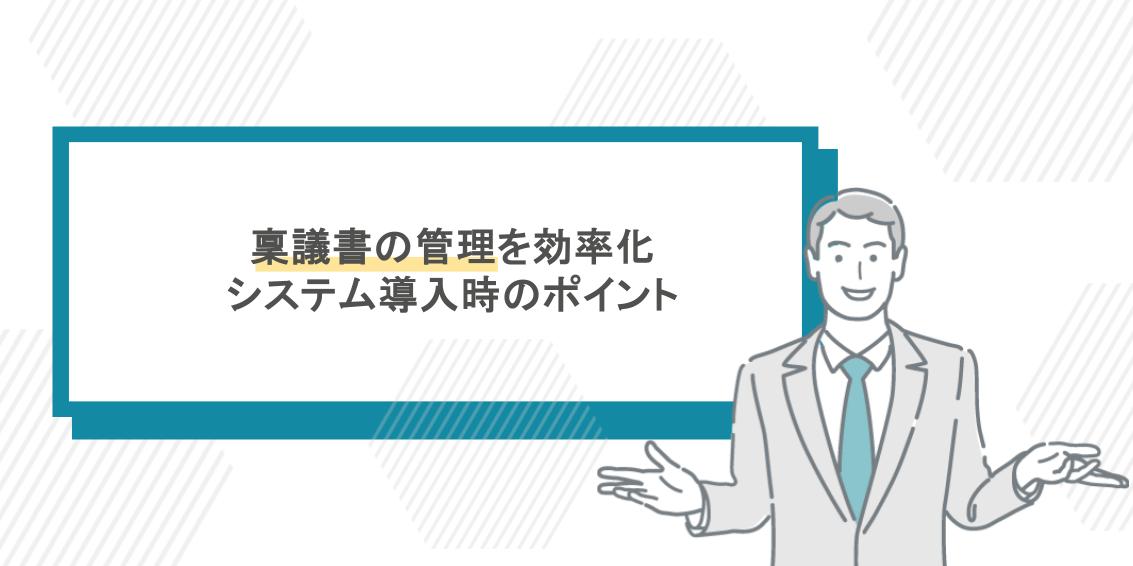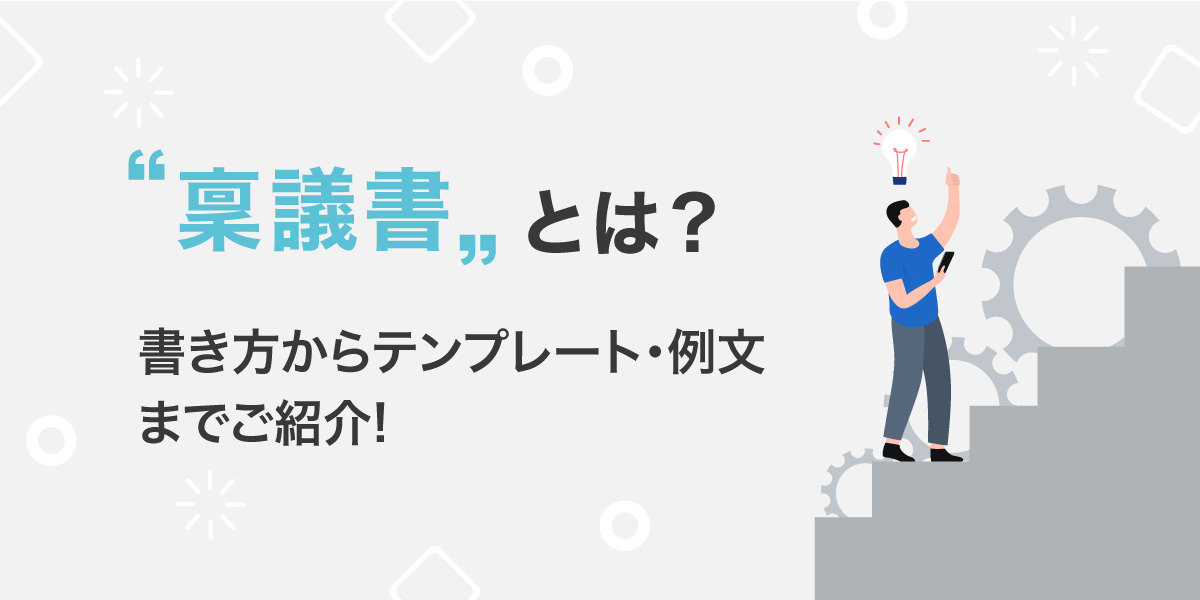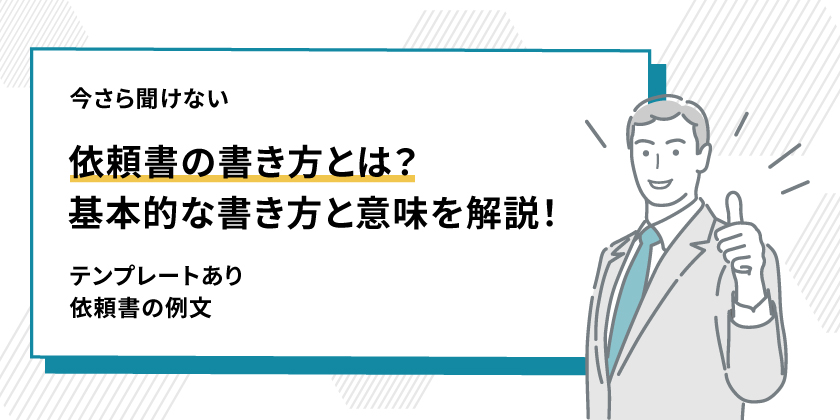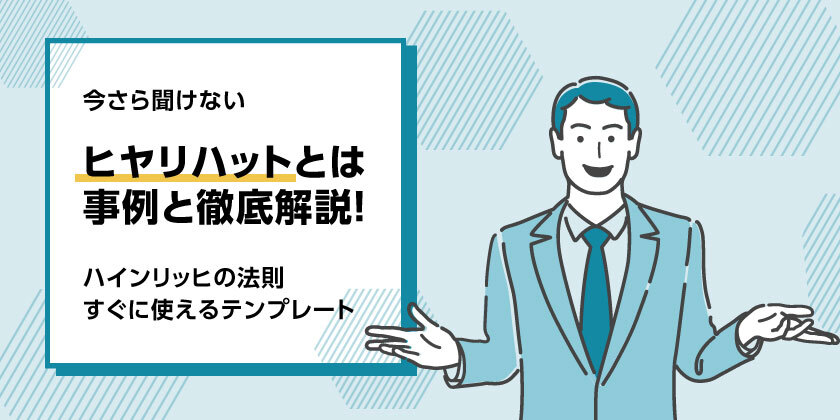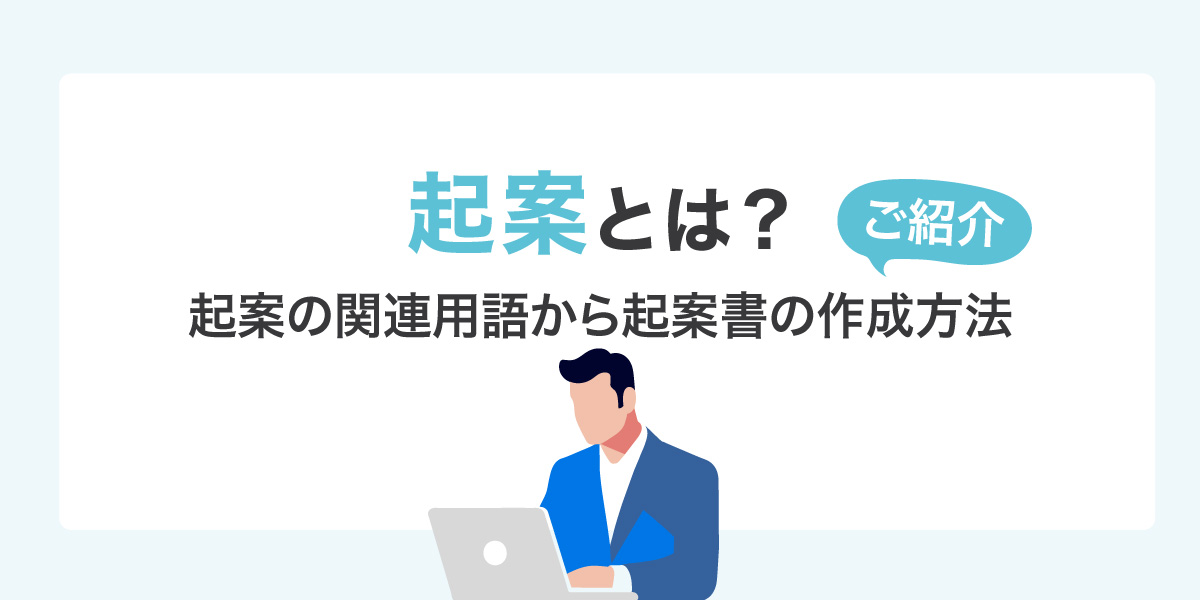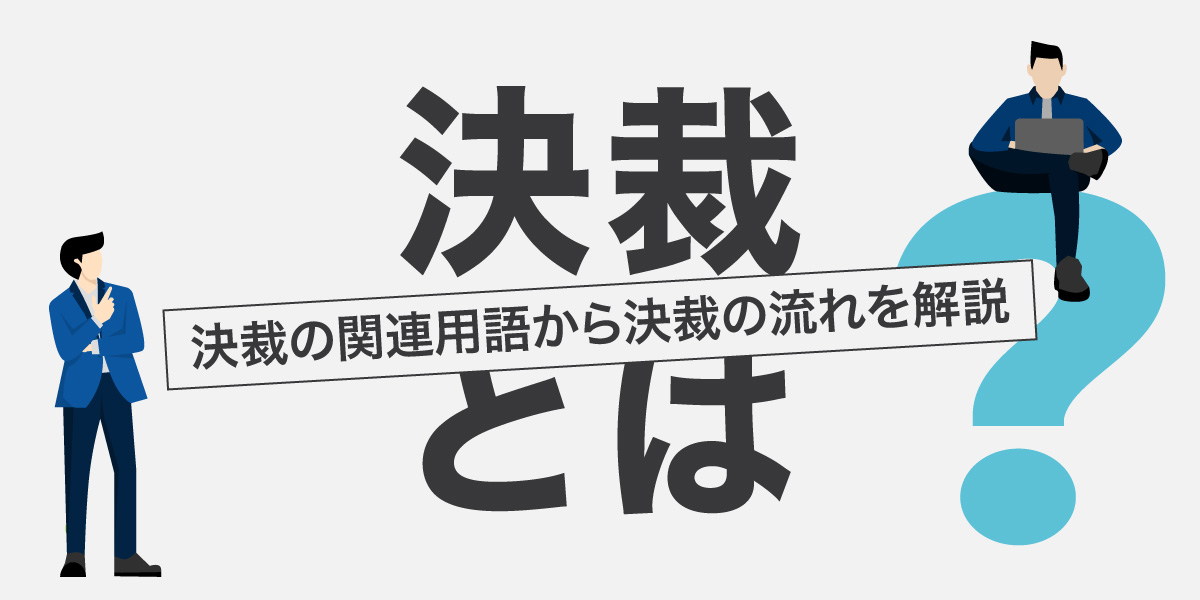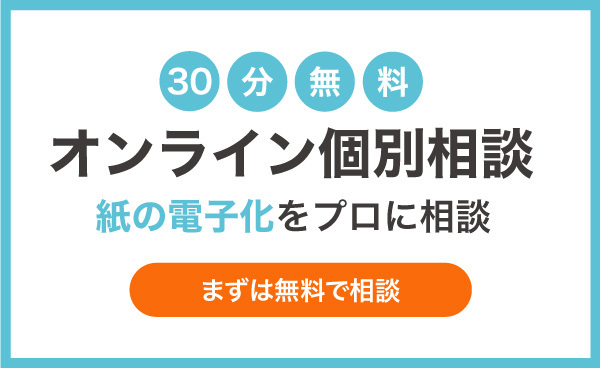この記事の目次
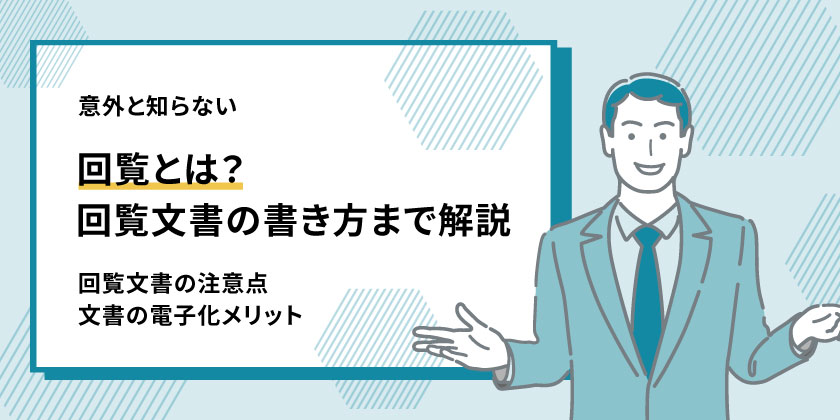
社内文書などの回覧は多くの企業でも活用されていますが、実は上手に活用できていないケースやそもそも問題に気づいていない企業も存在します。今回の記事は、企業内で回覧を効率よく活用する方法、書き方、注意点を解説します。
回覧とは
回覧とは、共有事項を記載した文書を人々へ順番に回すことです。回覧は企業においてとても重要です。ただし、回覧をするときは、ルールを守り、効率的に活用するためのポイントに留意する必要があります。
記事の最初に、回覧の基礎知識と必要性、種類を紹介します。
企業における回覧とは
企業における回覧は、回覧文書とも呼ばれます。回覧文書は、企業において関係者内で共有する内容を書いた文書です。
回覧文書は企業内で経営陣の意見を聞くときや、会議の議事録・関係者へ周知したい内容があるとき、社内で決裁を必要とするときなどに使われます。
複数の部署に回すため、関係者全員へ回るまでに時間を要してしまう場合がほとんどです。
回覧文書の必要性
回覧文書は意見を聞きたいときや情報を周知したいときに使われます。
口頭での伝達は、共有内容が正確に伝わらない、伝達漏れが起こる、などの危険性があります。
文章として回せば、各自でサインや捺印をして、確認の記録が可能です。文書を見れば共有事項が伝わり、回覧途中で共有内容が変わることを防ぐ効果もあります。
回覧文書の種類
回覧文書には、いくつか種類があります。たとえば、以下のような書類があげられます。
・上申書:異動に関する異議申し立て・トラブルに対する苦情および相談などに使われる
・稟議書:契約書や人事異動など、特定の案件に対し関係者の承認や決裁をする
・議事録:会議の内容を記録する
・通知文:関係者へ重要事項を伝える
・回覧文:複数で同じ情報を共有するため、関係者へ順に回す
関連記事はこちら
⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介
⇒帳票とは?帳票の種類から作成手順、効率化まで解説
⇒書類の電子化とは?導入前後で知りたいポイントや導入ステップを解説
回覧文書においての5つのルール
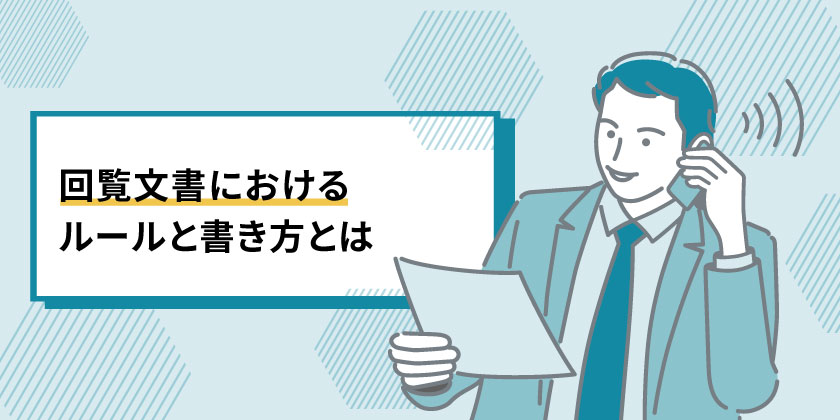
回覧文書は、いくつかのルールに従って発信すると効率よくスムーズに回せます。回覧の役目をしっかり果たすためにも、ルールを把握しておきましょう。
①閲覧者がすぐ理解できるよう簡潔にする
回覧文書の内容を最低限にすると、作成時間を短縮できます。それだけでなく、伝達スピードの促進が期待できるでしょう。
回覧文書のほとんどは、関係者へ早期に周知したい内容を含みます。文書はできるだけ早く全員へ回さなければなりません。
関係者は多忙な可能性が高く、じっくり文書を確認する時間の確保は難しいでしょう。全員へ効率よく通知するためにも、すぐに内容を把握できるような文章を心がけてください。
②リストを作成する
回覧文書を回すだけでは、関係者全員へ伝わりません。回す順番を把握する目的で、回覧者の一覧を作成しましょう。
一覧表に、内容を確認した人がサインもしくは捺印できる欄を作ると、誰が読んで誰がまだ読んでいないのかが分かりやすくなります。最後は誰に戻すのかも記載しておくと、文書がきちんと戻り、文書の紛失を防げます。
③メール回覧は返信を義務化する
メール回覧はすぐに送れるメリットがある一方で、誰が確認したかが分からないデメリットがあります。
確認後の返信を義務化すれば、確認の把握が可能です。別途で作成したリストを添付し、確認後に記名またはチェックをする方法もあります。
④すぐ確認し次へ回す
回覧において大切なことは、早く回すことです。共有したい内容を素早く全員へ送れば、その後の業務をスムーズに進められます。
すぐ内容を確認して回さなければ、回覧自体を忘れて、回覧が止まる恐れがあります。回覧が止まると、情報共有ができません。回覧が回ってきたら、すぐ内容に目を通すようにしてください。
⑤不在の人は飛ばす
回覧を回すときに、不在の人がいれば順番を後にしましょう。不在の人を待つと、回覧が停滞します。一時的に順番をスキップし、後から改めて確認してもらいましょう。不在者リストを作成すれば、再度回覧を回す際に便利です。
ただし、不在の人が役職者や案件の担当者である場合、順番通りに内容を確認しなければならないかもしれません。回覧内容によっては、不在の人や上司へ相談した上で対応するようにしてください。
回覧文書の書き方
回覧文書は、適切な書き方をするとより伝わりやすくなります。回覧を作成するときは、複数の人が多忙の中確認する点を前提に作りましょう。ここからは、回覧の基本の書き方を紹介します。
①タイトルを簡潔に書く
回覧を確認する関係者の多くは、他にも業務を抱えています。業務の合間で内容を確認できるよう、タイトルは分かりやすくしましょう。
たとえば、予定している研修の開始時間の変更を通知したい場合、「○○研修の開始時間変更のお知らせ」や「○月×日実施予定の研修開始時間変更について」など、研修名や開催日を入れると、伝わりやすくなります。
②発信元と対象者を明確に書く
回覧文書は、多く出回ります。誰からの発信で、誰に向けての回覧かをはっきりさせなければ、関係者全員へ正しく回覧されない恐れがあります。発信者と回覧対象者を明確にして、関係者が識別しやすいようにしてください。
回覧対象者として個人名を並べると、文章量が多くなり分かりづらくなります。「●●部署各位」「関係者各位」など、宛名はまとめて記載しましょう。
発信元は、問い合わせ先の電話番号や内線番号、業務用携帯の番号の明記がおすすめです。確認事項や不明点があった場合にすぐ聞けるようにする配慮が欠かせません。
③主文から書く
閲覧した人がすぐ内容を把握できるよう、必要事項のみ記載しましょう。挨拶文や締めの文は省きます。
作成するときも、主文以外の内容を考えると時間がかかり、回すまでに時間がかかるでしょう。
対象者は社内の人であり、わざわざ挨拶文や締めの文を載せる必要はありません。
見る側が邪魔に思わないためにも、作る側が面倒にならないためにも、回覧文書には必要最低限の通知内容のみ書くようにしてください。
④箇条書きで重要な内容を分かりやすく書く
回覧文書で特に共有したい重要部分は箇条書きでの表記がおすすめです。箇条書きは内容を強調する効果があります。
ただし、すべてを箇条書きにすると重要なところが分かりにくくなります。
基本は「です・ます」を使った敬体で作成して、大切なところや強調したい部分はポイントで箇条書きを使うとよいでしょう。
また、専門用語や難しい漢字を多用せず、閲覧する側がすぐ内容を理解できる言葉での表現も大切です。
⑤回答期限を記載する
回覧した文書には、回答期限を記載しましょう。回答期限を設けないと、閲覧者が回答を後回しにする恐れがあります。
特に、業務量が多い人は、回答期限がない文書の優先順位を低くしてしまうかもしれません。
また、期限がない文書は回覧が止まる原因にもなります。
このような事態を防ぐため、回答期限ははっきり記載しておきましょう。期日の表記方法は、文書作成日と統一しておくことも大切です。
社内で年を西暦もしくは和暦で記載する指定がある場合は、規定に従いましょう。
回覧文書における4つの注意点・問題点
回覧文書を関係者全員へ迅速に回すにあたって、注意しなければならないポイントや問題点が存在します。注意点や問題点を把握して、回覧文書を効率よく活用するための解決策も検討しておきましょう。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
⇒書類の電子化とは?導入前後で知りたいポイントや導入ステップを解説
①回覧がどこまで回っているかが分からない
回覧文書を共有する関係者の数が多いと、どこまで回っているか把握しづらくなります。誰が文書に回答したかどうかの確認もできず、回答の集計も不可能になるでしょう。
回覧がどこまで回っているかを知るためにはリストがおすすめです。しかし、リストが回覧文書と一緒に回っていると、発信者は状況が分からなくなります。
②回覧が止まる
回覧が途中で止まり、関係者全員に回せない点も問題です。多忙で確認を後回しにする人は多いと想定できます。
紙媒体の回覧文書は、テレワークや外回りなどの理由で会社にいない人を確認できません。不在の人は飛ばすとよいと紹介しましたが、出社しない人は、紙媒体の回覧自体を見ないでしょう。
③紙媒体文書のセキュリティ問題
紙媒体の回覧文書は、文書自体を紛失してしまうリスクをもちます。
第三者へ見られて内容が漏洩する危険性もあり、内容が機密事項である場合は大きな問題に発展するかもしれません。セキュリティ面でのリスクが伴います。
このような事態を防ぐためにも、セキュリティに配慮した回覧方法が必要です。
④紙媒体だと出社が必要
社内で紙媒体の文書を回すと、出社していない人が確認できないデメリットがあります。
最近は、働き方改革による在宅勤務や直行直帰など、出社しなくても働ける環境が増えています。出社しない人にとっては、紙媒体の文書は確認も情報共有もできない問題が考えられるでしょう。
どのような働き方をしていても、関係者全員で情報共有できる方法が求められます。
回覧文書を電子化することのメリット
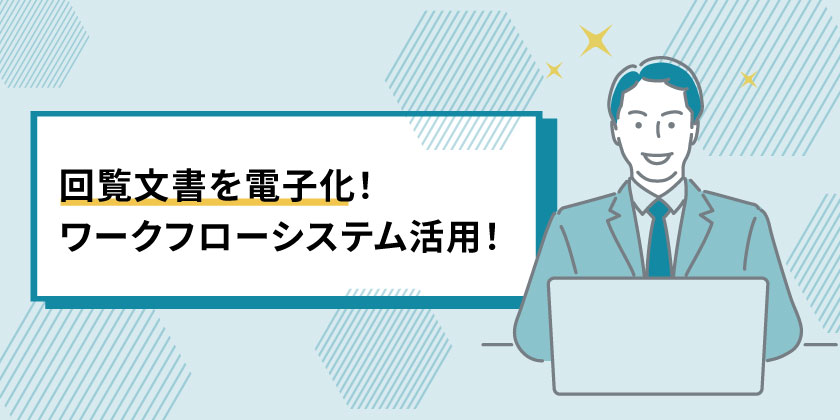
紙媒体の回覧文書には、多くのデメリットがあります。この問題を解決するためには、回覧文書の電子化が有効です。ここからは、回覧文書の電子化におけるメリットを紹介します。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介
書類テンプレートのダウンロードはこちら
リンクをクリックして、使いたい書類を検索してください。
⇒テンプレート一覧ページ
ワークフローシステム「コラボフロー」にアップロードして活用できるExcelテンプレートを無料で配布中
①素早く回覧でき情報共有が早くなる
回覧文書を電子化するシステムは多く存在します。
テンプレートを作成できるシステムを選べば、文書作成が手軽になります。文書の作成スピードが速くなり、誤字脱字を防ぎやすくなる点もメリットです。
過去の文書の内容も引き継げるため、継続した案件を通知する場合や複数の日に渡って回覧するときにも便利です。
②回覧状況が分かる
紙の場合、文書のほかに回覧リストを作成します。
しかし、文書と回覧リストは社員に順番で回していくため、いま誰の手元にあるのか、回覧し終わったのか確認する管理者の手間が増えてしまいます。
記録機能がついているシステムを使えば、誰が確認したかを自動的に記録できて大変便利です。確認した人の記録により、確認していない社員がすぐに分かり、早期に催促できます。
回覧の確認催促もシステム上でできるため、業務を効率よく進められます。
③セキュリティ向上
紙媒体の回覧文書は、セキュリティ面でのリスクが大きいといえます。
システムに、順を追って確認しなければ確認済みの記録ができないルールを設定すれば、確認漏れを防げます。
見る人や文書を編集をする人の権限をつけられる機能を活用すると、セキュリティ向上に大きな役割を果たすでしょう。
④コスト削減
回覧文書を電子化すると、紙媒体で負担となる紙やインクなどの消耗品を削減できます。消耗品にかかっていた経済的なコスト削減は、企業にとって大きなメリットです。
近年は、政府が環境に配慮した取り組みを推奨する動きが高まっています。紙やインクなどの消耗品を削減すれば、環境保護への貢献が期待できるでしょう。
⑤場所を選ばず閲覧可能
回覧文書の電子化で最大のメリットは、どこにいても回覧を確認できる点です。
システム上で回覧すれば、閲覧者が場所を選ばずにスマートフォンやパソコンで確認できます。テレワークや直行直帰をしている人も、わざわざ出社する手間を省けることは大きなメリットでしょう。
どこでも確認できる環境を作ると、すぐに回覧を確認でき、回覧スピードが上がります。
まとめ
紙媒体の回覧文書には、さまざまな問題点があります。このような問題を改善するためにも、回覧の電子化がおすすめです。
株式会社コラボスタイルでは、ワークフローシステム「コラボフロー」を提供しております。コラボフローは簡単な操作で、回覧に必要なルール設定を行えます。回覧する関係者の設定や記録も、パズル感覚でスムーズにできる点が特徴です。
30日間の無料お試しもできるため、実際に操作して利便性を体感してみてください。導入にあたってのご相談もお受けしております。
ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。