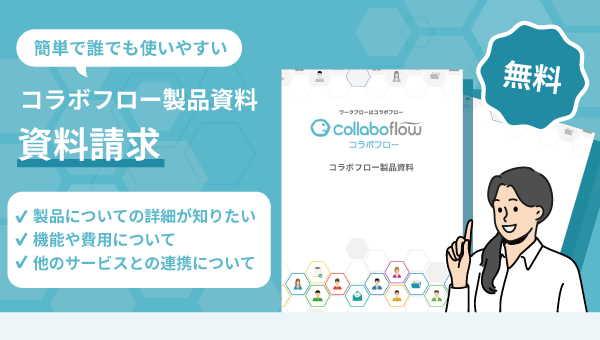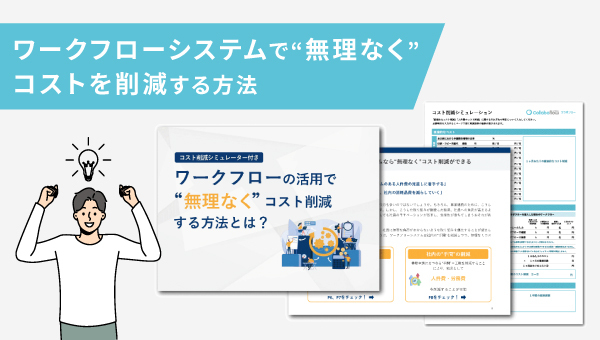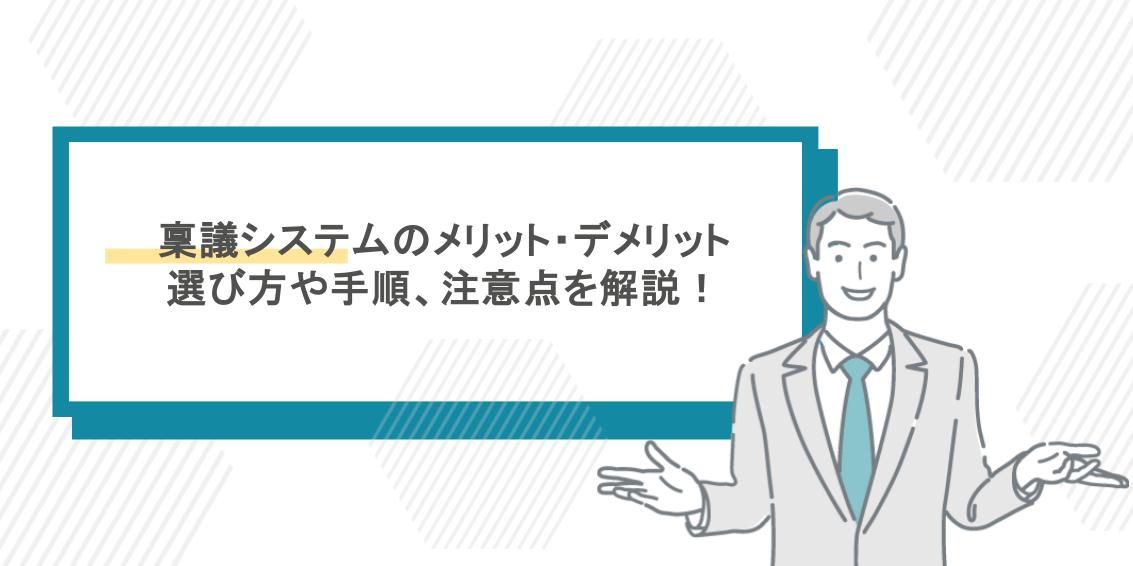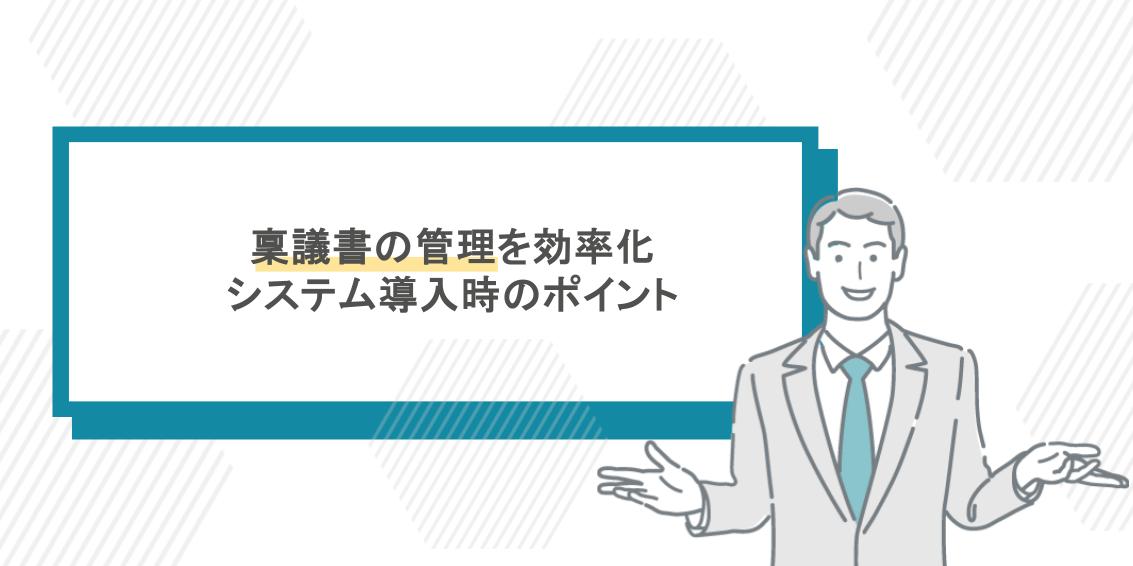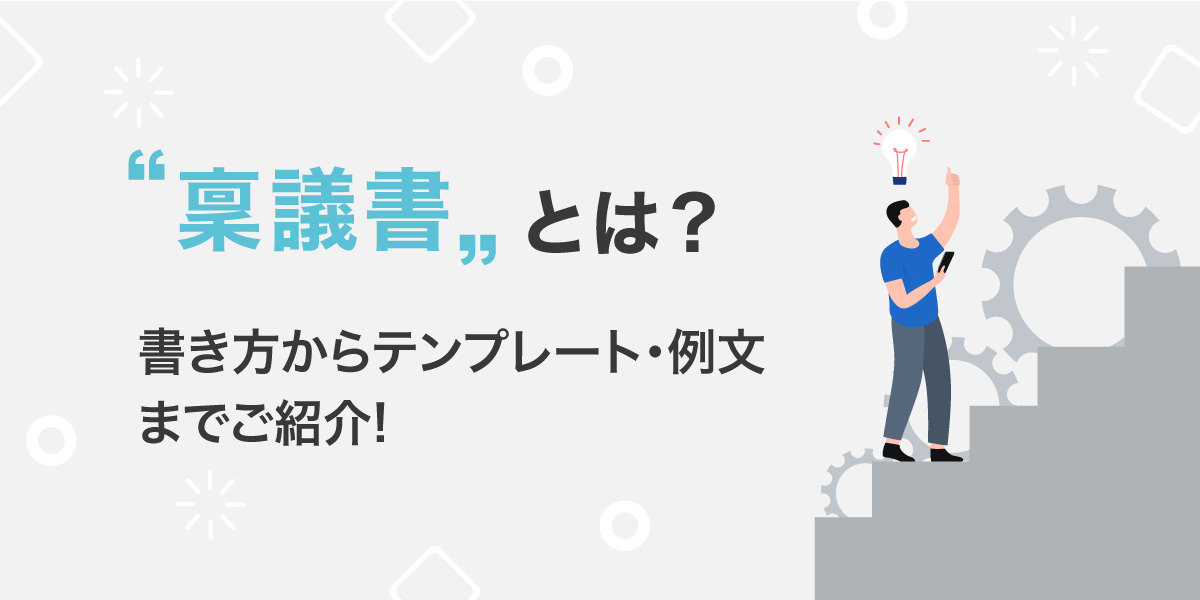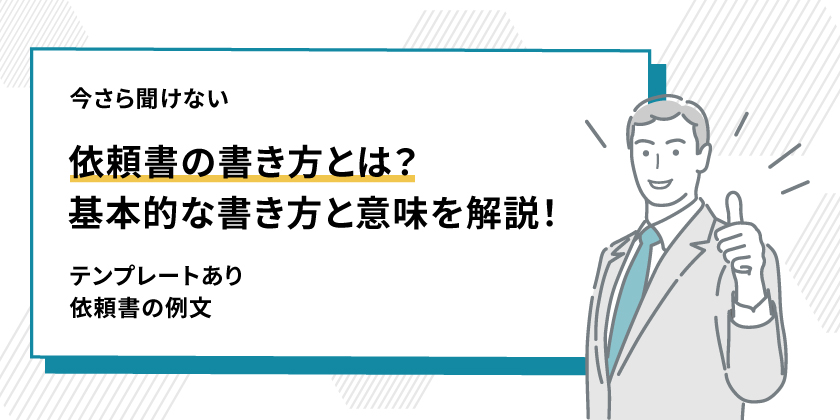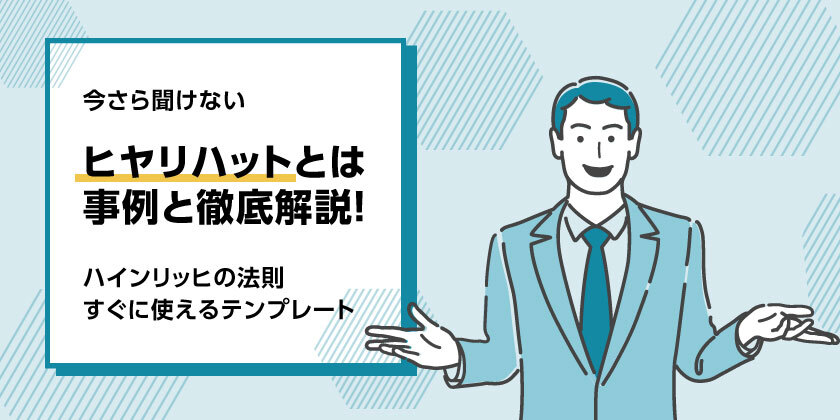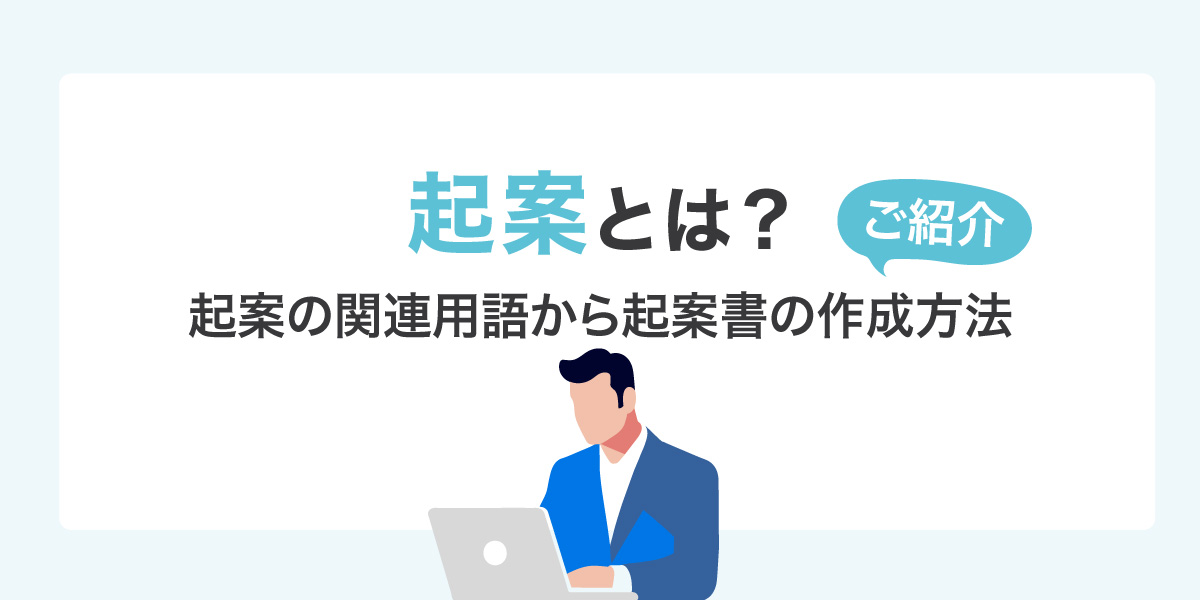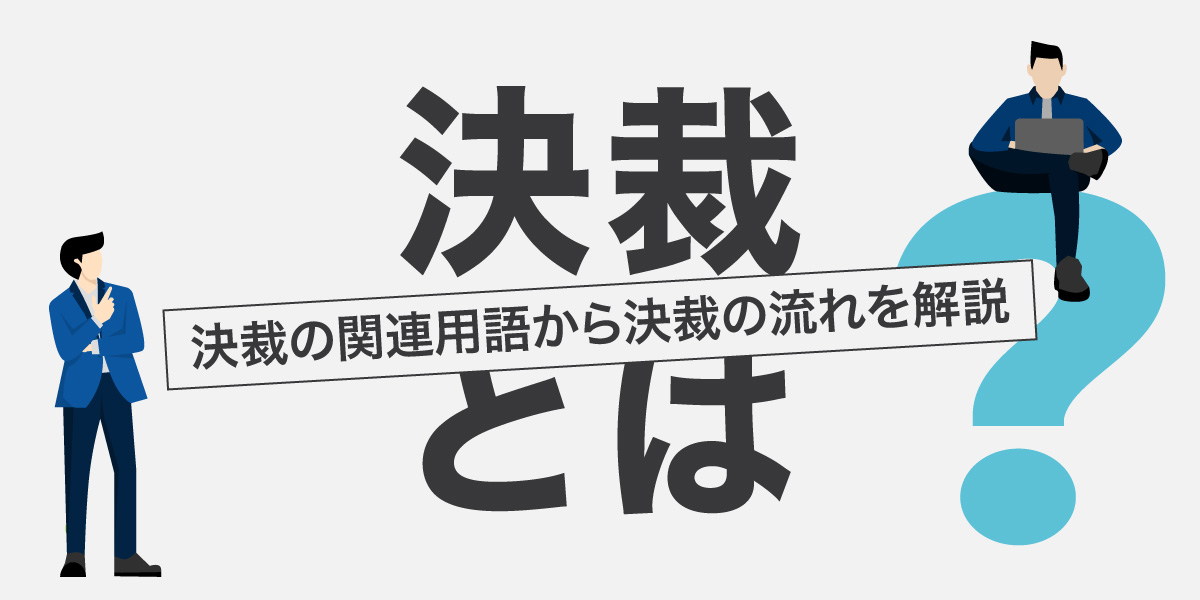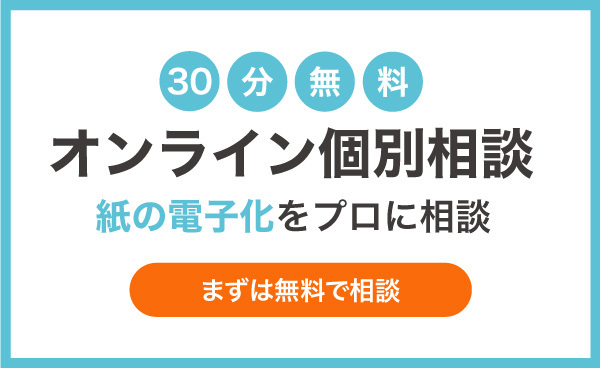この記事の目次
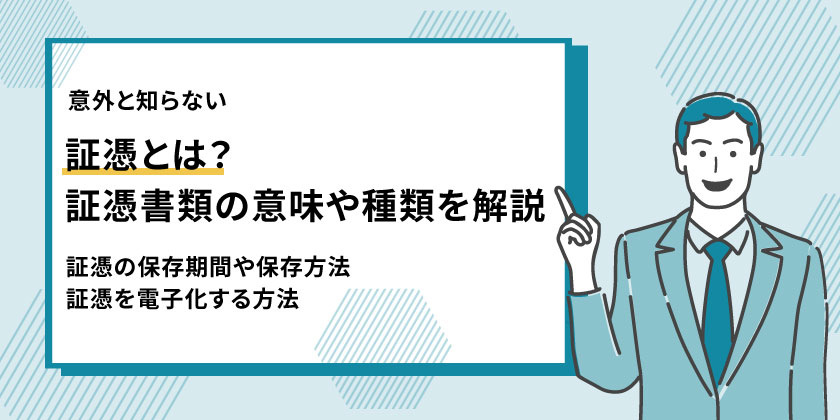
証憑は、取引の詳細とその事実を記録しておく書類です。企業の活動を示す重要な書類です。法律により区分や保存する期間が定められています。
今日、証憑は改正電子帳簿保存法によって電子化することが推奨されています。証憑の種類や保存期間、電子化のメリットを解説します。
証憑とは
証憑は「しょうひょう」と読み、取引を証明する書類の総称です。英語では”documented evidence”であり、記された証拠と訳せます。それぞれの取引について記録した書類として作成、保存をします。
証憑と帳票の違い
証憑と似た言葉に「帳票」があります。帳票は会計の内容を記した帳簿や伝票を指す言葉です。入金、出金の伝票や現金出納帳などは帳票にあたります。帳票のうち、それぞれの取引の証拠である入金伝票と出金伝票は証憑にも該当します。
「証票」は異なる書類です。何かを証明する札や書き付けという意味をもち、身分証明書や登記書などを含みます。
関連記事はこちら
⇒帳票とは?帳票の種類から作成手順、効率化まで解説
証憑書類の種類
証憑書類には売上や諸経費、物品、雇用、契約、その他多くの書類が該当します。証憑書類の分類、それぞれについて解説します。
売上・諸経費に関する証憑
売上についての書類や仕入れに関連する書類は、証憑に含まれます。
主に以下のものが、売上・諸経費に関する証憑として扱われます。
・請求書
・領収書
・借用証明
売上に関係する証憑は、金銭のやり取りが発生したことを証明する書類です。売上や仕入れについての書類のほとんどは証憑といえます。取引先との金銭による取引を証明する書類ともいえるでしょう。
借用証書は借主が貸主に対して作成するお金の借入や返済の期日を証明する書類です。これも金銭を伴う取引の証明であり、売上や諸経費についての証憑に含まれます。
物品に関する証憑
物品の移動に関する書類も証憑です。取引の結果によって商品や付属品などの品物が移動する場合、移動を示す納品書や受領書が含まれます。注文請書や納品書も物品についての証憑です。
移動だけでなく、在庫数を証明する棚卸表などの物品の管理についての書類も証憑とみなされます。
物品に関する証憑には、以下のものが含まれます。
・発注書
・納品書
・受領証
このほか、研修書や見積書なども物品に関する証憑として扱われます。
検収書は、商品や製品の数量や仕様を確認する、検収という作業を行ったことを証明する書類です。これもまた物品に関する証憑です。
雇用に関する証憑
雇用における書類も証憑に含まれます。従業員と雇用関係を結び、給与を支払うことが取引に相当します。
雇用に関する証憑には、以下のものが含まれます。
・雇用契約書
・給与明細
・賃金台帳
契約書は労働についての取引の証明にもなります。履歴書や雇用契約、給与の支払明細なども雇用についての証憑の一つです。
雇用関係を結ぶために、相手との間でやり取りした書類はいずれも証憑に含まれます。働き出してからの、タイムカードや出勤記録、賃金台帳なども雇用に関する証憑です。人事に関する書類も、給与や勤務内容に関連するため証憑とみなされます。
契約に関する証憑
契約についての書類も証憑です。金融機関との間でかわされる銀行取引約定書や土地家屋に関する賃貸借契約書などは証憑とされます。
契約に関する証憑には、他には以下のものがあります。
・取引基本契約書
・業務委託契約書
・秘密保持契約書
社内や取引先との会議における議事録に加え、相手方と交わした念書、社内で複数の関係者の同意を求めて交わされる稟議書なども、契約についての証憑です。契約をする行為が取引の前提とみなされます。契約に関係する書類も証明のための書類と考えられます。
その他証憑
その他、取引に関する証拠書類であれば、証憑に含まれます。
例えば、以下のものが、その他の証憑として扱われます。
・通帳
・議事録
・稟議書
銀行口座の通帳や銀行から融資を受けている場合は、返済予定表も証憑です。会計のミスを修正するためのメモや、業務の手順を示したマニュアルも証憑とみなされます。
秘密保持契約書は、自社の秘密情報を目的以外で第三者に開示したり、漏洩させないことを義務付ける契約書です。契約であり取引に関連する事項である以上はこちらも証憑です。
証憑を保存・管理する目的
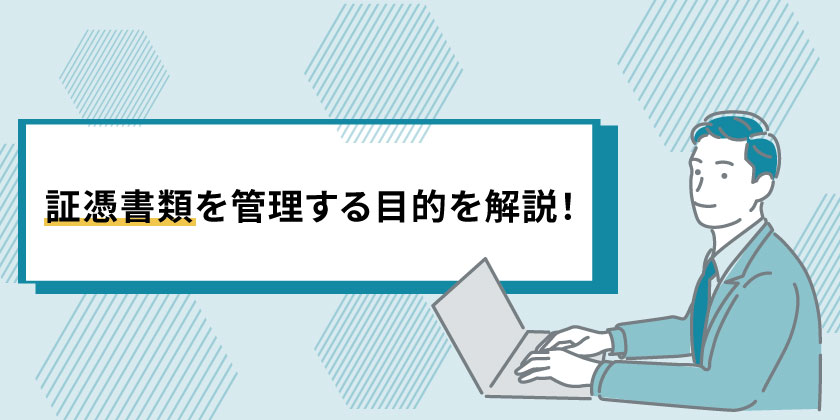
証憑書類は、基本的に書面を受け取ったあと、一定の期間の保存が義務づけられています。定められた保存期間中に、書類を処分したり紛失したりすると罰則の適用となる可能性があります。
証憑は、相手方との取引や金銭のやり取りの証明です。万が一取引先とのトラブルが発生した場合、証憑は適切に対処をするための材料になります。
証憑の保存期間
証憑の保存期間は、法人と個人事業主で異なります。関連する法によっても対象となる書類や保存期間が変わる点に注意しましょう。ここからは、それぞれの場合における保存期間について解説します。
法人の場合
法人の証憑の保存期間は以下の通りです。
| 関連法 | 対象 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 法人税法 | 帳簿と取引について作成または受領した書類 | 7年 |
| 法人税法 | 青色申告書を提出し欠損が生じた事業年度と青色申告書を提出せず災害損失金額が生じた事業年度について | 10年 |
| 会社法 | 会計帳簿、事業の重要な資料 | 10年 |
| 消費税法 | 適格請求書 | 7年 |
個人事業主の場合
個人事業主の場合、証憑の保存期間は以下のようになります。
| 関連法 | 対象 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 所得税法 | 青色申告:総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿類、決算書類、現金の取引に関する証憑 | 7年(前々年分所得が300万以下の事業主は5年) |
| 白色申告:決算に関して作成した棚卸表その他の証憑書類 | 5年 | |
| 消費税法 | 適格請求書 | 7年 |
証憑の保存方法
証憑はいつでも確認できる状態での保存が求められます。目的にあう形で適切に管理・保存しましょう。ここからは、証憑の保存方法を紹介します。
内部で保管
内部で保管する場合、会社の倉庫や専用の保管庫による保管方法があります。その場合、どこに何があるのかという点を管理するシートを作成しましょう。保管場所の把握が必要です。
保存期間は長期にわたります。紙やインクが劣化しやすい環境は、紙媒体の書類保管に向いていません。保存場所の空調を整える、湿度を一定に保つなど環境に配慮しましょう。
内部で保管すると、スペースと管理、環境維持の手間が膨大になる可能性があります。
外部で保管
外部で保管する場合、専門の保管業者に委託します。内部よりも、劣化や盗難の危険性を抑えられる方法です。
ただし、外部に保管を任せると、書類の参照がすぐにできません。業者に連絡し、郵便で送ってもらうと時間がかかります。
外部の委託は費用もかかります。書類が莫大な量の場合は負担が大きくなるでしょう。
証憑は電子保存が可能
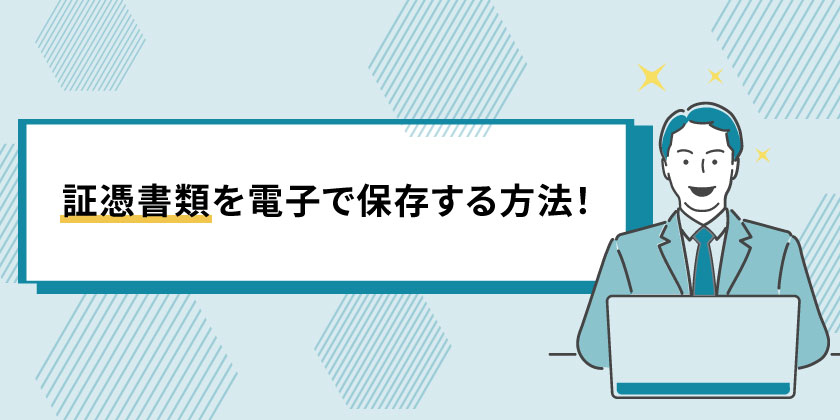
経理の電子化の推進を目的として、2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されました。税法で保存が義務とされている書類の電子的な保存を認めた法律です。この改正法により、証憑のデジタル保存が加速すると予想されています。
ワークフローシステムのような証憑書類を扱うシステムでは、連携するサービスなどを活用して電子帳簿保存法に対応することができます。
電子取引
改正法は、電子データの形式の書類は、デジタルでの保存を必須とします。
紙で受け取った書類は紙のまま保存できます。メール添付などで受け取った電子データの証憑に関しては、デジタルで保存しなければなりません。
猶予期間は2023年12月に迫っていて、電子データでの証憑のやり取り及び保存については早期の対応が求められます。
スキャナ保存
改正法では、紙で存在する書類を電子化し保存するための要件も定められています。
電子化にはスキャナが用いられます。200dpi以上の解像度でのカラー読み取りが要件です。一般的なスキャナであれば、この要件は満たすでしょう。
スマートフォンやデジタルカメラの撮影による画像化も「スキャナ」の要件を満たします。例えば、スマートフォンのアプリを使用したスキャン保存も可能です。ただし、書類の真実性を担保するため日時の記録が必要です。
証憑を電子化するメリット
証憑の電子化には、コストや手間がかかるでしょう。しかし、証憑の電子化には多くのメリットがあります。証憑を電子化するメリットを解説します。
業務の効率化
証憑を電子化する最大のメリットは、検索性の向上や業務の効率化です。
証憑書類を電子化すると、ソフトウェアやアプリによる自動化が進められます。自動化は、書類同士を関連、同期させることで必要事項が自動で記載される機能です。こうしたシステムは業務の効率を大幅に高めるでしょう。
電子化された証憑は検索により即座に探し出すことができます。書類の保管や移動のタイムロスがありません。
働き方改革
証憑の電子化は、テレワークの促進や定着にも効果を発揮します。
電子化は、書類の手渡しによる回覧やハンコを使った確認を不要とします。
書類が紙化されず、やり取りがセキュリティで保護された内部ネットワークで行われるため、第三者による閲覧や持ち出しといった情報リスクの軽減が可能です。
クラウド管理を行えば、場所によらず書類の作成や発送、承認が可能となります。リモートワークの推進につながります。
省スペース化
電子化による省スペース化も、大きなメリットです。
電子化により紙媒体の証憑が減れば、保管庫や書類棚といった保管スペースが節約できます。劣化を防ぐための環境調整設備も不要となるでしょう。
大きな企業であるほど、過去の証憑は莫大な量となります。こうしたスペースが不要になればオフィスに必要な面積が減り、賃貸料の削減につながります。
コスト削減
単純に、証憑の電子化は印刷の用紙やインク、ファイル、保管棚といった備品を必要としません。こうした物品にかかるコストを大きく削減できます。
紙媒体の使用を最低限に抑えることで、コピー機などのOA機器も削減、あるいは縮小することができるため、決して小さい削減ではありません。
また、紙媒体の保管のために管理を行う人員を必要としていた場合、人件費の削減と人材の有効活用にもつながります。
ワークフローを活用でコスト削減!
コスト削減シミュレーター付きの資料を公開中!
セキュリティ強化
紙媒体の証憑の保管は、場合によってはセキュリティシステムでの監視が必要です。証憑には特許関連の書類や個人情報も含まれており、盗難リスクがあります。
証憑の電子化はそうしたリスクを緩和できます。もちろん電子セキュリティへの注力は必要です。高いセキュリティをもったクラウドを活用すれば、リスクを最小限にできるでしょう。
クラウド型のワークフローを導入すれば、セキュリティは強化されます。
証憑電子化の成功事例
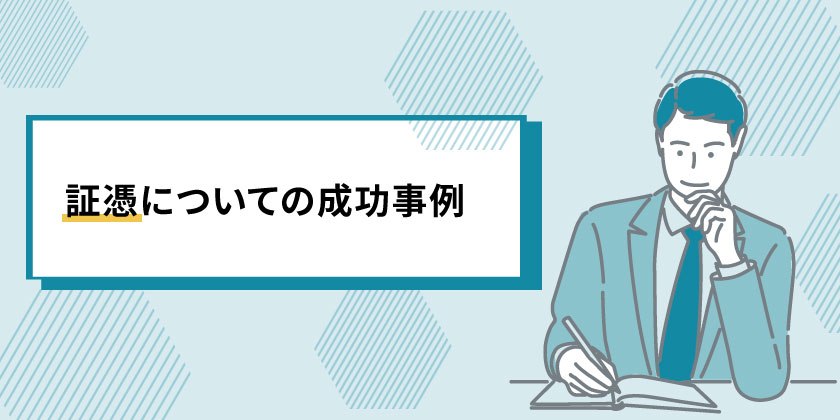
ここからは、証憑についての電子化、ワークフロー導入の成功例をご紹介します。電子化のメリットを最大限に生かして、業務の改善や効率化に成功した事例です。
紙ベースの書類処理時間を85%削減した例
株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズは、コラボフローの導入により紙ベースの書類処理時間の85%削減に成功した事例です。
これまで申請書は、紙とExcelによる運用をしておりましたが、Excel帳簿を再利用可能なコラボフローに置き換えたことで、手間や時間の問題が解決できました。
承認フローの可視化や入室申請のオンライン化などにより、大幅な業務の効率化を実現しています。
事例記事の詳細はこちら
⇒紙ベースの運用やローカルルールの横行が問題に。コラボフロー導入で85%の紙削減と業務フローの円滑化を実現
経理の残業時間を「ゼロ」にできた事例
株式会社フォーバルテレコムでは、コラボフローの導入により経理部門の残業時間を「ゼロ」にできた事例です。
導入前はExcelの運用を行っており、それが原因で各々の進捗が見にくく、使い勝手が悪いなど社員・管理側双方の負担となっていました。
その後、Excelのシートを活用しながらコラボフローを導入をすることで承認フローの効率化に成功。社員の書類回収のスピードも改善され、中長期的に見ても効果的な取り組みと言えます。
事例記事の詳細はこちら
⇒経理の残業ゼロを実現! 業務効率化とコスト削減を両立できた
まとめ
証憑の種類や保存期間、電子化のメリットを解説しました。証憑に限らず、経済活動全体について書類の電子化とワークフロー化の流れは進んでいます。電子化は、対応を求められる課題ではなく、ワークフローを効率化するチャンスです。
コラボフローは、高い柔軟性と使い勝手の良さで企業の電子化をより効率的に進められるワークフローシステムです。ご興味のある方はぜひご検討ください。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。