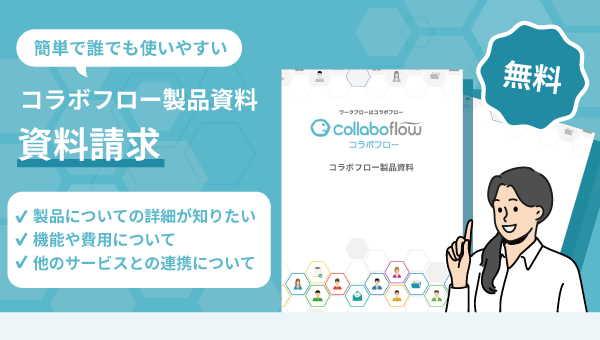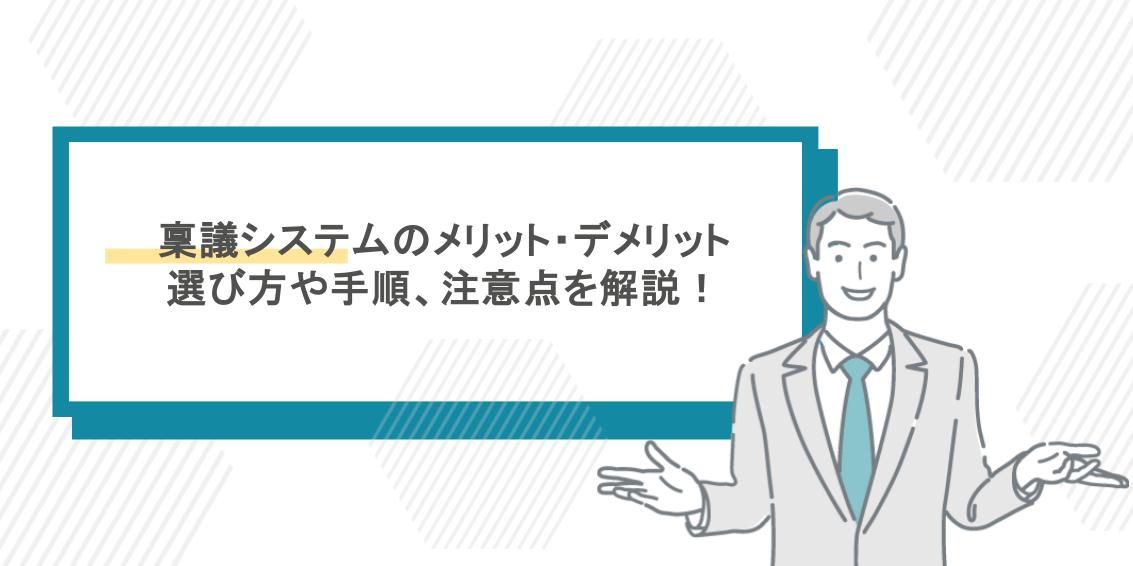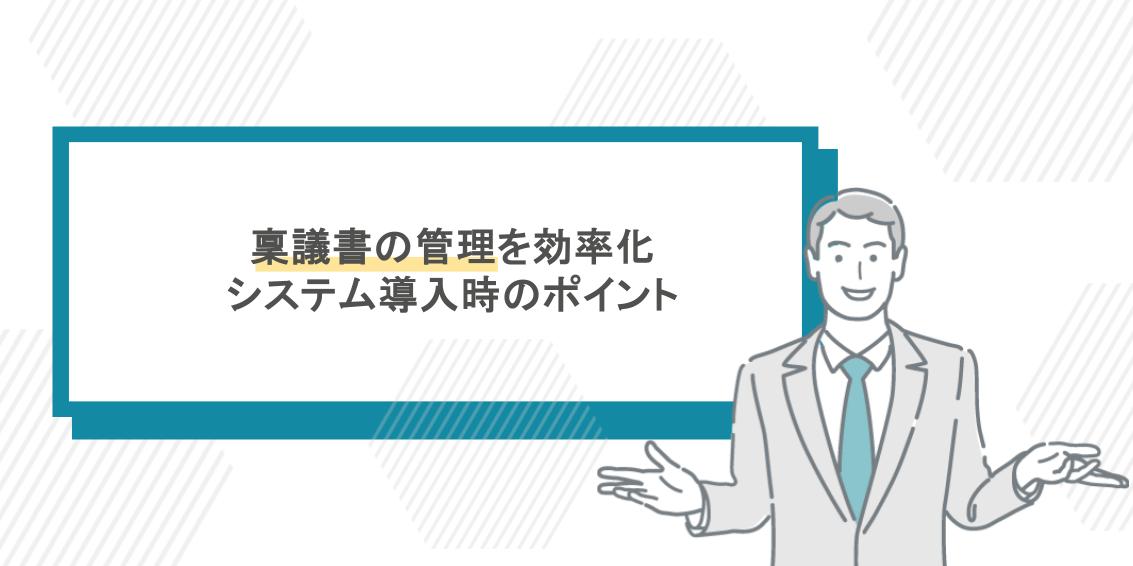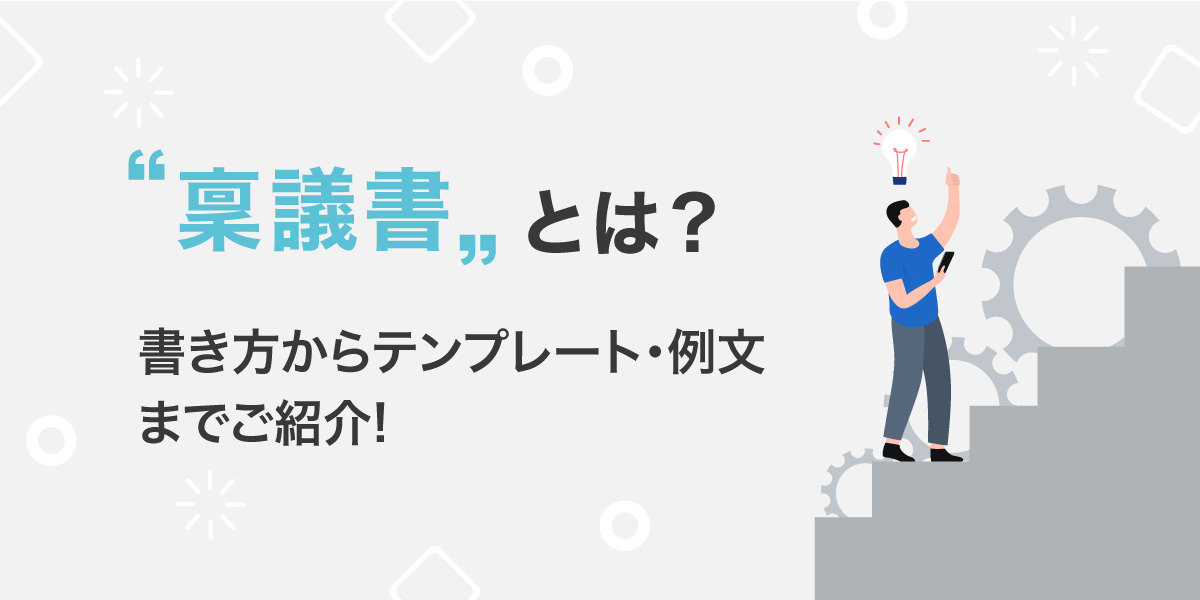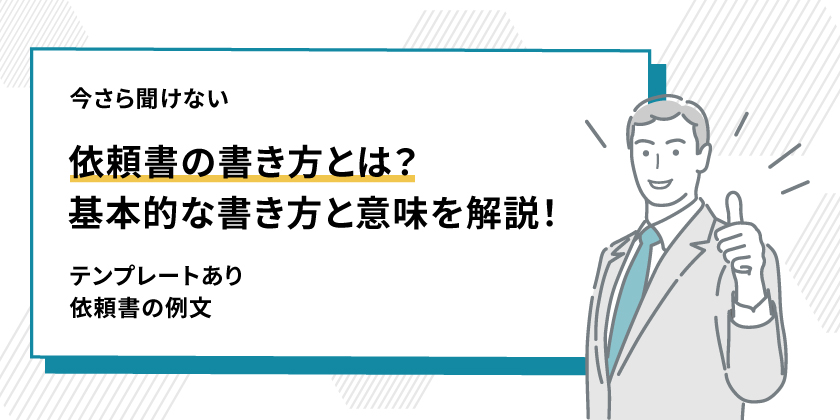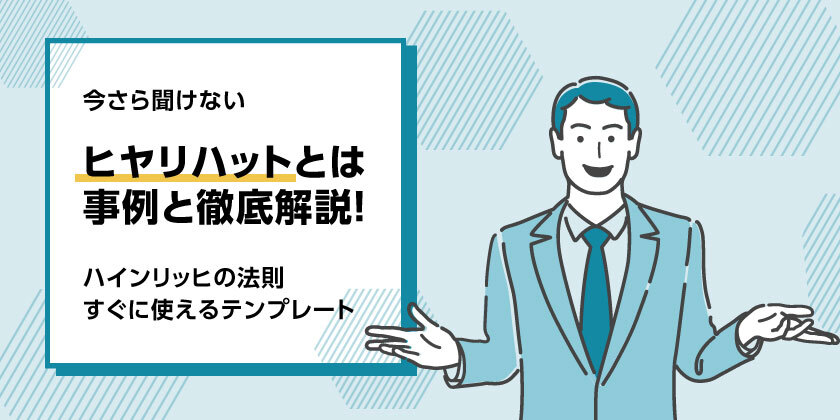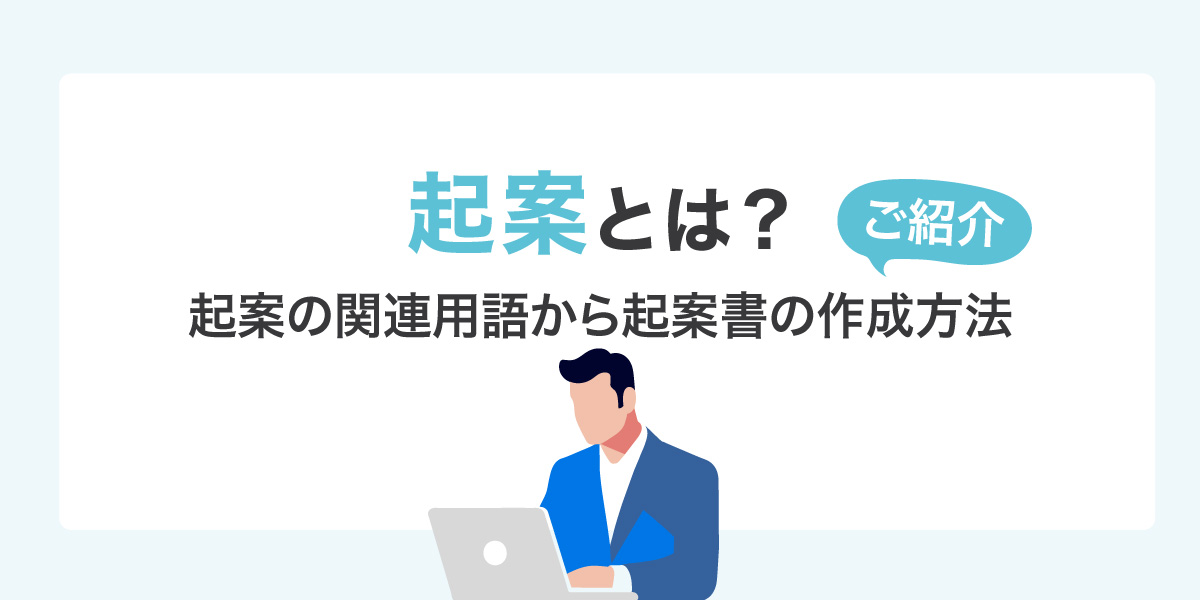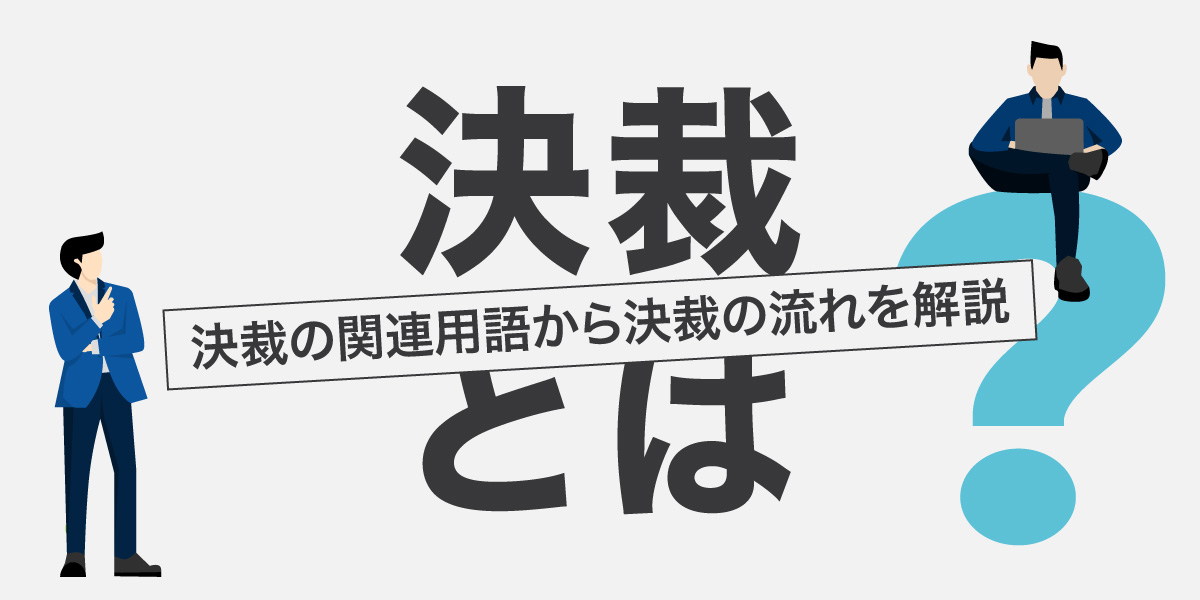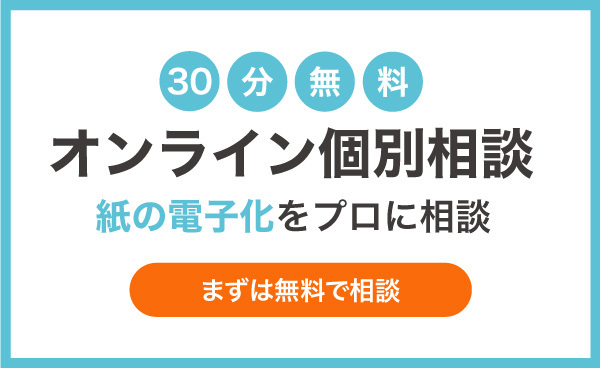この記事の目次

監査とは、財務や経営の状況、業務内容などを調べるために社内の監査役や、依頼を受諾した外部の会計士が実施する調査です。
本記事では監査の種類と目的のほか、監査のデメリットとその解決方法や、ワークフローシステムを使うことで監査に与える影響について解説します。
監査とは
監査とは、企業の会計や経営を監視、監督することです。
法律および社内規定に沿って、ルールが守られているか・違反行為や不正がないかを監査員が検査します。企業は監査に引っかからないように、内部の状況を正しく把握しておく必要があります。
企業における監査の役割
企業における監査は、業務の実態や財務の状況、法令や社内規定が守られているかどうか、企業活動が有効かどうかが評価されます。
監査には大きく分けて2種類あります、法律で義務付けられる監査が「法定監査」、任意で実施する監査が「任意監査」です。
監査結果の中に指摘事項があると、罰金や罰則が科せられるケースもあります。罰金や罰則を受けた企業は社会的信頼に大きな影響が出ます。
監査が必要な理由
企業は、株主・債権者・投資家・取引先などの利害関係者(ステークホルダー)に多大な責任を負っています。運営状況や財務状態の報告に誤りや改ざんがあると利害関係者が不利益を被る危険性があります。
それを避けるための手段の1つが監査です。利害関係者を保護し、社会的信頼を確保するために、企業は監査を受けなくてはなりません。
企業規模が大きいほどステークホルダーが増えます。上場企業や一定以上の規模の企業は、法定監査を必ず受ける必要があります。
監査が必要な会社
会社法監査の主な目的は、株主および債権者の保護です。上場企業や一定の要件を満たす企業は、会社法・金融商品取引法に基づいて法定監査を受けなくてはなりません。
監査が必要な企業の条件を以下に示します。
- 大企業
最終事業年度に係る貸借対照表にて資本金が5億円以上
または負債の部の合計額が200億円以上
- 監査等委員会設置会社
会社法の改正によって2015年から導入
- 監査役会設置会社
- 会計監査人の任意設置を行った会社
監査と査察、調査、考査の違い
会社内の状況を調査や報告する行為として、監査以外に査察、調査、考査があげられます。
以下では、監査の意味や、それぞれの言葉が持つ菅里の意味の違いについて解説します。
・監査とは
社内規定や法令に照らし合わせて、業務や社内、成果物などの状況を確認し、適切な指導を行うこと。主に経理担当者が社内状況を把握するために実施する。
・査察と監査の違い
どちらも社内状況を把握するために行われるが、査察は査察官という、それを専門にする職業の者が行う。脱税や犯罪が行われている場合、事実を明らかにする目的で行われる。
ほとんどの場合、事前の承認や許可などはなしで行われる。
・調査と監査の違い
真実を明らかにするという目的では、査察と似た要素がありますが、査察は事前の承認や許可なしで行われる強制的な行為を指すことが多いのに対して、調査は事前の承認があったうえで行われます。
・考査と監査の違い
考査は、日本銀行が実施する調査のことです。そのため、一般的な企業ではなく、金融機関が対象となることが特徴です。
その他、テレビCMに対しても使用されます。総じて、考査は特定業種にのみ行われる調査という認識が一般的だといえます。
監査の種類と目的
監査はその形式によっていくつかの種類に分けられ、異なる役割を持ちます。ここからは監査の種類ごとの目的を解説します。
内部監査
内部監査は、組織内部の担当者もしくは部門によって行われる監査です。
業務が適切に行われているかを調査し、更なる効率化や不正防止が目的です。リスクマネジメントや内部統制などが正常に機能しているかなどが評価点とされます。不備があった場合は指摘が入り、規定の改善や行動是正が求められるでしょう。
内部監査は組織が任意で選出した担当者によって行われます。義務ではなく自主的に行います。
外部監査
外部監査は監査法人や公認会計士など、第三者組織が行う監査です。主に会計監査を指します。
調査点となるのは財務諸表、そのなかでも財務三表と呼ばれる賃借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などです。
社外の利害関係者に対して財務情報が正確であると保障することが目的です。監査役は株主総会で任命されます。
外部監査は上場企業および大企業に対して義務付けられています。
監査役監査
監査役監査は、株主総会で任命された監査役によって、取締役による職務執行の適法性・妥当性を評価する監査です。
監査役監査は法令やコンプライアンスの遵守を監査し、必要に応じて助言や勧告を行います。監査役は、違法行為をやめさせるために請求を実施したり、調査や報告を請求したりなどの監査義務があります。
株式会社のほか、任意で監査役を設置している会社もこの監査対象です。結果の報告は株主総会で行われます。
会計監査
会計監査は、決算書などの財務諸表を対象に、会計処理の適正や経営状況を評価し報告する監査です。
損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書の内容などが確認されます。主に外部監査が相当し、財務諸表監査と呼ばれることもあります。
健全な財政状態が保たれているかどうかの調査が目的です。
業務監査
業務監査は会計監査の対象以外の業務活動が対象です。
内部統制の有効性および効率性などを評価・報告することを目的とした監査です。監査役監査の一環として行われたり、内部監査で行われたりします。
具体的にはマニュアルの有無や、そのマニュアルが守られているかどうかを調査します。
監査が企業の負担になる理由

監査は企業の健全性を保つために必要です。しかし、監査に向けた準備が大きな負担となり、通常業務の時間を圧迫する恐れがあります。
ここからは、監査がなぜ企業にとって負担になるか、要因を紹介します。
監査の準備が膨大
監査の準備や対応には苦労します。理由の1つに、監査のための事務作業の膨大さが挙げられます。
特に財務諸表のチェックや準備書類の作成に時間がかかるでしょう。監査前から監査のための作業に時間を取られます。
記載内容に不備があった場合、その修正にも時間を取られる可能性もあります。
電子化が進んでいない
電子化が進んでいない企業は、資料の確認や訂正に非常に時間がかかります。デジタル化が進んでいる企業と比べて監査による負担が大きくなるでしょう。
アナログな方法で書類管理をしている企業は、監査に必要な書類の捜索にも時間がかかります。
監査に向けて、できる限り電子化を進めておくとよいでしょう。このような文書の電子化を行う際には、ワークフローシステムが有用です。
ワークフローシステムには、稟議書や申請書などの書類をペーパーレス化する機能があります。また、作成した書類は承認フローに則って管理されるため、参照性も高いことが特徴です。
内部統制が最適化されていない
内部統制とは、企業が効率的に業務を行うための仕組みです。
業務効率を最大にするためには、全従業員が内部統制を意識して動かなければなりません。内部統制が適切に機能していない企業では、日常業務で不備や不正が発生しやすくなります。監査書類にも不備が生じやすいといえるでしょう。そのため、監査のための準備作業が負担になります。
監査に向けた作業に時間を取られているときは、内部統制が適切かどうかを意識してみましょう。
関連記事はこちら
⇒内部統制をわかりやすく解説|基本的要素や目的についても
監査をスムーズに対応するために準備すること

監査が入る前に準備をしておく必要があります。
ここからは、監査の前にやっておくことや、知っておきたいことを紹介いたします。これらを意識して、スムーズな監査のための準備をしておきましょう。
監査の手順を知っておく
どの種類の監査が入るのか、監査はどのような手順で行われるのか、を把握しておきましょう。
例えば内部監査は、収集した情報をもとに監査計画を作成し、予備調査を行ったあとに本調査がはじまります。調査終了後、情報や証拠物品をもとに調査報告書が作成されます。
監査の流れを把握しておけば、整理しておくべき資料や見直すべき業務が分かりやすくなるでしょう。
ワークフローの最適化
ワークフローは、申請・承認・決裁の流れです。企業の意思決定を支える重要な工程といえます。
ワークフローの改善は意思決定の迅速化や精度・生産性の向上につながるでしょう。資料や情報を管理しやすくもなります。
ワークフローの最適化や管理システムの導入を行えば、監査に向けた準備がスムーズに進みます。ワークフローシステムを導入して業務を改善し、いつ監査が来ても問題ない体制づくりをするよう心がけましょう。
関連記事はこちら
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
ワークフローをシステム化するメリット
ワークフローシステムは、企業が行う手続きを電子化し、可視化します。監査対応を効率化する有効な手段の1つといえるでしょう。
ここからは、ワークフローシステムによって得られる利点を紹介します。
内部統制が強化される
ワークフローシステムを導入すると、申請や稟議などの意思決定プロセスが電子化されます。なにがどのような流れで行われているのかが可視化されます。
これにより、不正な承認や決裁が防止され、正当な流れで適切な意思決定が行われるようになるでしょう。
ワークフローシステムは、申請や承認の流れの確認も可能です。そのほか、資料や書類を電子化して閲覧権限を設定し、不正な持ち出しや不注意による紛失を防ぐ効果もあります。
業務を効率化ができる
ワークフローシステムによって申請の流れを電子化すれば、紙媒体よりも証跡管理が容易です。
承認、決裁された稟議・申請をいつ誰が承認したのかが記録されます。不備があった場合にどこで発生したのかが分かりやすくなるでしょう。
また、過去の申請がデータとして保存され、古い資料の捜索に時間がかかりません。監査の情報開示においても必要な文書がすぐ検索・出力可能であり、かかる時間を大幅に減らせます。
その他
その他、ワークフローのシステム化のメリットを以下に示します。
- 意思決定プロセスが可視化・迅速化する
責任の所在が明確になるほか、スピード経営が可能です。
- ペーパーレス化の推進
紙代の削減や資料を探す時間の短縮に加えて、環境保護に取り組んでいる会社としてイメージ向上も期待できます。
- テレワークの推進
紙の資料に判子を押す作業がなくなり、オフィスに来て仕事をしなくてはならない場面が減ります。
- バックオフィス業務の効率化
業務手続きをシステム上で完結させられるため、作業効率が向上します。
内部体制を整えて監査に対応しよう
監査は大きな役割を持ち、企業にとって必要なものです。しかし、その準備には膨大な作業が必要です。
負担を少しでも減らしたい場合には、ワークフローシステムの導入をお勧めいたします。ワークフローシステムには監査に向けた準備の効率化だけでなく、テレワーク促進や意思決定の迅速化など、さまざまなメリットがあります。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。