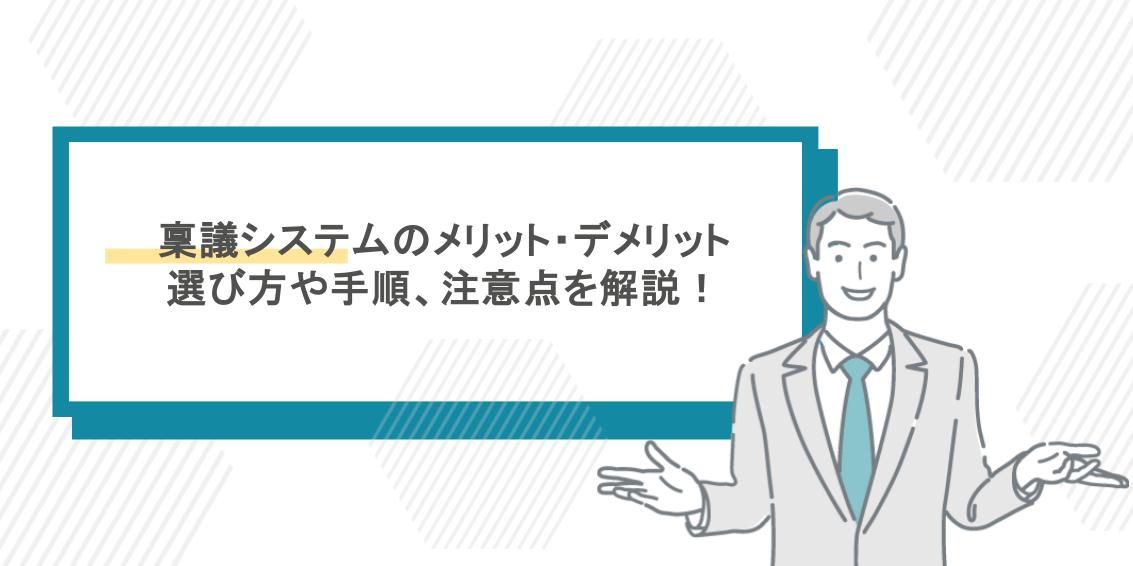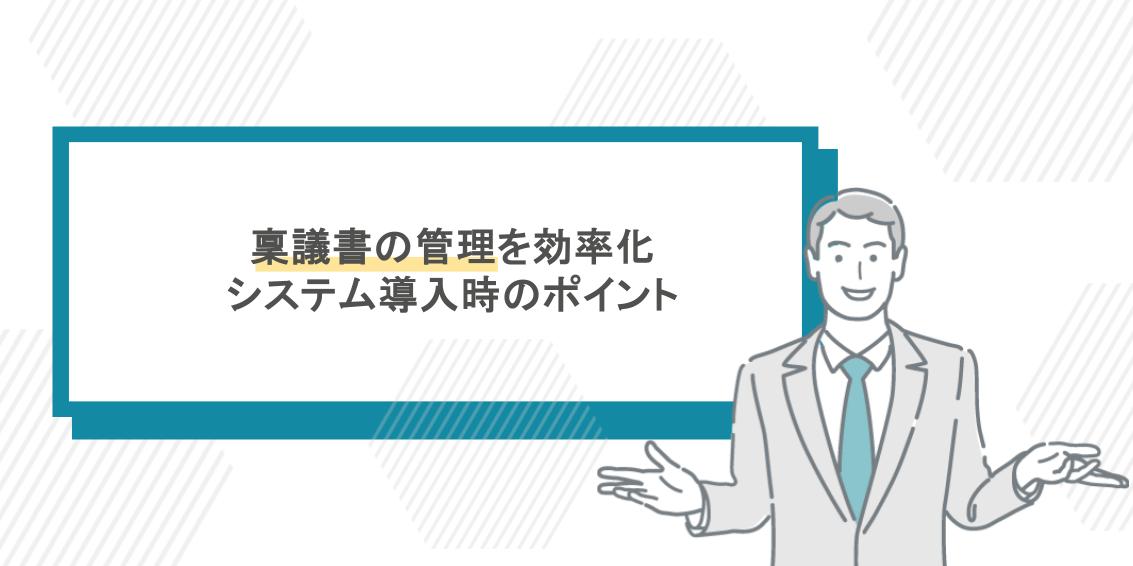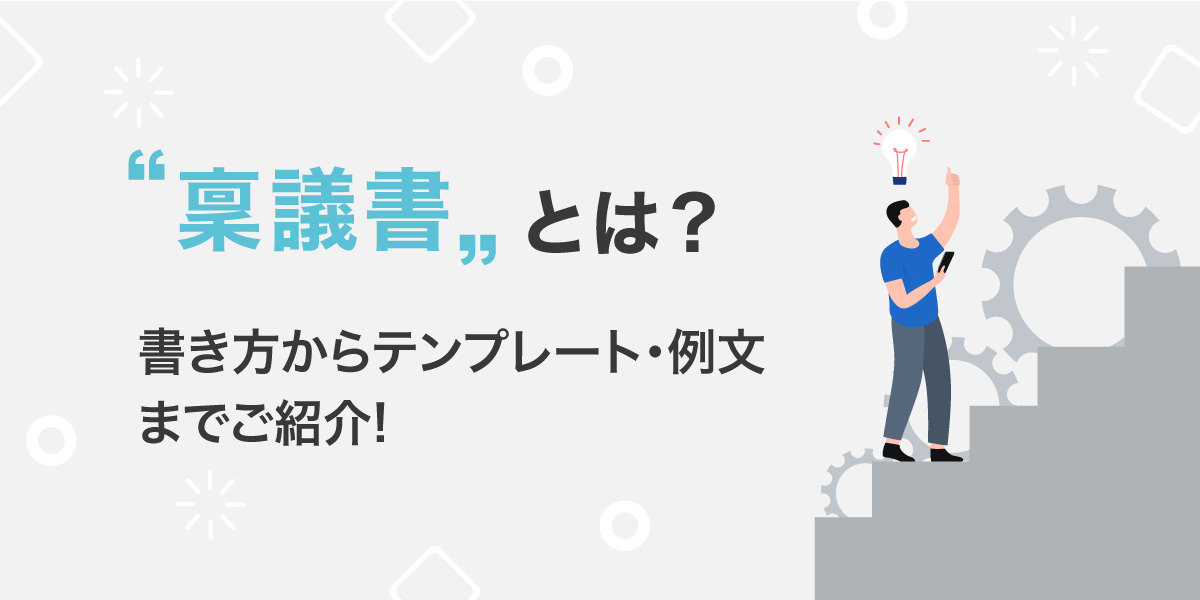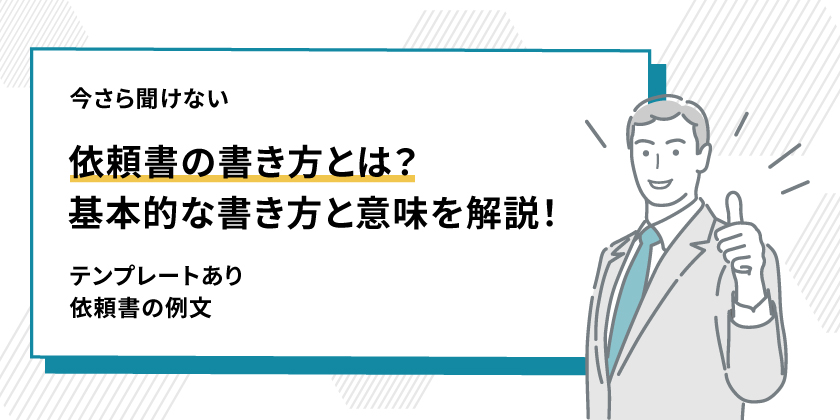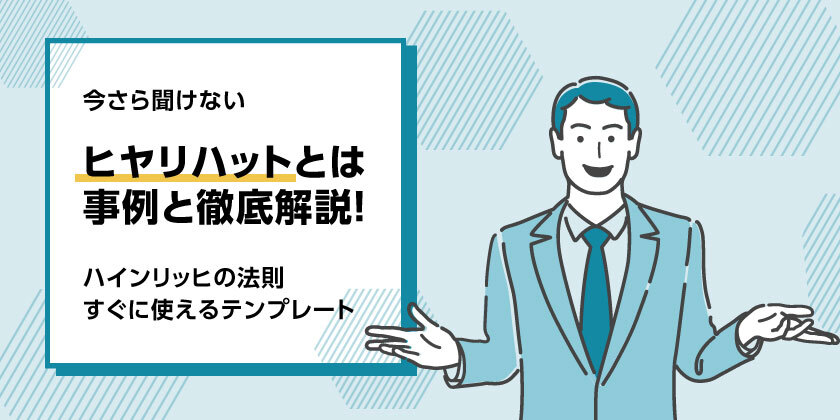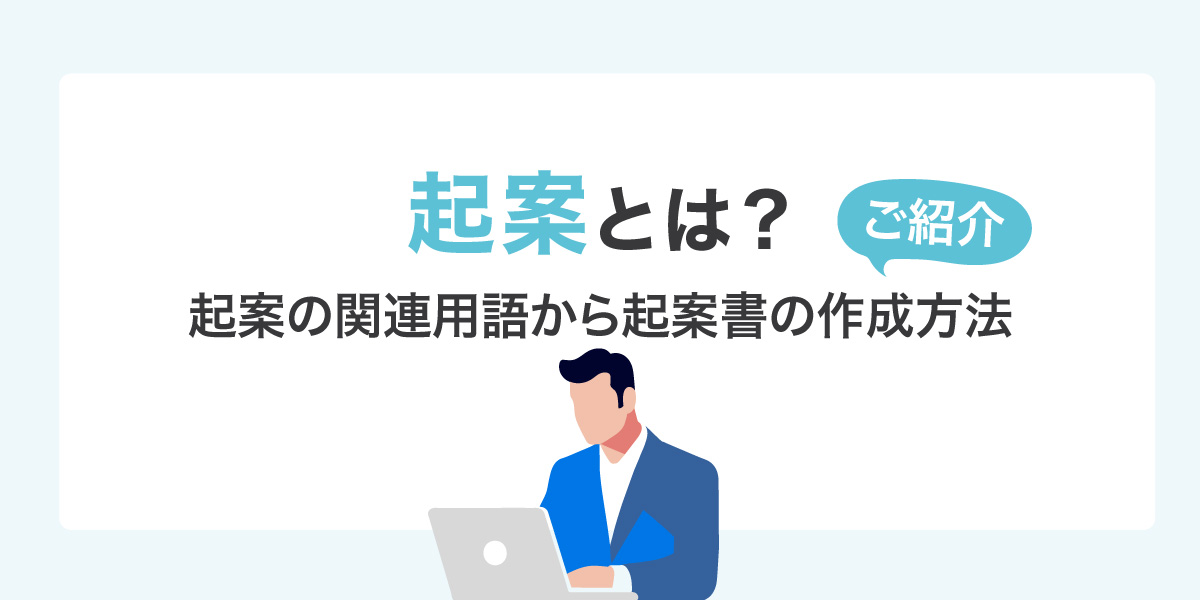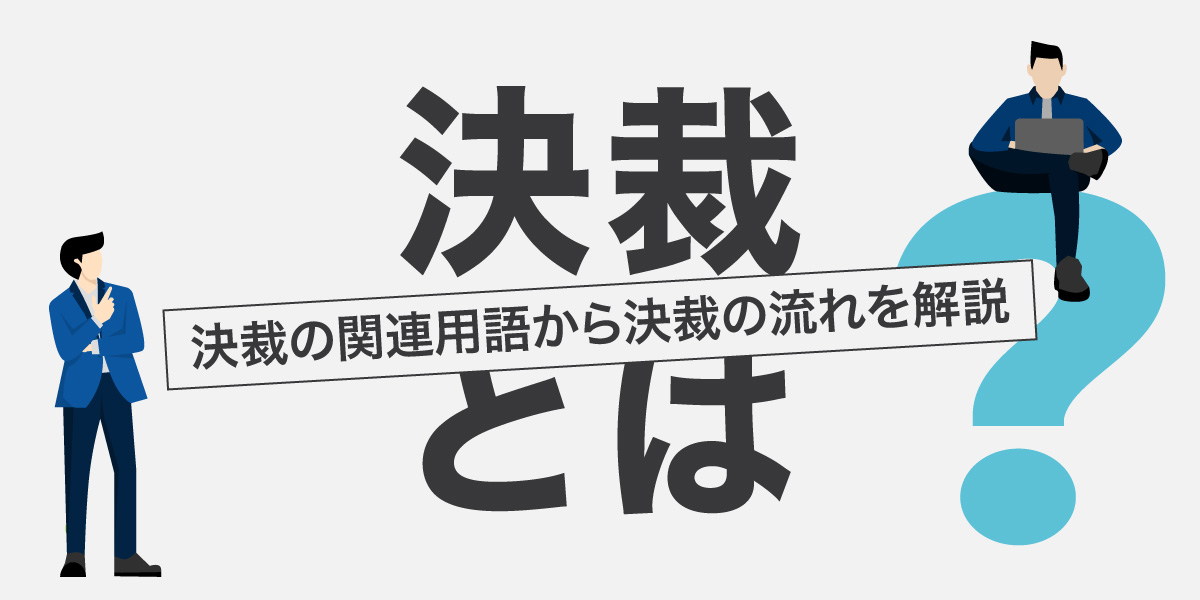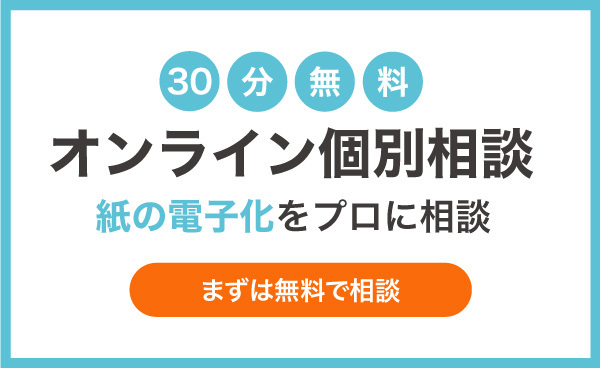この記事の目次
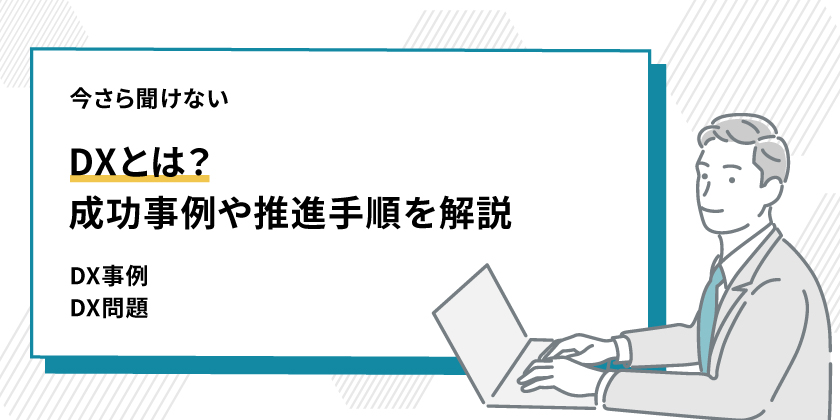
働き方の変革や消費活動の多様化によって、企業の在り方は変化を求められています。企業を変化させる手段のひとつとして導入されるDXとは、どのようなものでしょうか。
この記事ではDXを導入することによって解決できる問題や、部署別の成功事例、推進手順などについて徹底解説します。今後、自社のDXを促進したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
DXとは|デジタル技術を取り入れる変革
そもそもDXとは、どのような意味を持つ言葉でしょうか。
言葉の意味や、類義語との違いについて解説します。
DXという言葉が持つ意味
DXとは、「Digital Transformation」の略称です。「Transformation」が「変革・変容」などの意味を持つため、全体では「デジタルによる変革・変容」の意味になります。
デジタル技術で変革することで社会や組織をより便利にする取り組みを指し、その言葉がビジネスシーンでも浸透しました。
特に、企業におけるDXは企業が持つ既存の価値観から脱却し、革新的な変化を起こすものと捉えられています。
IT化との違い
企業の進化や変化を表すときに、「IT化」という言葉をよく耳にします。DXとIT化のもっとも大きな違いは、その目的です。
IT化とは、業務にITツールを取り入れて効率化を図ることです。業務の内容は維持しつつ、デジタル技術で補える部分を取り入れ効率化します。
一方でDXの目的は、企業の変革にあります。IT化は、あくまでもDXの前段階に過ぎません。
デジタライゼーション・デジタイゼーションとの違い
デジタライゼーションは、業務のデジタル化を指す言葉です。IT化と、ほぼ同じ意味として使用されます。
一方、デジタイゼーションはアナログなものをデジタルデータに置き換えることを指す言葉です。紙書類をPDF化して管理したり、書面・口頭の連絡をメールや電子ツールに置き換えたりすることを指します。
どちらも、企業をDX化するために必要なステップです。DXの目的を明確にして、デジタライゼーション・デジタイゼーションを推進しましょう。
DXが注目されている理由
近年、DXが注目されている理由について解説します。
以下の2つの問題が注目されており、企業はそれに対応できる在り方を求められている状況です。
2025年の崖
1つ目の問題は、「2025年の壁」です。
「2025年の崖」とは、日本企業がDXの取り組みを十分に行わなかった場合、2025年以降に年間10兆円以上の経済損失が発生し、国際競争力を失うという課題を表す言葉です。
2018年に経済産業省が公表した「DXレポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜」の中で問題提起されました。
経済産業省が発表しているデータによれば、2024年現在も多数の企業が国内すべての企業が到達すべきとされたレベルに達していません。このまま状況を改善できなければ、企業の未来にも影響すると予測されています。
企業の早急な現状把握と、状況に合わせた対応が求められています。
働き方と消費活動の多様化
2つ目の問題は、働き方と消費活動の多様化です。
2020年以降、新型コロナウイルスの影響もありリモートワークが急速に普及しました。
リモートワークは社員にとってメリットの大きい働き方ですが、事前準備が必要不可欠です。企業は、自社社員が効率よく安全にリモートワークできる環境づくりを求められています。
また同時に、消費者の活動範囲や消費方法が多様化しています。今の消費活動に合った店舗形態や、市場の構築が必要でしょう。
DX化によって解決される社会的な課題
企業がDX化を促進することによって、さまざまな社会的問題が解決できると予測されています。具体的には前述した2025年問題をはじめとして、人口減少や高齢化による労働力不足が問題視されている「2040年問題」や気候変動が関係する「2050年問題」などです。
ここでは今挙げたものの他に、業界別に解決できる課題をご紹介します。
農業の分野では、作業にかかる時間をデジタル技術で可視化して管理することで、より適切な人数で効率よく作業に取りかかれるようになります。
それによって、人材不足の解消や生産計画の改善など、農業全体の状況把握・改善に役立つでしょう。
また、医療の分野では、ビッグデータの活用による新たな治療法の確立や住民の健康問題の把握、創薬プロセスの最適化などに取り組めます。
業務フローのみならず組織基盤まで変革し、新しいアイデアの構築から実践までの時間を短縮できるでしょう。
企業がDXを推進する主な目的
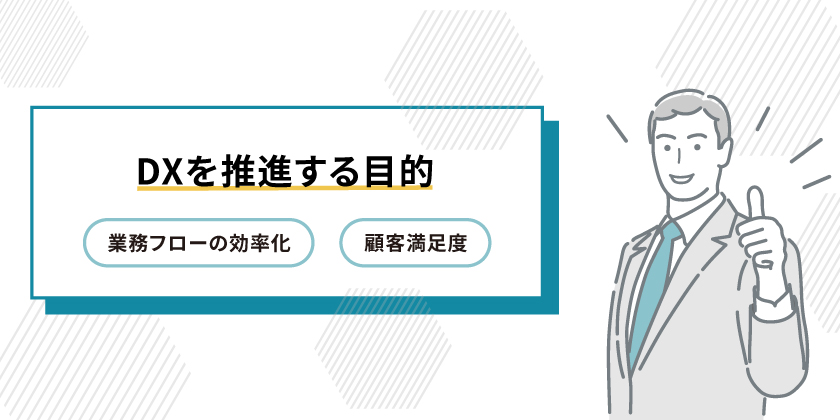
企業がDXを推進する目的は、主に4つあります。
目的を明確にすることで、DXの内容もブレずに統一感を保ちつつ取り組めるでしょう。
企業の優位性を高める
企業の優位性とは、自社の強みを踏まえた競合他社と比較したときの優れた点です。
市場競争で優位に立つためには、その企業ならではの優位性を持つ必要があります。前述したような今後の日本市場における課題を乗り越えるためにも、優位性の明確化は欠かせません。
優位性のないまま既存システムを放置してしまうと、システムの複雑化や人材不足の問題を抱える危険性があります。
既存システムの最適化や、新しい事業への挑戦をして企業の優位性を明確にしましょう。
業務フローの効率化
業務フローの効率化は、企業にとって非常に重要です。
紙で管理していた書類のデジタル化やITツールの導入、業務工程の見直しなどが業務フローの効率化の実例として挙げられます。
業務フローを効率化することによって、作業時間の短縮化が実現できます。
また、現場の業務を見直して単純作業から人材を解放することで、他のコア業務に専念させられます。不要な人員の削減も可能になるでしょう。
新しいビジネスの創出
DXは、新しいビジネスを創出するチャンスです。
社内の管理ツールを一元化しコミュニケーション方法を改善することで、これまで見えてこなかったビジネスモデルが生まれる可能性があります。
また、顧客との関わり方も改善により、サービス拡大のアイデアや顧客満足度の向上につながる提案も出てくるでしょう。
DXにより、今後の市場変化にも迅速に対応できるようになります。自社が競合他社に置いていかれないように、常に前進的に思考し対応できる体制を整える必要があります。
顧客満足度を高める
DXによって、顧客満足度の向上も期待できます。
DXは、顧客との接点を増やすことが可能です。これまでよりも、より顧客一人ひとりに合った体験や商品を提供できます。
また、顧客からの意見や感想を集めて分析できる環境を整えられるでしょう。
分析結果を参考にしながらサービス内容に顧客の意見を反映することによって、顧客満足度の向上につながります。
日本はDXへの対応が遅れている
2023年時点で、日本のDXは対応が遅れているといえます。
2020年にスイスの国際経営開発研究所から発表された「世界デジタル競争力ランキング2020」によると、日本のランキングは27位でした。
また、2021年にIMDが発表した「デジタル競争力ランキング」では28位の結果が出ています。アジア圏にある他の先進国と比べても順位は低く、DXに対応できていない問題が浮き彫りになっています。
企業それぞれで早急な対応が必要な状況であり、真剣にDXに取り組む必要があります。
日本でDXが遅れている理由
日本でDXが遅れている理由は、主に5つ考えられます。
日本が抱えている人材不足の問題や、昔からの企業体質など考えられる理由について詳しく解説します。
深刻な人材不足の影響
日本は、深刻なIT人材不足に陥っています。
DXを促進するためには、IT分野に対応できる人材が必要不可欠です。しかし、ITに明るい人材は限られており、企業がDXを進めたいと考えても人材を確保できない現状があります。
また、DXを進めるためには実績が欠かせません。DX推進の実績がある人材はさらに限られるため、人員が足りずDXが遅れる原因となっています。
社内で人員が確保できない場合は、外部の人材に頼る方法がおすすめです。
基幹システムが古く、刷新できていない
DXが遅れている企業の中には、使用しているシステムの属人性が高く、さらにその開発者は既に退職してしまっている場合があります。
そうした企業ではシステムについて完全に理解している従業員がいないまま、データが保存されているため使わざるを得ないという状況が生まれています。そのため新規のシステムへの移行が難しく、仕方なくそのシステムを使い続けている企業もあるでしょう。
システムが属人化してしまう現状は前述した人材不足とも関係しており、多くの企業で見受けられます。既存システムを活用しながら、新しいシステムに移行していく仕組みづくりが求められるでしょう。
経営陣のDXへの理解不足
現場がDXを求めていたとしても経営陣がその必要性を感じていない場合、DXは進みません。そもそも、DXしようという考えにすら至らない場合もあります。
基本的に紙作業で行っている企業では、データを紙媒体で保存することが慣例となってしまっており、クラウド上のデータ保存に信頼が置けないと感じることもあります。
経営陣がDXについて理解し前向きに支援をすることで、企業のDXスピードは上がるでしょう。
保守的な企業体質
日本には、保守的な体質の企業が多くあります。
DXについては必要になれば対応しようとは思っているものの現状うまくいっているため、DXを推進しなくても問題はないと考えている場合があるでしょう。
また、多くの額を投資するぐらいなら、従業員を手作業で動かせばよいという考え方の経営陣もまだまだ残っています。経営陣だけではなく、未知のものには手を出したくない、既存の手段で代用したいと考える従業員も少なくありません。
企業全体が保守的な考えから抜け出さなければ、DXは進まないでしょう。
情報漏洩への危惧
ネットワーク接続が不要なスタンドアロン環境や、必要に応じてスケーラビリティを持てるオンプレミス環境は、セキュリティ的には高度なものといえます。外部に情報が漏れるリスクを減らすため、あえて採用している企業もあります。
それに比べ、新しいツールを導入して管理や情報共有においてネットワーク通信が行えるようにすると、セキュリティ的には弱体化するのは事実です。現場で問題が起こっておらず、セキュリティが弱体化するなら現状維持でよいという考えがあっても不思議なことではありません。
セキュリティ対策が万全なツールやシステムを構築することで、それらの懸念点は解消できます。
DXが遅れることのリスク
このまま日本企業のDXが遅れ続ければ、どのようなリスクが考えられるでしょうか。
組織全体で危機管理を持って対策を考えなければ、以下のリスクに巻き込まれる可能性があります。
システムの維持管理費が高騰する
古いシステム(レガシーシステム)は、保守管理が属人化しやすくシステム維持に費用がかかります。
ハードに挙動が左右されることもあるため、老朽化が進んだ際に新しいものに置き換えられない可能性もあります。もし、システムに使用している部品の生産が終了していれば、高い料金を払って部品を特注で作ってもらったり、そもそも維持管理が不可能になったりといったケースが考えられるでしょう。
資金不足が原因で、機会損失につながりかねません。
万が一の際の復旧に時間がかかる
社内システムをスタンドアロンで運用していた場合、サーバ本体とバックアップの両方が災害で破損してしまうとシステムの復旧ができません。
この場合、手書きのデータから全てを復旧することになります。会社の規模が大きい場合、その作業に何十時間、何百時間と要するため現実的な方法とはいえません。
また、データを紛失するリスクもあります。
クラウドを取り入れて社内データを管理していた場合は、災害時にも簡単に復旧ができます。DXは、災害時のBCP面においても重要視される施策です。
IT競争に敗北して他企業との差が生まれる
DXによって業務を効率化すれば、対処できる案件の数が単純に増加します。
また、ビジネスツールにはデータの保存から分析までできるものもあるため、自社に足りない要素を理解しグローバルな競争に参加しやすくなるでしょう。
逆にいえば、DXが遅れると競争に参加しても弱点や強みが掴みづらく、他企業との間に差が生まれやすいといえます。
業界によってはDXが急速に進んでいるため、今DXに対応できなければ2025年問題や2040年問題に直面した際に取り残されてしまうでしょう。
【部署別】DXの成功事例
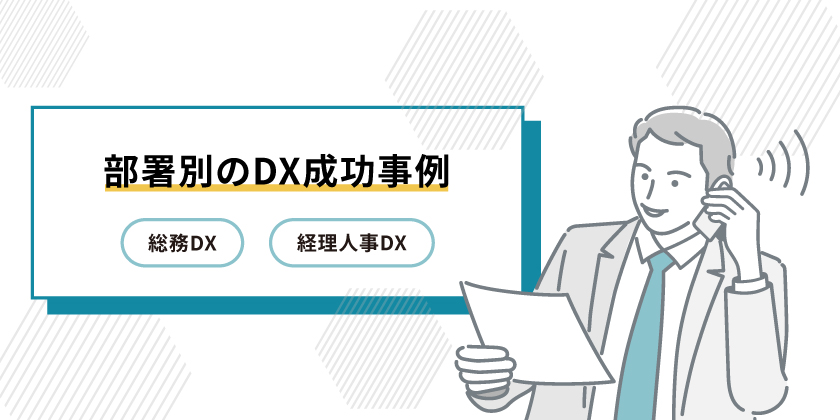
企業の部署別に、DXの成功事例を紹介します。
部署によって、業務内容や使用しているツールや改善できる業務内容は異なります。
それぞれ該当する部署について、どのようなDXが成功しやすいのかを知りましょう。
総務部
総務部は、企業内でもっともDXが進めやすい部署です。
管理に関しては物品管理用のシステムや書類、契約管理用のシステムを導入して、ペーパーレス化を実施できます。ペーパーレス化が完了すれば、無駄がなくなった業務からワークフローの構築が進められるでしょう。
また、RPAやFAQ、チャットボットを導入すれば、社内問い合わせを効率的に捌けます。
さらに、インターネット上での申告書作成や社内の情報共有の場を作ることで、業務の効率化につながります。
高機能ワークフローを進めたい企業には、コラボフローがおすすめです。見つけ出すまで時間がかかる書類の一元管理や、書類の申告に関する無駄を省きます。
経理部・人事部
社内人事や社内決算に関する書類を、書面で管理している会社は多くあります。経理部・人事部はそれらの重要書類をいくつも管理しており、紛失や書き間違えが許されません。重要なデータの入力ミスや紛失を防ぐために、DXが求められます。
DXの例としては、独自の社内フォームを作成して申請や管理を簡単にする、インターネットを介してどこからでも申請できるようにする、などが挙げられます。
また、経理部・人事部は、紙の書類に押印する機会が非常に多い部署です。これらを電子化し、整理することでワークフローが整うでしょう。
コラボフローを活用することで、経費精算や休暇届、出張申請などが簡単に行えます。それぞれの書類がバラバラになることなく一元管理が可能なため、担当者・申請者の負担を大幅に減らせるでしょう。
営業部
営業部は、社内だけでなく対外との関わりも非常に多い部署です。DXによって、顧客情報をデータで登録・管理できるようになります。
また、DXで営業状況を部署全体で把握できるようにすることで、社員が一人で業務を抱えすぎていないかや、営業の進捗が確認できるでしょう。
情報伝達や管理に関する電子化を進めて、その後ワークフローを整理するようにしましょう。現状を整理すれば、顧客からの問い合わせをチャットボットの導入で簡潔化する、これまでにない販路を広げるなどの新たなワークフローに着手できます。
コラボフローを導入することで、取引先からの新規取引依頼をWebから受け付けられるようになります。
また、kintoneと連携して営業状況の管理をすることも可能です。他にも、フォームを作成するときにkintoneデータを自動で転記できたり、コラボフローでの承認結果をkintoneアプリへ自動登録できたりします。
コラボフローをうまく活用することで、営業部の活動をより効率的に進められるでしょう。
開発部
開発部は、他部署から送られてくる顧客情報や商品の動向データを分析・管理します。
DXを行うことによって、顧客の動向をより深く理解し新商品の開発や既存商品の改善が可能になります。
また、他部署との情報共有をスムーズに行うことで、よりよい商品の開発にもつながります。
情報共有を効率化する方法は、作業工数の見える化やチャットツールの導入などが挙げられます。ワークフローの透明化や簡略化は、作業効率や商品品質の向上にも影響するでしょう。
コラボフローは、申請フォームを簡単に作成できます。社内のデータ管理が簡単になり、社内のワークフローも簡略化可能です。kintoneと連携することによって、工数管理の見える化や商品マスタ管理もできるようになります。
DXするメリット
企業がDXするもっとも大きなメリットは、企業の変革です。
具体的なメリットについて、詳しく解説します。
人材不足解消
これまで自社社員で行っていた単純な業務を効率化することによって、その業務に人手を割く必要がなくなります。
これまでは人手不足の問題を解決しようとすると、新たな人材の雇用を考える方も多かったでしょう。
しかし、業務を効率化することで今の人員数のまま人手不足を解消できます。
さらに、より専門業務に精通している人員を集めれば、サービスや商品のクオリティ向上にも期待できます。
働き方の幅を広げられるため、人材雇用の幅も広がります。
BCP(事業継続計画)を充実させられる
BCPとは、災害や既存システムの障害によって企業が危機的な状況に陥った際に、業務を再開するための計画です。
DXで事業や企業体制のデジタル化を推進することで、災害が起こった場合に対応できる業務や事業が増えます。
非常事態における企業の対応は、社会的信用度の向上や顧客満足度の維持につながります。危機が起こったとき、業務に対応できる環境づくりをしておきましょう。
既存システムにおけるリスクを回避できる
既存システムを長年使用していると、保守運用の費用上昇やサイバー攻撃のリスクが考えられます。また、システムに修正を繰り返すことで、複雑化して管理が難しくなったり費用がかかりすぎたりすることもあります。
DXによって新しいシステムやツールを導入することによって、それらのリスクを回避できるでしょう。ウイルス対策や、緊急事態におけるシステムの環境づくりも可能です。
管理を一元化することによって、担当者の負担軽減にもつながります。
社内でDXを推進する4つの手順
社内でDXを効率よく進めるためには、以下の手順がおすすめです。
闇雲にDXを促進するのではなく、現状の把握から始めましょう。
①目的と現状把握
まず、なぜDXを行いたいか、その目的を明確に設定します。
DXを行ったあと、どのような会社になっていたいか、そのイメージを具体的に膨らませましょう。
また、目的を設定したあとに、自社の現状について把握・分析を行います。自社が抱えている問題を把握し、どのようにすればその問題が解決できるかを模索しましょう。同時に、自社が残したい強みについても分析します。
その後の施策がブレないよう、残したい強みと解決したい問題点について整理する必要があります。
②組織体制の構築
つぎに、DX促進の組織体制を構築します。
DXには、デジタル技術やITツールに精通している人材の確保が必要不可欠です。DX人材を揃えた部署やチームを設立し、DXを進めましょう。DX人材には、プロジェクトマネージャーやビジネスデザイナー、テックリード、エンジニアなどが当てはまります。
全員がDXに意欲的であり、失敗を恐れずに挑戦できる人材であることが重要です。
もし、組織内でのチーム構築が難しい場合は、外注も視野に入れて取り組みましょう。
③施策の推進
つぎに、チーム内で出た施策を推進します。自社の現状を打開できるITツールや、システムを選定しましょう。既存システムを一新する方法もあれば、既存システムと連携しつつ新しいツールを導入する方法もあります。
予算や改善したい業務を把握することで、最適なDXが実現できるでしょう。
コラボフローは、kintoneやサイボウズシステムと連携できる高機能ワークフローシステムです。既存システムを活かして、さらに効率のよい業務のワークフロー化を推進します。
④定期的な分析や改善
DXを実施したあとは、定期的に分析・改善を繰り返しましょう。
DXに取り組むことで得られた結果を蓄積・分析することによって、客観的な変化を可視化できます。
また、DXの目的は業務の効率化を図ることではなく、会社の変革です。DXすることによって得られた視点や時間を、うまく活用できているかを確認しましょう。
定期的に顧客のニーズや社内の意見を集め、DXで改善を続けます。そうすることで、企業はさらに優位性を高めて企業としての価値も高まるでしょう。
DXを進めるうえで求められる人材とは
DX人材とは、DXをリード・実行する人材のことです。
DXの実行には、以下のような多彩な業務を含みます。
●戦略策定
●施策策定
●商品やサービスのデザインと構築
DX推進業務に部分的にでも関わる人員は、DX人材に含まれます。
求められるDX人材について、業務の種類やスキルをご紹介します。
進めたいDX施策次第で必要な人材は異なる
進めたいDX施策によって、求められるDX人材は異なります。
たとえば、仕事のやり方を変えたい企業であれば、業務効率化・業務改善などのプロセスをDXできる人材が求められます。また、新しい事業を生み出したい企業であれば、新規事業の開拓やビジネスモデルを構築できるDX人材が必要です。
DXの目的が定まらないままDX人材を集めてしまうと、企業の状況に合わないチームが構成されてしまう危険性があります。
DXの目的と実施したい施策を明確にしてから、人材を集めましょう。
DX人材が担う業務の種類
DX人材が担う業務は、主に5つの職種に分かれます。
- 職種名
- 職種の説明
- ビジネスプロデューサー
- DXやデジタルビジネスプランを先導するリーダーです。デジタル技術だけでなく、経営環境や市場の動向も把握しておく必要があります。
- データサイエンティスト
- データ分析に精通した役割です。技術的なスキルはもちろん、プランに合わせた提案力も求められます。
- デザイナー
- ビジネスプロデューサーが描いた戦略をより具体的にする役割です。ファシリテーション能力や折衝能力が求められます。
- エンジニア
- システムの実装やインフラの構築を担う役割です。プログラミングに関する知識が求められます。
- サイバーセキュリティ
- サイバーセキュリティリスクに関する対策を担います。システムが攻撃されたときも対応できる実績と知識が必要です。
それぞれの人材が自分の業務を意欲的に遂行することで、DXは促進できます。
DX人材に求められるスキル・資質
DX人材に求められるスキルや資質は、主に2つです。
1つ目は、IT関連の基礎知識やデータサイエンスの知識です。
DXを進めるうえで、ITに関する知識は欠かせません。IT知識が不足していれば客観的な情報分析ができず、現場の改善に寄与できないためです。
知識だけでなく、その企業の状況に合わせた提案力も求められます。
2つ目は、マネジメントスキルや新規事業の企画力です。
DXを推進すれば業務の改善だけでなく企業全体の変革が起きるため、全体像を見据えるマネジメントスキルが必要になります。また、やりたいことを実現するための企画力や、できる・できないの判断力も求められるでしょう。
他にも、チームでの活動を円滑に進められるコミュニケーション能力や、AIなど最先進技術の知識も必要な場面があります。
チームで役割分担をして、DXを効率よく進めましょう。
DX人材を確保する方法
DX人材を確保するためには、外部から専門の人材を採用する方法と社内のメンバーを育成する方法があります。
外部から専門の人材を採用する場合は、企業側から率先して人材獲得を目指す必要があります。自社に不足している職種を洗い出し、求めるスキルや知識について整理してから人材を探しましょう。
社内メンバーを育成する場合は、ある程度時間がかかることを念頭に置いて人材の発掘から開始します。中長期的に育成を進めることで、社内の状況を理解したDX人材が育ちます。
DX推進において気をつけたいポイント
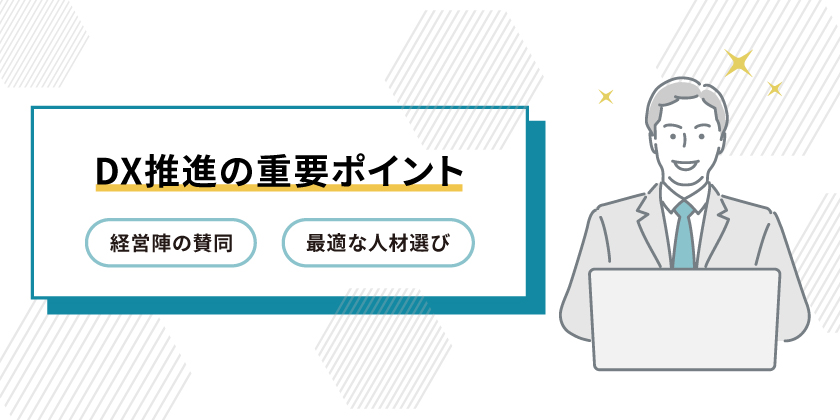
DXを推進するにあたって、気をつけたいポイントについていくつかご紹介します。
以下のポイントを押さえれば社内意識を統一でき、企業が目指すDXに近づくための施策を進められるでしょう。
企業トップや経営陣の賛同を得る
DXを迅速に推進するためには、企業トップや経営陣の賛同が必要です。一方で、DX推進において企業の上層部が意思決定を下してその指示に従うトップダウン式は、実施まで時間がかかり気軽に挑戦ができないためおすすめしません。
DX推進チームからの提案をまとめてDXの意味を明確にし、企業内のトップや経営陣の賛同を得ましょう。経営陣が社内チームに施策を一任することで、DXの実施や改善が短期間に行えます。
ただし、企業トップにはDXの旗振り役をやってもらう必要があります。経営陣自ら率先してDXの推進を口にすることで社内の雰囲気がまとまり、空気づくりに貢献するでしょう。
経営戦略に合ったDXを目指す
経営戦略に合ったDXができていなければ、推進スピードが落ちるおそれがあります。
経営のトップがDXを推進したとしても、経営戦略に合っていないと社員の賛同が得られず効果も出にくくなります。
経営戦略に合ったツールの導入や、デジタル化を図りましょう。そのためには、企業が目指すビジネスの目標を明確化し、経営戦略についても改めて整理する必要があります。
DXを開始する前に認識を統一することで、経営戦略に沿った施策案が出てくるでしょう。
最適な人材を確保・育成する
DXには専門的な知識やツールの活用方法から、その後の戦略まで理解できる人材が必要です。社内に最適な人材がいれば、その人を中心にチームを作りましょう。
前述したようにDXに必要なメンバーを数人集め、もし適切な人材がいない場合は外部から採用・または委託で補います。
チーム構成ができたあとは、会社全体でそのチームがDXを推進しやすい雰囲気づくりに努めましょう。ポジティブな空気感を作り出すことで、DXによる変化が会社にとってプラスになると全体に伝わります。
自社に合ったITツールを導入する
企業が抱えている問題点によって、導入するべきITツールはさまざまです。自社に合ったツールを見つけて導入しましょう。
たとえば、総務部の仕事を簡略化したい場合は、ワークフローシステムの導入がおすすめです。また、営業部の業務を可視化したい場合は、管理ツールが最適でしょう。
これらのツールは、社員全員が簡単に操作できることが重要です。費用面だけで決定するのではなく、使用方法や手順を考慮してツールを選びましょう。
また、機能性やセキュリティ面も確認する必要があります。
DXを進めるにあたって着手すべきおすすめの順番
DXを進めるためには、まずデジタイゼーションとデジタライゼーションを事前に行いましょう。ITシステムの導入による業務のデジタル化や書類や手続きのデジタル化で、スムーズにDXを推進できます。
DXを実施する段階まできたら、最初にワークフローを見直しましょう。
必要なものや課題を見極めてツールを導入することで、DXがスムーズに進行します。
DXの第一歩にワークフローシステムの導入を
DXの目的は、企業の優位性や社内フローの改善、顧客満足度の向上などです。これらの目的を達成するためには、ワークフローシステムの導入が最適です。
ワークフローシステムとは、業務の流れ(稟議や申請、社内手続き)を自動化するためのシステムです。
社内の申請書や在庫管理表を紙やメール、あるいはExcelで毎回作成してプリントアウトするなどのアナログな運用で行っている場合、申請書や管理表などを探すのに手間がかかります。
ワークフローシステムを導入することで、時間がかかる申請業務のスピードを上げられ効率化できます。また、ペーパーレス化や内部統制の強化、柔軟な働き方への対応などDXの推進も可能です。
まとめ
企業が推進するべきDXについて、解決できる問題や推進するメリット、その手順を解説しました。
自社の状況を整理し、どの部分で業務の効率化を図れるか分析できれば、DXの第一歩です。
コラボフローは、誰もが使いやすい高機能ワークフローシステムです。申請・承認業務を簡略化し、書類の運用も適切に行います。
また、kintoneやサイボウズシステムとも連携が可能で、既存システムをそのまま利用できる場合もあります。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。