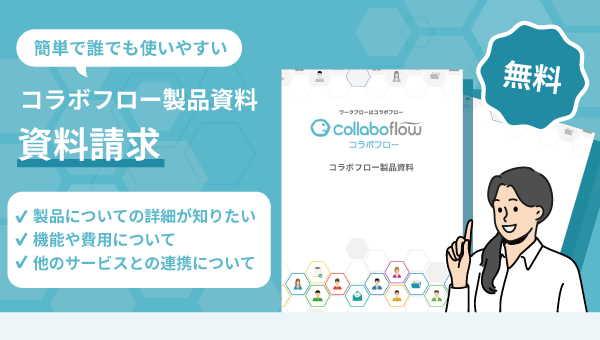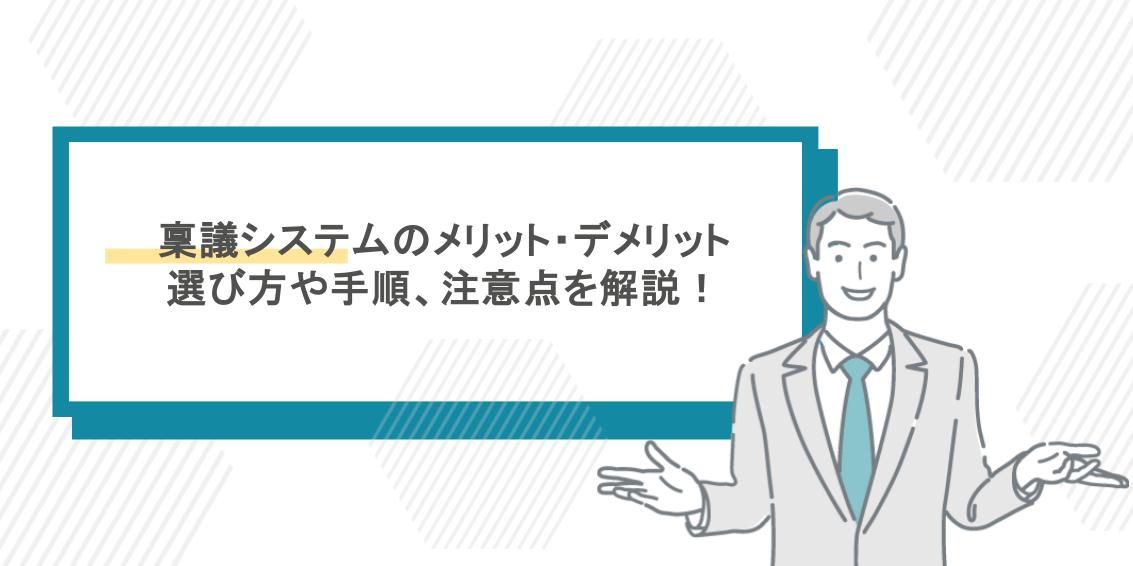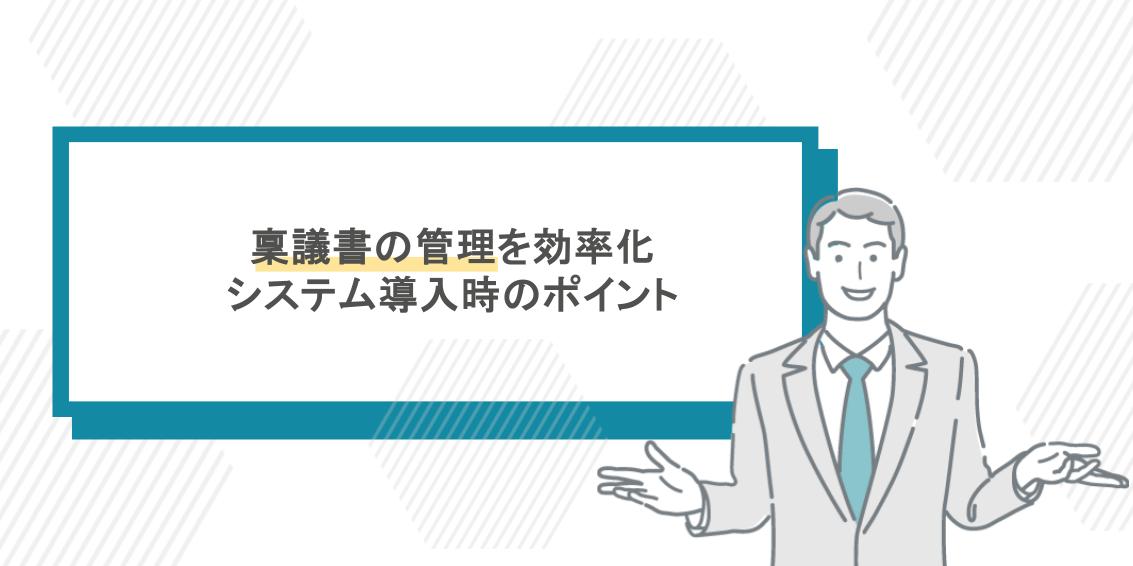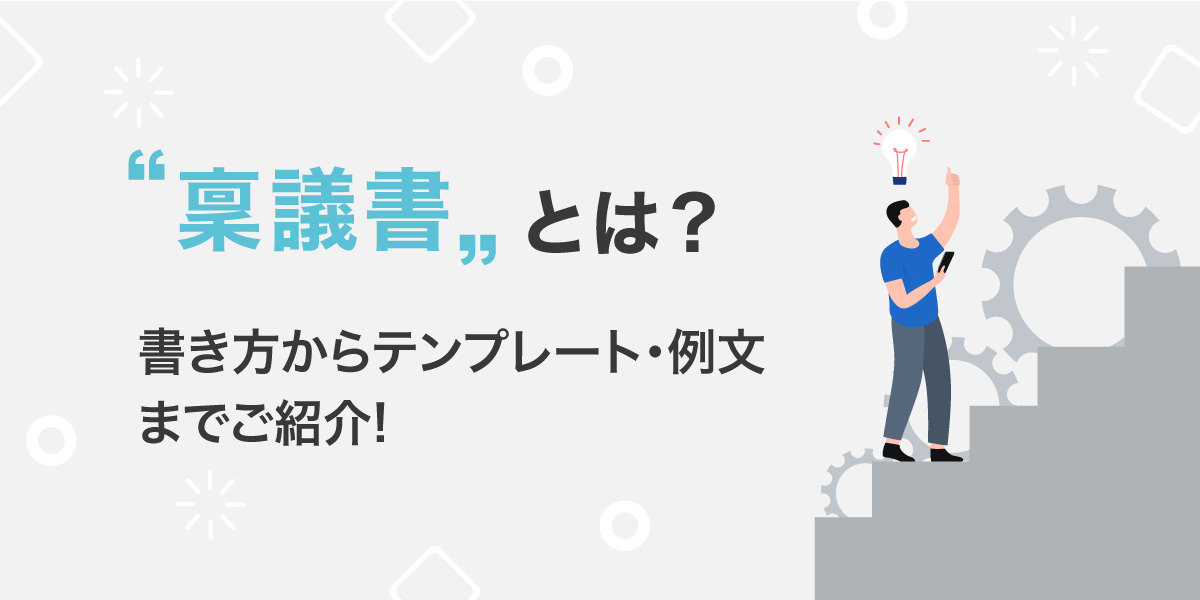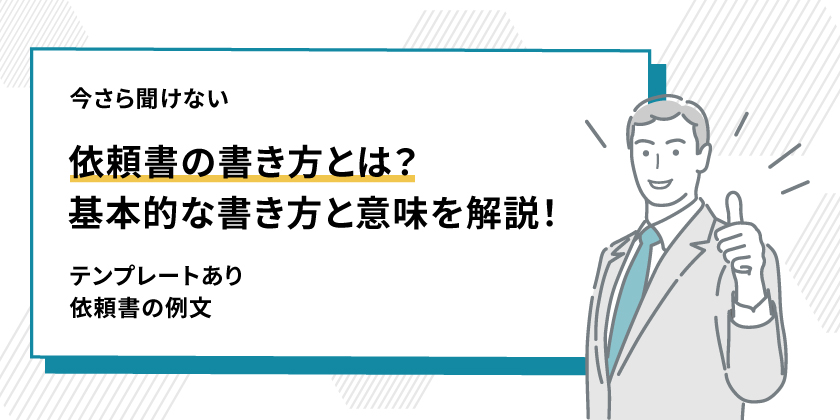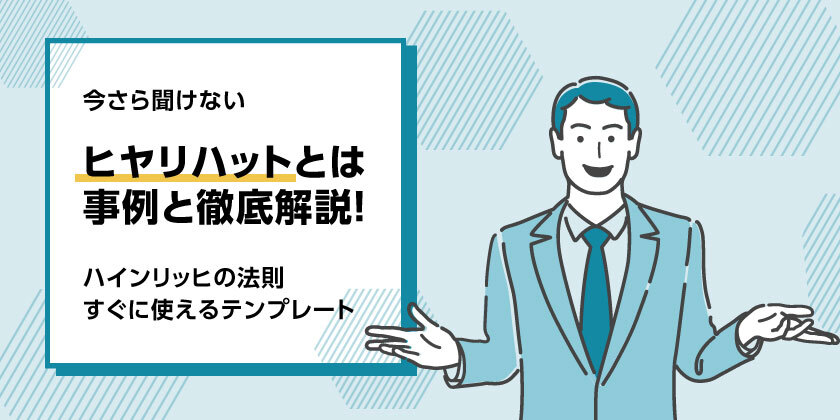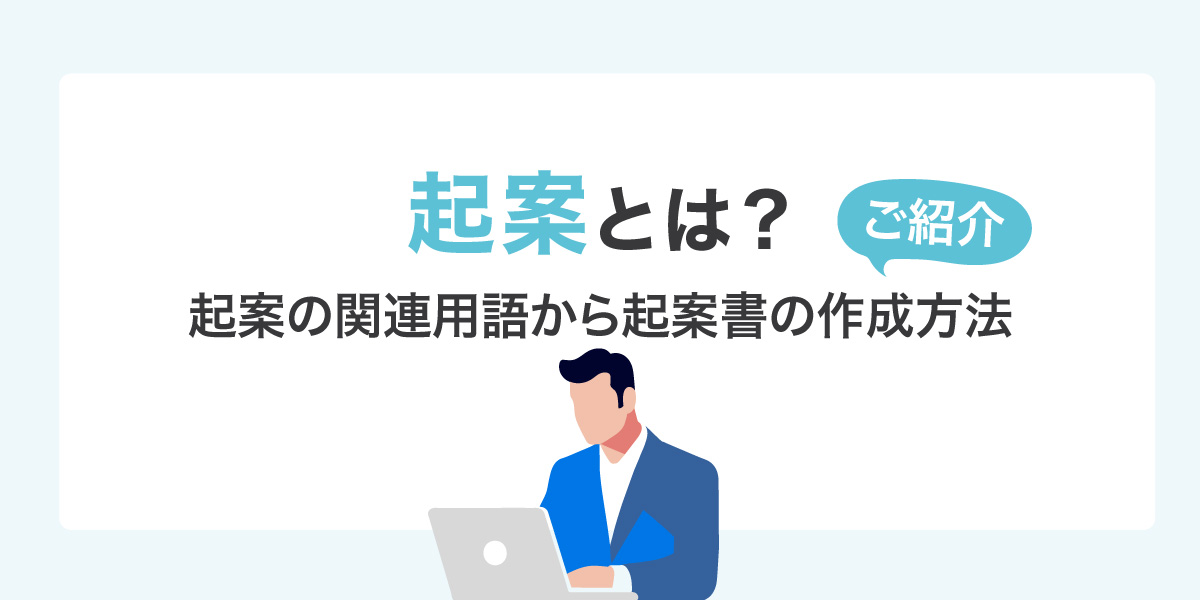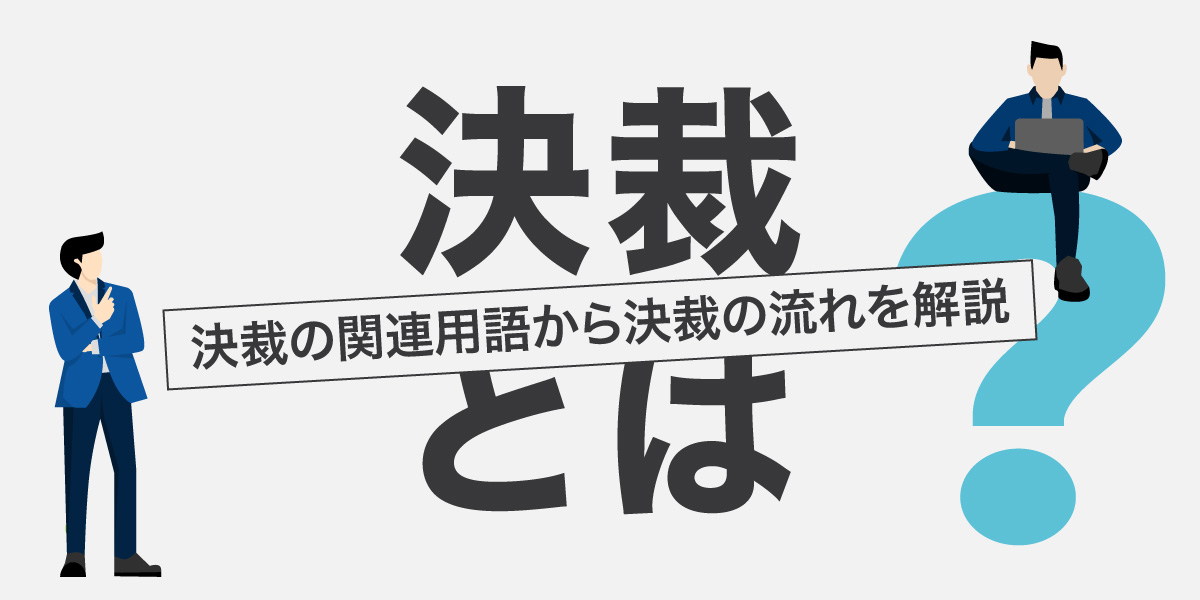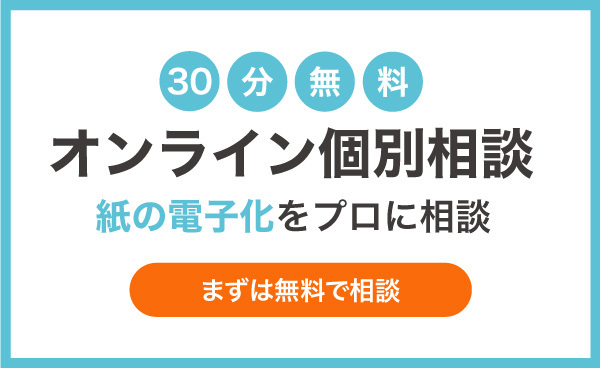この記事の目次
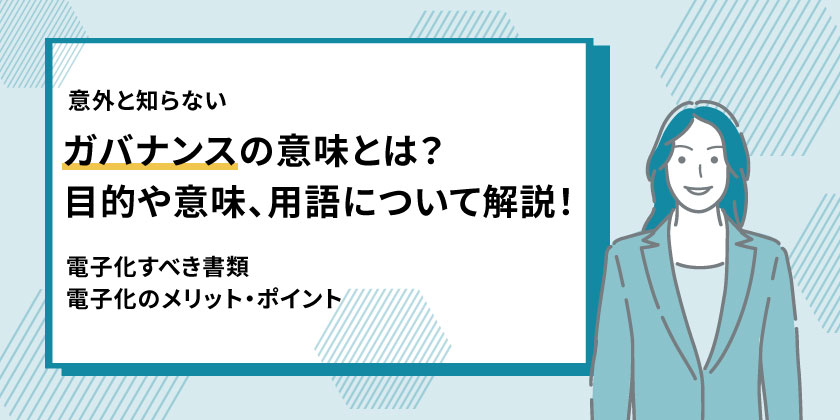
ガバナンスとは、企業が自らを律し自律的に行動するために定める規範やルールです。ガバナンスは企業の統制力や企業価値を高め、経営の安定にも寄与します。今回の記事は、ガバナンスの意味、目的、強化するメリットについて解説します。
ガバナンスの意味
ガバナンスは、英語で”governance”と表記します。統治や管理を意味する言葉です。
企業におけるガバナンスとは、その組織における不正や不祥事を防止し、企業の価値を高める取り組みを指します。健全で公正な企業経営を目指すための、企業自身による管理体制です。
具体的には、内部統制とリスクマネジメントを向上させるために専門の部署の設置、企業内部で部門ごとの役割と指示系統を明確にする仕組みづくりがあげられます。
ガバナンスの目的
ガバナンスを行う目的は、企業経営の健全化です。透明性や公平性の確保も含まれます。株主の権利を守り、平等性の確保も含まれるでしょう。株主以外だけでなく、全ての利害関係者(ステークホルダー)の権利や立場を尊重し、信頼関係の構築が重要です。健全な企業活動の維持がガバナンスの目的です。
ガバナンスを行うことによって不正や不祥事だけでなく、法令順守の徹底や男女平等に働ける状態を維持して、企業の健全化や透明性、信頼性に寄与させる効果があります。
ガバナンスが注目される背景
ガバナンスが注目されている背景として、企業を取り巻く環境の変化があげられます。
個人情報保護の観念の普及により、情報の価値が向上しています。その結果、情報管理や保守に対する企業の責任が重くなりました。情報の流出が企業に与える損失は大きく、企業による自律統制の重要性が増しています。
ガバナンスの向上は単なる企業の公正さ、透明性の向上だけでなく、社会的信用の向上、さらに国際的な企業の競争力を高めることにもつながるでしょう。
ガバナンスと似た用語と違い
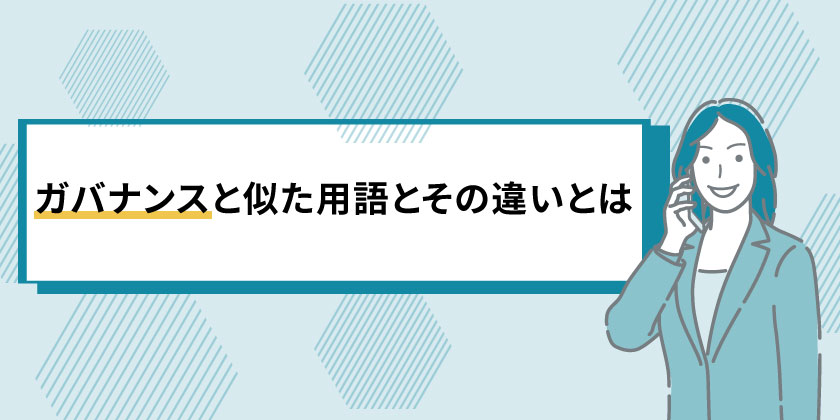
ガバナンスに意味的に似ている用語がいくつかあります。例えばmガバナンスコード、コンプライアンス、リスクマネジメントなどです。ガバナンスを正確に理解するために、類義語の定義を知っておきましょう。
ガバナンスコードとは
ガバナンスコードとは、企業のガバナンスを実現するためのガイドラインです。
以下の5つの原理から成り立っています。
1) 株主の権利、平等性の確保
2) 株主以外のステークホルダーとの、適切な協働
3) 適切な情報開示、透明性の確保
4) 取締役会などの責務
5) 株主との対話
日本金融庁、東京証券取引所が中心となって策定されました。不祥事を未然に防ぎ、国際的な競争力を強化するためにつくられました。
上場企業は報告書の提出が必要がです。ガバナンスの強化を実施する際に理解しておきましょう。
詳しくはこちら
⇒コーポレートガバナンス・コードとは
コンプライアンスとの違い
コンプライアンスは、企業による法令や社内規則、社会規範に従った行動、あるいは規範そのものを指す言葉です。
ガバナンスは企業が自らを監視、統制する仕組みです。コンプライアンスは、受動的ではあるものの、目的はガバナンスとほぼ一致しています。強い因果関係があります。
両者の違いは「外的な規範に従う」と「自ら自律して能動的に対応する」です。ガバナンスは、コンプライアンスより厳しく、進歩的であるといえます。
リスクマネジメントとの違い
リスクマネジメントは、外的要因から生じるリスクを緩和、軽減させる方策をいいます。コンプライアンスと表裏一体の関係です。
例をあげると、取引先企業の違法行為の精査はリスクマネジメント、取引先の違法行為を知りながらの取引はコンプライアンス違反です。
リスクマネジメントは、他者に向けるコンプライアンスといえます。自律方針であるガバナンスは、相手企業に求めるのは難しいといえるでしょう。
内部統制との違い
内部統制とガバナンスは、共に健全な企業経営を実現するものです。
内部統制は、事業の目的や経営の目標を適正に達成するためのルールや仕組みの構築と運用のことです。
内部統制は同時にガバナンスの重要な要素の1つとも捉えられます。企業を効率的に運用するのではなく、やるべきことや禁止事項、ルールを自ら設定するガバナンスにおいては、内部統制を確立して始めて、実現が可能になります。つまり、内部統制はガバナンスに関して必須の要件です。
内部統制については、こちらもご参照ください。
関連記事はこちら
⇒内部統制をわかりやすく解説|基本的要素や目的についても
ガバメントとの違い
ガバメント”goverment”は、政府や政治を表す言葉です。ガバナンスとは音は似ていますが全く意味が異なります。
ガバナンス”governance”とのスペルを比べると、同じ語からの派生語であることがわかります。どちらも、統治する、という意味の”govern”が由来となった言葉です。
ガバナンスを強化するメリット
ガバナンスは、自律的規範であるだけに、自社に厳しい内容も含みます。ガバナンスを強化すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ガバナンス強化のメリットを解説します。
中長期的な企業価値の向上
ガバナンスの強化は、中長期的に自社の企業価値の向上に寄与します。
ガバナンス強化により公平性や透明性を確保した企業は、対外的な信頼や魅力が向上し、優良企業として認知されます。
ガバナンスの強化により、株主やステークホルダーの利益が守られます。優良企業としての認知は、中長期的な財産となり企業活動を後押しするでしょう。
上昇した企業価値は株価算出の基準となります。出資や融資の幅を広げ企業の財務状態を安定させます。
持続的な競争力の向上
ガバナンスの強化が企業価値を上昇させ、中長期的な収益力を高めると、新規事業への投資や人材獲得に活用できます。ガバナンス強化によって得られた企業価値や優良企業としての認知度が後押しする形で、企業は前向きな積極性をもつでしょう。
ガバナンスの強化が内部統制にも着実に表れていた場合、積極的な施策の成功率は高まります。さらに競争力をもつでしょう。こうした効果は社内全体のエンゲージメントをさらに高め、強固な組織体制へとつながります。
従業員の労働環境改善
ガバナンスの強化は、内的なメリットも持っています。
従業員の労働環境の改善は、重要度が高いポイントです。労働環境が悪いと、良いサービスや価値の提供はできません。ガバナンスによる公平性と透明性が労働環境にも適用されると、労働問題の多くの面が改善します。
労働環境の改善は従業員のモチベーションを高め、より良いサービスの実現に寄与します。より良い人材を確保する採用の面でも役立つでしょう。
ガバナンスが効かないときに起こる問題
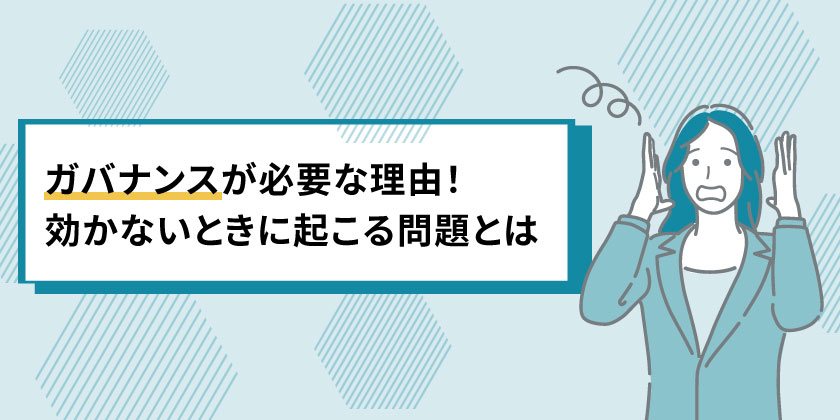
企業によるガバナンスが上手く機能しなかった場合、どのような問題が起こるのでしょう。ガバナンスが効かない際に起こりうる問題点を解説します。
社会的信用を失う
ガバナンスが確立できず、企業が内部統制の強化に失敗すると、組織の中で不正や不祥事が発生してもそれに気付くのが遅れます。発覚した際には大きな問題に発展しているかもしれません。
企業の不祥事は大きく社会的信用を損ねます。存続の危機につながるほど大きな影響を持ちます。
インターネットの普及により不祥事の詳細が素早く拡散されるようになりました。消費者や投資家から強い批判を浴びて経営不振を招き、倒産につながる恐れもあります。
社会情勢や国際情勢に対応できない
グローバル化が進む国際情勢のもと、市場競争を勝ち抜くにはガバナンスの強化が欠かせません。
ガバナンスの強化が不足していると、健全で効率的な経営はできないでしょう。世界経済の大きく急速な変化に対応する柔軟性も、維持できないことがあります。
海外へ市場拡大などをねらう企業は、価値観や文化の差によるリスクが伴います。ガバナンスが弱い企業はこうしたリスクを回避できず、進出に失敗する可能性が高くなります。
ガバナンスが効く体制を構築する方法
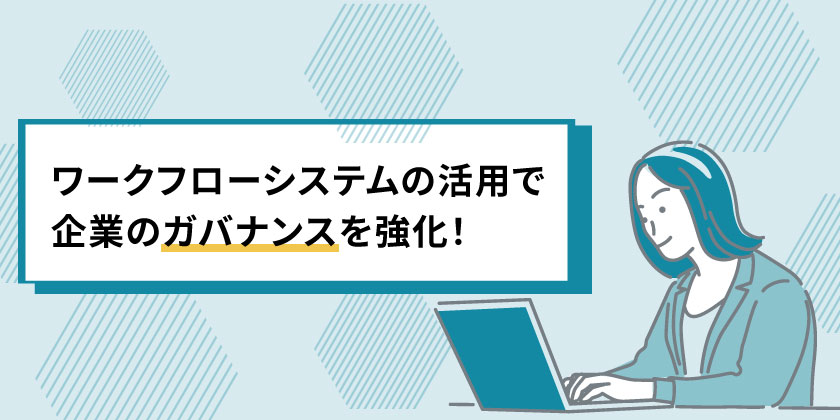
ガバナンスが効果的に働く企業体制は、どのように確立するのでしょうか。ガバナンスが働く体制を構築する方法を解説します。
内部統制の構築
ガバナンスのためには、組織としての内部統制の構築が重要です。内部統制が機能していれば、社内、社外への透明性の高い情報の開示が可能です。
内部統制は、ただの指示系統ではありません。社内で遵守するルールを定め、かつルールに従って業務が行われているかを監視する活動です。定められた規則の元で業務を実施できているかを監視し、問題点や課題を発見して適切に指導できる体制が必要です。
関連記事はこちら
⇒内部統制をわかりやすく解説|基本的要素や目的についても
監査体制の構築
監査体制とは、内部統制による監視や指導とは異なり、外部の第三者的視点での監視体制を意味します。
内部統制や内部監査では気付きにくい課題や問題点も、独立性をもって客観的に評価できる第三者機関であれば気付けます。
監査体制は社内と利害関係をもたない専門の人材を用いましょう。かつ企業側が指導や注意点を遵守できるような監査が理想です。
関連記事はこちら
⇒監査とは?種類や目的、スムーズに進めるために準備するべきことを解説
社内教育の投資
ガバナンスの強化にあたって、自社の従業員への教育と投資は欠かせません。従業員に会社の方向性や考え方を浸透させると、ガバナンスはより強固になります。
行動規範や倫理憲章を作成し、従業員が業務や意思決定を行う際の判断基準を明確にすることも重要です。従業員の業務プロセスを可視化し、遂行内容を把握して、不公正や無茶な仕事、業務量の偏りを防ぎましょう。ガバナンスの強化につながります。
ガバナンス強化にワークフローシステムを活用した事例
ワークフローシステムの活用による企業体制の変化が、ガバナンスの強化に大きく貢献する場合があります。ここでは、そのようなガバナンス強化とワークフローシステムが嚙み合って効果を発揮した事例を紹介します。
ワークフローシステム導入が内部統制強化のキッカケに
株式会社エスネットワークスは、企業の成功を実行力のあるコンサルティングで大きな実績を上げています。しかし、紙ベースのワークフローでは稟議、承認、報告を効率的におこなえませんでした。
コラボフローを導入したところ、こうした問題点がクリアされました。決済進捗状況の可視化や電子化による自動化により、ワークフローも改善されています。内部統制の強化につながった事例です。
事例記事の詳細はこちら
⇒ワークフローで内部統制を強化、電子化の一歩を/簡便さと機能性、連携性を軸にワークフロー選定
ワークフローシステム導入で組織変更・強化をできた事例
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社は、三社の経営統合により発足した会社です。当初はワークフローが共通化されず、電子化の度合いにもばらつきがありました。早期の統合が求められていました。
コラボフローを採用したところ、紙の大幅な削減に成功しました。帳票や経路が見やすくなり、内部統制の強化に成功した事例です。
事例記事の詳細はこちら
⇒経営統合によって全体最適が急務に。コラボフローの導入で社内業務の統一化に成功
まとめ:内部統制強化にワークフローシステムを活用
ガバナンスの強化は、企業が大きく業績を伸ばす過程で必要な取り組みです。またガバナンスの強化にはワークフローシステムによる可視化や効率化が重要です。
コラボスタイルでは、内部統制の強化にもつながる、柔軟で直観的に操作しやすいワークフローシステムを提供しています。興味のある方はぜひご検討ください。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。