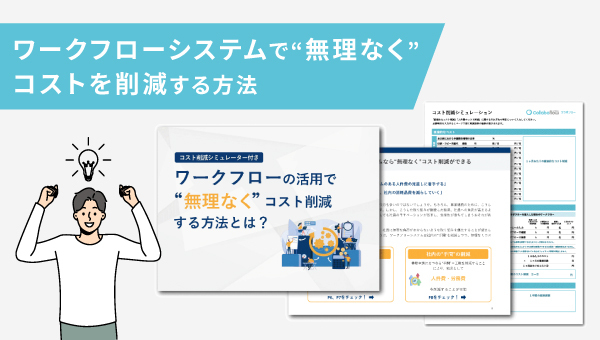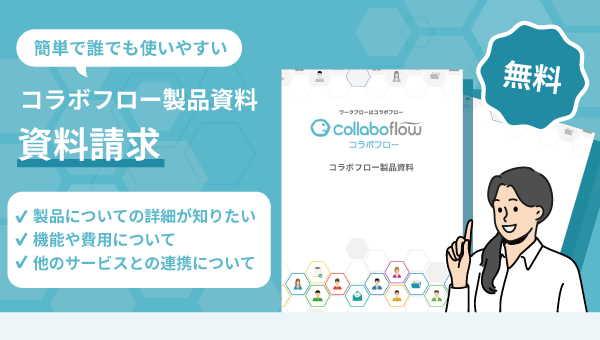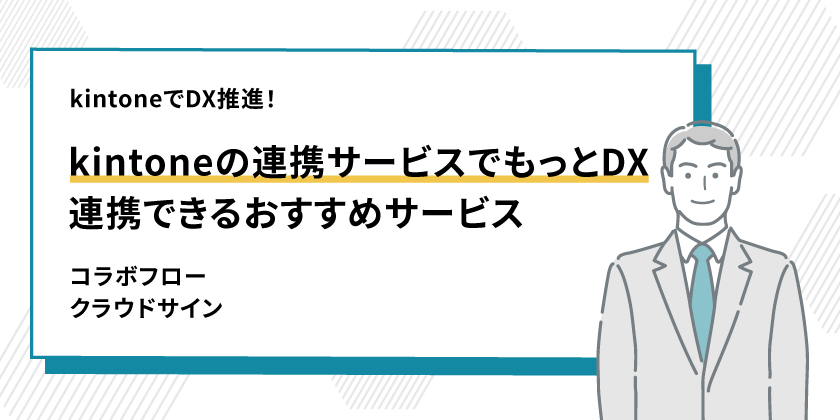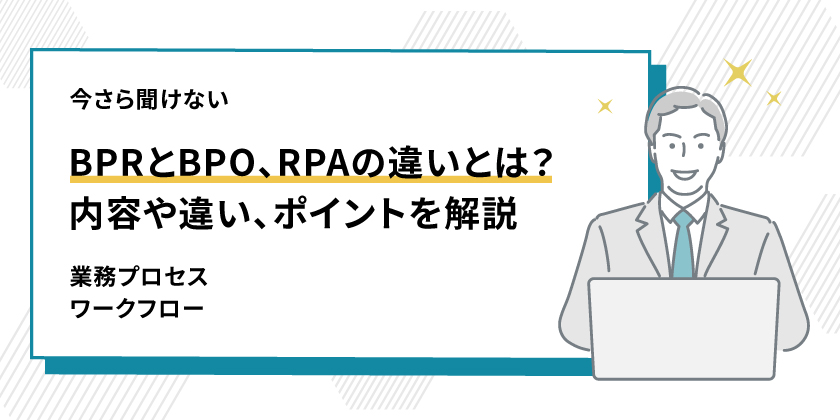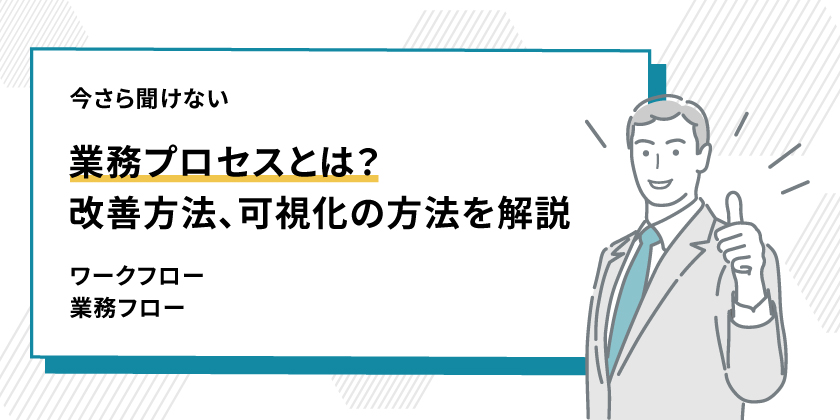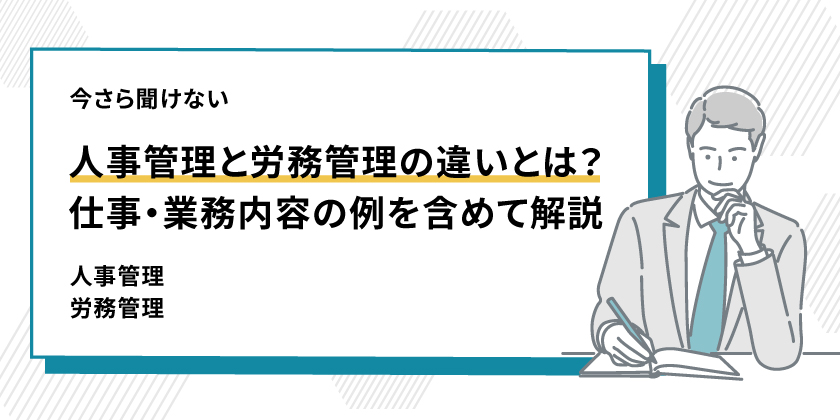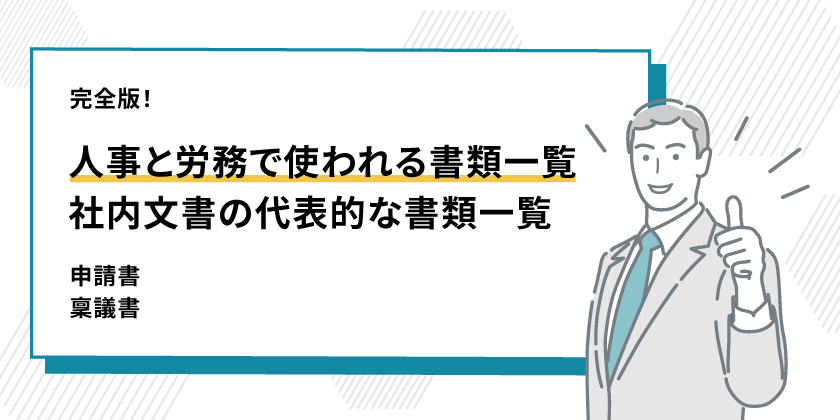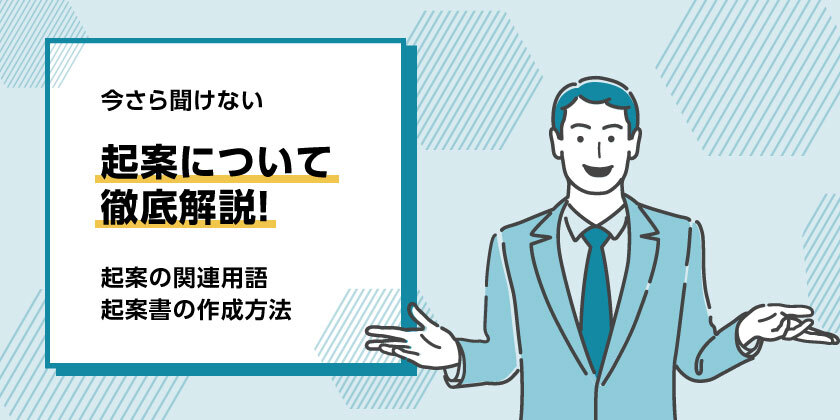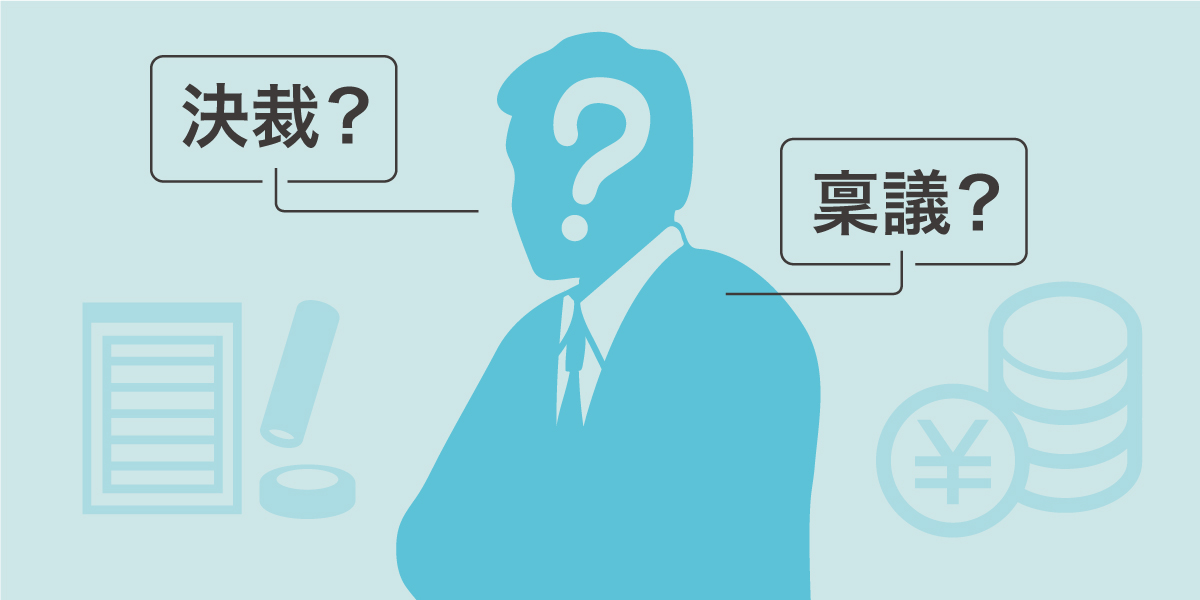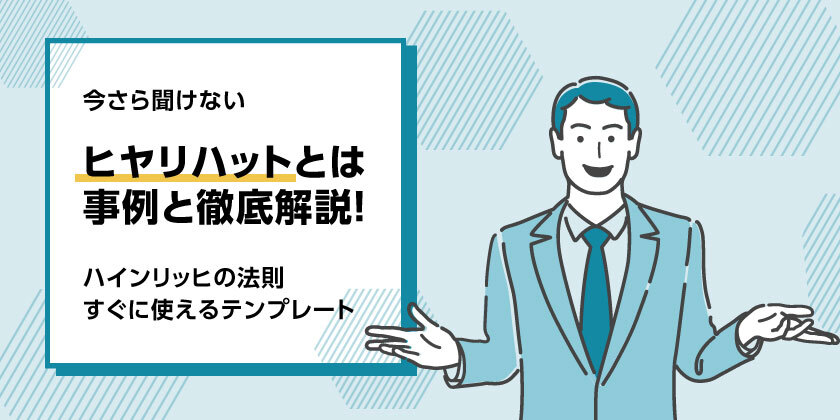この記事の目次
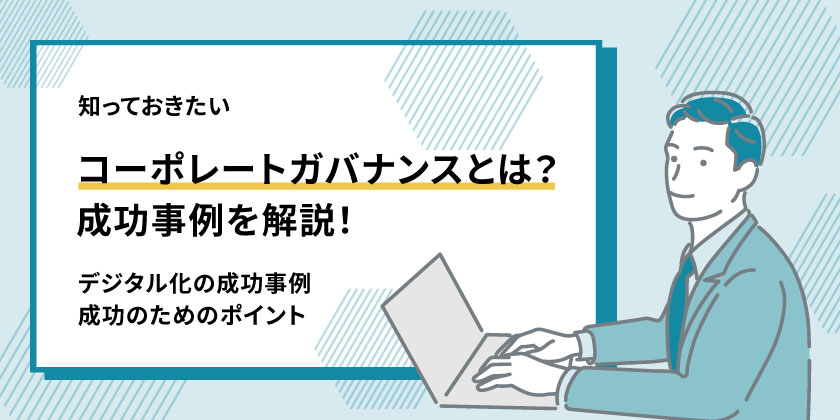
コーポレートガバナンスは「企業統治」と訳されます。企業が健全な経営のために自発的に目的やルールを定め、それに沿って活動していくことで不正や不祥事を防ぐ考え方がコーポレートガバナンスです。
今回の記事はコーポレートガバナンスの詳細や目的、強化の仕方について詳しく解説します。
コーポレートガバナンスの基本
コーポレートガバナンスは、企業が公正さや健全性を持つために自主的に定めた、組織を統制する指標です。企業が経営陣の私物ではなく、株主や従業員に対し責任を持つ組織であることを常に念頭においた指標ともいえます。
ここからは、コーポレートガバナンスの基本知識や背景を紹介します。
コーポレートガバナンスとは
日本には「企業は社長が意のままにできる組織」という認識があります。しかし、そうした考え方は企業組織の不正や不祥事が起きる原因です。企業をただの営利組織とみなす考え方は過去のものであり、コーポレートガバナンスに基づく企業の自主統制が注目されています。
コーポレートガバナンスは、組織の不正と不祥事を防ぎ、経営で公正な判断と運営がなされるよう統制する仕組みです。
また、株主やステークホルダーの利益を最大化する義務を負うこと、企業は経営者のものではなく資本を持つ株主のものであることを前提とした考え方です。
コーポレートガバナンスが重視される背景
コーポレートガバナンスが重視される背景として、バブル経済の崩壊後に企業による不正や不祥事が相次いで発覚した状況があげられます。不祥事の増加は、経営者が企業を私物化し、公正さや社会的責任を軽視する傾向が原因でした。
そのため、経営を監視する仕組みの必要性が高まりました。
現代の日本企業は、外国人投資家の持株比率が高く、国内だけでなく国際的な競争力を求められています。これらの点もコーポレートガバナンスが重視される背景に含まれます。
コーポレートガバナンスと類似用語の違い
コーポレートガバナンスの類似用語には、内部統制、コンプライアンス、CSRが挙げられます。
ここでは、それらの類似用語とコーポレートガバナンスの違いについて説明します。
内部統制
内部統制は、コーポレートガバナンスと方向性の近い概念です。ただし、コーポレートガバナンスがステークホルダーの利益を守る対外的取り組みであるのに対し、内部統制は健全性と効率性を求める対内的取り組みである点が違いといえます。
詳細な内容は、下記で紹介しています。
関連記事はこちら
⇒内部統制をわかりやすく解説|基本的要素や目的についても
⇒ワークフローで内部統制を強化、電子化の一歩を/簡便さと機能性、連携性を軸にワークフロー選定
コンプライアンス
コンプライアンスは企業が求められる法や社会的良識への遵守を指します。コーポレートガバナンスは法や良識の順守より一歩深く、ステークホルダーへの責任にまで及んでいる点が違いといえます。
CSR
CSRは、企業の社会的責任を意味する言葉です。消費者や従業員、さらに社会や地球環境への責任も含まれる、広い範囲での企業責任を指す言葉といえます。コーポレートガバナンスはCSRの一部と考えられます。
コーポレートガバナンスコードとは
コーポレートガバナンスコードとは、金融庁及び東京証券取引所が上場企業に対して順守を求めて示したガイドラインです。5つの基本原則と31項目もの原則、さらに42の補充原則を持つ3層構造となっており、プライム市場やスタンダード市場に上場する企業は3層全てのガバナンスコードの原則が適用されます。
上場企業の不正防止と、国際的な競争力の獲得を目的として定められています。上場企業には報告書の提出が義務付けられています。
参考:日本取引所グループ:コーポレートガバナンスについて
コーポレートガバナンスの目的と役割
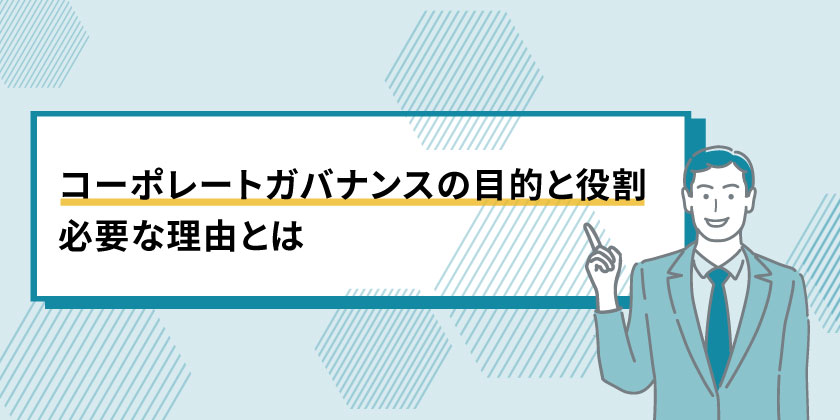
コーポレートガバナンスには、企業経営の透明性の確保や、株主とステークホルダーの保護、不正や不祥事の抑制といった目的と、中長期的な企業価値の向上といった役割があります。ここからはコーポレートガバナンスの目的と役割について解説します。
企業経営の透明性の確保
企業経営の財務状況や経営戦略方針、現状の課題といった情報は経営陣だけでなく株主やステークホルダーにも共有するべき情報です。
株主やステークホルダーと良好な関係を築くためにも、適切な情報の開示と経営の透明性の確保が重要です。
これらの情報が一部の経営陣に独占されると不正の原因となるため、これらの情報が適切に管理されるよう、統制されるべきです。コーポレートガバナンスによるこうした透明性の確保が、企業内部の不正や不祥事の防止につながるのです。
株主やステークホルダーの保護
企業経営は、経営者の利益のみを求めるのではなく、ステークホルダーの利益を守るために運営されることが原則です。株式会社であれば会社は株主のものであり、経営陣はあくまで経営を委託された立場となります。
コーポレートガバナンスはこの原則を遵守し、維持できるように定められています。企業と株主など全てのステークホルダーとの信頼関係を構築し、企業の目的が逸脱しないように適切な監査が受けられる状態を保持することが目的です。
一部の経営陣による不正や不祥事を防ぐ
バブル経済が崩壊した際、日本では企業内の一部の経営陣による不正、不祥事がいくつも表面化しました。これは、当時の日本がコーポレートガバナンスを重視していなかった結果もたらされたものです。
不正や不祥事が発生すると、株主やステークホルダーだけでなく日本経済にも深刻な影響が及びます。また近年は、ネットやSNSによる情報の分散が加速したことにより、影響が広まるのも早く、悪いイメージを植え付けてしまうことにつながります。
コーポレートガバナンスにより社外取締役や監査役が設置され、経営陣を監視する体制の構築をすることは極めて重要です。
中長期的な企業価値向上につながる
コーポレートガバナンスの導入は、企業の中長期的な価値向上に寄与します。
コーポレートガバナンスに取り組み、経営の透明性を高めると、投資家は企業のリスクや将来性を正しく評価できます。
企業の評価は金融機関に安心感を与え、市場を安定させる材料となり、また新たな投資や出資を呼び込む要因となるでしょう。
上場や非上場、また企業規模の大小に関係なく、現代の投資では社会的な信用を高めることは非常に重要な要素なのです。
またステークホルダーからの評価が高まると、販売促進や人材採用面にも有利に働くという側面もあります。
コーポレートガバナンスを強化する方法
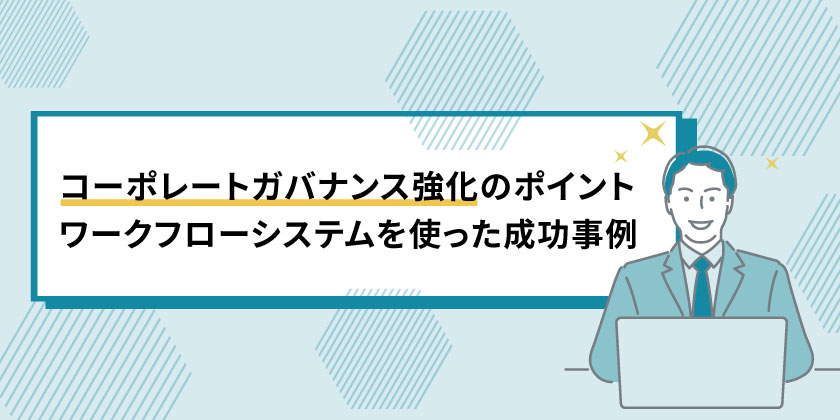
コーポレートガバナンスは現代の企業に求められる非常に重要な要素ですが、その実施は決して簡単ではありません。古い体質の企業であるほど、慣習や前例による縛りとコーポレートガバナンスの対立点が生まれやすいです。
コーポレートガバナンスを強化し、万全の体制を築くための方法について解説します。
内部統制の強化
コーポレートガバナンスと内部統制は、対外的と対内的という違いはあれども、相互に深く関係した要素です。
内部統制の強化により適切な監視体制が整備され、社内の不祥事や不正を未然に防ぐことができます。
適切な情報を提示し、財務状況などの透明性を確保するには、内部統制による社内の意思統一とルールの共有が欠かせません。
内部統制は企業統治の根幹であり、健全な企業経営に不可欠な要素といえます。
関連記事はこちら
⇒内部統制をわかりやすく解説|基本的要素や目的についても
⇒ワークフローで内部統制を強化、電子化の一歩を/簡便さと機能性、連携性を軸にワークフロー選定
社外取締役と監査役の設置
内部統制の強化だけでは企業統治は不十分です。企業の状況の客観的な評価、内部からは気付きにくいリスクの発見のためには、社外取締役と監査役の設置が不可欠です。第三者の視点からの監視があって初めて、経営陣の不祥事や不正を防止できます。
社外取締役や監査役は、ステークホルダーの代弁者として企業経営の監視を行う機能が期待できます。株主の利益を守るという観点からも、社外取締役や監査役の設置は必要といえます。
社内規定の明確化
内部統制の強化には、社内規定を明確化し、企業としての考え方や経営の方向性を従業員に周知徹底することが有効です。社内規定を明確化すると、社内での業務における判断基準が定まり、従業員1人1人の意識改革につながります。
社内既定を明確化することで、意思決定や業務遂行の判断基準の浸透が、ガバナンスの強化につながるといえるでしょう。
執行役員制度の導入
執行役員制度の導入も、ガバナンス強化に有効です。
執行役員は、取締役に代わって企業の業務を執行する権限を持ち、取締役とは別に選任されます。
意思決定を行う取締役と業務執行の権限を持つ執行役員を分離させる執行役員制度は、業務の透明性を高め不正や不祥事の抑制に大きな効果を発揮するでしょう。
コーポレートガバナンス強化による弊害
コーポレートガバナンスの強化は、中長期的に企業の健全性と透明性を高めて企業価値を底上げします。しかし、特に導入直後はさまざまな弊害が発生することも予想されることがあります
例えば、社外監査の業務が逼迫し、事業の意思決定スピードが遅くなる可能性などがあります。さらに、内部統制などの体制構築には時間、コストが必要です。
本社がガバナンスを整備した場合、グループ会社にも同様の整備が求められます。規模の小さいグループ会社には負担が大きくなるでしょう。
こうした弊害を事前に想定し、緩和策と合わせたガバナンスの強化が求められます。
ワークフローの導入でコーポレートガバナンスの強化を
ワークフローシステムは、本来企業での意思決定の過程をシステム化し、業務の遂行を支援するシステムです。ワークフローシステムの導入はコーポレートガバナンスの強化にも有効です。
ワークフローシステムの導入がガバナンスにもたらす効果を解説します。
関連記事はこちら
⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介
⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説
内部統制の強化
ワークフローシステムは、文字通りワークフローの支援と効率化を行うシステムです。ワークフローシステムが導入されると、社内の意思決定の過程が可視化され、進行中の申請や稟議の進捗を確認できます。それだけでなく、いつ、誰が、何を承認したのかというルート、つまり証跡もデータとして保存されます。
これにより、意思決定プロセスの監査が容易となり、業務手順の透明性が担保されるでしょう。業務手順の透明性の向上は、コーポレートガバナンスの強化に大きく寄与します。
マニュアル、業務規程の明確化、社員への浸透
もし、マニュアルや業務規程が整理されていないと社員の業務に支障が出ることが予想されます。ワークフローシステムの導入をすることで、社内規定や業務マニュアルが整理・保管できます。
各部署により異なるマニュアルや承認ルートが整理されることで、社員が分かりやすく確認・閲覧することができ、業務規定の明確化の浸透及び、ガバナンスの強化が可能です。
コストの削減
ワークフローシステムの導入は、紙や印刷代、書類の輸送費や作成のための人件費などのコストの削減につながります。保管スペースの管理といった業務の削減にも寄与するでしょう。特にバックオフィス業務の効率化への貢献度は大きいといえます。
バックオフィスの経費やコストは細かく煩雑であり、不正を隠す経理処理の温床となりうる側面があります。ワークフローシステムの導入は、こうした部分への透明化にも役立ちます。
ワークフロー導入による成功事例
ここまで、ワークフローシステムの導入がどのようにガバナンス強化に寄与するかを説明しました。実際にワークフローシステムの導入がコーポレートガバナンスの強化につながった例を2つ紹介します。
紙帳票の電子化を業務効率化と内部統制強化に|株式会社高田工業所
株式会社高田工業では、紙帳簿の電子化という課題の解決、生産性の向上、働き方改革を期してコラボフローを導入しました。
また、内部統制の強化の必要性も感じており、社内決裁基準にコラボフローが対応できた点が大きなポイントです。
それだけでなく、導入による電子化の実現、決裁履歴によるデータとの差分比較やチェックで、ガバナンスの強化もできました。
事例記事の詳細はこちら
⇒紙帳票の電子化による効果は、業務効率化・スピードアップにとどまらない! 申請・決裁データの分析や内部統制強化など自社に合わせて活用
電子決裁導入をガバナンス改革につなげる|学校法人追手門学院
学校法人追手門学院は、幼稚園から大学までの一貫連携教育を進めています。他大学に先駆けて「ガバナンス改革」を実施し、さまざまな業務改革を推進しました。
コラボフローの導入は学校機関においても力を発揮し、操作性や柔軟性から業務の改善につながりました。教育機関ならではの監査や補助金申請の面でもワークフローが威力を発揮し、決裁スピードだけでなく進捗管理や監査の面でも効果がでています。
事例記事の詳細はこちら
⇒教育機関のワークフロー選定基準は総合力と柔軟性/電子決裁導入で業務改革をさらに加速
まとめ
コーポレートガバナンスの強化現代に必須な国際的な企業価値を高めます。ワークフローシステムは、業務の効率化とともに企業統制の強化にも威力を発揮します。
ワークフローシステムによるガバナンス強化に興味をお持ちの方は、ぜひ下記までお問合せください。
ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。