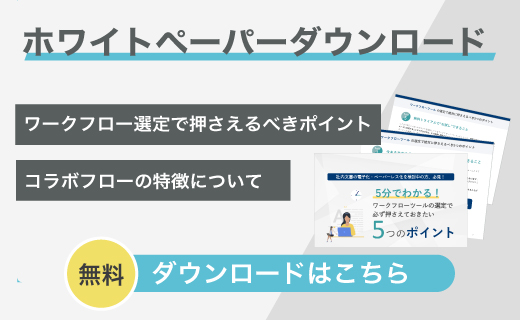ワークフローシステム
まるわかりガイド
活用できる業務やシステム選びのポイントなど
ワークフローシステムについてまるわかり!

ワークフローシステムとは?
活用できる業務とシステム選びのポイント
ワークフローシステムとは、企業内で行われる各種申請や承認などの業務フローを電子化し、オンライン上で管理・運用する仕組みのことです。 申請内容の入力フォームや利用するユーザーと組織の管理、承認ルートや承認者の条件設定機能などが備わっています。 ワークフローシステムを活用すると、申請作業にかかる時間やコストの削減だけでなく、ペーパーレス化や迅速な意思決定の実現にもつながります。 企業が成長し、多様な業務フローを抱えるようになると、申請内容や承認ステータスの把握が困難になりがちです。ワークフローシステムを導入すれば承認プロセスや申請履歴がシステム上に記録されるため、業務全体の可視化が進みます。
この記事の目次
ワークフローシステムとは
「ワークフローシステム」とは、業務における申請・承認・報告などの一連の流れ(ワークフロー)を、電子化・自動化するための仕組みです。
近年はテレワークやリモートワークの導入など働き方が多様化し、従来の紙ベースの申請フローでは処理が追いつかないケースが増えています。
こうした変化に柔軟に対応するため、オンライン上で承認作業を完結できるワークフローシステムの導入が進んでいます。
ワークフローシステムを活用すれば、申請の進捗が可視化され、意思決定が迅速に行えるだけでなく、内部統制の強化や情報の一元管理にも役立ちます。
この記事では、ワークフローシステムの概要や活用シーン、導入メリット、そしてシステム選定時のポイントについて解説します。
そもそもワークフローとは
ワークフローとは、業務の一連の処理や手続きの流れのことです。また、流れを視覚的に表したものを「ワークフロー図」と呼びます。
従来は広い意味で使われていましたが、近年での意味のワークフローとは「組織内における申請や承認や決裁、その後の確認や回付といった一連の流れ」を指すようになりました。
企業の規模が大きかったり、申請条件や承認ルートが煩雑だったりすると
「どの申請書を使えば良いのか?」「どの承認ルートを使えばよいのか?」「申請から承認までの進捗状況は?」「承認から決裁までに時間がかかりすぎ」
といった問題が発生し、業務の効率化を妨げてしまいます。
業務の効率化とスムーズな処理のためには、ワークフローを組織内で適切に運用する必要があります。

ワークフローシステムが活用できるシーンの例
ワークフローシステムは、さまざまな業務プロセスを効率化できる汎用性の高いシステムです。
以下に代表的な活用シーンを紹介します。
稟議や決裁の申請
上長や関係部署の承認が必要な稟議や決裁は、プロセスが複雑になりがちです。
ワークフローシステムを使えば、申請段階で承認ルートを自動で設定し、関係者全員に同時に通知を送れます。
結果として、稟議や決裁の進捗が可視化され、申請漏れや承認の遅延を防ぎつつ、スピーディな対応が可能になります。
経費や交通費の申請
領収書の保管や交通費の計算など、経費精算には細かな作業が伴います。
ワークフローシステムでは、電子証憑を活用して簡単に添付・参照できるため、紙の受け渡しやチェック作業におけるミスが減少します。
また、承認ルートが明確になることで、承認者は短時間で内容を確認でき、結果として社員側の待ち時間も削減されます。
勤怠や休暇の申請
ワークフローシステムを導入すれば、出勤状況や有給残日数をもとに、オンライン上でリアルタイムに休暇に関する申請や承認を行えます。
勤怠情報の正確性が向上するだけでなく、休暇残日数を自動で集計できるシステムも多く、社員にとっても利便性に優れています。
申請の手間が軽減されることで、業務の効率化にもつながります。
管理者側も実績の一括確認が容易となり、認識の食い違いによるトラブルを未然に防げます。
物品購入や発注の申請
業務に必要な備品や資材の購入申請から発注までをワークフローシステムで管理することで、申請・承認・発注の一連の流れがスムーズになります。
あらかじめ予算と紐づけて承認フローを設定できるため、無駄な支出の抑制にもつながります。
さらに、購買履歴がシステム上に残ることで、業者との取引状況やコストの管理・分析も容易になります。
ワークフローシステムの主な機能
ワークフローシステムには、業務を効率化するための機能が備わっています。
ここからは、ワークフローシステムの主要な機能について解説します。
申請書のフォーマット作成機能
申請書のフォーマット作成機能は、ワークフローシステムの基本的な機能の一つです。
従来の紙ベースの申請書をデジタル化し、効率的に管理することが可能になります。
システムではドラッグ&ドロップなどの直感的な操作により、簡単かつ素早く申請フォームを作成できます。
また、テンプレートの再利用機能も備わっていることが多く、入力ミスも減らせます。
さらに、申請内容に応じて必要な項目を動的に表示したり、入力値の自動チェック機能を設定したりすることで、より正確で効率的な申請業務を実現できます。
承認経路の定義と管理機能
ワークフローシステムでは「承認者」や「承認フローの順序」などを柔軟に設定できます。
具体的には、部署や役職、金額などの条件に応じて、適切な承認者や承認ルートの設定が可能です。
例えば、「10万円以上の経費申請は部長承認が必要」といった条件分岐のルールを組み込むことができます。
また、フローが現在ステータスか、どの承認者のところまで進んでいるかが一目でわかる機能も備わっています。
したがって、申請者も承認者も進捗状況を容易に把握できます。
さらに、システムによっては、組織改編や人事異動にも自動で対応できる仕組みが備わっています。
こうした仕組みがあれば常に最新の組織体制に沿った承認フローを維持することができ、承認ルートのメンテナンス作業が大幅に削減されます。
通知・リマインド機能
通知とリマインド機能により、申請や承認のプロセスがスムーズに進行し、業務の滞留を防ぐことができます。
ワークフローシステムは、申請時や承認が必要なタイミングで、対象者にメールなどの通知が届く仕組みがあります。
これにより、承認者は迅速に対応しやすくなります。
また、期限前のリマインド通知機能も備わっており、処理の遅れや漏れを効果的に防ぐことができます。
さらに、多くのシステムにはコメント機能が搭載されています。
これにより、差し戻し理由や申し送り事項を直接システム上で伝えることが可能となり、関係者間のコミュニケーションが円滑になります。メールやチャットツールとの連携機能を持つシステムもあり、よりスムーズな情報共有が可能です。
ワークフローシステムを社内に導入するメリット
ワークフローシステムの導入により、企業全体の作業スピードや生産性、管理体制の向上が見込めます。
具体的なメリットを見ていきましょう。
意思決定の効率化
ワークフローシステムを導入する最大のメリットのひとつが、「意思決定の効率化」です。
ワークフローシステムでは、申請内容が上長や関係部署に即時に共有され、承認者はどこにいても申請確認と承認・非承認の判断を行うことができます。
従来の紙ベースやメールでの承認プロセスでは、担当者の不在や書類の滞留によって、意思決定までに多くの時間がかかるケースが少なくありませんでした。
ワークフローシステムでは、申請から承認、決裁までのプロセスがすべてオンライン上で完結します。
これにより、各担当者への通知や進捗管理が自動化されるため、承認者が外出中でもスマートフォンやパソコンから迅速に対応することができます。
また、承認ルートが明確化されることで、誰の承認が滞っているのかが一目でわかります。
担当者へのリマインドや代理承認などの対応も容易になり、意思決定のスピードが大幅に向上します。
ペーパーレスやリモートワークに対応できる
ワークフローシステムを導入すれば、同時にペーパーレス化した運用が可能となるため、オンライン上で申請や承認が完結します。
これまで紙で運用していた業務フローをオンライン化することで、印刷や保管、郵送にかかるコストや手間が大幅に削減されます。
したがって在宅勤務時や出張時でも申請・承認を行いやすくなります。
また、書類の紛失リスクや、必要な書類を探す手間も解消できるため、日々の業務効率が向上します。
紙書類の保管コスト、郵送費、印刷費などの削減に加え、物理的なファイル保管場所も必要なくなります。
承認ルートの明確化
ワークフローシステムを導入すると、申請から承認までのルートを事前に明確化し、自動化することができます。
これにより、「誰が・いつ・どの申請に対して承認したか」がシステム上に記録されるため、承認プロセスの不透明さや属人的な運用を排除できます。
監査や内部統制の観点からも、申請履歴や承認経路が自動的に記録・保存されるため、後から証跡を確認でき、ガバナンス強化に直結します。
不正な処理の防止やミスの防止
紙やメールによる従来の申請フローでは、承認手順が曖昧になったり、承認者が飛ばされてしまうなどのヒューマンエラーが起こりがちです。
ワークフローシステムでは、ルールに則った承認経路が必ず守られるため、不正やミスの発生リスクを最小限に抑えられます。
また、全ての処理内容がログとして残るため、いつ・誰が・どのような対応を行ったかを後から簡単に追跡可能です。これにより、組織全体での透明性が高まり、ガバナンスの強化につながります。
ワークフローシステム導入時の注意点
ワークフローシステムの導入はメリットも多いですが、同時に慎重に検討すべき点もあります。
特にシステムでは社内の機密情報を管理することになるため、セキュリティ面や運用上の注意点を事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、導入時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
セキュリティ機能を確認して安全性を高める
ワークフローシステムのセキュリティ機能は、企業の重要な情報を守る上で欠かせません。
導入時には、以下のポイントを重点的に確認し、システムの安全性を高めることが重要です。
まず、必要以上の情報アクセスを防ぎ、情報漏洩のリスクを低減できるようになっているかを確かめましょう。
社員ごとに閲覧・操作できる範囲を制限する機能が備わっていると安心です。
加えて、アクセス履歴を詳細に記録する機能の有無も重要なチェックポイントです。
誰がいつどのような操作をしたかを追跡できれば、万一のトラブル時にも迅速な対応が可能になります。
データを保護しバックアップ体制を整える
データ保護とバックアップは、ワークフローシステムの信頼性を確保する上で極めて重要です。
まず、保存されているデータが適切に暗号化されているかを確認します。
さらに、データ通信時は暗号化技術(SSLなど)が使用されていることが理想的です。
続いて、自動バックアップが作られる機能の有無をチェックします。クラウド型サービスを選択する場合は、データセンターの安全性や災害対策、復旧体制についても詳細に確認しておきましょう。
また、データの保管期間や廃棄方法についても事前に確認し、法令遵守や内部統制の観点から適切な設定を行うことが大切です。
利用する社員のリテラシーを向上させる
ワークフローシステムの効果的な運用には、システムそのもののセキュリティだけでなく、利用する社員のリテラシー向上が不可欠です。
利用する社員に対してはシステムの使い方だけでなく、情報の取り扱い方についても注意するよう伝えることが重要です。
もちろん新入社員の入社時や部署異動をした社員にも教育を行い、セキュリティ意識の定着を図りましょう。
システムの更新や新機能の追加時には、速やかに関連情報を共有し、必要に応じて追加の教育を行います。
ワークフローシステム選びで失敗しないためのポイント
ワークフローシステムを選定する際には、機能性や操作性、連携性などを見極めることが重要です。
稟議書や申請書などの社内手続きが煩雑で、承認フローに時間がかかっている――そんな課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。
ペーパーレス化やリモートワーク、内部統制強化など、現代の多様な働き方にも対応できるのが大きな特徴です。
自社に合ったワークフローシステム選びの参考に、ぜひご一読ください。
自社業務に合ったフォーマットが使えるか
稟議や経費申請などで使用する申請書の形式や承認ルートは企業によって異なるため、ワークフローシステムが自社仕様にカスタマイズできるかどうかは重要なポイントです。
申請書のフォーマット変更や承認ルートの柔軟な設定に対応していれば、業務の実態に沿った運用が可能になります。
業種特有の申請業務がある場合には、それに対応できる機能が備わっているかを確認しておくことも大切です。
テンプレートの種類や設定項目の豊富さも、導入時のチェックポイントとなるでしょう。
現場で働く社員が使いやすい形か
ワークフローシステムは、実際に使う現場の社員にとって使いやすいものでなければ、その効果を十分に発揮できません。
操作が複雑だったり、画面がわかりづらかったりすると、かえって混乱を招いてしまいます。
システムを検討する際は申請者・承認者の両方の視点で使いやすさを判断するようにしましょう。
ワークフローシステムは、誰にとっても直感的に使える操作画面になっているのが理想的です。
入力フォームや申請の流れに無駄がなく、操作案内やヘルプがわかりやすい設計になっているかを確認しましょう。
また、システムを導入する前に働く社員の意見をヒアリングするのもおすすめです。
現場で働く人の課題を解消できるシステムを探しやすくなるでしょう。
今使っているシステムと連携できるか
現行の基幹システムとデータを連携できるかも重要な要素です。
API連携やファイル連携など複数の連携方法が用意されているワークフローシステムを選ぶと便利です。
今後の業務拡大やDX推進を見据えて、クラウドストレージやERPなど、他の業務システムと連携できるかどうかもチェックポイントです。
API連携やデータのインポート・エクスポート機能など、拡張性の高さも重要です。
サポート体制・導入実績も要チェック
トラブル発生時や運用中の疑問をすぐに解決できるよう、サポート体制が充実しているかを確認しましょう。
導入事例が豊富なベンダーは、業種ごとのノウハウも蓄積されているため、自社に最適な提案やサポートを受けやすくなります。
事前に導入実績やサポート体制をチェックしておくと安心です。
ワークフローシステム導入のステップ
ワークフローシステムの導入は、単にシステムを選んで導入するだけではなく、事前の準備や段階的な進め方がとても重要です。
現状の業務フローや課題を正しく把握し、自社に最適なシステムを選定・定着させることで、初めて本当の業務効率化やガバナンス強化が実現できます。
ここでは、ワークフローシステム導入を成功させるための基本的なステップを、分かりやすく解説します。
資料ダウンロードはこちら
⇒ワークフローツールを選定する上で絶対に押さえるべきポイントは?
⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント
⇒ハイブリッドワークを導入するために導入すべき、5つのITツールご紹介
現状業務の分析と要件定義
まずはワークフローシステム導入にあたって現状業務の詳細な分析と要件定義を行います。
現在の業務フローを図や表を使って「見える化」し、無駄や課題を洗い出します。
この過程で、どの業務をシステム化するか、承認ルートは誰にするかなどを具体的に決定していきます。
関係者の巻き込みと教育
ワークフローシステムの成功には、実際に使用する社員の理解と協力が不可欠です。
したがって、導入の早い段階から関係者を巻き込み、適切な教育を行うことが重要です。
まず、現場の社員や承認者など、実際にシステムを使用する人々の意見を事前に聞くことが大切です。
ワークフローに関わる社員たちの業務における課題や要望を把握して、システムでどのように解決していくかを検討しましょう。
段階的な導入とトライアル運用
ワークフローシステムの導入によって、現場が混乱するリスクもゼロではありません。
急激に導入を進めたり、十分な移行期間が足りなかったりすると、社員がついて行けない可能性もあります。
こうしたリスクを最小限に抑えるには、段階的な導入とトライアル運用が効果的です。
まずは一部の部署や業務で試験的に導入することから始めましょう。比較的シンプルな申請業務から着手するのがおすすめです。
トライアル期間中は、ユーザーからのフィードバックを積極的に収集します。使いにくい点や改善要望を丁寧にヒアリングし、必要に応じてシステムのカスタマイズや運用ルールの調整を行います。
試行結果をもとに修正を加えれば、本番運用時のトラブルを減らすことが期待できます。
運用後の改善とフィードバック活用
ワークフローシステムを導入した後は、継続的な改善とフィードバックの活用を行います。
定期的に「困っている点はないか」「使いづらいところはないか」を利用している社員に確認しましょう。
利用状況の分析やユーザーアンケートを通じて、便利になった点と改善すべき点を把握します。
特に、使用頻度の低い機能や、ユーザーからの不満が多い部分については、原因を詳しく調査し、改善策を検討します。
社員からの要望を積極的に取り入れ、システムをアップデートすることで、ユーザー満足度を高められます。
例えば、頻繁に使用される申請フォームの改善や、新しい承認ルートの追加など、実際の業務に即した改善を行います。
ただし、すべての要望を無条件に受け入れるのではなく、費用対効果を考慮しながら判断することが大切です。
また、社内の組織変更や業務プロセスの見直しに合わせて、承認フローを適宜見直すことも重要になってきます。
ワークフローシステムで業務効率化と組織力を高めよう
ワークフローシステムは、申請・承認といった日常的な業務を電子化・自動化することで、業務全体の効率化と生産性向上を実現します。
テレワークや勤務先の多拠点化が進む中で、時間や場所にとらわれず申請・承認業務を進められる点は大きな強みと言えるでしょう。まずは自社の業務フローや課題を整理し、どのような仕組みを見直しましょう。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。