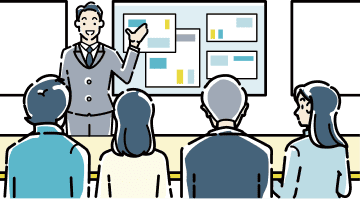ワークフローの作り方は?作成の際に押さえておきたいポイント
2025.10.30
この記事の目次

よくあるワークフローの種類
ワークフローは様々な業務プロセスに適用できます。
ここでは、一般的によく見られるワークフローの種類について解説します。
社内申請・承認に関する業務
経費精算や業務で使用する備品の購入申請などは、承認ワークフローが重要な役割を果たします。
一般的な承認フローは、申請者が申請を作成し、上長、経理部門が確認するといったように、段階を踏んでフローが進みます。
このような承認プロセスをワークフロー化することで、申請ミスや承認漏れの防止、業務効率化などが期待できます。
社外とのやりとりが発生する業務
社外とのコミュニケーションを含む業務プロセスも、ワークフロー化の重要な対象です。
見積書・請求書の発行、契約書の締結、納品・検収などが該当します。
ワークフローを活用すると、対応漏れや情報の行き違いを防止できます。
人事・労務に関する業務
採用や勤怠管理などの人事・労務業務は、個人情報を扱うため慎重な管理が必要です。
こうした管理をワークフローに当てはめればより情報管理が徹底でき、標準化や法令遵守の実現にもつながります。
勤怠管理や休暇申請を自動化すれば、労働時間の適切な管理や有給休暇の取得促進など、コンプライアンスの強化にもつながります。
部門を横断する業務
新製品開発などの部門横断業務では、情報共有と進捗管理が課題になりがちです。
しかし、ワークフローを構築すれば、役割分担の明確化と効率化が図れます。
部門間の連携強化に有効です。
ワークフローの作り方
効果的なワークフローを作成するためには、明確な手順とポイントを押さえることが重要です。
ここからは、ワークフロー作成の基本的なステップを解説します。
1.目的を明確にする
まずはワークフローを作成する目的を明確に定義します。
目的が不明確なまま作成を始めると、効果的なワークフローにならない可能性があります。
目的を明確にすることで、ワークフローの設計方針や優先順位が定まり、より効果的な業務プロセスの構築が可能になります。
また、目的を関係者と共有することで、ワークフロー導入に対する理解と協力を得やすくなるというメリットもあります。
2.関係者と業務を洗い出す
定義した目的をもとにワークフローに関与する部署や担当者をリストアップして、各関係者の役割や業務内容を明確にします。
例えば、経費精算のワークフローを作成する場合、申請者、承認者(上長)、経理担当者などが主な関係者となります。
各関係者の具体的なタスク(申請書作成、内容確認、支払い処理など)を明確にし、それぞれの責任範囲を定義します。
関係者の役割の明確化が重要です。
3.業務の流れを整理する
業務の流れを整理する段階では、各タスクの関係性を時系列で明確にし、プロセス全体を可視化します。
この作業により、業務の全体像が把握でき、効率化の余地や潜在的な問題点を発見しやすくなります。
整理する際に重要なのは、例外的なケースや条件分岐も考慮することです。
「もし承認が得られなかった場合は?」「緊急の案件が入った場合は?」といった状況も想定し、それぞれのケースでの対応フローを整理しておけば、より柔軟かつ実用的なワークフローとなります。
4.図にして視覚化する
整理した業務の流れをフローチャートや業務フロー図など、わかりやすい形にまとめます。
図で表すことで、複雑な文章説明よりも直感的に理解しやすくなり、確認や修正がしやすくなります。
図解による視覚化がポイントです。
必要に応じて、使用する記号や図形のルールを簡潔に説明しておくと、さらに理解しやすくなるでしょう。
5.社内で共有し改善する
作成したワークフローを関係者と共有し、フィードバックを得ます。
フィードバックをもとに問題点を洗い出し、より使いやすい形へと改善していきましょう。
運用を始めてしばらく経ったタイミングで課題が見えてくることも多いので、定期的なフィードバックと改善が欠かせません。
ワークフロー作成時のポイント
効果的なワークフローを作成するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
これらのポイントを押さえれば、実用的なワークフローを構築することができるでしょう。
現場の声を反映しているか
現場の意見を取り入れることで、実用的で定着しやすいワークフローが構築できます。
使いづらいシステムの導入は、逆に業務効率を下げる可能性もあるため注意が必要です。
現場との対話が重要です。
承認ステップが複雑すぎないか
承認者やステップが多すぎると、業務が滞る原因になります。
必要最低限の承認に絞ることで、迅速で柔軟な運用が可能になります。
ステップのシンプル化を意識しましょう。
例外ルートはあるか
効果的なワークフローには、通常のフローとは異なる例外的なケースへの対応も含まれていることが重要です。
緊急対応や特別処理などの例外ルートを想定し、あらかじめ対応策を用意しておくことで、業務の柔軟性と安定性を両立させられます。
定期的な見直しを前提にしているか
ワークフローの作成は一度で完了するものではありません。
業務環境や組織体制の変化に応じて、定期的に見直すことが重要です。
見直し・改善の継続を前提に設計しましょう。
使いやすいワークフローを作るコツ
ここからは、ワークフローを作成する際のコツについて詳しく解説します。
より使いやすくスムーズに運用できるワークフローが作れるように、これらのコツも押さえておきましょう。
現状分析を行う
ワークフローを作成する前に、現状の業務プロセスを把握しましょう。
正確な現状分析がなければ、的外れなフローとなるリスクが高いため、まず現行業務の実態をつかむことが重要です。
現状把握をしっかり行いましょう。
全体の流れを先に設計する
全体像を把握せずに詳細設計に入ると、整合性が取れず断片的なフローになってしまうリスクが高いです。
したがって、最初に全体の構造をつかむ必要があります。
まずは大まかな部分を設計して、そこから詳細を詰めていくようにしましょう。
部署や業務内容に応じた流れを作る
効果的なワークフローを作成するためには、部署や業務内容に応じた柔軟な設計が必要です。
業務の実態に合わない一律の設計では、運用が形骸化し現場に浸透しづらいため、業務ごとの特性に応じた設計が求められます。
部署ごとの特性を意識した構成にしましょう。
効果的なワークフロー作成で業務効率を向上させよう
効果的なワークフローの作成は、業務効率向上のカギです。
目的を明確にし、現状分析を行い、全体の流れを設計した上で、部署や業務内容に応じた柔軟なフローを構築することが重要です。
また、定期的な見直しと改善を行うことで、適切な業務プロセスを維持できます。
今回紹介したポイントを押さえてワークフローを作成し、組織の生産性向上に取り組んでみてください。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。