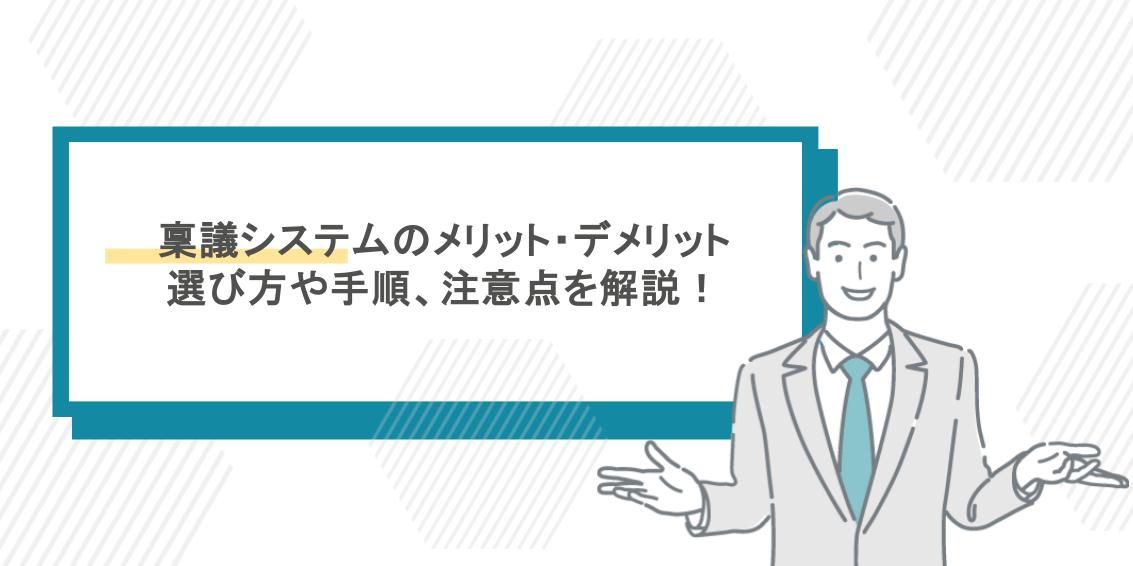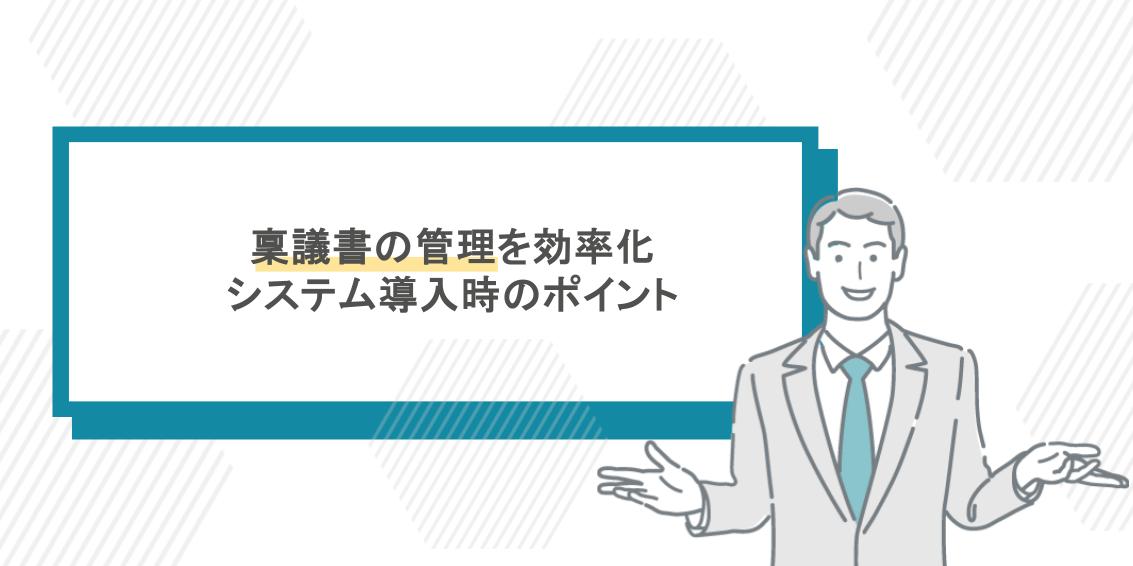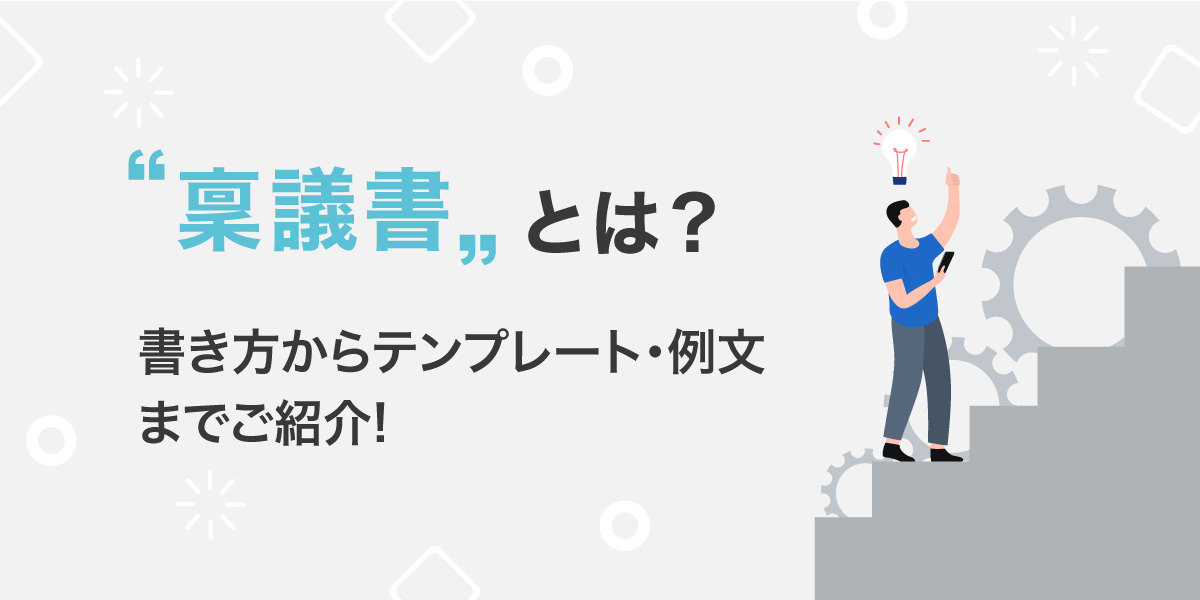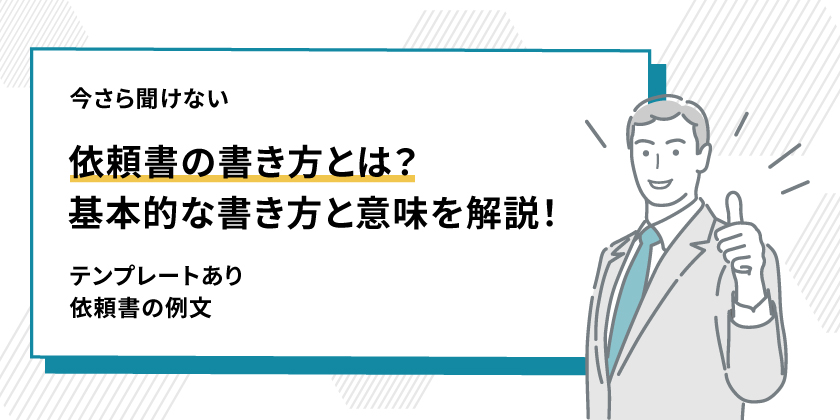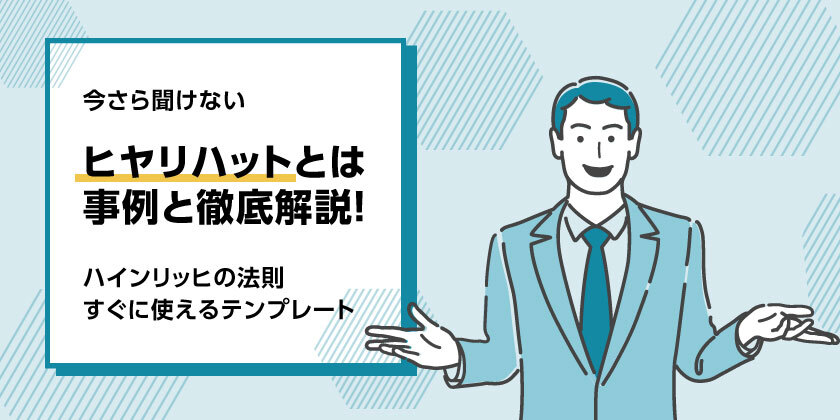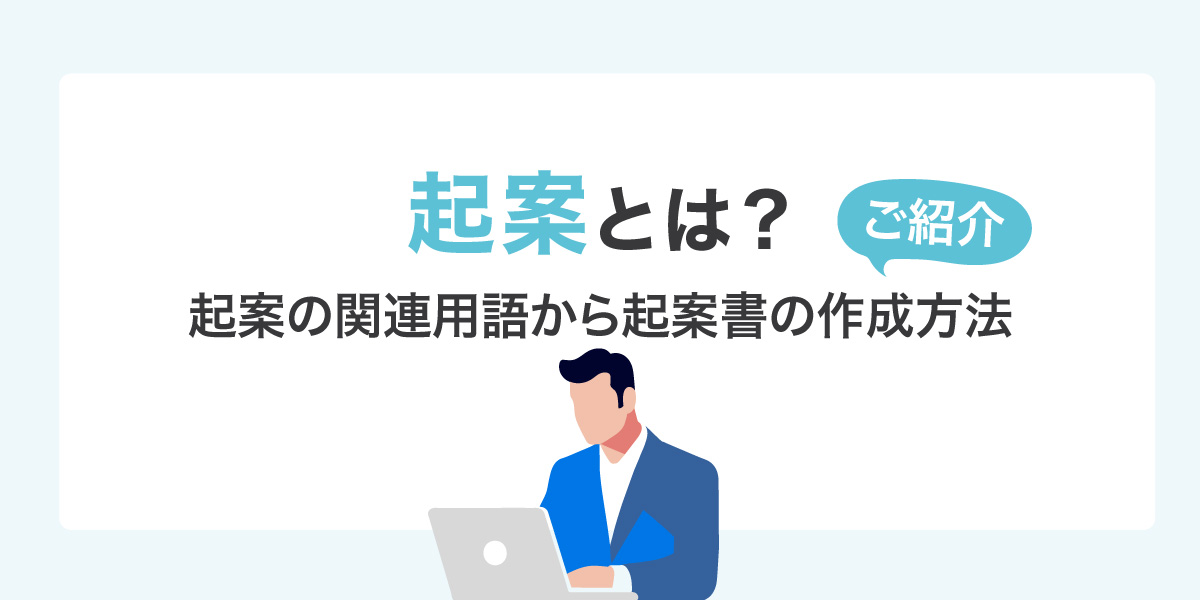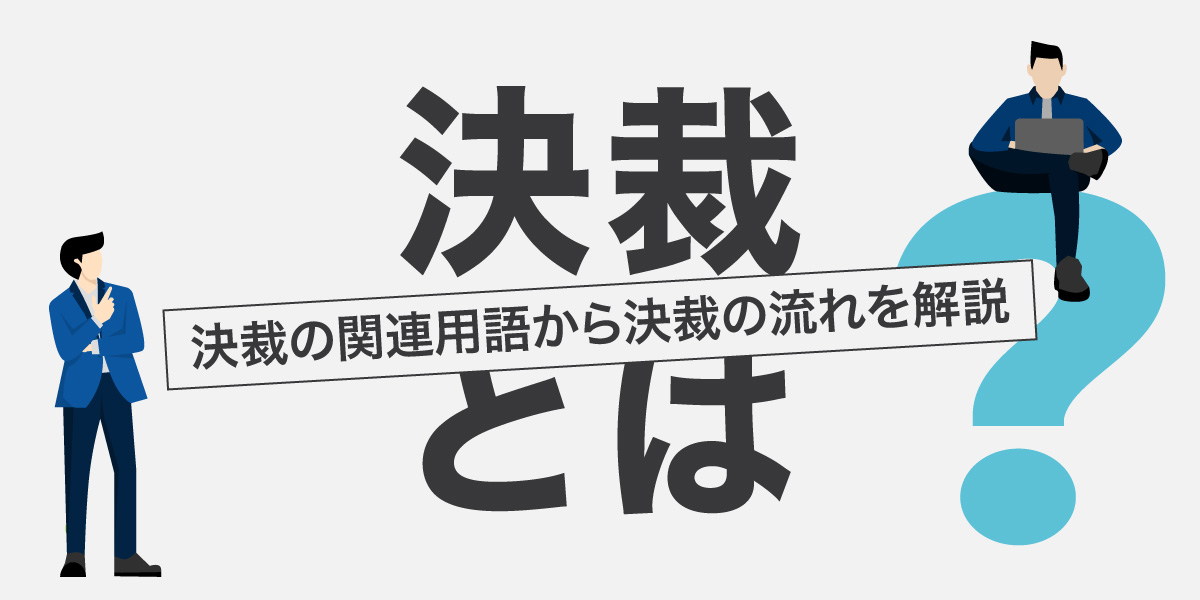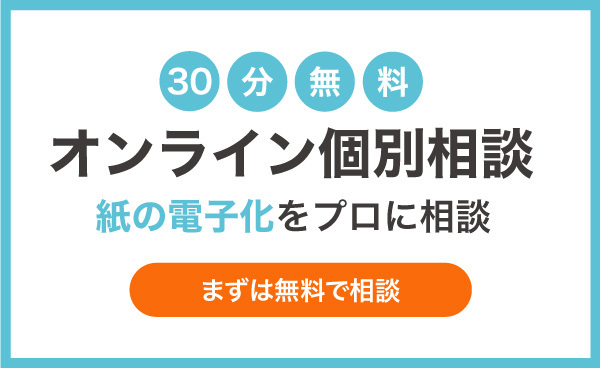この記事の目次
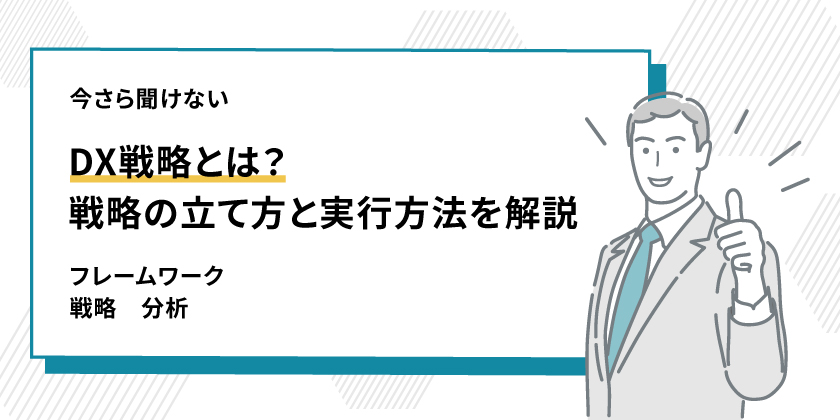
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、今や多くの企業にとって大きな関心事のひとつです。業務の効率化や新規ビジネスの開拓など、企業活動の多くの場面でデジタル技術の活用が進んでいます。一方で、急速に広まったDXという言葉・概念について、正確に理解できている人は少ないかもしれません。
効果的なDX戦略の遂行は、企業の生存・成長に直結します。そのためには、DXに対する正しい知識・深い理解が必要です。
この記事ではDX戦略について、その定義・予算目安・進め方のコツなど詳しく解説します。会社部門ごとに行うことのできるDX戦略事例についても取り上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。
DX戦略とは
近年「DX」という言葉や、それを活用した企業戦略である「DX戦略」について耳にする機会が増えています。
それらがどのようなものを意味するのか、その定義を確認しましょう。
ITを活用してビジネスをよりよくしていく計画や方法
「DX戦略」とは、DX(広義のデジタルトランスフォーメーション)を実現することにより、企業がビジネスモデルの展開・新たな価値の創造を実現していくための戦略を意味します。
企業はDX戦略によって、業務の効率化や経営戦略実行のスピードアップを目指します。
そもそもDXとは
そもそもDXとは、何を意味するのでしょうか。DX(ディーエックス)とは、「Digital Transformation」の略称で、デジタル技術を使って社会を変革し、より便利にする取り組みを意味します。
「トランスフォーメーション」を「X」と表記する理由には諸説ありますが、接頭辞「Trans-」を「X」と表記する習慣が英語圏にあることや「DT」と表記される略称がすでに存在していたことなどが主な理由とされています。
DX戦略の構築に必要な3つの要素
実際にDX戦略を構築するには、どのようなことが必要になるのでしょうか。大きく3つの要素に整理して、それぞれ見ていきましょう。
次の3段階をしっかりと踏むことが、効果的な戦略構築に欠かせません。
自社の現状把握
第一に、自社の現状を把握することです。
自社が抱えている問題点や改善すべき業務を検討し、業務の効率化が見込める部分を洗い出します。具体的には、各部門や部署の業務内容における慢性的な課題や、すぐに改善が可能な業務などを社内で調査をしましょう。
DXの目標設定
第二に、DXの目標を設定することです。
できるだけ具体的に、数値を用いた目標を設定することが重要です。
既存業務にデジタルを活用して経営課題を解決するだけではなく、デジタルだからこそ可能になる業務方法やビジネスを開拓することを視野に入れた目標設定が求められます。
DXの目標設定には、フレームワークの活用が効果的です。フレームワークについて、詳しくは後述します。
外部の環境変化を把握・分析
第三に、外部の環境変化を把握・分析することです。
同業他社や市場・顧客の動向など会社を取り巻く環境について、現状を把握・分析します。最たる例としてコロナ禍以降の社会変化が挙げられますが、それに限らず日々変化し続ける周辺環境に自社の業務内容が対応できているか検討しましょう。
どの業務が変化に対応できていて、どこができていないかの入念な確認が求められます。
DX戦略は着手状況によって3つの領域に分けられる
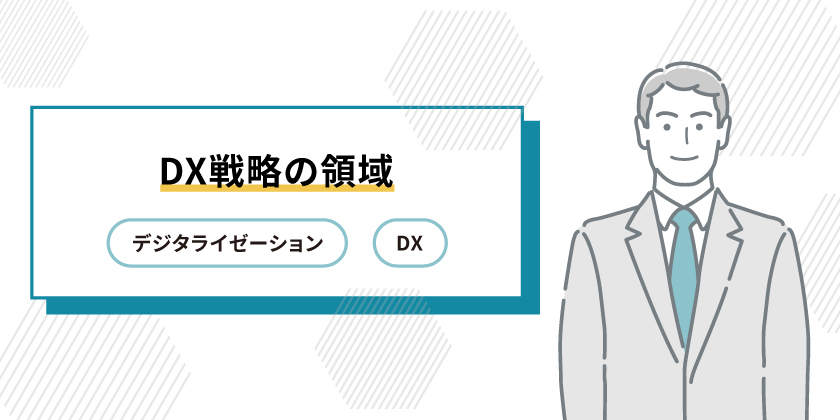
DX戦略は、ひとつの取り組みを指す概念ではありません。デジタル技術を活用し社内に変革を起こすDX戦略は、その変革の進行度合いによって次の3段階に分類されます。
①デジタイゼーション(Digitization)
②デジタライゼーション(Digitalization)
③(狭義の)デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)
この3つについて、語義や内容を詳細に見ていきましょう。
①デジタイゼーション
デジタイゼーション(Digitization)は、アナログ・物理データをデジタルデータに変換するプロセスです。
Digitize(計数化する)という動詞の名詞形で、非デジタルのデータをコンピューターが処理することのできるデータに変換することを意味します。具体的には、書類をスキャンして、PDFなどのデジタルファイルとして保存するのがデジタイゼーションです。
後2段階の前提となる工程で、まだ紙で管理している業務が多く残っているのであれば、ここから取り掛かる必要があります。
②デジタライゼーション
デジタライゼーション(Digitalization)は、業務プロセスをデジタル化することです。
語感としては①のデジタイゼーションと似ていますが、内容は全く異なります。デジタイゼーションがデジタル化の対象がアナログデータであるのに対し、デジタライゼーションは業務プロセスがその対象です。
この段階ではデータを利用して、ビジネスプロセスの効率化や高度化を図ります。自社のビジネスフローを最適化することで、組織の生産性を高めることがその目的です。
③(狭義の)デジタルトランスフォーメーション
(狭義の)デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)とは、ビジネスモデルまたは企業自体をデジタル化することを指します。②のデジタライゼーションの推進によるノウハウ蓄積の先に、デジタルトランスフォーメーションはあるのです。
この段階は、組織横断的な業務・製造プロセスのデジタル化や、ビジネスモデルの変革が目的となります。より広範囲で大規模な取り組みが行われるのが、この段階の特徴です。
DX戦略において活用できるフレームワークとは
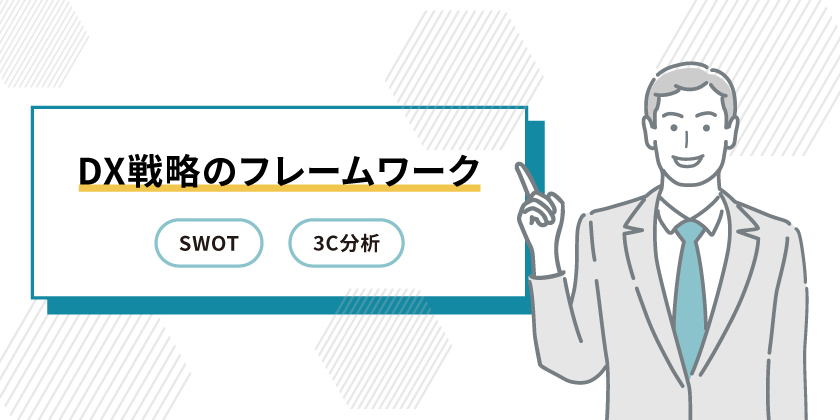
大規模な情報の集積・分析・運用が求められるのが、DX戦略構築・運用の特徴です。最良な計画、実践へとつなげるため、フレームワークの活用がおすすめです。
ここでは、DXで有用なフレームワークの具体例を紹介します。
DX戦略における分析方法(フレームワーク)
DX戦略に不可欠なのが、分析です。DXにおいてよく用いられる分析フレームワークには、次の3つがあります。
①SWOT分析
②PEST分析
③3C分析
それぞれについて、紹介します。
①SWOT(スウォット)分析
SWOT分析とは、企業の外部・内部環境についてプラス面・マイナス面を分析することで、企業の現状を正確に捉えようとするものです。
Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会・、Threat(脅威)の頭文字を取ってSWOTです。
社内外の要素を(外部・内部)×(プラス・マイナス)の組み合わせで、次の4セクションに分けて分析します。
●Strength(内部×プラス=強み)
●Weakness(内部×マイナス=弱み)
●Opportunity(外部×強み=機会)
●Threat(外部×マイナス=脅威)
②PEST(ペスト)分析
PEST(ペスト)分析とは、企業を取り巻く外部環境を分析するためのフレームワークです。
Politics(政治)・Economy(経済)・Society(社会)・Technology(技術)の頭文字を取ってPESTです。
4つの外部環境が、現在もしくは将来的にどのような影響を与えるかを把握・予測します。
③3C分析
3C分析とは、3つのCで表される観点から市場環境の分析を行い、マーケティングにおけるKSF(Key Success Factor =重要成功要因)の特定を目的とします。
Customer(顧客)・Competitor(競合他社)・Copany(自社)が、「3つのC」の観点です。
DXフレームワークを活用するコツ
DXフレームワークは、目標から逆算した具体的なプランの検討や取り組み事項の振り返りに活用できます。DXフレームワークは目標設定時だけではなく、DX戦略の取り組み状況を明確化する際にも有用です。
DX戦略の進行段階や、企業活動のどの分野でDXを行うのかなどに合わせて、最適なフレームワークを選択する必要があります。
DX化すべき業務例
具体的には、どのような業務がDXできるのでしょうか。
ここでは、具体的な業務として「製造業における製造プロセス」「社内のペーパーレス化」を取り上げ、それぞれにおけるDXの実例を紹介します。
社内の紙文化→デジタル化におけるDX例
【課題】
B社では、社会決済において紙文化が続いています。そのため会社の意思決定に必要以上の時間を要したり、社員にストレスがかかってしまったりなどの弊害が発生しています。
【DX戦略の取り組みイメージ】
①デジタイゼーション
社内承認業務(社内稟議・経費精算・申請書類・日報など)に関する書類を電子化するツールを導入する。
②デジタライゼーション
多様なシステムとの連携によるデータ化を進め、遠隔での対応も可能にする。
③デジタルトランスフォーメーション
デジタル技術・データを活用し、新たなサービスや付加価値の高い情報の提供を実現する。
製造業の製造プロセスにおけるDX例
【課題】
A社の製造部門は、次の課題に直面しています。
①装置を占有する作業時間を減少する・1ロット生産にかかる時間を短縮する
②職人ノウハウをデータ化することで、高付加価値な業務を不特定の従業員に任せられるようにする
【DX戦略の取り組みイメージ】
前述した「DX戦術の3段階分類」で、考えられるDX戦略を整理してみます。
①デジタイゼーション
製造装置を電子化する。集積した製造に関するデータをデジタル化する。
②デジタライゼーション
製造プロセスのソフトウェア化・システム構築を進める。
③(狭義の)デジタルトランスフォーメーション
製造各部門を横断したデジタルシステム構築による製造の自動化・遠隔化を実現する。
部門別のDX例
ここでは企業の部門別に、DXをどのように導入できるかを紹介します。
総務部のDX例
総務部におけるDXにはどのようなものがあるのか、業務の効率化に着目した例を紹介します。
【代表的なDX活用シーン】
●既存の承認フローやルーチンワークをペーパーレス化・電子化する。
●デジタルの活用によりコミュニケーションを円滑化する。
【総務部のDXで活用できるRPA・ワークフローシステム・電子契約】
●RPAは「Robotic Proess Automation」の略であり、ソフトウェア上のロボットを利用して、データ入力などの主に機械的業務を自動化するシステムのことである。
●ワークフローシステムとは、企業内での申請およびそれに対する承認・確認等の諸手続きを電子化するシステムのこと。ワークフローを最適化することで、組織全体の業務の効率化につながる。
●電子契約とは、デジタル形式で作成・締結される契約のこと。データ管理しやすい点や、契約書の締結までの流れをすべてオンライン上で完結させられる点がメリットである。
情シスのDX例
情報システム部門は、DXを推進する立場につくことが多い部門のひとつです。また、情シス部は情シス自身のDX・全社をあげたDXのどちらにも取り組みます。
ここでは、情シス部に求められる動きについて紹介しましょう。
情シス内部ではコミュニケーションツールを活用したやりとりの電子化により、コミュニケーションの円滑化を図ります。
社内全体においては、業務フローをDX可能なものに変更するよう先導したり、業務にあったツールを探したりすることで社内全体のDX化を進めます。
前述した各部門でのDXの推進を支える要としての役割が、情シス部には期待されるのです。
法務部のDX例
法務部で行われるDXにはどのようなものがあるか、見ていきます。
【代表的なDX活用シーン】
紙ベースの業務を電子化することにより、作業ボリュームを削減する。
煩雑になりやすい契約書管理を、デジタル管理に移行することで簡略化する。
他部門とのやり取りをクラウド化することで、誤送信リスクを低減する。
【総務部のDXで活用できる電子契約】
先ほど紹介した電子契約が、法務部で最も活用できるDX手法のひとつです。
営業部のDX例
営業部でのDX事例について、システムの内製化に着目した例を紹介します。
【代表的なDX活用シーン】
●手書きの報告資料を、フォーマット化された入力フォームによって作成する。
顧客・見込み顧客のデータを分析分析し、インサイドセールス(顧客と遠隔の手段でコミュニケーションをとる、内勤での営業)で活用する。
●オンラインでの販売システムを構築する。
【営業部のDXで活用できるCRM・SFA・MAの3つ】
●CRMは「Customer Relationship Management」の略であり、企業と顧客間の良好な関係の構築・維持するマーケティング手法のことを指す。
顧客情報・行動履歴・対顧客コミュニケーションを一元的に把握・管理し、既存顧客との関係維持につなげる。
●SFAは「Sales Force Automation」の略であり、営業支援システムのことを指す。
顧客・案件・名刺などの情報をデータ化し一元管理することで、営業実績に関する情報を蓄積・分析できる。
●MAは「Marketing Automation」の略であり、マーケティング活動の自動化ツールを指す。
見込み顧客へのコンタクトなど、新規顧客の開拓段階におけるマーケティング活動の自動化・効率化を行うためのツール。
企業がDX戦略に取り組むメリット
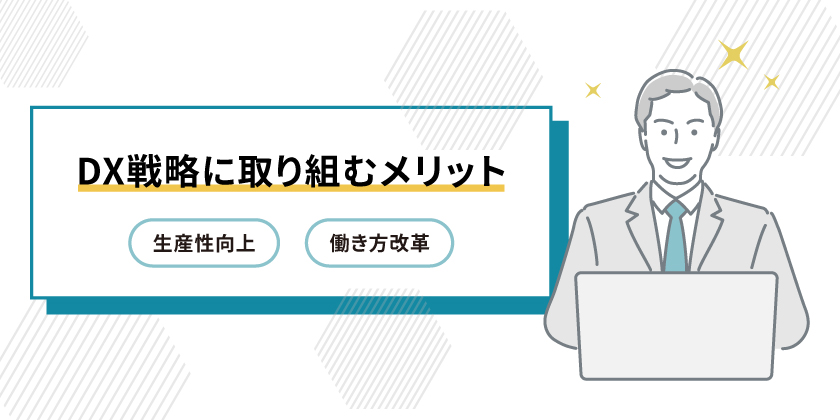
企業がDXに取り組むことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。なんとなくのイメージでDXを進めるのではなく、DXが会社に何をもたらすのかを意識して推進していくことが大切です。
生産性の向上
DX戦略の実施により、ビジネスプロセスをデジタル化できます。
単純作業については、人間ではなく機械で行う方が正確性・迅速性を担保できます。
また、人間が行う業務についてもデジタルを駆使することで、能率の向上・効果の最大化を図れるでしょう。
定型業務からマーケティングまで、幅広い業務の自動化・効率化が可能です。
データ収集の効率化
DXによる業務の自動化で、恩恵を最大に受ける業務のひとつがデータ収集です。
デジタルツールの導入により、手作業がなくなります。これはヒューマンエラーの排除と、情報の一元管理につながります。
データ収集・運用におけるDXの促進は、会社の業務全体でパフォーマンスを向上できる重要な鍵です。
働き方改革の促進
DXは、従業員の働き方にも良い影響をもたらします。
DX戦略の推進でオンラインでの労働のシステムが整えば、出社して仕事をすることは必須ではなくなります。書類作成、申請や承認などをネットワーク内で解決できるようになるのです。
オフィスへの出勤にとらわれない業務体系は、リモートワークの推進・外出先からの書類提出を可能にするなどのメリットがあります。社員に自由な働き方を提供するものであり、生活の質改善・幸福度の向上などにもつながるでしょう。
付加価値の高いビジネスモデルが創造
DXの本来の目的は、単なる業務効率の改善ではなく新規ビジネスモデルの創造にあります。
DX戦略の推進によりデジタルトランスフォーメーションが実現されれば、新たな商品・サービスの開発や顧客体験の創造につながります。また、既存の業務手法ではアプローチしえなかった顧客層にもリーチでき、自社の商品をより多くの人に届けられるようになるのです。
社内課題の解決
DXによって、テレワーク導入や書類のペーパーレス化、改正された法律への対応など、現代企業が抱える課題を解決できます。
デジタルツールの拡充は、テレワーク環境の整備には欠かせません。またDXによりデジタル情報管理システムが拡充されれば、ペーパーレス化が実現できます。改正法への対応も、社内の情報を一括で管理するシステムが整っていれば容易です。
情報の集約
DXは、社内の情報の集約システムに変革をもたらします。
日々の業務で得られる情報を一元管理することで、社内に業務に関する知識が蓄積されます。
業務活動で何よりも重要になる知識の継承・ナレッジマネジメントにおいても、DXのもたらす恩恵は計り知れません。
費用や時間などのコスト削減
DXは、費用や時間のコスト削減をもたらします。
ペーパーレス化による紙代の削減・不要なフローにかかっていた時間の削減・紙の資料を保存しておくための物理的スペースの削減など、さまざまなコストの削減が期待できます。
また、DXは「物」から離れた業務の在り方をもたらすため、資源の使用量削減にもつながるでしょう。
DX戦略の立て方
ここでは、実際にDXを進めていくフェーズに入っていきます。
DX戦略を実行に移していくための第1段階、戦略の立て方について解説します。
①ビジョンを策定(改変)する
DX戦略をスタートするには、ビジョンの策定と必要に応じたビジョンの改変が必要です。
DXが生み出す経済効果や新たな経済価値について、具体的にビジョンを描きましょう。ここで描くビジョンは、その後のDX実施における重要な指針になります。
②現状の把握と課題の抽出を行う
前述したDX推進指標とフレームワークを使用して、自社の現状・課題について整理します。どの項目でどの程度DXが進んでいるのか、目標値に対しての定量的達成度などを把握します。
この段階で大切なのが、DXについてのリテラシーです。
DXプロジェクトを成功させるには、DXに関するリテラシーを全社員が身につけておく必要があります。従業員のDXリテラシーの水準を事前に把握しておくことで、より自社にあったDX戦略の実施ができます。
③DX戦略を推進する体制を整える
DX戦略を推進するためには、まずその体制づくりから始めなければなりません。
体制づくりとしては、DX推進のチームや部署を組織内部に設置することが理想です。
しかし多くの業界で人手不足が叫ばれる今、ノウハウを持った人材を社内で確保し専門チーム・部署を結成するのは難しいことでしょう。
人員確保が難しい場合は、アウトソーシングがおすすめです。外部人材や外部システムの導入により人手不足の対応やイニシャルコストの低減などが期待できます。
アウトソーシングを導入する際には、かかる費用をしっかりと見積もることが必要です。アウトソーシングを請け負う企業に資料請求・問い合わせを行い、入念に検討しましょう。
この段階で大切なのが、DXについてのリテラシーです。
DXプロジェクトを成功させるには、DXに関するリテラシーを全社員が身につけておく必要があります。従業員のDXリテラシーの水準を事前に把握しておくことで、より自社にあったDX戦略の実施ができます。
③DX戦略を推進する体制を整える
DX戦略を推進するためには、まずその体制づくりから始めなければなりません。
体制づくりとしては、DX推進のチームや部署を組織内部に設置することが理想です。
しかし多くの業界で人手不足が叫ばれる今、ノウハウを持った人材を社内で確保し専門チーム・部署を結成するのは難しいことでしょう。
人員確保が難しい場合は、アウトソーシングがおすすめです。外部人材や外部システムの導入により人手不足の対応やイニシャルコストの低減などが期待できます。
アウトソーシングを導入する際には、かかる費用をしっかりと見積もることが必要です。アウトソーシングを請け負う企業に資料請求・問い合わせを行い、入念に検討しましょう。
④戦略の実行と改善を繰り返す
戦略の実行とフィードバック・改善を繰り返すことが、DXの実現には欠かせません。
まず、社内で対案されたDX戦略について、最適なツール・フレームワークを導入して実行に移します。次に、期間を決めて計測を行い、戦略によってどのように業務内容が改善されているか、また新しいビジネスモデルが確立できているか、効果を確認します。
改善が必要と判明した内容についてはその都度、修正対応を行いましょう。
DXフレームワークの項目
DX化を戦略的に進める上では、前述のようにいくつかに分けてDX戦略を立てることが重要です。
ビジョン策定時や現状課題の把握・抽出時のような、自社や外部環境、顧客に関する調査が必要な場合には、既存のビジネスフレームワークの利用が効果的です。
以下は、DX戦略を成功させるために利用できるフレームワークの例です。
●SWOT分析
自社の強みや弱み、機会や脅威を評価するためのフレームワーク。脅威に対して弱みをどのようにカバーするかや、どのような強みを活かして機会獲得につなげるかを分析する手法
●PEST分析
政治や経済、社会や技術のトレンドや動向を書き出し、自社に影響を与える可能性がある内容について特定するという手法
●3C分析
顧客、競合他社、自社の3つの視点から、業界のトレンドと自社の置かれている立ち位置を分析する手法
●SMARTの法則
具体性・計測可能性・達成可能性・関連性・期限の明確性の5つの要素から、自社の打ち立てた目標について分析する手法
このほか、現在は公開が停止されておりますが、経済産業省のWebページに掲載されていた「DXレポート2」というPDFファイルでは、分野ごとの進捗段階に分けて示したDXフレームワークが公開されていました。
自社の現状のサービスについて、以下の表を使って整理することも、自社の置かれた状況や優先して着手すべき内容を洗い出すために役立つでしょう。
| 分野/進捗段階 | 未着手 | デジタイゼーション | デジタライゼーション | デジタルトランスフォーメーション |
| ビジネスモデル | ||||
| 製品/サービス | ||||
| 業務内容 | ||||
| プラットフォーム |
DX戦略にかかる予算の目安
DXにどれほどの予算がかかるかは、なかなか想像しにくい部分です。
ここでは予算の目安をはじめ、その作成・運用に関して簡単に解説します。
予算の目安はDX戦略の段階によって異なる
予算の目安は、DX戦略の段階によってそれぞれ異なります。
第1段階のデジタイゼーションにかける予算の目安は、50万〜200万円程度です。
第2段階のデジタライゼーションにおける予算の目安は、100万〜3,000万円程度といわれています。
第3段階のデジタルトランスフォーメーションの予算は、1,000万~1億円程度になることもあります。
費用対効果を考えて予算を作成する
予算の作成においては、費用対効果を考慮に入れることが必要です。費用対効果とは、かけた費用に対して得られる利益や効果がどの程度かを示す指標です。費用対効果=(利益または効果)−(費用)という式で表せます。
費用対効果を可視化するためには、収益の増加・生産性の向上・コスト削減・顧客満足度の向上などを数値化し、定量的に評価することが必要です。ここでいう「費用」には、開発費用・導入費用・運用費用・人件費などの項目が含まれます。
DX戦略を実現するための予算を確保する方法
次に、DX戦略を実現するための予算を確保します。
新規に予算を調達する主な方法は、主に次の2つです。
①既存事業の利益を充てる
②外部から資金を集める
そのほかにも現在の予算配分を変えたり、既存システムの廃止を行ったりすることで予算を確保できます。
DX戦略を成功させるポイント
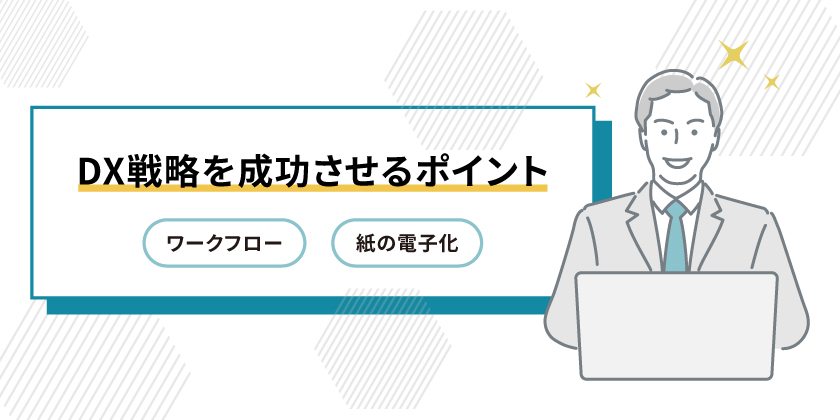
多くのお金と労力を要するDX戦略は、やみくもに取り組んでも成功しません。
ここでは、DXを成功に導く6つのポイントを紹介します。
1. 課題とゴールを明確にする
何よりも大切なのが、DXで解決したい課題と達成したいゴールを明確にすることです。
課題があやふやなままでは、有効な方策を立案することも社内の協力を得ることもできません。またゴールを明確にしなければ、手段であるはずのデジタルツールの導入自体が目的と化してしまうおそれがあります。
2. 担当者を中心に会社全体で取り組む
次に、担当者を中心にしながら会社全体で取り組むことです。スピーディーかつ効果的にDXを進めるためには、組織全体での取り組みが必要です。
会社の風土から改革する意識で、DXに取り組みましょう。特に、的確な意思決定を迅速に行える体制を整えることを目的とした施策が求められます。
何よりも大切なのが、DXで解決したい課題と達成したいゴールを明確にすることです。
課題があやふやなままでは、有効な方策を立案することも社内の協力を得ることもできません。またゴールを明確にしなければ、手段であるはずのデジタルツールの導入自体が目的と化してしまうおそれがあります。
3. 段階的に進行し、試行錯誤しながら進める
どのようなDX戦略をとるにしても、その成果は一朝一夕に現れるものではありません。日々改善を重ねながら継続的に行うことで、ようやく成果が形として表れるものです。
一度ツールやシステムを導入したからといって、それで完結はしません。また、会社の状況に合わせて段階的に導入するなど、画一的ではない臨機応変な対応をとるとよいでしょう。
長期的視座に立った戦略の推進・改善を行うことで、新たなビジネスモデルや価値の確立などのデジタルトランスフォーメーションにつながります。
4. 情報やノウハウを蓄積して、誰でも使える状態にする
今まで培ってきた情報やノウハウは、個人や部門ごとに独占せず一元管理して社内の誰もが活用できる状態にしましょう。
情報やノウハウが孤立している状態では、新たなアイデアの創出につながりません。それらを一元管理し誰もがリーチできる状態にして初めて、新たなアイデアが生まれ実現するのです。
5. DX戦略を進めた成果を評価する
DX戦略を進める際には、各過程ごとに成果の評価が必要です。
戦略策定における目標をどれだけ達成できたか、顧客にどれだけの価値が提供できたかを定量的に評価できる数値目標を設置しましょう。週次、月次など短期間での評価と、長期的な評価の併用が効果的です。
成果の評価には、報告しやすい雰囲気づくり・失敗しても柔軟に対応できる社内体制づくりが大切です。
6. ユーザーの意見を取り入れる
企業活動では、顧客体験の向上は市場での企業評価につながります。
自社が進めるDXが、顧客にとって価値のあるものであるのかという視点をしっかりと持つようにしましょう。そのためには、自社がユーザーからどのようなものを求められているのかを把握することが必要です。
ユーザー対応の速さが魅力なのか、丁寧な仕事が魅力なのか、ユーザー視点での自社の魅力を把握したうえでその魅力を強化し、足りない部分は改善するDX施策を実施します。
自己分析には限界があるため、顧客や顧客候補に自社の魅力を問うためのアンケートを取るのもよいでしょう。
DX戦略を進めるなら、紙の電子化がおすすめ
DXにおいて、電子化は重要な第一歩です。
ここで紹介したいのが「ワークフローシステム」です。
ワークフローシステムとは、業務の流れを自動化するためのシステムを指します。業務の流れを人間の手だけで管理しようとすると、申請書探しなど作業に手間がかかってしまいます。
ワークフローシステムを導入することで、時間がかかる申請業務のスピードを上げて効率化が可能です。ペーパーレス化・内部統制の強化・柔軟な働き方への対応、さらにはDXの推進につながります。
まとめ
この記事では、DX戦略についてその定義・予算目安・進め方のコツなどを詳しく見てきました。
DXの第3段階であるデジタルトランスフォーメーションを、すべての企業が実現することは困難かもしれません。しかし、その第1段階であるデジタイゼーションや第2段階のデジタライゼーションは、日々の細かな業務に変化を加えていくことで少しずつ達成していけるものです。
DX戦略の実践は難易度が高く、不明確な目的のもと効率化と関連が薄い施作に取り組む事態に陥るケースもあります。DX戦略の先に何を目指すのかという明晰なビジョン、戦略の到達度を測る定量的な基準をしっかりと持ち、トライアンドエラーを繰り返しながら進めていくことが大切です。