2025年最新版|おすすめワークフローシステムとは? ~ワークフローの選び方~
2025年最新版|おすすめワークフローシステムとは? ~ワークフローの選び方~
この記事の目次
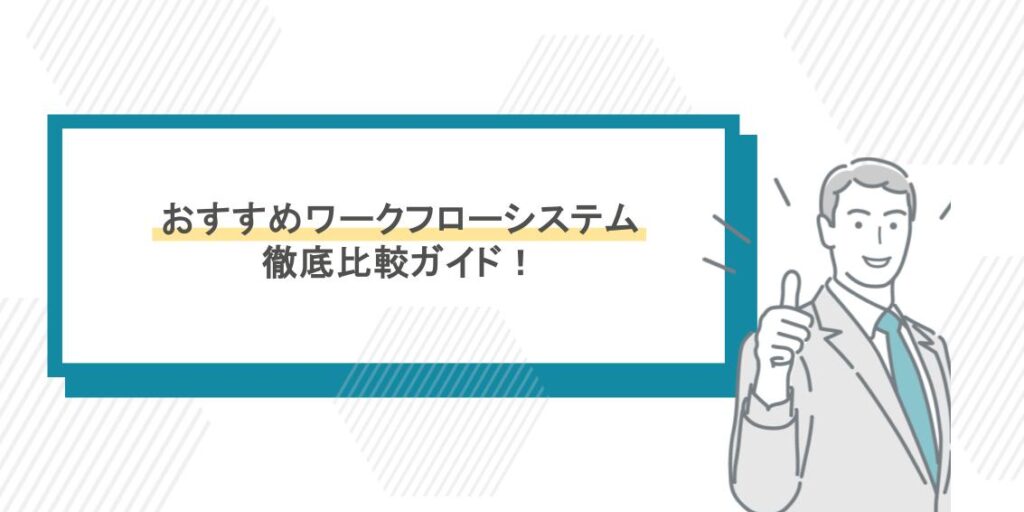
ワークフローシステムは、企業内で行われる各種申請や承認フローをデジタル化し、業務全体の効率化に大きく貢献するソリューションとして近年注目を集めています。紙の稟議書や申請書に頼らずにプロセスが進行し、情報共有や管理が容易になるのが最大のメリットです。
システム上で申請や承認を行うことで、どこからでも即座に対応できるため、テレワーク時や外出先でもスムーズに意思決定が進められます。さらに、承認履歴やドキュメントを一元管理できるので、不正防止や監査対応にも有効です。
この記事では、ワークフローシステムの概要や機能、導入メリットに加え、タイプ別の特徴や料金相場を詳しく解説します。さらに、実際に人気のシステムを比較し、導入を検討する際の選び方やポイントも網羅的に紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
ワークフローシステムとは
まずはワークフローの定義やシステム化する意義、注目背景を押さえ、導入の重要性を理解しましょう。
ワークフローシステムの導入は、ただ業務をデジタル化するだけにとどまりません。承認プロセスの見える化や、問い合わせ先の明確化によって部門間の連携がスムーズになる効果も期待されます。結果として、属人的になりやすい社内のやり取りが整理され、業務標準化や業務リスクの軽減につながることが大きな特徴です。
最近では、新型コロナウイルス感染症をきっかけにリモートワークが定着し、オンラインでの申請・承認環境がますます重要視されています。紙媒体やハンコに頼った従来の方法では、出社しなければ手続きが進まず、業務が滞ってしまうケースが多く見られます。そこで、ワークフローシステムを導入することで、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現する土台が整うのです。
また、システム上で各フローの履歴を残すことで、コンプライアンス面への対応も強化できます。監査対応時には、これまでの申請記録や承認情報を簡単に抽出できるため、調査時間の短縮や正確性の向上に寄与します。こうした点からも、DX推進や業務の高度化において、ワークフローシステムは欠かせない存在となっています。
ワークフローの定義
ワークフローとは、企業内で行われる申請や承認、あるいはタスク依頼から実行までの一連の流れを指します。経費精算や稟議決裁など、多くの部門を横断するフローも含まれます。
こうした一連の手続きを可視化することで、誰がどの段階で対応すべきかが明確になり、業務トラブルの回避に役立ちます。あわせて、業務手続きを統一化することで、ミスや重複作業の発生を防止する効果も得られます。
近年は企業のコンプライアンス意識が高まり、承認経路の監査と記録管理を徹底する必要性も増しています。ワークフローの定義をはっきりさせ、その流れをデジタル化することが、リスク管理と効率化の両面で大きく寄与すると言えます。
ワークフローシステムの概要
ワークフローシステムは、上記のワークフローを電子化・標準化する仕組みを提供します。申請書の作成から承認、最終的な決裁までをすべてシステム上で完結させることで、業務の抜け漏れや二重入力を制御し、不正に対する抑止力も高めます。
また、電子化により申請書の提出ステータスや誰が承認待ちなのかをリアルタイムでモニタリングできるので、状況が一目で把握できます。管理者としては、稟議や承認作業の停滞を早期に発見し、対応を促すことが容易になるでしょう。
このように、ワークフローシステムは業務プロセスの透明性とスピードを高めるだけでなく、内部統制や監査業務の効率化にも大きく貢献します。
ワークフローシステムが注目される背景
ワークフローシステムが脚光を浴びる大きな理由として、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進とリモートワークの普及が挙げられます。紙とハンコが中心の文化では、在宅勤務や出張時に承認が滞りがちで、業務速度が落ちてしまいます。
システム導入によって、出社しなくても手続きが進む環境を整えれば、重要な意思決定のスピードアップや意思疎通の変革が実現可能です。導入企業が増えたことで、多様なサービスやタイプも登場し、さらに利便性が高まっています。
また、社会的にはペーパーレス化やコスト削減のニーズが強まっており、ワークフローシステムの活用は環境負荷削減や省スペース化といった観点でも有効な手段として評価が高まっています。
ワークフローシステムの主な機能
ワークフローシステムには申請・承認をはじめ様々な機能があります。代表的な機能を理解し、自社に必要なものを検討してみましょう。
システム導入の際には、どのような機能が備わっているかをしっかり確認することが重要です。承認フローの自動化だけでなく、ドキュメント管理や通知機能、外部サービスとの連携など、多岐にわたります。
自社で今後どのような業務効率化を目指すのかを考え、その目標に合致する機能に優先的に注目するとよいでしょう。また、操作のしやすさや既存システムとの統合性も長期的な運用性を左右するため、詳細を比較検討する必要があります。
ここでは、一般的なワークフローシステムが備える主要機能を紹介しますので、導入前のリストアップや要件定義の参考にしてみてください。
申請・承認機能
ワークフローシステムの基本は申請と承認をオンラインで完結させることにあります。紙の書類を回す手間が省けるだけでなく、申し送りミスや文書紛失を防ぐ効果も期待できます。
また、誰が承認すべきかをシステム側で自動的に割り当てる仕組みもあり、担当者の設定ミスを最小限に抑えられるのが利点です。承認依頼が届けば通知されるため、タイムリーな対応が可能になるでしょう。
この機能を活用すれば、全社規模で申請や承認プロセスを一元化し、業務スピードと正確性を飛躍的に向上させることができます。
フロー定義機能
部署や役職ごとに異なる承認ルートを柔軟に定義できるのも大きな特徴です。事前に組織図を反映した経路を設定しておけば、申請時に自動でルートが選択されるため、複雑な稟議もスムーズに進められます。
プロジェクトごとに特別な承認者を追加するなど、必要に応じてフローを細かく調整できるシステムも増えています。これにより、企業規模や業種を問わず、多様なニーズに対応可能です。
ただし、あまりにも細かすぎる承認ルートを設定すると、管理が煩雑になる場合があるため、運用ポリシーづくりが大切になります。
自動通知・リマインド機能
申請や承認依頼が発生した際に、自動でメールやプッシュ通知を送ることで、担当者が見落とすリスクを減らす機能です。
締め切りが近い場合や未処理の案件が多くなった場合にはリマインドを出すことで、作業の抜け漏れを防水堤のように食い止める効果があります。
この機能が充実していると、承認待ちが原因で業務が滞るリスクを最小限に抑えられます。忙しい現場では必須の機能と言えるでしょう。
ドキュメント管理機能
ワークフローでやり取りする申請書や稟議書、添付ファイルなどを一元管理できる機能です。書類ごとにファイルサーバを探し回らなくて済むので、管理コストの削減に直結します。
また、検索機能が充実しているシステムでは、過去の承認書類を素早く見つけ出すことが可能です。監査時には、アーカイブとして提出資料をまとめる際にも役立ちます。
バージョン管理に対応したシステムならば、修正履歴を追跡し、いつ、誰が、どの項目を変更したのかを簡単に把握することもできます。
外部システムとの連携機能
ワークフローシステムを有効に活用するには、他の基幹システムやクラウドサービスとシームレスに連携できるかが鍵となります。代表的には会計システムやERP、人事管理システムとのデータ連携が挙げられます。
たとえば経費精算の申請が承認されると、自動的に会計システムへ仕訳データが送られるなど、二重入力の手間が省け、業務効率が高まります。
APIを利用したカスタマイズ性が高いシステムも多く登場しており、社内の開発リソースや要望に応じて拡張性をもたせることも可能です。
スマホ対応・モバイルアクセス
外出が多い社員やリモートワークを積極的に行う企業では、スマホやタブレットから申請や承認ができる機能が求められます。
PCを立ち上げなくても手続きが可能となり、会議や出張の合間でもすぐに対応できるため、フローが停滞しにくくなる効果があります。
企業のデバイス管理ポリシーにもよりますが、アプリケーションによってはオフラインで作成し、ネット接続後に送信するといった機能を備えているケースもあります。
承認状況の可視化・レポート機能
どの申請が今どの段階にあるかを一覧で確認できるだけでなく、各承認者の対応速度やフローのボトルネックもレポート化して示すシステムがあります。
経営陣が判断を下す際の情報源として利用できるほか、業務改善の材料として組織全体のフローを見直す際にも非常に有用です。
リアルタイムの進捗把握に加え、過去のデータを分析することで、季節的または部門的に繁忙期に偏りがあるかなど、多角的にモニタリングが可能になります。
ワークフローシステムを導入するメリット
導入を通じて得られる代表的なメリットを整理し、自社の課題解決や業務効率化へのヒントを得ましょう。
ワークフローシステムを導入することで、迅速な意思決定やコスト削減といった即効性のある恩恵を受けられます。さらに、ペーパーレス化によってオフィス環境の改善やセキュリティ強化にも寄与するなど、企業にとってさまざまな切り口のメリットが存在します。
特に、多拠点展開や海外拠点を持つ企業にとって、電子化された承認フローはかなりの時短効果を生み出します。連絡のやり取りがメールベースからシステム化されることで、情報の散逸を防ぎつつ、業務を可視化できる点は重要です。
ここからは代表的なメリットを5つに分けて解説するので、自社の抱える課題や改善したいポイントと照らし合わせながら検討してみてください。
1. 申請・承認スピードが向上する
ワークフローシステムを導入すると、申請者から承認者への連絡がタイムリーに行われます。紙の持ち回りや対面でのやり取りが不要になるため、フロー全体の時間短縮が期待できるでしょう。
さらに、承認者が複数いる場合でも、システム上で同時並行に承認依頼を送る設計が可能です。こうした機能を活用すれば、日前に提出しても承認が滞るといった現象を最小限に抑えることができます。
結果として、経営層やプロジェクトメンバーが必要とする決裁が早まり、ビジネスチャンスを逃さずに済むだけでなく、社内での意思決定スピードそのものが飛躍的に高まります。
2. エラー・抜け漏れの削減
システム化された場面では、入力必須項目を設定できたり、フォームに自動チェック機能があったりと、人為的ミスの発生を抑制する仕組みが充実しています。
たとえば、数値の合計値や日付の整合性など、手作業では見落としがちな部分をシステムが補助してくれるため、作業負荷も低減します。
間違った書類が承認まで通ってしまうというリスクも抑えられるため、監査上の信頼性や承認プロセス全体の正確性が向上するメリットがあります。
3. ペーパーレス化でコスト削減
紙の申請書や稟議書の印刷、郵送、保管といったコストは、長期的に見ると無視できない金額になります。ワークフローシステムを導入することで、それらのコスト削減と環境負荷の軽減を同時に実現できるのです。
また、紙書類を物理的に保管する場合には、書庫スペースの確保や資料の紛失リスクなども考慮しなければなりません。電子化すれば、スペースだけでなくセキュリティ強化の面でも大いにメリットがあります。
必要に応じて電子データを印刷することも可能であり、物理資料が完全に不要になるわけではありませんが、それでも大幅な削減効果を期待できます。
4. 内部統制と監査対策の強化
承認の履歴が詳細に記録され、誰がいつ、どのような判断をしたのかが明確になります。これは内部統制の観点からも極めて重要です。
不正な申請や不正承認があった場合でも、データを遡って特定のプロセスにおける不適切な行為を洗い出すことができます。
さらに、監査部門や外部監査人からの問い合わせに対して、迅速に参照データを提示できるため、監査作業の効率向上や企業の信頼性向上につながります。
5. リモートワークとの相性が良い
場所を問わずにシステムへアクセスできることは、リモートワーク下での業務継続に直結します。特に、急な外出や在宅勤務など柔軟な働き方をしているメンバーが多い場合、オンラインで承認作業が完結するワークフローは必須と言えるでしょう。
申請書がデスクに置き去りにされるような状況がないため、承認待ちのストレスやプロセスの滞留を大幅に減らすことができます。
リモートワークを積極的に取り入れる企業にとって、ワークフローシステムの導入は生産性維持と労働環境の改善を同時に叶える重要な一手です。
ワークフローシステムの主なタイプ
ワークフローシステムにはさまざまなタイプが存在し、導入企業の規模や用途によって適した選択肢は異なります。各タイプの特徴を把握しましょう。
自社の規模感や運用ポリシー、さらには既存システムとの連携など、ワークフローシステムを選ぶ上で考慮すべき要素は多岐にわたります。たとえば、大企業では複雑な承認経路と強度の高いセキュリティが望まれ、中小企業では手頃な価格とシンプルな操作性が求められるでしょう。
また、グループウェアと一体になったタイプや、Excelーフォーマットと連携しやすいものなど、企業のワークスタイルに応じて最適な機能構成は異なります。まずは主要なタイプを知り、自社の利用シーンを想定しながら検討を進めることが大切です。
以下では、代表的なシステムタイプと特徴について解説します。自社の環境に合った導入形態を選択するための比較材料としてご活用ください。
大企業向けワークフローシステム
大規模組織向けシステムは、多くの場合で高度な承認経路設定と強固なセキュリティ対策が求められます。複数部署や海外拠点を含むようなグローバル展開を想定した設計がなされており、マルチ言語や時差を踏まえたフロー設計もカバーする場合があります。
大企業では監査要求や内部統制チェックの頻度が高いため、運用履歴やログ管理が非常に重要です。そのため、システム自体に詳細なアクセス権限設定や改ざん防止機能が備わっているのが一般的です。
初期導入コストは高めに設定される場合が多いものの、長期的な運用の安定性や拡張性が期待できる点がメリットです。
中小企業向けワークフローシステム
中小企業向けのワークフローシステムは、導入や運用のハードルを下げるため、シンプルなUIが採用されていることが多いです。複雑な機能よりも、必要最低限のフロー定義や通知機能などに特化している場合があります。
価格面ではリーズナブルな月額制を導入しているケースが多く、初期費用を抑えながらも基本的な承認ワークフローを使い始められます。特に、クラウド型を選べばサーバー管理などを外部に任せられるため負担が少ないです。
迅速な導入や運用開始を優先したい企業にとっては、手軽さと高いコストパフォーマンスを両立できる中小企業向けパッケージが魅力的な選択肢となるでしょう。
Excelフォーム型ワークフローシステム
既存のExcel文書を流用し、ワークフローを構築できるタイプです。Excelに慣れ親しんだ社員が多い場合、移行期の学習コストを最小限に抑えられるメリットがあります。
セルや関数を活用して必要な申請フォーマットを作成できるので、カスタマイズ性も高いといえるでしょう。特別なプログラミングスキルがなくても現場レベルで柔軟に対応できます。
ただし、データの整合性管理や多人数で同時編集するケースにおいては慎重な運用設計が必要です。クラウド連携やアクセス管理が充実していないと、データ衝突やバージョン違いが発生するリスクがある点に注意しましょう。
グループウェア一体型ワークフローシステム
スケジュール管理やチャット機能、メールなどと一体化したグループウェア製品にワークフロー機能が組み込まれたタイプです。一度の導入で幅広いコミュニケーション手段をまとめて電子化できるのが特徴です。
既にグループウェアを利用している企業であれば、追加ライセンスを取得するだけでワークフローも使えるケースが多く、シームレスな連携が期待できます。
多機能ゆえに操作方法を覚えるハードルは多少上がる可能性がありますが、使いこなせば社内コミュニケーションと承認フローの一本化ができ、利便性は非常に高くなります。
バックオフィス業務一体型ワークフローシステム
経費精算などの関連業務と合わせて利用できる統合型システムです。経理や総務などのバックオフィス部門が主に利用する機能と承認フローが直結しているため、情報連携に強みを持ちます。
たとえば、経費精算の申請から会計処理までが同じプラットフォームで完結するので、データ入力や二重管理の手間を大幅に削減できます。
全社的な業務効率化を狙う企業や、特にバックオフィスの負担が大きい企業にとっては、導入効果が非常に高いシステムタイプと言えるでしょう。
クラウド型とオンプレミス型の違い
クラウド型は、サーバーなどのインフラを自社で用意せず、外部サービスとしてワークフローを利用する形態です。初期導入費用を抑えられるほか、常に最新バージョンを利用できる利点があります。一方、セキュリティ要件の厳しい企業にとっては懸念が残る場合もあります。
オンプレミス型は、自社サーバー内にシステムを構築するため、カスタマイズやセキュリティ施策を自由に施せるメリットがあります。ただし、導入コストや運用管理の手間が大きくなる傾向があります。
企業の規模や業種、セキュリティ要件などによって最適な導入形態は異なるため、双方の特徴を踏まえたうえで比較検討しましょう。
ワークフローシステムの料金相場
価格体系はクラウド型・オンプレミス型・無料プランなど多岐にわたるため、各社の見積もり比較が重要です。
ワークフローシステムを導入するにあたり、もっとも気になるのが導入コストではないでしょうか。料金形態は提供形態や機能範囲によって大きく異なるため、単純な比較は難しい部分があります。
一方で、システム導入による効果を鑑みれば、人件費や印刷コストの削減などで十分にペイできる事例も多数存在します。ですから、導入時は初期費用だけでなく、運用・保守にかかるコストやシステム導入で得られるROIを総合的に判断することが肝要です。
ここではクラウド型とオンプレミス型、それぞれの一般的な料金や無料プラン・オプション費用に関して押さえておきたいポイントを解説します。
クラウド型の料金相場
クラウド型では月額課金制が主流となっており、ユーザー数や利用する機能数に応じて料金が変動するケースが多いです。必要に応じてライセンスを追加・削除しやすいのもメリットでしょう。
また、クラウドサービスならではのスピーディな導入が可能で、システム管理リソースが限られた企業でも手軽に利用を開始できます。サーバー管理やバージョンアップ作業が不要なのも大きな利点です。
ただし、契約を継続するかぎり課金が発生するため、長期的に利用する場合はオンプレミスと比較してコスト差がどうなるかを試算しておく必要があります。
オンプレミス型の料金相場
オンプレミス型は、ライセンス費用やサーバー購入費、導入コンサルティング費などが初期投資として発生します。導入後もバージョンアップやメンテナンスを自社で行うケースが多く、保守費用も考慮が必要です。
大規模組織の場合、長期的には月額課金のクラウドよりも安価に済む可能性があります。特にカスタマイズ性を重視する企業や機密情報を完全に社内に留めたい企業に向いていると言えます。
導入には専門知識を持つIT担当者やベンダーのサポートが必要になるため、プロジェクト管理体制を整えたうえで検討することが望ましいでしょう。
無料プランの有無
一部のベンダーでは、ユーザー数や利用可能機能を制限した無料プランを用意している場合があります。たとえば、少人数の試験運用向けに一定の範囲内で無料提供を実施しているケースです。
無料プランはスモールスタートを希望する企業にとってリスクが低く、まずは操作感や機能を試してみたいというニーズに応えられます。
ただし、無料プランを利用できるユーザー数が限定されることも多いため、本格導入の前には有料プランへの切り替えタイミングや費用感を必ず確認しておきましょう。
オプション費用やカスタマイズ費用に注意
標準機能ではカバーしきれない部分を追加開発する際に、カスタマイズ費用が別途必要になるケースがあります。連携APIの開発や独自の承認画面設計など、要件に合わせた見積もりが必要です。
また、サポート体制を強化するオプションを別途契約する場合もあるため、導入当初の想定を超えた出費が発生しないように慎重に確認しておきましょう。
運用開始後に機能不足が判明してから追加コストがかかるより、導入前に要件定義を丁寧に行い、必要な機能とコストを把握しておくことが賢明です。
ワークフローシステムの選び方・比較ポイント
導入製品を選ぶ際は価格や機能性だけでなく、セキュリティ対策やサポート体制も重視する必要があります。実際の口コミも参考に検討を進めましょう。
システム選定では、単に価格や機能だけで決めるのではなく、セキュリティや拡張性、ユーザビリティなど、長期的な視点から見て企業ニーズを満たせるかが大切です。たとえば、業界特有の規約や法規制に対しても対応力が求められる場合があります。
社内担当者だけで判断がつかない場合は、ベンダーが提供するデモや無料トライアルを活用するのも有効な手段です。操作画面の使いやすさや導入後のサポートがしっかりしているかをチェックしましょう。
ここからは、口コミや評価も含めた比較ポイントを7つに整理します。機能表だけでなく、実際に導入した企業の声を参考にすることで失敗リスクを減らすことができます。
ワークフローシステムの実際の口コミや評価
口コミやレビューサイトでは、実際の利用者が感じた利便性や課題などが率直に共有されていることが多いです。特に、導入後にどのようなサポートを受けられたか、想定外の課題は起きなかったか、などのリアルな声は非常に参考になります。
ただし、中には宣伝目的の情報を含むものもありますので、複数の情報源をクロスチェックすることが重要です。文脈や企業規模が大きく異なる口コミは必ずしも自社に当てはまらない場合があります。
自社と条件の近いケーススタディや、同業他社の事例などに注目して、実際の運用感をイメージすることが失敗を避けるコツと言えるでしょう。
1. 自社規模や業種への適合
大企業には複雑な承認フローや多言語対応が必須となる場合がありますが、中小企業ではそこまでの機能を必要としないこともあります。業種固有の帳票が多い場合は、そのフォーマットに柔軟に対応できるかが選定の鍵です。
たとえば製造業や医療機関など、規制が厳しい業界ではセキュリティ要件やデータ保持期間の設定が厳格になることもあります。ベンダーにあらかじめ相談し、標準機能で対応可能かを確認しましょう。
自社の業務フローを正しく把握していないと、導入後にギャップが生じるリスクが高まります。最初に現行の承認フローを整理してからシステム選定を行うと、よりスムーズに導入を進められます。
2. 必要な機能要件の洗い出し
システムに求める機能をあらかじめリストアップし、優先度を付ける作業は欠かせません。たとえば、外部SYS連携や電子印鑑、検索性、レポート機能などは企業ごとに重要度が異なります。
不要な機能が多すぎるシステムを選ぶと、かえって導入コストが嵩むだけでなく、ユーザーが使いこなせずに混乱する可能性があります。
基本機能を押さえたうえで、自社に本当に必要なオプションやカスタマイズが何かを明確化することが、失敗のリスクを下げる第一歩です。
3. 操作性やユーザビリティ
申請や承認のオペレーションが煩雑だと、システム導入によるメリットが半減してしまいます。画面が分かりづらかったり、クリック数が多すぎるUIだと、ユーザー定着率に悪影響を与えます。
可能であれば、導入前に実機デモやトライアルを行い、日常的な使用感を試してみるのがおすすめです。ユーザーインターフェースがシンプルで分かりやすいか、動作が軽快かなどを確認しましょう。
利用者が増えるほど、些細な操作性の課題が大きな問題に発展する可能性があります。特に、承認フローが日常業務の中心となる部門には、操作のしやすさが重要なポイントです。
4. セキュリティ・コンプライアンス対策
ワークフローシステムでは企業の機密情報が扱われる可能性が高いため、アクセス制御やデータ暗号化、ログ監査機能の有無は重要なチェックポイントです。
また、業種や企業の規模によっては、ISOやプライバシーマークなどの外部規格・認証を取得しているかどうかも導入判断に影響します。
クラウド型を選択する場合は、データセンターの所在地や運営ポリシーについても事前に確認することで、内部統制の観点から安心して運用を行えるでしょう。
5. 他システムとの連携や拡張性
ワークフローシステム導入後に、会計システムや人事システムへデータを連携したいといった要望が出てくることは珍しくありません。導入前にどの程度統合が容易かを調査しておくと安心です。
APIやWebhookなどの技術的連携ポイントが充実しているベンダーであれば、さらなるシステム拡張が必要になった際にもスムーズに対応できます。
一方、閉鎖的なシステムだと連携コストやカスタマイズ費用がかさむおそれがあるため、自社の将来像を踏まえて長期的な視点で選ぶことが望まれます。
6. 柔軟なカスタマイズ性
企業によっては独自の承認ステップや書式を必要とする場合があります。その際に、小規模な修正だけで実現できるか、大幅なカスタマイズが必要なのかを事前に見極めることが重要です。
ノンプログラミングでフローを編集できるツールも増えており、IT部門のリソースが限られる企業には特に魅力的です。
画面レイアウトやステート管理など、細部まで柔軟に作り込めるシステムは導入後に運用を定着させやすく、現場レベルでの抵抗を減らす効果が期待できます。
7. サポート体制・導入支援の充実度
導入時にはシステムの初期設定や運用者向けのトレーニングが必要になるケースがほとんどです。ベンダーのサポートが手厚いかどうかは、円滑な導入のために非常に重要な要素と言えます。
トラブル発生時の問い合わせ対応やバージョンアップ時のサポート方針など、事前に確認しておくことで、運用開始後にスムーズなサポートを受けられます。
特にクラウド型の場合、サーバー側のアップデートが頻繁に行われるため、その際の情報公開やユーザーサポート体制がしっかりしているベンダーを選ぶと安心です。
おすすめのワークフローシステム
多数存在するワークフローシステムの中でも、代表的な15製品をピックアップし、その特徴や利点を簡単に紹介します。
製品ごとに注力している分野や価格帯、連携可能なシステムは異なるため、複数製品を比較検討することが大切です。ここで取り上げるシステムはいずれも高い評価を得ており、導入企業からの満足度が高いものばかりです。
なお、実際の導入にあたっては、カスタマイズの範囲や運用サポートの充実度など、公式サイトや担当営業への問い合わせで詳細を確認することをおすすめします。
次に紹介する15製品は機能性や連携性に特徴を持ち、幅広い業界・規模の企業に対応できる可能性が高いシステムです。
コラボフロー
シンプルで使いやすいUIが魅力で、承認画面のレイアウトを直感的にデザインできます。導入までのハードルが低く、ITに詳しくない現場でもすぐに使い始められるのがポイントです。
また、申請フォームの作成や承認経路の設定もドラッグ&ドロップ感覚で行え、現場の要望に合わせて幅広いカスタマイズが可能です。
サポート体制も充実しており、初めてワークフローシステムを導入する企業でも安心して利用できると評判です。
ワークフローシステム導入の流れ
導入前の準備から本格運用までの手順を知っておくことで、プロジェクトをスムーズに進められます。
システム導入プロジェクトは、きちんとした計画と運用設計があってこそ成功します。ワークフローの構築は業務プロセスの抜本的な見直しの機会でもあるため、現行業務とのギャップを洗い出したうえで進めることが大切です。
一気に全社導入を試みると混乱を招くこともあるため、テスト導入やパイロット運用を段階的に実施する企業が増えています。これにより、導入初期の課題を早期に発見し、最適化の手が打てるメリットがあります。
以下に示す4つのステップを参考に、導入計画とシステム選びを進めてみてください。
1. 現行業務フローの整理
まずは、社内でどのような申請書類が使われているか、誰が承認者なのか、どのような経路を通って最終決裁まで進んでいるのかを明確化しましょう。
既存の業務プロセスを洗い出すことで、無駄な手順や、システムで自動化できる部分が見えてきます。導入を機に業務自体を再定義することで、さらなる効率向上を狙えます。
この段階でステークホルダー(現場担当者や管理者、経営層)との合意形成を得ると、導入計画がスムーズに運びやすくなります。
2. 製品比較と要件定義
現行フローを整理したら、必要な機能や予算、運用体制などを盛り込んだ要件を洗い出します。システムに求める優先事項が明確になるため、この段階でベンダー比較を行うと絞り込みが容易になります。
ベンダー提供のデモや無料トライアルを活用し、操作性や連携性、セキュリティ面などを実機でチェックすることも重要です。
導入後のサポート体制や将来的な拡張性も考慮し、数社程度に候補を絞ったうえで見積もりを依頼しましょう。
3. テスト導入(パイロット運用)
導入候補を絞ったら、小規模でテスト導入を行うのがおすすめです。一部部署や少数のユーザーでパイロット運用をすることで、システムの実用性や運用課題を把握できます。
この段階で得られたフィードバックをもとに、承認ルートの修正や権限設定、通知方法などを最適化していきましょう。
テスト運用期間中にトラブルや不満点が出た場合は、ベンダーとの連携を密に取り、迅速な対応を依頼することで、本格導入前に大きな問題を解消できます。
4. 全社導入と運用定着
パイロット運用の結果を踏まえ、修正を加えた最終版のワークフローシステムを全社的に展開します。操作マニュアルの整備や研修を実施することで、現場の戸惑いを軽減しましょう。
最初の数週間から数カ月間は、何かしらの追加要望や不具合が出ることも珍しくありません。専任担当者やベンダーと連携し、迅速にPDCAを回す仕組みを整備することが大切です。
運用が安定すれば、さらなる拡張や他システムとの連携を検討することで、生産性や業務品質を一段と引き上げる可能性も広がります。
ワークフローシステムの実績
多数の企業がワークフローシステムを導入し、業務効率改善やペーパーレス化などさまざまな成果を上げています。
近年の導入事例を見ていると、ペーパーレス化、コスト削減、リモートワーク対応といった効果はもちろん、業務全体の可視化や承認プロセスの属人化解消など、組織力向上にも寄与していることがわかります。
特に、ワークフローシステムで蓄積されたデータを分析することで、プロセスのボトルネックを発見し、さらなる業務改善につなげる取り組みを実践している企業も増えています。
今後もテレワークやDXの加速に合わせてワークフローシステムのニーズは高まり続けることが予想され、多くの企業が競争力を高めるための重要なITインフラとして位置づけています。
まとめ|ワークフローシステムの導入で業務効率化を実現
ワークフローシステムは単なる申請・承認の電子化にとどまらず、企業全体のDX推進や働き方改革にも貢献する重要なツールです。ぜひ自社の特徴や課題に合わせて最適なシステムを選定し、さらなる業務効率化を実現してください。
ワークフローシステムの導入は、申請者から承認者までのフローをスピーディにし、エラーや抜け漏れを減らすだけでなく、コスト削減や内部統制の強化にも寄与します。
また、リモートワークとの相性が良く、場所を問わずに承認手続きを進められるため、テレワークの定着にも大きく貢献するでしょう。導入にあたっては、自社に本当に必要な機能の洗い出しと、操作性に優れたシステム選びがカギとなります。
最終的には、ワークフローシステムの活用を通してDXを推進し、意思決定のスピードや業務の透明化を高めることが、企業競争力の向上につながります。
ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。




