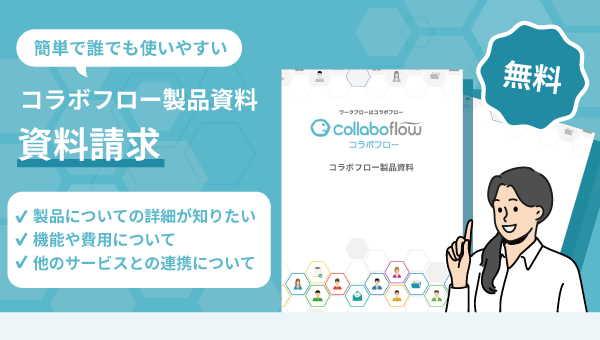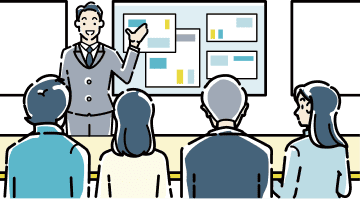社内稟議が必要なケースや理由とは?作成のポイント、効率化のコツ
2025.08.06
この記事の目次
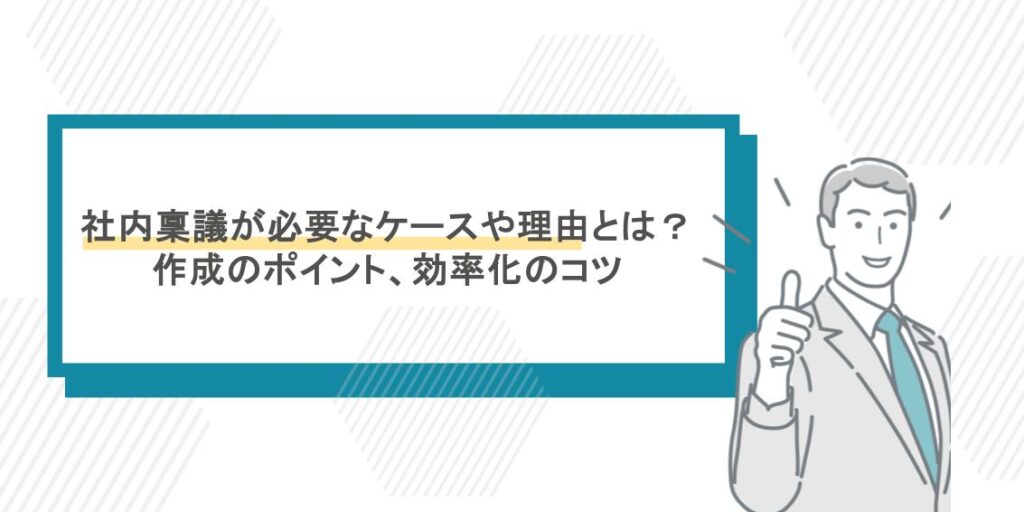
社内稟議に関する基礎知識
社内で何か新しいことを始めるときや、大きな支出を伴う場面では、社内稟議の手続きを通して組織としての意思決定を行うのが一般的です。
まずは、社内稟議の基本的な仕組みや、稟議と決裁の違い、そして社内稟議が必要となる典型的なケースについて解説します。
社内稟議は組織の意思決定に不可欠です。
社内稟議とは?
社内稟議とは、組織内で何かを決定する際に、関係者や上司の承認を段階的に得る手続きのことです。
例えば高額な備品の購入、外部業者との契約、新しいプロジェクトの開始など、企業の方針や運営に関わる判断には、企業のルールとして一定の承認プロセスを経ることが定められています。
社内稟議のプロセスは、発案者が「稟議書」を作成するところから始まり、部署内の上司、関連部門の担当者、最終的には決裁権を持つ役職者まで、順番に確認・承認を得ていく流れが一般的です。
一連のプロセスにより、企業全体でリスクやコストをコントロールできる仕組みとなっています。
承認を段階的に得ていく手続きです。
稟議と決裁の違い
「稟議」と「決裁」は似た場面で使われますが、意味は異なります。
稟議とは、決裁を得るまでの承認プロセス全体を指します。一方、決裁はその最終段階で、最終的な決裁者が承認する行為です。
例えば課長や部長の承認を経て、最後に役員が承認した場合、役員の行為が「決裁」となります。
稟議はあくまで「意思決定のための流れ」であり、決裁は「最終的な承認」を指していると理解すると整理しやすいでしょう。
稟議=プロセス、決裁=最終承認と覚えましょう。
社内稟議が必要になるケース
社内稟議が必要になるのは、企業にとってリスクやコストが一定以上に及ぶと判断される場合です。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
・一定金額以上の備品購入や業務委託など、多額の予算を使う支出
・外部との契約(業務委託契約、顧問契約など)の締結
・部署横断で進めるプロジェクトの立ち上げ
・新規採用や部署間の人事異動
・社内ルールや制度の変更
これらは企業の意思決定に大きく関わるため、稟議を通して社内の承認を得る必要があります。
なお、どのような案件に稟議が必要かは、企業の規程によって異なるため、自社の稟議ルールをあらかじめ確認しておくと、スムーズに進めやすくなるでしょう。
大きなリスク・コストには稟議が必須です。
社内稟議の種類
社内稟議と一口に言っても、その内容によっていくつかの種類に分けられます。
支出に関するもの、人事に関するもの、社内ルールに関するものなど、目的に応じて適切な稟議書を作成することが求められるのです。
続いて、代表的な社内稟議の種類を見てみましょう。
用途別に複数種類があるのがポイントです。
契約稟議
契約稟議は、他社と新たな契約を結ぶ際や、既存の契約を変更する際に提出する社内稟議です。
取引金額が大きくなりやすいため、契約条件だけでなくリスク面も丁寧にチェックされます。
稟議書には、契約の目的や相手先、金額、支払い条件、契約期間などを詳しく記載します。
契約内容・金額・期間を明記しましょう。
購買稟議
購買稟議は、社内で使用する備品やサービスを購入する際に行われる社内稟議です。
日常的に使用する文具からシステム導入のような高額な物品購入まで幅広く対象になります。
稟議書には、購入の目的、品目、数量、単価、納期、見積書などを記載します。
特に高額な場合は、複数の見積もりを比較し、費用対効果を説明するケースが多いでしょう。
目的・数量・見積を明確にしましょう。
採用稟議
採用稟議は、新しく人材を採用するために行う社内稟議です。
正社員、契約社員、アルバイトなど雇用形態に関係なく、採用には予算が関わるため、社内稟議による承認が必要になります。
稟議書には、採用の背景、職種、人数、想定される人件費、採用スケジュールなどの記載が必要です。
スピード感が求められる中途採用などでは、社内稟議の早期承認が重要になる場合もあります。
職種・人数・背景を記載するのがコツです。
接待交際稟議
接待交際稟議は、取引先との関係強化や情報交換を目的とした会食や贈答などの交際費を使用する前に提出する社内稟議です。
稟議書には、目的、相手先、自社の参加者、費用、開催場所、日程などを明記します。
不正利用を防ぎ、経費の透明性を確保するためにも、事前申請が基本です。
経費の透明性・事前申請が大事です。
捺印稟議
捺印稟議は、すでに内容が承認された契約書に対して、会社印や代表印の捺印を依頼するための社内稟議です。
契約締結の最終段階で行われます。
稟議書には、契約書の内容、捺印の種類や箇所、契約相手、関連資料などを添付します。
内容・印の種類・資料添付を明記しましょう。
社内稟議が必要な理由
社内稟議は、単に形式的な手続きではありません。
企業における意思決定の精度やスピード、透明性を高めるうえで、大きな役割を果たしています。
ここでは、稟議制度が必要とされる主な理由を3つの観点から見ていきましょう。
精度・スピード・透明性が向上します。
会議に頼らずスムーズに意思決定できるため
稟議の仕組みを活用すると、判断に関与する人との会議を経ずに意思決定を進められます。
特に関係者が多い案件では、全員の予定を調整して会議を行うのは時間も手間もかかります。
稟議書を回覧すれば、内容を共有したうえで承認を得られるため、業務のスピードを損なわずに処理することが可能です。
会議を開かずスピーディに進められるのが大きな魅力です。
承認フローを明確にして、責任の所在をはっきりさせるため
稟議は、誰がどのタイミングで意思決定に関わったかを明確にする仕組みでもあります。
関係部署や上長の承認を経て決裁されることで、社内のガバナンスを強化できるのが大きなメリットです。
また、何かトラブルがあった場合にも、稟議書をたどることで責任の所在や判断の根拠が確認できます。
これにより、企業としての透明性が高まるほか、説明責任を果たしやすくなるのです。
責任の所在が明確になるのがポイントです。
文書として残すことで、後から確認がしやすいため
稟議書は、企業内で行った意思決定の記録でもあります。
口頭やメールでのやり取りとは異なり、誰がどのような内容を承認したのかが文書として残るため、後から確認しやすいのが特徴です。
例えば、数カ月後に「なぜこの支出が発生したのか」を振り返る場面があっても、稟議書を見れば判断の経緯や関係者がすぐに把握できます。
紙で保管する場合はファイリングの手間や保管スペースの確保が課題になりますが、電子データにすれば検索や管理も容易になります。
後からの確認や証跡が残るのも大事なポイントです。
社内稟議書を作成する際のポイント
稟議書は、読み手を納得させるだけの内容と構成が必要です。
特に多額の費用やリスクが絡む案件では、情報の正確さや論理性が重視されます。
ここでは、稟議書の作成時に押さえるべき基本的なポイントを、実務に即した形で紹介します。
読み手を納得させる構成が大切です。
目的や背景を明確に書く
稟議書を読む側にとっては、「何のための稟議なのか」「どのような経緯でこの提案に至ったのか」が最初に気になるところです。
前提や背景が不明瞭な場合、判断に迷って承認に時間がかかってしまいます。
例えば、設備導入の社内稟議であれば、「既存設備の老朽化」や「作業効率の低下」といった現場の課題を簡潔に伝えると、社内稟議の必要性が伝わりやすくなります。
背景が明確になれば、読み手の共感や納得も得やすくなるでしょう。
なぜ必要かを明確に伝えるのがポイントです。
提案内容を具体的に書く
目的・背景の次には、「具体的に何を実施するのか」を記載します。
どのような製品・サービスを、どういった条件で、どのタイミングで導入・契約・実行するのかまで、できるだけ具体的に記載しましょう。
このとき、読み手が「内容を想像しやすいかどうか」が重要です。
専門用語ばかりでイメージが湧かない社内稟議は、承認の判断がしづらくなります。
誰が見ても内容が明確になるように、丁寧な記述を心がけましょう。
具体的な内容・条件・スケジュールまで書くことが重要です。
数値や根拠を示して説得力を持たせる
提案内容が合理的であっても、数字の裏付けがないと社内稟議は通りづらくなります。
費用の妥当性や見込み効果、費用の回収期間など、判断材料となるデータは積極的に盛り込みましょう。
例えば「○年で投資回収できる見込み」「従来と比較して○%のコスト削減が可能」といった具体的な数値があると、説得力が高まります。
数字の正確性にも注意し、出典がある場合は併せて明記すると安心です。
数値・根拠の明示で説得力UPです。
比較案を示して選定理由を補足する
「なぜこの案なのか」を補足するために、他の選択肢との比較を示すことも有効です。
例えば、複数の業者から見積もりを取っている場合は、その中から今回の案を選んだ理由を記載すると、意思決定者の納得感が上がります。
例えば「費用はやや高めだが、サポート内容が充実している」といった補足説明を入れておくと、合理的な選定だと判断されやすくなるでしょう。
選択の理由を示すことで、検討のプロセス自体が評価される場合もあります。
比較と選定理由も明記しておきましょう。
社内用語や専門用語は避け、読みやすく書く
稟議書は、必ずしも同じ部署の人だけが読むとは限りません。
特定の業界用語や社内略語が多いと、理解するのに時間がかかり、誤解が生じることもあります。
そのため、誰が読んでもわかるような表現を心がけ、文章も冗長にならないように整理しましょう。
構成としては、「見出しをつける」「箇条書きを活用する」といった工夫も有効です。
読み手のストレスを減らすことが、稟議の早期承認にもつながります。
誰でも理解できる文章を目指しましょう。
社内稟議を効率化するためにできること
社内稟議は、適切な内容と手順によって、よりスムーズに通過させることが可能です。
逆に言えば、内容が正しくても「段取り不足」や「社内調整の甘さ」が原因で止まってしまうこともあります。
最後に、稟議を通りやすくするために現場で実践できる工夫を紹介します。
段取りと調整が成功のカギです。
事前に関係者とすり合わせておく
稟議書を提出する前に、関係部門や上司と事前にすり合わせを行っておくと、承認プロセスがスムーズになります。
特に部門横断で影響がある場合や、高額の支出を伴う場合には、事前説明が欠かせません。
「稟議書を出してから調整する」のではなく、「出す前に調整する」ことで、余計な差し戻しを防げます。
協力を得やすい雰囲気を作ることも、稟議を通すうえでは重要と言えるでしょう。
事前の根回しがスムーズ化のコツです。
想定される質問や懸念に先回りする
読み手の立場に立って、どのような疑問や懸念が出るかを想定し、それに答える形で稟議書を仕上げると、承認されやすい内容になります。
例えば、「なぜ今、このタイミングで必要なのか」「費用対効果が妥当か」といった問いに対する回答を盛り込んでおくと、稟議内容の信頼性が高まるでしょう。
一歩先を見越して準備する姿勢が、承認のされやすさにもつながります。
先回りで承認率アップです。
過去の稟議書を参考にする
同じ部署で過去に通った稟議書を参考にするのも、効果的な方法です。
構成や使われている表現、盛り込まれている情報などを確認し、自分の稟議書にも活かしてみましょう。
過去の成功例を分析することで、どのような情報が求められているのかが見えてきます。
承認者の好みや重視する視点がつかめれば、稟議作成もより進めやすくなります。
過去の成功例を活用してみましょう。
ワークフローシステムを導入して稟議のスピードを上げる
稟議がスムーズに進まない理由の一つが、「どこで止まっているのかわからない」「紙で回しているので時間がかかる」といった運用面の問題です。
こうした課題を解決する手段として有効なのが、稟議をデジタルで進められるワークフローシステムの導入です。
稟議をシステム化すれば、提出から承認までの流れを可視化でき、誰がどこで止めているかもひと目でわかります。
また、社用携帯や在宅環境でも承認ができるため、組織全体の意思決定スピードが大幅に上がります。
属人的な運用を排除し、効率と透明性を両立させる仕組み作りが重要です。
ワークフロー化でスピードUP&見える化を実現できます。
社内稟議の流れや目的を正しく理解しよう
この記事では、社内稟議の基本的な仕組みや必要なケース、種類、作成のポイントについて解説しました。
稟議は単なる社内手続きではなく、企業として適切な意思決定を行うための大切なプロセスです。
誰がどこで何を判断したのかを明確にし、後からのトラブルを防ぐためにも欠かせない存在と言えるでしょう。
稟議=組織運営の基本インフラと理解しましょう。
ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。