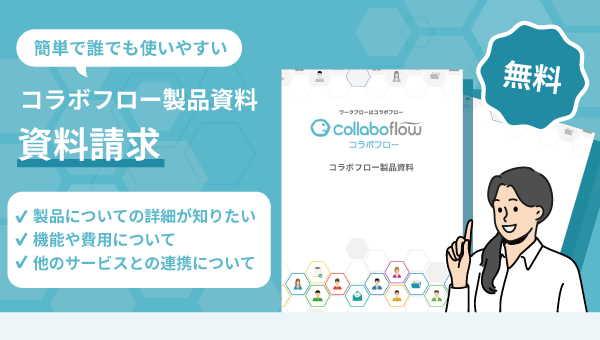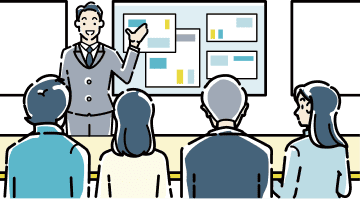稟議と合議の違いとは?メリット・デメリット、使い分けのコツ
2025.08.15
この記事の目次
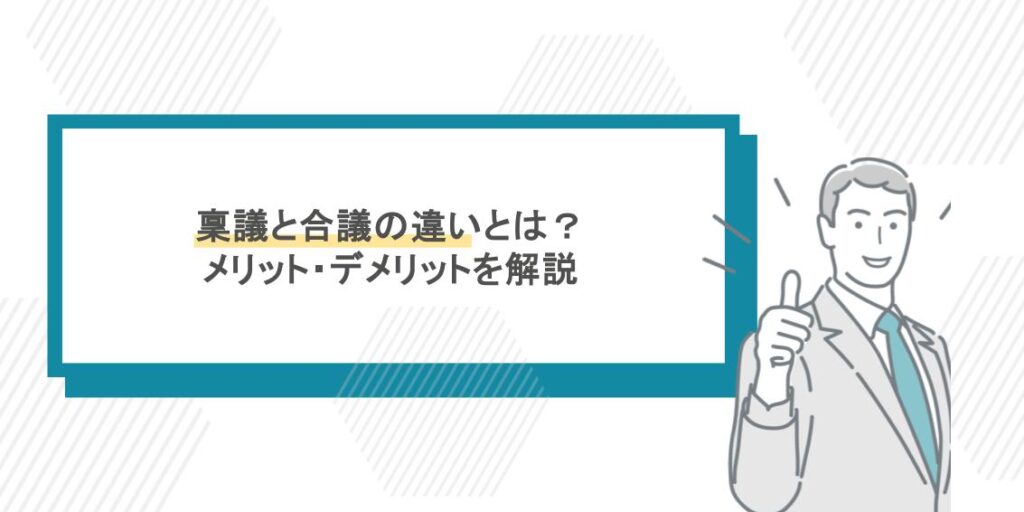
稟議と合議の違いとは?メリット・デメリット、使い分けのコツ
業務上の意思決定を進める中で、「稟議」と「合議」という言葉を目にすることはありませんか。ただ、なんとなく使っていて、実はその違いや使い分けをしっかり理解できていないという人も多いかもしれません。
この記事では、それぞれの意味や特徴を整理し、場面ごとの使い分けのポイントを解説します。
稟議と合議に関する基礎知識
まず稟議と合議の基本的な意味と、両者の違いについて整理しておきましょう。
稟議の意味
稟議とは、ある案件について起案者が文書を作成し、それを関係部署や役職者に順番に回して承認を得る形式の手続きです。一般的には、起案者が稟議書を作成し、直属の上司、部門長、役員、最終的には社長など、あらかじめ定められた承認ルートに従って回覧していきます。
このように段階的に承認を得ることで、組織の各階層が意思決定に関与する仕組みとなっており、透明性や妥当性を確保しやすいのが特徴です。
稟議は、誰がどの段階で承認したかを文書で明確に残せるため、後から確認しやすく、責任の所在もはっきりします。
特に高額な支出や他部門にまたがる重要な判断など、組織全体への影響が大きい案件では、慎重な判断が求められるため、稟議を通して意思決定を行うプロセスが適しています。
稟議制度はガバナンスの強化やコンプライアンス対応にもつながり、大企業や官公庁など、多くの組織で採用されています。近年では、電子稟議システムの導入が進み、紙での回覧からデジタル化されたワークフローへと移行する企業も増えています。
承認履歴が文書で明確に残るのが稟議のポイントです。
合議の意味
合議とは、関係者が同じ場所または同じタイミングで集まり、対話を通じて意思決定を行う形式の手続きです。関係する担当者や管理職などが一堂に会して、案件に対する情報を共有しながら、それぞれの立場や視点から意見を出し合い、合意形成を目指します。口頭でのやりとりを中心に進めるため、書面による手続きよりも柔軟でスピード感のある対応が可能です。
合議は、主に現場レベルの迅速な判断が求められる場面で活用されます。例えば、日常的な業務判断や、部署内で完結するような比較的軽微な案件などに適しており、会議の中で即時に意思決定できることが強みです。
ただし判断に至った経緯の記録が残りにくく、責任の所在が曖昧になりやすいという面もあるため、判断の重さや関係者の数に応じて、稟議との使い分けが求められます。
対話を通じて合意形成が特徴です。
稟議と合議の主な違い
稟議と合議の大きな違いは、意思決定の方法と進め方にあります。稟議は「文書を順に回して承認を得る」縦型のプロセスであるのに対し、合議は「関係者が同席して話し合いながら決める」横型のプロセスです。
縦型(稟議)と横型(合議)の違いがポイントです。
稟議が向いているシーンとは?
稟議は、文書による正式な承認を必要とする場面で特に力を発揮します。関係者の承認履歴が明確に残るため、後から確認や説明がしやすいのが特徴です。
例えば以下のようなケースでは、稟議が適しています。
・高額な支出を伴う購入や契約(システム導入、設備投資など)
・社内規程に基づく正式な承認フローが必要な業務(予算申請、人事異動など)
・決定までに複数階層の承認が求められる場合(役員・取締役の承認など)
このように、組織としての意思決定を明文化し、責任の所在を明確にしておきたい案件では、稟議が有効です。
承認履歴が残る案件に稟議は向いています。
合議が向いているシーンとは?
合議は、複数の関係者の意見を取り入れながら、スピーディーに結論を出したい場面に適しています。話し合いを通じて共通認識を作れるため、部門横断的なプロジェクトや価値観のすり合わせが必要な案件で力を発揮します。
例えば以下のようなシーンが挙げられます。
・新規プロジェクトの方向性を決める会議
・部門間で協力して対応すべき業務(例:複数部署が関与する制度改定)
・前例のない課題に対して、複数の視点から柔軟に考えたい場合
このように、合議はスピードと議論の質を両立したい業務に向いています。
スピーディーな議論に合議が最適です。
稟議のメリット・デメリット
稟議は安定した運用が可能な一方で、スピード感や柔軟性に課題が生じる場合もあります。ここでは稟議の代表的なメリットとデメリットを整理します。
稟議のメリット
稟議の大きなメリットは、誰がどの段階で承認したのかが文書として残るため、後からトラブルがあった際にも責任の範囲が明確になる点です。また、社内の承認フローが定型化されていれば、全体の手続きに統一性が生まれ、管理の効率化にもつながります。
さらに、稟議書という形で承認内容が記録として残るため、監査への対応や社外への説明を行う場面でも有効に活用できます。
責任の明確化がメリットです。
稟議のデメリット
一方で、稟議にはいくつかのデメリットもあります。まず、承認までに複数の人の確認が必要となるため、どうしても時間がかかってしまうという点です。
また、一度稟議書を提出してしまうと、その後の修正や柔軟な対応が難しくなり、意見交換の機会が限られてしまうことも少なくありません。
さらに、形式的な手続きに終始することが多く、関係者の本音や細かな意見が見えにくくなるという側面もあります。
時間がかかるのがデメリットです。
合議のメリット・デメリット
合議はその柔軟さが魅力である一方、関係者が多くなるほど調整が難しくなる側面もあります。ここでは合議の利点と課題を整理します。
合議のメリット
合議のメリットは、関係者が直接意見を交わすことで、多様な立場や視点を取り入れた意思決定ができる点です。
話し合いを通じて方向性を定めると、スピーディーな対応が求められる場面でも柔軟に決定を進めやすくなります。
また、議論を重ねると、参加者全員が納得しやすく、最終的な合意形成がスムーズに進むという特徴もあります。
多様な視点を集約できるのが利点です。
合議のデメリット
ただし、合議にも注意点があります。まず、関係者が一堂に会して話し合うためには、スケジュール調整が必要で、実施のハードルが高くなる場合があります。
また、意見が対立したまま議論が進まない場合、結論が出せずに話し合いが長引くケースもあります。
加えて、議事録などが十分に整備されていない場合には、誰が何を了承したのかが曖昧になり、後からの確認や責任の明確化が難しくなることもあります。
調整や記録の難しさが課題です。
稟議と合議の使い分けのコツ
稟議と合議は状況に応じて使い分けることが大切です。
最後に、金額やリスク、意思決定に求められるスピード感、関与者の数に基づいて、どのように使い分ければ良いかを解説します。
金額やリスクに応じて選択する
高額な支出や大きなリスクが想定される案件では稟議が適しています。
稟議は、慎重に審査し、責任を明確にするため、影響の大きな意思決定に向いていると言えるでしょう。
逆に、小額の案件やリスクが少ない場合は、その場で迅速に決定を下せる合議を選ぶと効率的です。
リスク・金額で使い分けが基本です。
意思決定の緊急性に応じて選択する
速やかに意思決定が必要な場合は、合議が適しています。緊急の判断を要するトラブル対応などでは、合議を利用することで時間を短縮できます。
一方、時間に余裕があり慎重に進めたい場合は、稟議を選ぶのが望ましいです。
稟議は合議と比べると決定までに時間がかかりますが、十分な検討が可能です。
スピード感で判断するのがコツです。
関係者の数に応じて選択する
少人数で決定を下す場合や意見が一致しやすいケースでは、合議が有用です。逆に、多くの関係者がいる場合は、稟議が向いています。
稟議は、順を追って承認を得るため、大人数が関わる決定に適していると言えるでしょう。
人数が多いなら稟議です。
稟議と合議の違いを理解して適切に使い分けよう
この記事では、稟議と合議の違いやそれぞれのメリット・デメリット、そして場面ごとの使い分けの考え方について解説しました。
どちらの方法も一長一短があり、業務の性質や状況に応じて選ぶことが大切です。
意思決定の正確さや求められるスピード、関係者の人数などを踏まえて、適切な方法を選択していきましょう。
状況に応じた使い分けがポイントです。
ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。